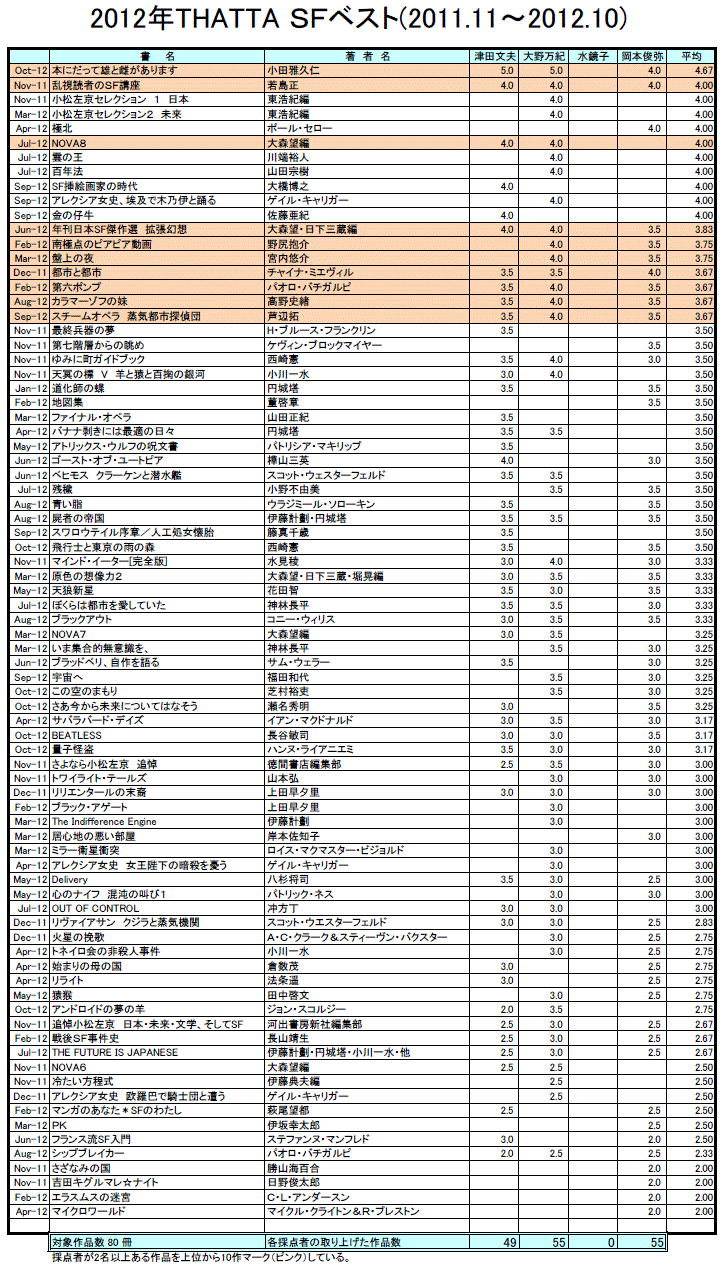|
2012 Best SF Winner
本にだって雄と雌があります
前評判が耳に入ってしまっていたので危惧しつつ読み始めたが、杞憂であった。いやあ、これは第2のデビュー作というか、ファンタジーノベル大賞はコレで取るべきだったかも。戦時中の話がやや重力が違うとはいえ、ほぼ満点のエンターテインメント。この内容が300ページちょっとに収まっているという驚き。小松左京のコテコテと筒井康隆のスキゾをどろどろに混ぜ合わせて、モリミー印のウォーターで薄めたような凄いペーソス。今年の日本SFベスト候補は高水準だなあ(津田)
純然たるファンタジイである。しかしその幻想は、普通のエブリデイ・マジックな物語やSF的な異界と違って、この日常の裏側や次元の亀裂の向こうにあるのではなく、このリアルなご近所の世界そのものに、見たまんまに存在しているのである。でも空飛ぶ本や羽の生えた白象なんてぼくらは普通目にしていないわけだから、これはちょっと居心地が悪い(こういう描写を受け付けない読者もいるだろう)。そこが著者の語りの技で、少なくともぼくには何の違和感もなく納得することができた。マジックリアリズムとはこういうものを言うのだろうなと思う(大野)
本書で書かれた真相とは少し違うが、ジョン・スラデックの短編、読まれなくなった本が飛び去ってしまう「教育用書籍の渡りに関する報告書」を思い起こさせる。大量に蓄積された本は、単なる紙束ではなくなり、独特の生命/目的を得るようになるのだ。そんな奇想をベースに、本書では祖父を取り巻くユニークな人物たち、売れない探偵小説家だった曾祖父、祖母は識字に難のある天才画家、祖父のライバルコレクター資産家の御曹司、冴えない政治家の伯父、放浪のシンガーである叔父等々が続々と登場する。これだけ多彩な登場人物が詰め込まれた割に、この分量でも物足りなさは感じさせないのは、優れた文章力の賜物だろう。(岡本) |
  |
第2位 乱視読者のSF講義
ほとんどの文章が再読だけれど、十分に面白い。きちんと作品を読めるというのは凄いことだなあとあらためて感心する。ここで採りあげられた作品は未訳のもの以外はほとんど読んだことのあるものばかりなのに、どれもディテールは勿論あらすじさえ忘れてしまっているんだから、よけい新鮮に感じる。そのうえここに収録された文章自体、そのほとんどを数年前に読んでいるにもかかわらず、またもや感心するに至っては驚くのも情けない。ますます老人力が増してるなあ(津田)
ぼくも書評を書いたり解説を書いたりしているが、あくまで一人のSFファンとして、SFとしての面白さを基準に書いている。ところが本書では「SFというジャンルの中だけにしか通用しない議論にはさほど興味はない」として、対象を単なる小説、単なる文学として、それをひたすら丁寧に読み込むという態度で分析していく(でもそれはSFらしさを無視するということではない)。ところがそれが、決してアカデミックで無味乾燥な授業のようではなく、知的で意外性に満ち、とても面白いのだ(大野)
最初は毎回1つの短編小説を取り上げ、その内容を精査する「SF短編講義」で、主人公/個人を排し、初めて人類の視点から小説を書いたウェルズの意義からスタートする。各短篇の見どころを実に詳細に解読する(長編ではとても1回の講義に収まらない)。読書の深みを理解/再確認するには最適な講義といえるだろう。第3部は、ウラジミール・ナボコフと比肩しうるジーン・ウルフだけを論じた6編である(著者はナボコフを20世紀最大の作家と称賛する)。ややマイナーかも知れないが、本書で言及された作品は、何度でも読み返せるだけの奥行きを備えている。アカデミックな研究や斜め読みの時間潰しから離れ、本来の読書の楽しみに立ち還る意味でも、本書の内容は参考になるだろう。(岡本) |
  |
第3位 NOVA8
最大の読み物はやはり山田正紀「雲の中の悪魔」だろうなあ。ここまで科学用語/SF用語をゆがませて使い倒すと、なんか別の世界が開けてるんじゃないかと思ってしまう。それが面白いのかどうかはよく分からないのだけど。その後に飛浩隆そして東浩紀を読むとホッとする。前半の収録作では粕谷知世と松尾由美の女性陣がオーソドックスな職人芸を見せてくれて嬉しい。松尾由美を読んだのははじめてかも。青山智樹はまるで田中啓文みたいな突っ走り方だけれど、そういやこの人もはじめて読んだような。第一印象がこの作品でよかったのだろうか(津田)
まず問題なのが山田正紀「雲のなかの悪魔」。(中略)この作品ではほとんど意味不明な科学用語が圧倒的なノイズとなって読者に襲いかかるが、誰とも知れない話者によって直ちにそれに独特な解釈が与えられる(それが物理的な用語の意味とずれているので、ますますわからなくなるのだが)。この話者こそ、恣意的な同調圧力を強いる悪魔ではないのか。と考えれば、理解できない科学用語によって構築された超物理的牢獄からの脱獄という本作のテーマは、そのままこの閉塞的な3・11後の情報環境からの脱出を意味しないか。そのパワーとなるのは何と「愛」(あるいはクオリア!)なのだ。(大野) |
  |
第4位 拡張幻想
集中一番感心したのが、再読の円城塔「よい夜を持っている」で、円城塔が芥川賞を取って当たり前の作家だと云うことが改めて納得された。表面的な書きようはちっとも叙情的でないのに、読後にもたらされる圧倒的な叙情は他の収録作品からぬきんでている。円城塔も含め、収録作の面白さはバラエティに富んでいて出したお金以上のエンターテインメントが得られることは間違いない。テイストも50年代SF風から最先端数物宇宙理論まで、ファンタジーからホラー、おバカなだけのミステリまでタイトル通りの守備範囲の広さだ(津田)
目玉は第3回創元SF短篇賞の受賞作が掲載されていることだろう。それが理山貞二「〈すべての夢|果てる地で〉」だ。縦書きだとわかりにくいが、このタイトルは量子力学の教科書に出てくるディラックのブラ=ケット記法である。(中略)それが多世界の直交性(一言でいえば、あちらを立てればこちらが立たずということね)というアイデアにつながり、さらにメインテーマである想像されるもの=夢=物語と現実との関係性という話に発展していく。さらにここで、実在のSF作家の名前が出てきて、涙無くしては読めない(笑うという人も多いのだけど)SFファン大喜びのラストへと続くのだ。だがジャンルへのオマージュということも、この小説の本質ではないだろう。ここに出てくるSF作家たちを知らずとも、昔夢見た未来、あの21世紀はどこにいってしまったのだろうと思う読者なら、十分共感できるはずだから(大野)
はやぶさの帰還(10年6月)、3.11の震災、小松左京の死(11年7月)と、2010年から11年にかけて、さまざまな社会的大事件が起こった。その波紋の中から、新たな作品がいくつも生まれている。伊藤計劃の死は2009年のことだが、その影響はまだ広がり続けている。本書では、そういった関連作品、オマージュ、トリビュートが半数を占めている。ミステリタッチの3編も、それぞれ広義の元ネタから影響を受けた作品と看做せるだろう。(中略)さてしかし、最大の注目はSF短編賞の受賞作である。量子力学をベースに、さまざまなSFに対するリスペクトを鏤めるなど、本書を代表する傾向をすべて内在しているからだ。結末がそのまま2011年を象徴する終わり方になっているというのは、ちょっと出来すぎではないか(岡本) |
  |
第5位 南極点のピアピア動画
これは紛れもなく傑作である。ニコニコ動画や初音ミク、Twitterなどに興味がない、あるいはオタクっぽいものは無条件にイヤという人、表紙のせいで読む気がしないという人も、まあとりあえずは読んでみて欲しい。ある意味、徹底的に調子のいい、ご都合主義で無理やりな技術オタクのユートピア小説に見えるかも知れない(いや、そういう側面があることは否定できないが)。だが本書は『沈黙のフライバイ』につながる、著者のSF作家としての個性と信念が見事に結晶した、本格SFの傑作である(大野)
本書に書かれている日常/情報インフラ自体は、ほとんどが既にあるものだ。「ここにある未来」とは、そういう意味である。加えて、宇宙耐性を持った蜘蛛、ミクの姿をした宇宙人(表紙のイラスト)や、10年後にはニコニコ/初音ミク世代が要職に就いていて、ミクさえ掲げればどんなプロジェクトでも賛成などの、「周到なご都合主義/ギークのユートピア」が設けられている。すべてを個人の信頼ネットワークで繋ぐ考え方は、功利的な社会では決して明るい未来はこないという、作者の人生観を絡めた信念に基づいている。妄想(衆愚を増長させる危険思想)と見るか、理想(Web民主主義)と見るかは、読者の姿勢によって異なるだろう(岡本) |
  |
第5位(同率) 盤上の夜
いずれも異様な緊迫感をはらんだ対戦の描写が圧倒的で、魅了される作品だ。登場するのは異能のある人々ばかり。超天才の頭脳を描く作品としてはテッド・チャンが思い出されるが、囲碁や将棋の天才たちの頭脳はどうなっているのかと思ってしまう。ロジャー・ペンローズではないが、本当にこういう思考は多世界に広がって同時並列計算されているのではないか、とさえ思えてくる。人間量子コンピュータだ。本書では、そういう人々の人間ドラマも描かれるが、それ以上に、より抽象的なゲームの世界、ロジカルな世界と、その外部である日常の関係が、非常にSF的に、人工知能や認知科学的な視点でもって描かれている。壊れた日常、平凡な日常は、どのように抽象世界を支えるのか。ゲームの終焉とは何を意味するのか。しかし、こんな作品も書く一方で「スペース金融道」みたいな作品も書ける、この人は本当に才能があるよ(大野)
囲碁に始まり、囲碁に終わる構成。また、事実に基づいた作品(「人間の王」。書かれている不敗のチェッカーチャンピオン、マリオン・ティンズリーは実在の人物だが、著者による大胆な解釈が施されている)もあれば、自身の体験を色濃く出した作品(「清められた卓」)もある。そもそも、冒頭の(事故ではなく)四肢を無くした女性棋士の設定が異色だ。そういう、ほとんどありえない登場人物を、努めてノンフィクション/ドキュメンタリー風に描写している点が印象に残る特徴だろう。「象を飛ばした王子」はブッダに迫るテーマを、「千年の虚空」は政治テーマに挑むなど、SF的飛躍を含めたスケール感も面白い(岡本) |
 |
第7位 都市と都市
表向きのミステリがこの変な設定のおかげでそれなりのサスペンスを醸しているが、殺人事件の謎解きだけならこの設定でなくても似たような雰囲気の話は書けるのではないだろうか。しかしさすがはミエヴィルで、作者の興味は設定がもたらす効果に注がれている。そこがSFファンに強くアピールするところだろう。良くやるよと感心する。これまでの作品を読んで感じるのは、ミエヴィルは視覚的描写に長けているようで、読者に未知なものについて具体的なイメージを提出するのが意外と下手だということ。短編集でも見せたクトゥルー神話への強い志向はこの作品でも感じられるけれど、それが描写し得ないものを雰囲気で表して読む者を魅了するホラーという意味で、ミエヴィルの未知なるものの描写も読み手に不全感をもたらすのかもしれない。とはいえ、この作品の面白さは抜群だ(第3部は保留するけれど)。(津田)
作者自身、アレゴリーを否定しているとなると、本書はどう読めばいいのか。民族や宗教に関わる現実の差別を背景に置きつつも、この設定をそのままに受け入れて、犯罪捜査のミステリとして読むのが正解なのか。でも、例えばこんなルールを尊重するとしても、それに同調する必要のない外国人の立場というのがどうにも不明確で、その立場(つまり読者の立場だ)に立てば、本書で問題とされていることは何ら問題ではなくなるのである。主題が犯罪捜査から離れる第三部にしても、本格SFというのは苦しすぎて、裸の王様がずっと裸の王様でいられる理由がどうにも納得できない。何か読み落として、見逃しているのかしら。とはいえ、この二重都市、平行都市の雰囲気や空気は実に見事に描かれており、主人公たちの造形も良くて(特に前半で主人公の助手をする婦人警官が魅力的だ)、確かにとても読み応えがある作品である(大野)
ファンタジイとミステリ、SFとの境界にある作品。技量があるからこそ掴めた設定で、誰でもが書けるものではない、とマイケル・ムアコックは英国の新聞ガーディアン紙の書評で述べている。実際、カルヴィーノ風寓話とは対極にあるハードボイルドなミステリタッチにより、リアリティに乏しいファンタジックな2重都市を描き切るのは並大抵ではないだろう。主人公(警部補)は、旧ベルリンのような物理的な壁ではなく、心理的な壁=障壁に重圧を感じながら、境界線に隠れる殺人犯を追う。架空都市での犯罪捜査ものでは、シェイボン『ユダヤ警官同盟』などがあるが、それと比べても異色の設定である。犯人は2つの都市のどちら側に存在するのか、その確率は、シュレーディンガーの猫の量子論に似ている(岡本) |
  |
第7位(同率) 第六ポンプ
イーガンやチャンのような革新性はないけれど、レベルの高い短編集。デビュー作という「ポケットの中の法(ダルマ)」こそまるでサイバーパンク風の習作になってしまっているけれど、それでもストーリーテリング能力は十分発揮されている。収録作の中では『ねじまき少女』に繋がる世界を描いた作品がやはりよくできていて読ませる。その他の短編もバラエティに富むとはいえ、何らかの形で環境SFになっている。全体にバチガルピの世界認識は苦く倫理的で、それを読ませるストーリーに仕立て上げるところに作家としての力量を感じさせる(津田)
SF的設定が生かされている「砂と灰の人々」も好きだが、何といっても「第六ポンプ」が傑作だ。何十年もエラーを表示しながら、それでも動いているポンプたちの描写には涙が出そうになるし、このグロテスクな世界の中で、自分の仕事に責任感を持ち、きちんとやり遂げようとする主人公の、ごく当たり前で日常的な意識には、心から共感を覚える。日常を支えるのはこういう普通の人々の努力によるものだ。インフラをちゃんと動かす、保守するということの大事さ、しんどさ。その一方に、それを当たり前のこととして享受しながら、自分たちは何もせず、現場で働く人々に全ての責任を押しつけて、ただ非難するだけという連中がいるのだ(大野)
登場人物たちは、改革者や科学者といった、リーダー型人間ではない。大半は、状況に流されるままの小心な一般人だ。唯一「第六ポンプ」の主人公だけは、事態を食い止めようと苦闘するが、無力な一市民の域を出ることができない。バイオ化が暴走した未来は、大きな貧富の差と疫病の混乱に沈んでいる。そこには、今我々の知るような社会的秩序はない――という、デストピア的な世界観が著者の特徴だろう。ハッピーエンドのない、突き放された結末は読後に強い印象を残す。しかし、もう一ひねりが欲しい作品も多い。お話の展開が、あまりにストレートすぎるので、ちょっと食い足りないのだ(例えば、かつて衝撃的と話題を呼んだ1969年のハーラン・エリスン「少年と犬」と対比できる、「砂と灰の人々」の結末なのだが、あまりに淡泊すぎる)。(岡本) |
  |
第7位(同率) カラマーゾフの妹
『屍者の帝国』でもアリョーシャとコーリャがアフガニスタンで出てきたけれど、こっちは差分機械で計算してロケットに乗る話だもんなあ。まさか円城塔と相談して書いたわけでもないだろうに、あまりに高野史緒らしくて笑ってしまう。どちらの作品でもこの二人の大真面目な熱意がネタだしね。以前に書いたけれど、ドストエフスキーを読んだのは40年近く前の浪人時代で、カラマーゾフから始めて『死の家の記録』までを集中的に読んだ。あの熱に浮かされるような読み心地は今でも覚えているが、話の内容はすっかり忘れているので、作者の原作に対する創意工夫がどこらにあるのかはさっぱりだ。東野圭吾のオビ惹句は正しいと思うよ(津田)
19世紀ロシアにスチームパンクを幻視することは、作者にすれば議論の余地のない当たり前のことなのだろう。ディファレンス・エンジンは方程式を解くのが最大の目的であり、それはニュートン力学の方程式を数値計算するということだ。その手法が階差、差分計算であり、だからディファレンス・エンジンなのである。小さな差、それが積み重なって大きな真実になる。そう思えばカラマーゾフ事件の謎解きも、まさに前任者が残した小さな差分を読み解き、方程式を完成させることに他ならないだろう。ここでミステリとSFが結合するのである(大野)
テーマが8つある(諸説あり)とされる原典から、1テーマ=ミステリに絞り、視点も1つ(厳密には2つか)に統一。分量もコンパクト化され、元本の凡そ5分の1で済んでいる。そこまでなら単なる2次創作だが、いかにも高野史緒流の仕掛けを加えた点がポイントだろう(石田衣良はスチームパンク的と評している)。物語としての整合はエピローグで要約するなど、枚数的な無理はある。しかし何にせよ、ドストエフスキーの続編を書いて第58回江戸川乱歩賞を取ったのだから、企画力だけではない腕力(筆力)の勝利と言える(岡本) |
  |
第7位(同率) スチームオペラ 蒸気都市探偵団
スチームパンクを見事に由緒正しいご都合主義ジュヴナイル・パスティーシュとしてつくりかえた作者はなかなかの腕前だ。冗談極まる手品で落とすのも大したもの。しかし、何より1958年大阪府生まれ、同志社大学卒という作者紹介にビックリした(津田)
いやあ面白い。懐かしさもあるが、この世界のわくわく感が素晴らしい。本格ミステリとしても良くできているのだろうと思うが、ごめんなさい、そっち方面は疎いもので、もっぱらクラシックな(まさに「金背」の)SFとして楽しんだ。確かに今、〈スチームパンク〉が流行っているのだが、ぼくの印象では本書はちょっと違う。〈スチームパンク〉より、まさに〈スチームオペラ〉というのが相応しい。蒸気で動くレトロな機械が満ちあふれているにもかかわらず、このレトロフューチャーな世界は、懐かしい過去ではなく、懐かしい未来なのだ。とにかく、冒頭、第一章からの世界描写のわくわく感ときたら本当に素晴らしい。それは半端じゃなく、まさにセンス・オブ・ワンダーでいっぱいなのだ(大野)
19世紀、蒸気機関はあらゆるところに使われ、また我々の世界では否定された“エーテル”の存在により宇宙飛行も可能となっている。という、スチームパンク的な並行宇宙の設定が、既存SF作品でも踏み込んでいない領域まで、最大限応用されたSFミステリである。著者自身SFを良く知っているため、相当無理な設定(殺人事件の真相)も、ぎりぎり計算内と読める。ミステリなのだから、殺人事件の解明はもちろんされる。その上、世界そのものに対する驚愕の謎解まで用意されるのだが、これは確かにSFでは描けない内容だろう。本書には、1950、60年代の手塚マンガや初期アニメのリリシズムを強く感じさせる雰囲気がある。著者も、そういったイメージを思い浮かべながら書いたようだ(岡本) |