息子にと一緒にシネコンへ『009 RE:CYBORG』を見に行った。彼の選択は3D。3D初体験がコレでよかったのか、と思いつつ、初めての3D眼鏡が本来の眼鏡との関係でずり落ちそうになる不安な幕開け。でも物語に入り込めば、3D画面に大した意味はない(3Dで見ないとわからない仕掛けがあるというのなら別だけど)。良くも悪くも現代に合わせてアップデートされた009は1960年代後半に少年の心をふるわせたモノとは別物だ。作中004が自嘲するように00ナンバーサイボーグのスペックは前世紀の遺物であって、すでに作者自身が00ナンバーサイボーグに別れを告げた最初のシリーズで、ミュトス・サイボーグにスペックの低さを嘲られていたというのに、なぜ生き返らせる価値があると思ったのか。この作品世界の構えの大きさに対して、成層圏での009の叫びはちょっと辛い。あと大人の女として描かれるフランソワーズについてはアンビバレンツな感情が湧いてきたが、まあ仕方がない。彼女が58歳という設定の押井作品が見たかったかも。
1800円払って見た009で複雑な心境に陥ったあと、500円で見た近代フィルムセンター文化事業の1本、「ニッポン無責時代」は涙が出るほど嬉しい作品だった。1962年作で、当然リアルタイムでは見ていないが、おそらく70年前後、中学か高校の頃までにはテレビかリバイバルで見ていたような記憶がある。植木等をはじめ50年前のクレージーキャッツの面々の若いこと。社長室で端唄を口ずさむ田崎潤が最高に可笑しい。8頭身以上が当たり前の今の目からすれば、ここに出てくる若い女の子はみんなちんちくりんだが、愛らしさはよくわかる。タイトル通り時代の勢いがストレートに伝わってくる。
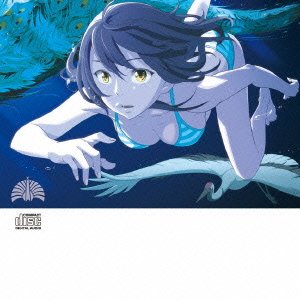 年内はもうCDを買わなくていいかといっていたら、何となく買い控えていた東京事変のラスト作『深夜枠』が聴きたくなって買ってしまう。鶴と孔雀を従えて水中を泳ぐアニメ絵のビキニ美少女がジャケットで、なんだかなあと歌詞カードを取り出したらそっちはトップレス。轟音イントロから英語が飛び交うトラックにあまり心は躍らず、半分も行かないうちにうたた寝してしまう。気がついたら鳴っていたのは後半の「Dynamite」という短い英詞唄。ブレンダ・リーを思い浮かべるのが、正しい年寄りだろうなあ。浮雲がカントリー系のフックを多用することもあるのかな。最初から聴き直すと割と面白く聴けたので良しとしよう。バーンスタインのマーラーは残すところあと1枚、第10番のアダージョと「子どもの不思議な角笛」のみ。たぶん当分聴かない。ゼルキンのベートーヴェンは「熱情」から「告別」とういう所謂中期の傑作というところ。久しぶりに聴くとピアノ協奏曲のカデンツァみたい。シューベルトは歌詞カードをダウンロードした所で、そこから前に進まない(だからなぜ買った)。
年内はもうCDを買わなくていいかといっていたら、何となく買い控えていた東京事変のラスト作『深夜枠』が聴きたくなって買ってしまう。鶴と孔雀を従えて水中を泳ぐアニメ絵のビキニ美少女がジャケットで、なんだかなあと歌詞カードを取り出したらそっちはトップレス。轟音イントロから英語が飛び交うトラックにあまり心は躍らず、半分も行かないうちにうたた寝してしまう。気がついたら鳴っていたのは後半の「Dynamite」という短い英詞唄。ブレンダ・リーを思い浮かべるのが、正しい年寄りだろうなあ。浮雲がカントリー系のフックを多用することもあるのかな。最初から聴き直すと割と面白く聴けたので良しとしよう。バーンスタインのマーラーは残すところあと1枚、第10番のアダージョと「子どもの不思議な角笛」のみ。たぶん当分聴かない。ゼルキンのベートーヴェンは「熱情」から「告別」とういう所謂中期の傑作というところ。久しぶりに聴くとピアノ協奏曲のカデンツァみたい。シューベルトは歌詞カードをダウンロードした所で、そこから前に進まない(だからなぜ買った)。
 西崎憲『飛行士と東京の雨の森』は刊行された時に気がつかなかった1冊。読んでみると気がつかなかったことがなんとなく正しいような、儚げな印象をもたらす物語集だった。「理想的な月の写真」から最後の「奴隷」まで中央に置かれた「淋しい場所」というタイトルに代表されるように静寂が漂う。作中で音楽が鳴っていることが多いのだが、たとえエレキ・ベースが鳴り響こうとも寂しさの感触がつきまとう。エンターテインメントが作品から身を引こうとしているような静けさだ。
西崎憲『飛行士と東京の雨の森』は刊行された時に気がつかなかった1冊。読んでみると気がつかなかったことがなんとなく正しいような、儚げな印象をもたらす物語集だった。「理想的な月の写真」から最後の「奴隷」まで中央に置かれた「淋しい場所」というタイトルに代表されるように静寂が漂う。作中で音楽が鳴っていることが多いのだが、たとえエレキ・ベースが鳴り響こうとも寂しさの感触がつきまとう。エンターテインメントが作品から身を引こうとしているような静けさだ。
 大森望もSFMの紹介でもこれから読むのもいいんじゃないかと書いていたので、2作目を積ん読したまま、籐真千歳『スワロウテイル序章/人工処女懐胎』に手を出した。2作目が積ん読になったのは、作品世界の基本設定に釈然としないものを感じたせいだったが、この中編集は勢いだけで読ませてしまう力があった。まあ、表面的にはラノベ風女子学園モノだから、ノリの良さが気にならないということもあるかも。SFとしての思考実験も結構うまくできていて、アシモフ3原則の読み換えも魅力がある。等級思考は今作でもピンと来ないけれど。
大森望もSFMの紹介でもこれから読むのもいいんじゃないかと書いていたので、2作目を積ん読したまま、籐真千歳『スワロウテイル序章/人工処女懐胎』に手を出した。2作目が積ん読になったのは、作品世界の基本設定に釈然としないものを感じたせいだったが、この中編集は勢いだけで読ませてしまう力があった。まあ、表面的にはラノベ風女子学園モノだから、ノリの良さが気にならないということもあるかも。SFとしての思考実験も結構うまくできていて、アシモフ3原則の読み換えも魅力がある。等級思考は今作でもピンと来ないけれど。
 長谷敏司に移ろうかと思ったら、10ページ読んだだけでスワロウテイルと続けて読むモノじゃないなと感じて、芦辺拓『スチームオペラ 蒸気都市探偵団』に鞍替え。それにしてもラノベ/ジュヴナイルしか読むモノがないのかっ。とかいいつつ、スチームパンクを見事に由緒正しいご都合主義ジュヴナイル・パスティーシュとしてつくりかえた作者はなかなかの腕前だ。冗談極まる手品で落とすのも大したもの。しかし、何より1958年大阪府生まれ、同志社大学卒という作者紹介にビックリした。
長谷敏司に移ろうかと思ったら、10ページ読んだだけでスワロウテイルと続けて読むモノじゃないなと感じて、芦辺拓『スチームオペラ 蒸気都市探偵団』に鞍替え。それにしてもラノベ/ジュヴナイルしか読むモノがないのかっ。とかいいつつ、スチームパンクを見事に由緒正しいご都合主義ジュヴナイル・パスティーシュとしてつくりかえた作者はなかなかの腕前だ。冗談極まる手品で落とすのも大したもの。しかし、何より1958年大阪府生まれ、同志社大学卒という作者紹介にビックリした。
 近所の本屋で手に入らなかったので、シネコンへ行った帰りに買ってきた小田雅久仁『本にだって雄と雌があります』は、前評判が耳に入ってしまっていたので危惧しつつ読み始めたが、杞憂であった。いやあ、これは第2のデビュー作というか、ファンタジーノベル大賞はコレで取るべきだったかも。戦時中の話がやや重力が違うとはいえ、ほぼ満点のエンターテインメント。この内容が300ページちょっとに収まっているという驚き。小松左京のコテコテと筒井康隆のスキゾをどろどろに混ぜ合わせて、モリミー印のウォーターで薄めたような凄いペーソス。今年の日本SFベスト候補は高水準だなあ。
近所の本屋で手に入らなかったので、シネコンへ行った帰りに買ってきた小田雅久仁『本にだって雄と雌があります』は、前評判が耳に入ってしまっていたので危惧しつつ読み始めたが、杞憂であった。いやあ、これは第2のデビュー作というか、ファンタジーノベル大賞はコレで取るべきだったかも。戦時中の話がやや重力が違うとはいえ、ほぼ満点のエンターテインメント。この内容が300ページちょっとに収まっているという驚き。小松左京のコテコテと筒井康隆のスキゾをどろどろに混ぜ合わせて、モリミー印のウォーターで薄めたような凄いペーソス。今年の日本SFベスト候補は高水準だなあ。
 技術評論社の本はどうしてこんなに高いのかと思いつつ、買って読んだ瀬名秀明『SF作家 瀬名秀明が説く! さあ今から未来についてはなそう』はB6ソフトカバーで、ゆるい字組で、エッセイで、200ページもないから読むのに2時間も掛からない。それでも、1500円もする、のだ。内容に文句はないけどね。
技術評論社の本はどうしてこんなに高いのかと思いつつ、買って読んだ瀬名秀明『SF作家 瀬名秀明が説く! さあ今から未来についてはなそう』はB6ソフトカバーで、ゆるい字組で、エッセイで、200ページもないから読むのに2時間も掛からない。それでも、1500円もする、のだ。内容に文句はないけどね。
瀬名秀明はSFファンダムからSF作家として認められないままSF作家クラブの会長をやっていると、今でもボヤいているけれども、コレはもう一種のトレードマークですね。茅田砂湖の時も話題になったSFファンダムの一部の声がそんなに気になるのかしら。まあ、瀬名秀明にSFのファニッシュは感じられないし、茅田砂湖のファニッシュにSFを感じないこともあるけれど(ウチの奥さんは茅田作品を何十冊も抱えて読んではまた繰り返して読んでますが)、そんなのはどういう風にSFを読んできてどういう風にSF的感性を形成したか、人によりけりな話だがなあ。この本を読むと瀬名秀明のパースペクティヴは、小松左京や石原藤夫や堀晃たちが持っている従来のSF的視点とは別の視点に立って存在しているということを感じる。それは瀬名秀明の書くSFが以前に読み慣れたSFと違う理由だろう。でも、『小説新潮』の「SFルネッサンス」特集では、ダントツで今のSFを書いているんだから、何の問題もないのではないでしょうか。
 ちょっと前に佐々木中の現代フランス思想紹介本を読んだように、いまでも時折その手の本を読んでしまう。最近ミッシェル・フーコー『知の考古学』が文庫になったので読んでみた。現代といったって既に40年以上も前の作品で、フーコー自身が世を去って30年近く経つわけだから、もはや「現代」はその時代の固有名詞ですね。
ちょっと前に佐々木中の現代フランス思想紹介本を読んだように、いまでも時折その手の本を読んでしまう。最近ミッシェル・フーコー『知の考古学』が文庫になったので読んでみた。現代といったって既に40年以上も前の作品で、フーコー自身が世を去って30年近く経つわけだから、もはや「現代」はその時代の固有名詞ですね。
佐々木作品ではヤラレ役を振られていたフーコーだけど、この本を読むと自ら憎まれ役を買って出ているらしいことが分かる。話の組立がけっこうコワモテなのである。フーコーは、それまでの個別テーマの著作(『狂気の歴史』も『臨床医学の誕生』も『言葉と物』も読んでないのでほんとにそうかは知りませんが)を成すにあたって、膨大な「言説」に身をさらしたらしく、よく分からないが、その経験から何かを見つけたらしいのである。そこでフーコーは彼のオリジナルな定義による「言表/言説形成」、「ポジテヴィテ」、「アルシーヴ」などにより論を立て、最後に彼独特の「考古学」にたどり着く、って全然そんな話じゃないような気もするけれど、まあ気にしない。フーコーが憎まれ役なのは、ここに出てくる文章の大半に「ではなくて」「ではない」「そうではなくて」という否定形ばかりが使われているからでもある。フーコーが否定に使う対象は読み手に分かりやすく、最後に決めに使われる「である」の中身はさっぱりわからないのだから、お手上げである。何をエラそーにしてんだよ、テメーは、である。しかもフーコーは「結論」で自分が断言したことを「構造主義者」に対して言い訳してるもんだから、余計に攻撃されやすい(いいキャラですね)。門外漢が関知する所ではないけれども。
この本を読んで何を思い浮かべたかというと「いわゆるパラダイムの形成と変換を外からではなく内側で観察しようとしているように見える」ということか。思考の過程を外部に頼らず記述することを「哲学」と呼ぶなら、この本は確かに「哲学」書だ。
 文庫になった村上春樹『夢を見るために 毎朝僕は 目覚めるのです−村上春樹インタビュー集 1997−2011』は、長期にわたるとはいえ、既にかなり安定した著者の受け答えで統一されている1冊。基本的に外国のインタビュアーに対する受け答えはスッキリしているのに対し、国内で行われたものはちょっとわかりにくい。同じ様な質問には同じ様な答えしかないというのは立派だが、何回も読まされるとちょっと疲れます。
文庫になった村上春樹『夢を見るために 毎朝僕は 目覚めるのです−村上春樹インタビュー集 1997−2011』は、長期にわたるとはいえ、既にかなり安定した著者の受け答えで統一されている1冊。基本的に外国のインタビュアーに対する受け答えはスッキリしているのに対し、国内で行われたものはちょっとわかりにくい。同じ様な質問には同じ様な答えしかないというのは立派だが、何回も読まされるとちょっと疲れます。
 村上春樹と同じ新刊文庫棚にあった城戸久枝『あの戦争から遠く離れて 私につながる歴史をたどる旅』は、単行本でもちょっと気になっていたのだけれど、とりあえず買わなかった1冊。でも今回読んでよかった。
村上春樹と同じ新刊文庫棚にあった城戸久枝『あの戦争から遠く離れて 私につながる歴史をたどる旅』は、単行本でもちょっと気になっていたのだけれど、とりあえず買わなかった1冊。でも今回読んでよかった。
中国大陸での、特に「満州」での敗戦に伴う混乱がもたらした悲劇は、これまでも多く書かれてきたけれど、当方は海軍がメインなのであまり手は出すことはない。仕事で必然的に読んだり、インタビューしたりする中で「満州」や「シベリア」には必ず当たってしまうんで、あまり深く突っ込みたくない所ではある。それでもこのノンフィクションは面白そうだという感触があった。実際に読んでそれを確かめられたのだから、満足である。
これはのちにいわゆる「中国残留孤児」呼ばれるようになる立場にありながら、早期に帰国を果たした父を描くことが自らの使命と定めたことにより、「ある歴史の娘」であることを自覚した女性の「生涯に1度だけしか書けない」作品だ。内容の豊かさに感心させられる一方、その文章が20代でコントロールできたことにも驚く。欲張りすぎともいえるが、その欲張りが作品を大きくしたことも間違いない。「大東亜戦争」が何だったのかは、おそらく言葉にならないと思うが、この作品は、たとえささやかでも、その片鱗を伝えることに成功したのだ。
THATTA 295号へ戻る
トップページへ戻る
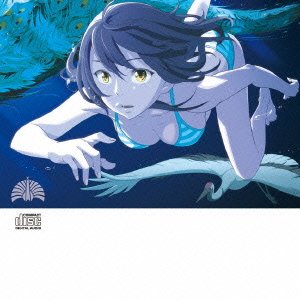 年内はもうCDを買わなくていいかといっていたら、何となく買い控えていた東京事変のラスト作『深夜枠』が聴きたくなって買ってしまう。鶴と孔雀を従えて水中を泳ぐアニメ絵のビキニ美少女がジャケットで、なんだかなあと歌詞カードを取り出したらそっちはトップレス。轟音イントロから英語が飛び交うトラックにあまり心は躍らず、半分も行かないうちにうたた寝してしまう。気がついたら鳴っていたのは後半の「Dynamite」という短い英詞唄。ブレンダ・リーを思い浮かべるのが、正しい年寄りだろうなあ。浮雲がカントリー系のフックを多用することもあるのかな。最初から聴き直すと割と面白く聴けたので良しとしよう。バーンスタインのマーラーは残すところあと1枚、第10番のアダージョと「子どもの不思議な角笛」のみ。たぶん当分聴かない。ゼルキンのベートーヴェンは「熱情」から「告別」とういう所謂中期の傑作というところ。久しぶりに聴くとピアノ協奏曲のカデンツァみたい。シューベルトは歌詞カードをダウンロードした所で、そこから前に進まない(だからなぜ買った)。
年内はもうCDを買わなくていいかといっていたら、何となく買い控えていた東京事変のラスト作『深夜枠』が聴きたくなって買ってしまう。鶴と孔雀を従えて水中を泳ぐアニメ絵のビキニ美少女がジャケットで、なんだかなあと歌詞カードを取り出したらそっちはトップレス。轟音イントロから英語が飛び交うトラックにあまり心は躍らず、半分も行かないうちにうたた寝してしまう。気がついたら鳴っていたのは後半の「Dynamite」という短い英詞唄。ブレンダ・リーを思い浮かべるのが、正しい年寄りだろうなあ。浮雲がカントリー系のフックを多用することもあるのかな。最初から聴き直すと割と面白く聴けたので良しとしよう。バーンスタインのマーラーは残すところあと1枚、第10番のアダージョと「子どもの不思議な角笛」のみ。たぶん当分聴かない。ゼルキンのベートーヴェンは「熱情」から「告別」とういう所謂中期の傑作というところ。久しぶりに聴くとピアノ協奏曲のカデンツァみたい。シューベルトは歌詞カードをダウンロードした所で、そこから前に進まない(だからなぜ買った)。






