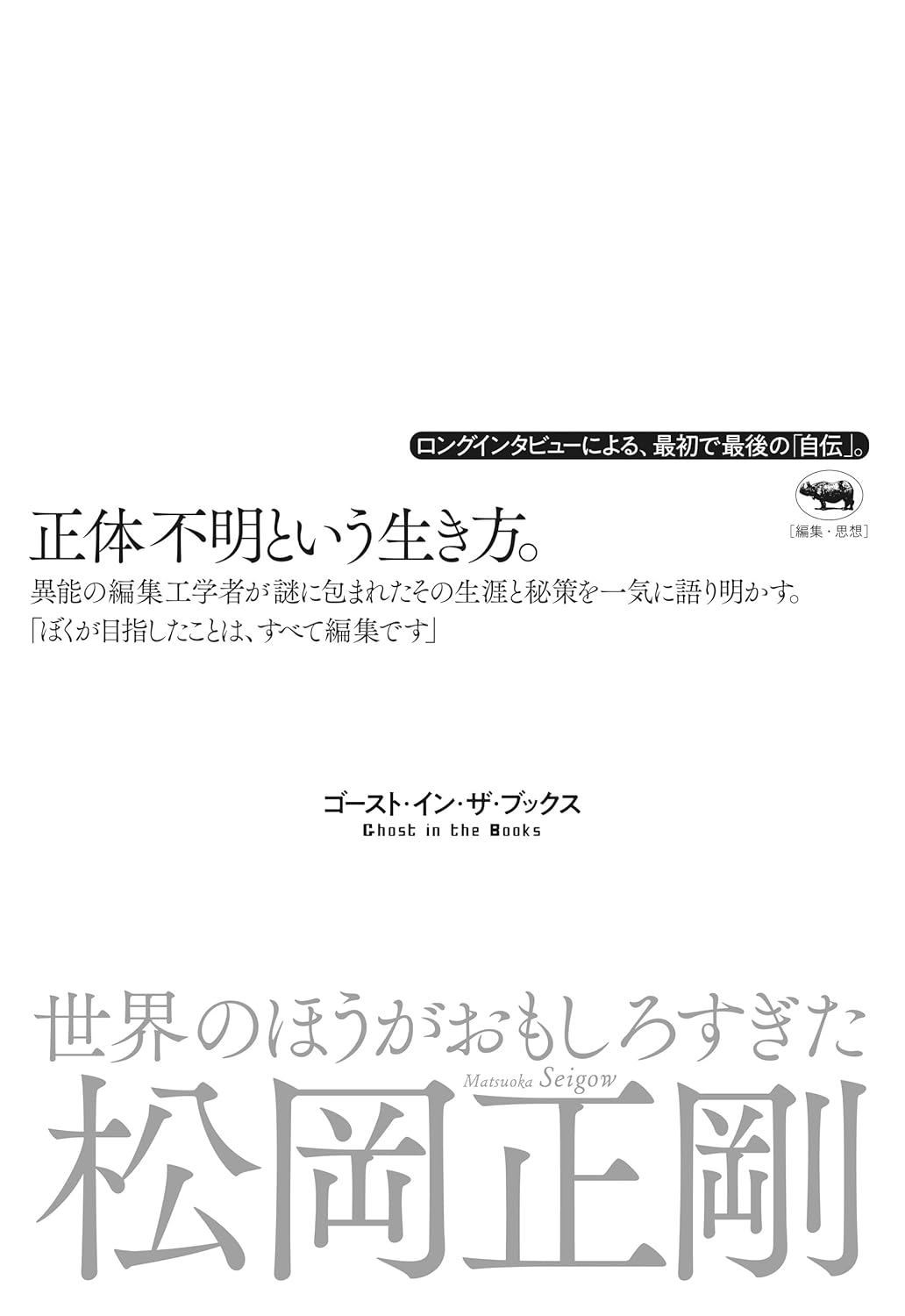これまでもたびたび言及してきた、電気も上下水道も止めてあるオンボロアパートに詰め込んだオヤジのキリスト教と哲学関係書を、広島の古本屋を呼んでついに引き取ってもらった。と、書ければ良いのだけれど、段ボール箱で24、5箱分あった内、古本屋が持って帰ったのはたった8箱分だった。お値段にして2万円。ひと箱分が2500円相当というのが高いのか安いのか分からないけれど、タダでもいいからもうちょっと持って帰って欲しかった。
プラトンとアリストテレスの全集は揃いを確かめて即箱に入れたけれど、でもまだピカピカの西田幾多郎全集には手を出さず。さすがにパスカル3巻本全集は箱に入れたけど。マルセルやヒルティやヤスパースの著作集は古くて箱が茶色に変色していることもあって無視。
キリスト教関係の全集・著作集では、オヤジが本を読めなくなったあとに完結したので全巻揃いではない(それでも30冊くらいある)フランシスコ会訳聖書や不揃いの『聖書外典』とかは箱に入れていた。アウグスチヌス著作集も入れてたなあ。そういえば『黄金伝説』4巻本も。大量にある内村鑑三とその弟子たちの全集や著作集には見向きもしない。ただし岩波から最後に出たソフトカバー版内村鑑三選集全9巻だけは箱に入れた。あと大型本はまったく売れないので持って帰れないと云っていた。B4判の『シャガールの聖書』とかA3判のルオー『受難』それに講談社の『図説大聖書』全7巻(定価68,000円)とか白川義員のキリスト教関連大型写真集などみんな残していった。
キリスト教関係の単著類では、関根正雄の『詩編注解』とか不揃いの外典にギリシャ語の新約聖書関係とかスウェデンボルグの著作類。ビックリしたのは、キリスト教関係のクセジュ文庫を持って帰ったこと。まあ、古本屋の眼鏡にかなった本がまた誰かの手に渡ると良いけど。
残った本はボロアパートを崩すときに処分するしかないかなあ。当方が集めた本はまだ50箱以上あるんだけど。
前号の「イギリス旅行記」も相変わらず誤字誤植が多くて申し訳ないのだけれど、2点だけ釈明を書いておこう。
ひとつは、元英連邦軍兵士Wilfさんが91歳なのか90歳なのか。これは年始めのメールに今年は91歳になると書いてあったので、てっきり91歳になったものと思い込んでそう書いていたのだけど、11月初めのメールで、12月生まれと云うことが判って直しかけてそのままになったところが残ったもの。と云うことで、前号の時点では90歳でした。
もうひとつは元教会の床の写真に付けたキャプションの「墓銘碑」。コレはもちろん「墓碑銘」が正しいのだけれど、半世紀あまり前に『クリムゾン・キングの宮殿』の国内盤が出て「エピタフ」を聴いたときに、なぜか「墓銘碑」と覚えてしまったために、いまだにそのように打ってしまうクセがあるのです。「シュミレーション」みたいなものですね。
さて読んだ本の感想に移ると、
「イギリス旅行記」に書いた手前、せっかくなのでエジンバラで買ったR.F.クァン編『The Best American SF and Fantasy 2023』関連の話題で始めよう。と云ったって読んだわけではありません。
 フィルム・アート社から出た税込み5000円超の黒人作家によるホラー・アンソロジー、ジョーダン・ピール編『どこかで叫びが ニュー・ブラック・ホラー作品集』は、『本の雑誌』10月号山岸真さんの新刊SF出版情報欄「SF新世紀」でトップに紹介されたにもかかわらず、なぜかその後SF界からの書評が少なかった1冊。『SFマガジン』でもホラー書評欄の最後にちょっとだけ言及があるのみで、翻訳SFやファンタジーの方では言及がなかった。
フィルム・アート社から出た税込み5000円超の黒人作家によるホラー・アンソロジー、ジョーダン・ピール編『どこかで叫びが ニュー・ブラック・ホラー作品集』は、『本の雑誌』10月号山岸真さんの新刊SF出版情報欄「SF新世紀」でトップに紹介されたにもかかわらず、なぜかその後SF界からの書評が少なかった1冊。『SFマガジン』でもホラー書評欄の最後にちょっとだけ言及があるのみで、翻訳SFやファンタジーの方では言及がなかった。
かくいう当方も買っただけで、積ん読になりそうだったところ、R.F.クァン編『The Best American SF and Fantasy 2023』をパラパラめくっていたらJohn Joseph Adams というこの年間傑作選のシリーズ編集者の名前に目が行って、巻末の注目作リストを作っているのもこのジョン・ジョゼフ・アダムズであることが判り、アダムズ君は自分が選んだ作品に毎年有名作家をゲスト/冠編集者にして年間傑作選をつくるタイプの編集者だということが分かった。
ちなみに内扉裏に2015年から出ているこのシリーズのゲスト編者が挙げられていて、ジョー・ヒル、カレン・ジョイ・ファウラー、チャールズ・ユー、N・K・ジェミシン、カルメン・マリア・マチャード、ダイアナ・ガバルドン、ヴェロニカ・ロス、レベッカ・ローンホース、で、R・F・クァンとなっている。ウーン、この編者の並びだと、ファンタジーとホラー寄りの作品選びが予想されますね。
で、『どこかで叫びが』をパラパラしてたら、最後の方に掲載作家紹介と編者紹介があって、ジョーダン・ピールの下にジョン・ジョーゼフ・アダムズの名があって、1行目から「Best American Science Fiction and Fantasyのシリーズ・エディターで」と始まり、「Wastelands、The Living Dead、A People's Future of the United States など四十冊を超えるアンソロジーの編集を担当」ときて、「ヒューゴー賞を受賞した雑誌『ライトスピード』の編集者でもあり、その姉妹誌『ナイトメア』の創刊から100号まで編集を務めた」とある。
ということで、実質的にはこれがアダムズのセレクトした作品のアンソロジーだということが分かる。なので山岸真さんが新刊紹介のトップに持ってきたのも当然、これは最新のアメリカSF/ファンタジーを読もうという人には貴重な情報だったわけですね。
ところが、この分厚いアンソロジーのそれなりに長い訳者解説(ハーン小路恭子)には、「近年ホラー映画ジャンルで評価の高いジョーダン・ピールによる序文に加え、SF、ファンタジー、スペキュレイティブ・フィクションと多ジャンルを横断しつつ、アフリカ系の経験に根ざした恐怖の表象を共通項として持つ、計十九のブラック・ホラー作品が収録されている」と、ピールと収録作家と作品への言及はあるものの、アダムズ君は無視されているのでした。
収録作家を見てみよう。N・K・ジェミシン、レベッカ・ローンホース、キャドウェル・ターンブル、レズリー・ンネカ・アリマー、ヴァイオレット・アレン、エリン・E・アダムズ、タナリーヴ・ドゥー、ジャスティン・C・キー、エスラ・クレイダン・ダニエルズ、ンネディ・オコラフォー、L・D・ルイス、ナロ・ホプキンスン、モーリス・ブローダス、リオン・アルミカー・スコット、ニコール・D・スコニアーズ、チェシャ・パーク、テレンス・テイラー、P・ジェリ・クラーク、トチ・オニェプチの19名。
この内、ターンブル、ドゥー、キー、ルイスの4人が『The Best American SF and Fantasy 2023』巻末に収録された2022年の注目作の作者に入っている。なお、収録作20作の内に『どこかで叫びが』収録作家の作品は選ばれていないが、そこには日本でも知られたソフィア・サマター、シオドラ・ゴス、キャサリン・M・ヴァレンテ、マルカ・オールダーなどが含まれている。LGBTQや白人以外の作家が大半というこのベストSF&ファンタジーのアンソロジーには、たぶん当方のようなロートルSFファンが読んで喜びそうなものはあまり入ってないような気がする。
で、ようやく『どこかで叫びが』の収録作19編を全部読んだワケだけれど、まあ、ホラーなので各作品への言及は省略。なお、巻末のトニ・オニェプチ「オリジン・ストーリー」は舞台劇の脚本/台本。
 『どこかで叫びが』に結構時間を取られたせいか、読むのが遅くなったのが、小川哲『火星の女王』。
『どこかで叫びが』に結構時間を取られたせいか、読むのが遅くなったのが、小川哲『火星の女王』。
地元の書店では、デビュー10周年フェアとやらで全作品が棚面陳でディスプレイされていた。基本的には新作を出す度に何らかの賞を取っているような作家ではあるわけで、当方も毎回期待して新作を手に取っていると云ってもいい。
そういう期待があると、作者デビュー10周年、早川書房創立80周年記念作品で、なおかつ最初からNHKの放送100周年ドラマ原作と帯に謳われているのは、ちょっとイヤな予感がした。
実際に読み始めると、商業的投資対象としての火星への植民が実現し、10を超えるコロニーと万単位の人類が居住するまでになったが、結局商業的には不採算であることが判明、投資企業は植民者の地球帰還を推進しようとしていた・・・というかなり地味目だけどありそうな設定で、そこへ量子論的同時収縮を起こす火星特産の鉱物の存在が明らかになり、その光速に制限されない通信を可能にする鉱物の利益独占を前提に、火星独立をあおる火星屈指の富豪の思惑が引き起こすドラマが物語をドライブする。
地球側の人物も含めて数名の主要キャラが織りなす多視点で語られる、そのナラティヴはスムースで、いかにも映像化を前提とした割り切りが感じられるキャラ造りも分かりやすい。作者はこの物語にハードSFとしての側面も一般的なレベルでの分かりやすい形にして落とし込んでいる。ただ、そのなだらかさが、やや物足りない感じを生じさせている原因だろう。
なお、表題の「火星の女王」は、投資企業側の重役の娘で、10歳くらいで火星にいるときに事故のため視力を失った主要キャラの女性が、いつの間にか火星独立運動のシンボルに祭り上げられることから来ている。彼女の立ち位置の両義性は、彼女を事件に巻きこむことになる大富豪のキャラクターにも用いられていて、そこら辺はドラマ化の主要なポイントになるかも知れない。
ニール・スティーヴンスン『ターミネーション・ショック』は、キム・スタンリー・ロビンスン『未来省』を出したパーソナルメディアからの新刊。『未来省』同様、解説の坂村健が強力に押すCli-Fiというタイプの、SFとしては現実にコミットしすぎていて情報小説の印象が強い1冊。650ページ以上ある。
スティーヴンスンの博覧強記は、テキサス・オランダ・インドカシミールにニューギニアを舞台にして多数の登場人物が躍動させている。なおかつ、要所要所で中国人の狂言回しをかませて中国というプレイヤーも舞台を動かす力であることも忘れない。
テキサスに巨大な貨物打ち上げ施設を作って、大量の硫黄を大気圏に送り込み、散布することで地球温暖化を防ぐというメイン・アイデアは、巻末解説でも示されているように費用を度外視すれば、現実に可能だろうと思わせる。もしそれが実行に移されたときに予想外の現象が発生しても止められない(ターミネーション・ショック)という可能性も含めて、この作者の思考実験はとても面白く読める。
ただ、当方は読んでいるうちに登場人物が女性も含めてスーパーマンばかりなのに疑問がわいてきて、やや興を殺がれるような気分に襲われた。この点は解説で、ローマ神話の神々のキャラクターが各登場人物に割り当てられていると謎解きをしてくれているので、自分の読後感に納得したのだけれど、それでも物語の後半では登場人物たちへの共感が失われたことは残念だった。ま、スティーヴンスンの最近作はちょっと肌に合わないところがあるので、その点も影響したかも。
昔出たベン・ボーヴァ『天候改造オペレーション』のタイトルが頭に浮かぶけれど、この半世紀余りで、SFとしての機能に変わりはなくても、あまりにも現実っぽくなってしまったと感じられるのがイヤですね。
 |
 |
前作がぶっ飛んだ設定で面白かった『鋼鉄紅女』の続巻、シーラン・ジェイ・ジャオ『天空龍機 鋼鉄紅女2』が出たので読んでみた。
前作は、どうやらこの中華世界は過去に植民された惑星であることが提示され、天庭に住むという神が直接ヒロインの行動に介入したところで終わっていた。
今作はその結末から直接の続編で、ヒロインと彼女が復活させた200年前の伝説の皇帝が、最終的に天庭に乗り込んで神々と戦おうとするのが大枠の設定。
しかし、ちょっと変わっているのが、復活した皇帝や側近の女官などがヒロインに労働者や民衆こそが社会の主体であるべきという社会主義思想を説いて、それまでの封建的で支配階級が暴利をむさぼる社会に、皇帝が上からの社会主義革命を起こすというところ。もともとフェミニズム反骨精神が旺盛なヒロインもあれこれと悩みながら上からの革命に協力する。そこに反革命派が割り込んで内戦にまで発展、ヒロインは皇帝の乗機である黄龍や他の霊蛹機と呼ばれる変形型巨大ロボットを操って大活躍する。
ここまでが物語の3分の2で、前作同様のヒロインのハッチャケぶりが楽しめるのだけれど、問題は最後の3分の1で、本当に天庭にたどり着いて神に戦いを挑もうとする本来の話に入るのだが、舞台が天庭(宇宙コロニー)に移った途端、物語がありふれたスペースオペラに転じてしまい、せっかくの中華世界のエキゾチシズムが見慣れた物語に取って代わってしまう。まあ、そういう設定で始めた話なので、予定調和ではあるのだけれど、それまでのハッチャケぶりからすると物足りない結末と思われる。
それにしてもこのヒロインの男選びの基準がわからん。
 竹書房でSFが復活というから、てっきり文庫で出るのかと思っていたら、四六判ソフトカバーだったのが、ジェイムズ・モロウ『ヒロシマをめざしてのそのそと』。
竹書房でSFが復活というから、てっきり文庫で出るのかと思っていたら、四六判ソフトカバーだったのが、ジェイムズ・モロウ『ヒロシマをめざしてのそのそと』。
大分以前の『SFマガジン』に分載されていたのは覚えているけれど、読んだ覚えはない。まさかこんな内容だったとは。
1984年、ホテルの一室で、絶望的な気分を感じて自殺まで考えている過去の特撮映画で人気を博した男が回顧録を書いている。その内容は、太平洋戦争末期にアメリカ海軍が陸軍の新兵器(原爆)開発に対抗して、日本の使節団が震え上がるだろう本物の大怪獣を育成するも、あまりの凶暴さに使用をあきらめて、着ぐるみ怪獣特撮映画に切り替え、その中の人として抜擢されたことが主筋となる。
日本の怪獣映画を含め、いかにも特撮映画の大ファンであろう作者が書いた、このパロディックでユーモラスな着ぐるみ怪獣映画製作の思い出話が、最後にタイトルの意味が明らかになるエピソードにたどり着いたとき、「ヒロシマ」のすぐそば(呉海軍は調査隊と救援隊を出し、大勢の市民が入市被曝)に住んでいる者として、この作者の真意にうなだれてしまうのだった。
翻訳者の内田昌之さんも訳者あとがきで、この作品の翻訳を『SFマガジン』で連載中に父を失ったことやその父の戦時中の体験を語っており印象に残る。
ちなみに、当方は最初にこのタイトルをみて「広島を目指しての、その外」と読んでしまい、変なタイトルだなあと思ったことは秘密だ(←表紙に大きくShamblingって書いてあるだろうが)。
 |
 |
同じように2011年から翌年にかけて『SFマガジン』に連載されながら単行本化に至らず、今頃になって河出文庫から出たのが、山本弘『輝きの七日間』上・下。
なんで出なかったのかは、下巻巻末の大森望解説で説明されているが、あくまでも作者側の言い分なので、当時の早川書房編集部がどう考えていたのかは不明。
しかし、実際に読んでみると、早川書房側が単行本化を見送ったのもうなずける内容であったことは残念だった。
この作品は作家山本弘の信念を小説として書いたものであって、SFとしての範疇からは外れていると思わせるものになっている。小説で「正しい道」を説いてしまえば、書いた者が「神様」になってしまう。「認識の拡大」や「情報の高度化」が「正しい道」を示すという考え方をSF的アイデアとして使ったいうのなら、それはそれで面白いものができると思うけれど、ここにあるのは生な願望(それ自体は尊いが)でしかない。
人類がフィクションを作り自らそれを信じることで文明を発展させてきたこと(言葉を現実と取り違える性質)を否定するような信念になぜ山本弘が囚われたのか、SFもまたその範疇にあることを忘れたかのような書きっぷりは悲しい。「善」や「正しさ」もまた「文化概念」のひとつにすぎないことは、これまでの人類の歴史を見れば明らかだろう。 とはいえ、スティングも「History will teach us nothing」と歌っているし、Sooner or laterで山本弘の願いが叶うことを祈ろう。
 これまで買って読んだことがなかったけど、『ナイトランド・クォータリイ Vol.40』にゼラズニイの翻訳が載っているということで買ってみた。序でに掲載された翻訳作品も読んでみた。何しろほかにムアコックやイアン・ワトソンにシーベリー・クインおまけにフリオ・コルタサルの詩が1編載っているんだからまあ、読んでみようかという気にはなる。その他にマンリー・ウェイド・ウェルマン、オスカル・パニッツァにアンジェラ・スラッターと盛り沢山。
これまで買って読んだことがなかったけど、『ナイトランド・クォータリイ Vol.40』にゼラズニイの翻訳が載っているということで買ってみた。序でに掲載された翻訳作品も読んでみた。何しろほかにムアコックやイアン・ワトソンにシーベリー・クインおまけにフリオ・コルタサルの詩が1編載っているんだからまあ、読んでみようかという気にはなる。その他にマンリー・ウェイド・ウェルマン、オスカル・パニッツァにアンジェラ・スラッターと盛り沢山。
奥付を見たら、あの岡和田晃が編集長と云うことで、この誌面でも八面六臂の活躍振り。コルタサルを訳していたのも彼だった。
この号の特集テーマは「一期一会のモノガタリ 異類との邂逅」ということで、そのような作品を集めている。とはいえ中にはそれが作品のテーマかと疑われるモノもあるけれど。
その点ロジャー・ゼラズニイ「リルの馬たち」は、叔父に呼ばれて湖畔の家にやってきた甥の視点から表題の「馬」を引き継ぐ話で、この馬は「チャリオット」と呼ばれる乗物を牽いて湖上を征く「馬」だった・・・。ゼラズニイとしては後期の短篇で、訳者はクトゥルー神話のこだまを感じているようだ。何の事件も無いに等しいが、それでもゼラズニイらしさが感じられる1編。
マイクル・ムアコック「尋常ならざるキリスト教徒~遙かなるマグリブの物語」は、エターナル・チャンピオン世界のエルリックものをさらに一ひねりしたようなエピソードで、フォン・ベックも出てくる独立した短篇とはおもえない1編。でも雰囲気はムアコックらしい懶怠な魅力がある。バックナンバーを見ると結構ムアコックが訳されている。
マンリー・ウェイド・ウェルマン「松の民」は、話が単純すぎて驚くことは出来ないけれど、悪くはない。仁賀克雄の「幻想と怪奇」シリーズに入っていそうな1編。
シーベリー・クイン「クレセント・テラスの男」は、医者で探偵の「ジュール・ド・グランダン」もの。今回は相棒役の医者トロウブリッジと夜にバスを待っていると、若い女が助けを求め走ってきて、ふたりが抱き留めると血を流しており、ミイラ男みたいなのが追ってきていた・・・という始まり。かなり怪しい謎解きが楽しめる。
イアン・ワトスン「異星人がボトル詰めのために駐留するとき」は、2018年にアナログ誌に掲載されたと云うから、最近のワトスンの作風を示しているのかも知れない。タイトル通りの話が女性の視点で語られる。鬱になりそうな話でかなり不気味。訳者は大和田始。
オスカル・パニッツァ「ブレネリのゲルトリ-チューリッヒの一事件」は、解説によると作者がドイツからスイスに脱出する時の経験を反映したものらしく、国境を抜けて人里を離れた場所にあった家にたどり着いたとき、ブレネリという名の、語り手にはヴィーナスとも目される女性の出迎えを受けて、三姉妹が住むこの家に招き入れられて一夜を過ごす話。話者のエロチックな観察が横溢しているが、結局女性とは寝所を共にしない。自作解説でこれは時代の制約だと作者が言い訳しているのが可笑しい。
ちなみに「ブレネリ」はスイスの童謡「おお、ブレネリ」に出てくるブレネリと同じ普通の女性名で「ゲルトリ」はスイス方言で「庭」を意味するとのこと。
アンジェラ・スラッター「赤い糸束」は、獣姦変身込みの「赤頭巾ちゃん」。岡和田晃の解説にもあるように、アンジェラ・カーターのスタイルを思わせる。
コルタサル「音楽 ムシカ」は、4行3連と3行1連からなる短い詩。訳は岡和田晃。
 11月末の刊行だったけれど、買ってすぐに読んでしまったのが酉島伝法『無常商店街』。収録3篇中、表題作と第2作「蓋互山、蓋互山」が『紙魚の手帳』に掲載済みだったけれど、当方はリアルタイムで読んでないので、まったくの初読。
11月末の刊行だったけれど、買ってすぐに読んでしまったのが酉島伝法『無常商店街』。収録3篇中、表題作と第2作「蓋互山、蓋互山」が『紙魚の手帳』に掲載済みだったけれど、当方はリアルタイムで読んでないので、まったくの初読。
冒頭の表題作の始まりは、翻訳を仕事にしている弟が、何の調査をしているのかよく分からない研究所の所員である姉から留守にするからネコの面倒を見てくれといわれ、指定された「浮図市」の「掌紋町」に行き、姉が留守にしたアパート「仏眼荘」の一室に到着、近所の散歩に出ると、姉には近づくなと云われた「無常商店街」にいつの間にか迷い込んでしまった・・・というもの。
3篇とも姉に振り回される弟の視点で語られるが、姉が関わる異様な町は毎回弟に異様な体験をもたらす。酉島伝法独特の造語が乱舞して、『奏で手のヌフレツン』を髣髴とさせる酩酊感に襲われるけれど、こちらは全体としてコメディ的な演出がされているので、酉島伝法作品にしては読みやすい気分にさせられる。
 締め切り前、最後に読み終わったのが、モロウと同時に竹書房からソフトカバーで出たサラ・ピンスカー『いつかどこかにあった場所』は、書き下ろし1編を含む12編を集めた作者の第2短編集。市田泉訳。
締め切り前、最後に読み終わったのが、モロウと同時に竹書房からソフトカバーで出たサラ・ピンスカー『いつかどこかにあった場所』は、書き下ろし1編を含む12編を集めた作者の第2短編集。市田泉訳。
巻末の訳者あとがきにある収録作紹介を参考に、各タイトルに簡単なコメントを付けておくと、
「二つの真実と一つの嘘」 2021年ヒューゴー賞・ネビュラ賞小説中篇部門受賞作。虚言癖のある女性の嘘が現実になってしまう話だが、一筋縄では行かないつくりになっている。
「われらの旗はまだそこに」 コロナ禍第1次トランプ政権下(禍)で書かれた、国旗として生身のまま掲揚される人々が愛国者であるアメリカ。
「ぼくにはよく、騒音の只中に音楽が聞こえる」 1920年代ジャズ・エイジのニューヨークの喧噪を、架空のものも含め、さまざまな有名人や有名ホテルをめぐる短いエピソードを積み重ねて、再現する。
「宮廷魔術師」 少年時代に奇術を極めたところ、本物の宮廷魔術師にスカウトされ、魔法を使う度に身体の一部を失う。暗い雰囲気のファンタジー。ヒューゴー・ネビュラ・ローカス・世界幻想文学大賞にノミネート。
「きょうはすべてが休業している」 解説によると長編の『新しい時代への歌』と同じ舞台設定の短篇とのこと。当方はもう忘れているので、パっと見には、理由の分からない何か(コロナ禍を思わせるが、解説ではカリフォルニアでのスタジアム爆破事件)のために仕事がなくなり失業した女性が、スケボーを女の子達に教えることで、自分たちの苦境をよりよいものにするために動き出すきっかけを作る話に見える。
「センチュリーはそのままにしておいた」 飛び込んだ者が帰ってこないことがある池にまつわる怪談みたいだが、視点人物の感覚はちょっと違う。掌編。
「ケアリング・シーズンズからの脱走」 理想の老人ホームを作ってそこに入ったはずなのに、経営が変わりAI診断で外出不可が覆らないことで施設に閉じ込められたパートナーを救い出すため、施設から脱出した高齢女性が、行方不明者を見つけてポイントを稼ぐ若者の操縦するドローンと遭遇する話。
「もっといい言い方」 サイレント映画時代、子どもだった語り手は姉がサイレント映画のセリフを読む訳を得たので、男声として一緒に雇われた。少年は字幕より良いセリフ案を考えついてその通り云うと字幕もそちらに変わったことに気がつき、後に脚本家を目指すきっかけとなる。この姉というのが「ぼくにはよく、騒音の只中に音楽が聞こえる」では大人になった姿で顔を出していた。実在の人物らしい。また最後にダグラス・フェアバンクスがホテルの屋上で射った矢が人に当たった話が出てくるが、これも実話とのこと。
「わたしのためにこれを覚えていて」 高齢女性画家が認知症を患った状態で、自分の回顧展を開くまでを、その女性の視点で書いて見せた1作。鬼気迫る。
「山々が彼の冠」 すべてを支配する王様のいる国で農業を営む女性の畑に、王の使いの乗物が入って数メートルの巾で作物を焼き払っていった。理由を突き止めると地面に王の肖像を描く線だという。女性は身勝手な王のワガママに策略を込めて絵柄を変えるための意趣返しを企む。
「オークの心臓集まるところ」 これは異色作。いわゆるチャットで交わされるマニア達の会話記録である。タイトルの「オーク」は鬼じゃなくてツリーの方なんだけど、このタイトルが頻出するにもかかわらず、毎回「鬼オーク」を思い浮かべてしまう。
実際はイギリスの小村に伝わるバラッドで、キングストン・トリオからグレイトフル・デッドにメタリカまでもがレパートリーにしたという有名曲(? 作者も歌っているらしい)だけど、歌詞のナゾについてはプロアマ入り乱れて議論されていた。
ということで、これはそのチャットの記録。2022年のヒューゴー・ネビュラほか4冠受賞作とのこと。
「科学的技術!」 書き下ろしの長めの中篇。相性が悪い大人の女性2人が6人の12歳ガールスカウトを率いてサマーキャンプ場で数日を過ごす。表題は誰かが科学的事実のエピソードを披露したら、次の者がそのエピソードに関連したやはり科学的に真実と思われるエピソードを話す、そしてそれをメンバー間で繰り返すゲーム。だれが科学的事実を判断するのかと思ってしまうが、大人がメンター役らしい。物語の主筋がこのタイトルを反映していると考えると、大人の女性や6人の少女達の思いや行動にささやかなファンタジーが宿っていると思われる。
全体としては、女性の物語が大半で、強い起伏はあまり用いられていないけれど、作品集としてはベストなレベルにある。
ノンフィクションは2冊。
 1冊目は筒井康隆『筒井康隆自伝』。これまでも回想録的なものを時折発表していたけど、これは作者本人が健在なうちに書かれた最後の回想だろう。もっとも1ページ33文字x15行、頭注付きで180ページもない。
1冊目は筒井康隆『筒井康隆自伝』。これまでも回想録的なものを時折発表していたけど、これは作者本人が健在なうちに書かれた最後の回想だろう。もっとも1ページ33文字x15行、頭注付きで180ページもない。
読みどころはやはり前半かなあ。幼少のころの同級生や女の子たちへの思い、中学高校時代になると演劇へ傾斜が著しくなって同志社大学でも演劇に熱中、しかし俳優を目指しながらもそちらに縁がないと悟って方向転換、SFに出会うまではここまで詳しくはこれまで書かれていなかったように思う。
もっとも個々のエピソードは虚実のあわいにあるような感じがして、たとえ地図や父母兄弟についての語りが事実確認できるものだとしても、あくまでも「作者」の「創作物」の感覚が付きまとう。
SF作家になってからのテンヤワンヤは、これまでもあちらこちらで読んできたので驚きはないのだけれど、それにしてもあの時代のエネルギーが尋常ではなかったことには、いまでも驚かされる。
日本SF第一世代といえば荒巻義雄が健在だけど、立ち位置が全く違うので、やはり60年代70年代の狂騒的な雰囲気は、筒井康隆の筆をもって描かれないといけなかったといえるだろう。
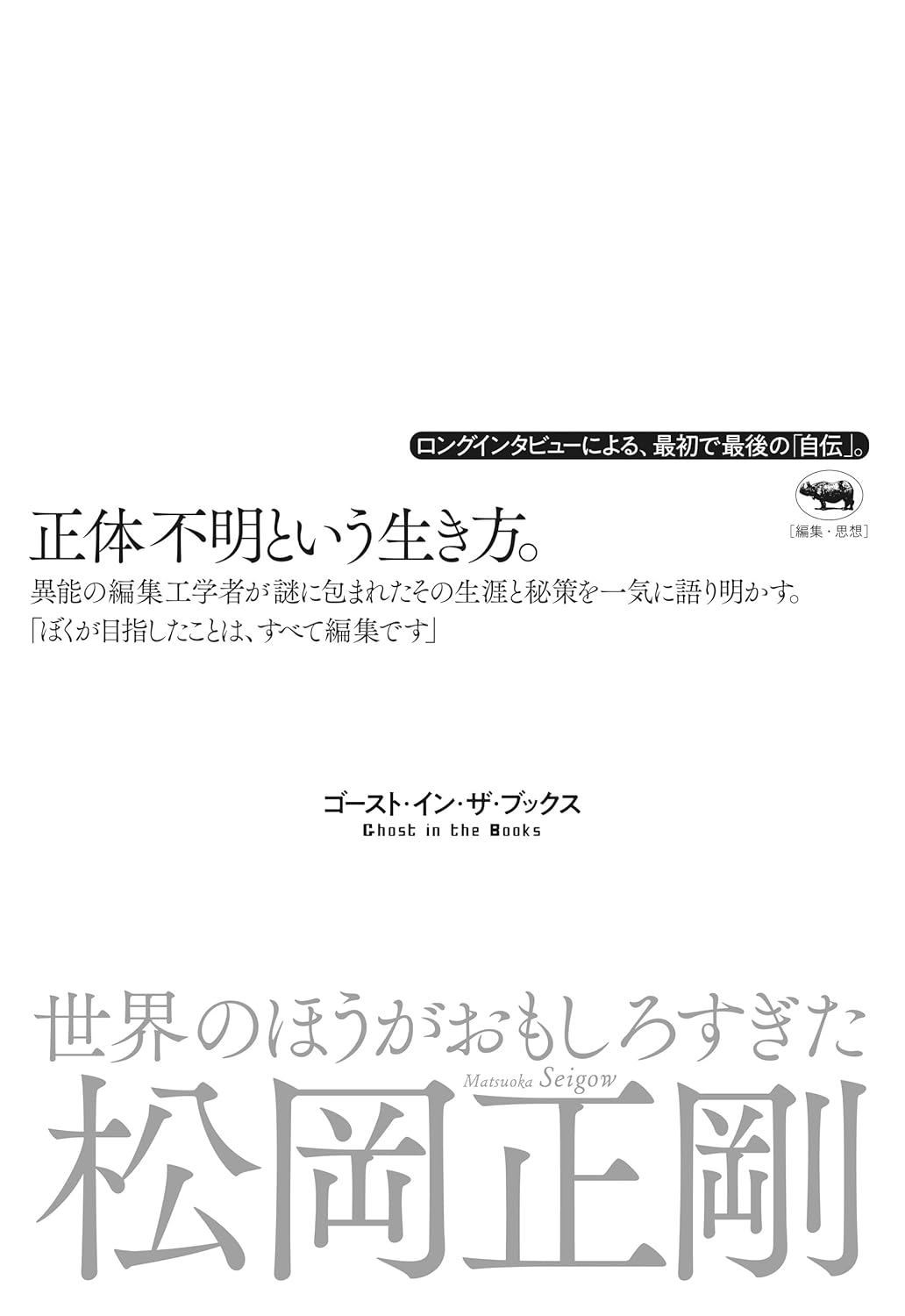 もう1冊はイギリスに行く前に読んだ、松岡正剛『松岡正剛 世界のほうがおもしろすぎた ゴースト・イン・ザ・ブックス』は、松岡正剛が奥付の著者ではあるけれど、もともと朝日新聞の連載記事のための新聞記者によるインタビューをまとめたもの。タイトルもインタビュアーである記者の山崎聡が著者に向けて発した言葉だと、松岡正剛事務所代表による「あとがきにかえて」にある。その意味では山崎聡の名が表紙に出ていないのはおかしい感じがするが、インタビュアーが了解しているらしいので、あくまで松岡正剛の本ということになっている。
もう1冊はイギリスに行く前に読んだ、松岡正剛『松岡正剛 世界のほうがおもしろすぎた ゴースト・イン・ザ・ブックス』は、松岡正剛が奥付の著者ではあるけれど、もともと朝日新聞の連載記事のための新聞記者によるインタビューをまとめたもの。タイトルもインタビュアーである記者の山崎聡が著者に向けて発した言葉だと、松岡正剛事務所代表による「あとがきにかえて」にある。その意味では山崎聡の名が表紙に出ていないのはおかしい感じがするが、インタビュアーが了解しているらしいので、あくまで松岡正剛の本ということになっている。
松岡正剛の本はときたま読むぐらいで、膨大な読書量に支えられた思考の展開は面白いのだけれど、この本でも自ら強調しているそのモットー「編集」という概念/方法論が最後まで当方の頭には入らなかった。
それでも松岡正剛の文章に惹かれるのは、ググれる時代になって、あれこれ参考になるものはないかと探していると、たいてい「千夜千冊」が引っかかってくるからだった。松岡正剛独特の編集力は読んでいてそのテーマの何がおもしろいのかを的確に知らせてくれる。
工作舎の『全宇宙誌』が出てから45年以上経つ。印象に残る本だったけれど、結局買わなかった。角川文庫の「千夜千冊」も買ったのは数冊のみ。でもお世話になったとは思う。
今回は積み残しが多い。
『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ
THATTA 451号へ戻る
トップページへ戻る
 フィルム・アート社から出た税込み5000円超の黒人作家によるホラー・アンソロジー、ジョーダン・ピール編『どこかで叫びが ニュー・ブラック・ホラー作品集』は、『本の雑誌』10月号山岸真さんの新刊SF出版情報欄「SF新世紀」でトップに紹介されたにもかかわらず、なぜかその後SF界からの書評が少なかった1冊。『SFマガジン』でもホラー書評欄の最後にちょっとだけ言及があるのみで、翻訳SFやファンタジーの方では言及がなかった。
フィルム・アート社から出た税込み5000円超の黒人作家によるホラー・アンソロジー、ジョーダン・ピール編『どこかで叫びが ニュー・ブラック・ホラー作品集』は、『本の雑誌』10月号山岸真さんの新刊SF出版情報欄「SF新世紀」でトップに紹介されたにもかかわらず、なぜかその後SF界からの書評が少なかった1冊。『SFマガジン』でもホラー書評欄の最後にちょっとだけ言及があるのみで、翻訳SFやファンタジーの方では言及がなかった。