 劉慈欣『時間移民 劉慈欣短編集Ⅱ』 早川書房
劉慈欣『時間移民 劉慈欣短編集Ⅱ』 早川書房
内 輪 第423回
大野万紀
寒くなりました。映画「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」を初日に見て来ました。中国アニメです。中華ファンタジー。前作は劇場で見逃してテレビで見たのですが、とても面白かったので、今度はちゃんと劇場で見ようと。超能力を持つ妖精たち(妖精と訳されているけど、いわゆる仙人であり、神仙の時代から続く神話的存在ですね)が人間と共存している現代中国(にとても良く似た世界)が舞台の作品で、この現代で生活をしている妖精たちの日常描写がとてもいい。とにかく超絶動くし、迫力満点だし、可愛いし、けっこう重いテーマだし、2時間ちょっとを堪能しました。旅客機が白骨竜に襲われるシーンなんてすごい。見て良かった。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
なお、短篇集についても原則として全部の収録作について途中までのあら筋を記載しており、ネタバレには注意していますが、気になる方は作品を読み終わった後でご覧になるようお願いいたします。
 劉慈欣『時間移民 劉慈欣短編集Ⅱ』 早川書房
劉慈欣『時間移民 劉慈欣短編集Ⅱ』 早川書房2024年12月刊行。大森望/光吉さくら/ワン・チャイ訳。訳者あとがき(大森望)付き。ショートショートも含め13編を収録。早川から出た『円』、KADOKAWAから出た『流浪地球』と『老神介護』に続く短編集で現在のところこれで劉慈欣の短編は全部翻訳されたとのことである。未訳の短編を集めたといえば、落ち穂拾い的な作品集になりがちなところだが、訳者がいうようにまったくそうは見えない。傑作ばかりとまではいえなくても、読み応えのある短編集である。
「時間移民」は人口過剰の対策として8千万人が人工冬眠により、未来へと移民することになるという古典的なアイデアストーリー。だが面白い。最初の目的地は120年後だったが、その世界は戦争で荒廃していた。そこでさらに先へと目的地を延ばしていく。先遣隊が先に目覚めては状況を調査し、場合によっては何年もそこで暮らして、ここで目覚めさせるのがいいかどうかを冬眠者全体の意思決定者である大使に答申する。
科学技術が高度に発達し自然が無くなった世界、人々がコンピュータの仮想世界で生きるようになった世界。だが大使は自分たちの生きる尊厳が軽視されるような世界には移民しようとはせず、さらに未来へと決断する。高度な科学技術で設備や装置を更新しつつもっと未来へ。
物語は彼らが見る未来世界のありさまを数百年、数千年、そして1万年後まで描いていく。手塚治虫の『火の鳥』でもあったような古典的な話ではあるが、その未来世界は現代SFらしくアップデートされている。ツッコミどころはある。なぜ相手はこちらに何もしないのかとか、8千万人の意思決定を1人の人間がやっていいのかとか。でも短編だからこれでいいのだ。未来世界への失望と、それでも希望にあふれる結末は読んでいて気持ちがいい。
「思索者」。これはとても好きな作品。天文台で事故があり救急車で駆けつけた青年医師は、そこで太陽のシンチレーション(光度の微弱なちらつき)を研究しているという若い女性天文学者と出会う。彼女の不思議な魅力に心を惹かれるが、彼は病院へ帰り、十年間の普通の日常生活の後、ふと彼女のことを思い出す。病院の慰安旅行で天文台のある山へ行ったとき、彼は旅行から抜け出して天文台へとおもむくのだ。
驚いたことに彼はそこでまた彼女と再会する。今の彼女は他の恒星のシンチレーションを観測しているという。だが彼女が見せてくれたアルファ・ケンタウリのシンチレーション波形は10年前に見た太陽の波形とそっくりだった。彼女も驚く。太陽のシンチレーションを起こした光がアルファ・ケンタウリまで届き、同じ現象を起こしてそれが今観測されているのだとしたら。もしそうなら次は7年後にシリウスで同じ波形が観測されるはず。
そして7年後、彼はまた彼女に会い、予想が正しかったことを知る。でも科学的には説明出来ない現象だ。次は17年後のアルタイル。その歳月の間に二人はそれぞれの分野での権威となっていた。再開した彼女は無数の恒星が互いにシンチレーションを交換し合っているという仮説を語る。一方彼は彼女にあるシミュレーション模型を見せる。それは大脳ニューロン間の信号伝達の模型だった。ならば宇宙は思考しているのか……とてもゆっくりと。
人間の時間と宇宙の時間、科学と夢想が重なり、壮大な宇宙への眼差しと二人の感情が溶け合って、甘やかなロマンとセンス・オブ・ワンダーを引き起こす。「宇宙よ、しっかりやれ!」(小松左京「神への長い道」)と思わず口にしたくなる、そんな傑作だった。
「夢の海」はかなり無茶な話だがアイデアは面白い。突然宇宙から「低温アーティスト」と自称する球体が飛来する。芸術家だと名乗り、言葉が通じるが、とても尊大ではた迷惑なやつだ。たまたま氷彫刻を作っていた主人公と話があい、自分も同業者だと言う。だがどこから来たか、どうやってきたかといった技術的な話は最小限しかせず、そんなつまらない話には興味が無い、芸術の話がしたいと言う。
主人公の氷彫刻がそこそこ気に入ったようで、創作意欲をかきたてられたと言ってとんでもないことを始めた。地球の海を無数の直方体のブロックに切り取ってそれを氷結させ、軌道上に引き上げて地球を巡る氷の輪を作ったのだ。おかげで地球の海は干上がり、自然環境は破壊され、地球の生物は(もちろん人類も)大被害を受ける。
主人公は「低温アーティスト」に抗議するが、かれは芸術が第一で、それ以外のことは意に介さない。確かに地球を巡る氷のリングはとても見事で、太陽光を受けるその色も光も変化していき息をのむほど壮大で美しい。完成したリングは「夢の海」と名付けられた。これをまた元の海に戻すことは可能かと聞くと、もちろんあった所に戻せばいいだけだと答える。どうやってと聞くと、知るかと言い捨てて去って行った。
主人公たちはその後人類の知恵を絞った海の回収作業を始める。完全に元に戻すことは不可能でも、人類が存続するために……。
この迷惑千万な、言葉は通じるが意思の通じない異星人がマンガ的に描かれていて面白い。
「歓喜の歌」も異星人の芸術家もの。国連が機能不全で廃止されることになりその最後の式典の夜に、突然空にもう一つの地球が現れる。だがそれは実体ではなく巨大な鏡像だった。導入部の、この超巨大な鏡をスペースシャトルが探査に行くシーンがいい。勇敢な宇宙飛行士の思いきった行動により、この鏡が物質ではなくある種の場であることがわかる。そして鏡は「わたしは音楽家です」と話しかけてくるのだ。
鏡はこの国連の式典の場でコンサートを開きたいという。鏡が使う楽器は恒星だ。彼は4年前にプロキシマ・ケンタウリを超新星にし、今そのビートが地球に届く。それに合わせて彼は太陽をつま弾き、音楽が人々の耳に響く。だがそれは雑音のようにしか聞こえない。しかしコンサートに招待されていたピアニストのリチャード・クレイダーマン(彼はぼくと同い年だから、この話はそんなに未来のことじゃないな)がその正しい聴き方を見つけ、列席する元首たちも理解する。人々はそれぞれに解釈するが、それは壮大な宇宙と生命の進化の歴史を描いているに違いなかった。
音楽が終わり、鏡はこれで失礼しますと言うが、クレイダーマンはちょっと待ってくださいと言う。太陽で人類の音楽を演奏して欲しいというのだ。そこで鏡はベートーヴェンの「歓喜の歌」を演奏し、地球の人々はそれを合唱するのだ。その歌は光の速度で遠い宇宙にまで広がっていった。国連の廃止は中止される。
こちらの芸術家は人々に希望をもたらして去って行った。もし「低温アーティスト」と共演したらどうなるのだろう。
「ミクロの果て」からの4編では『三体』に登場する天才科学者、丁儀(ディン・イー)が主役となる(『三体』との直接の関連はない)。
「ミクロの果て」は古いタイプのアイデア・ストーリーでショートショート。クォークを分割して(!)その構造を探るため、超巨大な粒子加速器が作られる。丁儀たちはその実験を見守る。ビッグバンに相当するエネルギーが一点に集まり、そこで果たしてクォークは分裂するのか、されないのか。だがそれは思いもかけない事態を引き起こす。アーサー・C・クラークがその昔短編SFにジョークとして書いたようなことが起こるのだ。登場人物の中に一人、科学者ではない人物がいる。加速器が建設された土地の中にある村で羊飼いをしていた現地のおじさんだ。彼は現地代表として招待されたのだ。科学者たちが右往左往するなか、このおじさんがとてもいい味を出している。アイデアは単純だが、面白かった。
「宇宙収縮」もショートショート。これは劉慈欣が最初期に書いた作品だそうだ。現代で最高の知性を誇る物理学者の丁儀教授がコンピュータでシミュレートした、宇宙が膨張を停止して収縮に転じる瞬間が刻刻と近づいている。天文台には教授の他、科学者や政府のお偉いさん(昔大学で物理を専攻していたという省長)も集まってその時を待っていた。省長が宇宙の膨張と収縮について基礎的な説明を述べると、天文台長はおべっかを使うが、丁儀は上っ面しか理解していないことがじつによくわかる説明だったと切り捨てる。宇宙の収縮とはどういうことなのか。その時何が起こるのか。すぐわかるオチだが、笑える。
「朝(あした)に道を聞かば」の丁儀は妻と10歳の娘を連れて世界一周旅行をする。とはいえ、地球を一周する加速器の直径五メートルのチューブの中を時速五百キロのヴィークルに乗ってだ。外の景色などほとんど見えない。それでも家族は久しぶりにいっしょに過ごせることを喜んでいる。60時間の旅を終え、今度は外で世界一周してねという娘に、想像力の目で見ていればそれで十分なはずだなどという丁儀。
翌日、加速器が突然消失し、謎めいたリスク排除官なる者が現れる。丁儀らが行おうとしていた実験で真空崩壊が起こる可能性が高く、それを防ぐため介入したのだ。人類がその実験で得ようとしていた大統一理論はすでにあるのだがガイドラインにより教えられないとも言う。丁儀はそれを自分に教えてくれ、教えた後は破壊してくれてもいいと懇願する。同様に言う科学者は大勢おり、排除官は宇宙の秘密を教えるが10分後には彼らの命を奪うことに同意する。そして――。
タイトルは知識を得られれば死んでもいいという孔子の言葉だが、ぼくはグレッグ・イーガンの「プランク・ダイヴ」のテーマを思い浮かべた。
「共存できない二つの祝日」はショートショート。1961年のソ連でガガーリンの乗ったボストーク1号の打ち上げの日に、自分は宇宙人で地球の重要な祝日を調査しに来たという男が労働者の姿をして、実在のロケット設計主任コロリョフと出会うところから始まる。男は今日が地球の祝日「誕生の日」になるかも知れないと言うのだ。
時は変わって2050年の中国、丁儀(ここでは丁一だが、おそらく同一人物)が脳とコンピュータの直接接続に成功する。そこへ宇宙人Aが清掃員の姿で現れ、以前にコロリョフにも会ったが、今日こそが人類にとって重要な日になるだろうと言う。丁はそれを聞き、これが宇宙開発よりさらに重要なエポックだになるだろうと語る。ブレイン・マシン・インタフェース技術はやがて人間をコンピュータにアップロードし、仮想空間で生きることを可能にするだろう。実際の宇宙に飛び出す必要はなく、何でも実現できるようになるのだ。それを聞いてAは、だが現実世界はどうなるのでしょうかといい、この日を別の名前で呼ぶよう本部に提案するのだ。
何だか当たり前だともとれるがとても理性的な話で、『三体』のVRゲームを思うとなるほどと思える。VRに浮かれている人たちにも読んで欲しい掌編だ。
「全帯域電波妨害」からの作品は(「運命」はショートショートなので別だが)いずれも大変読み応えのあるシリアスな中短編である。
「全帯域電波妨害」ではロシアが内戦状態になり、そこにアメリカを中心としたNATO軍が侵攻してくる。IT技術をベースに戦う現代戦が大変リアルに描かれるが、劣勢となったロシア軍は窮余の策として自軍にも影響の及ぶ、全帯域電波妨害を実施する。高度なIT戦が不可能となり最新兵器はほとんど役に立たない。第二次大戦のころに戻ったような、人間の目とカン、肉体能力に頼った戦闘が繰り広げられ、むしろ兵装的には劣っているロシア側が有利となる。
だがそれも長続きはしない。NATO側も体制を立て直していく。妨害装置は次々に発見され破壊される。あと少し電波妨害を長引かせられないかとの悲痛な叫び。そこで、思いがけない手段がとられる。
ロシア軍の指揮官である元帥の息子とその恋人。彼女は戦場でサイバー電子小隊の少佐として戦っていたが、小隊は壊滅し、悲惨な戦場を逃げ惑っている。息子は戦争に向かない性格で、軍人ではない。何の武装もないロシアの大型宇宙船にたった一人残って、水星軌道上に留まっている。最も遠くへ逃げた逃亡兵と揶揄する者もいる。だがその彼が決定的なキーを握っていたのだ。そして――。
戦争の悲惨さとそこに隠れているヒロイズム。今現在も続いているそんな戦争に思いを馳せないわけにはいかないだろう。
「天使時代」では飢餓に苦しむアフリカの小国ソンビアにアメリカ軍の最強の機動部隊が戦争をしかける。理由は国連生物安保理が定めた国際的な法に違反してその国の科学者、ノーベル賞受賞者のイータ博士が人間の遺伝子改造を行い、飢餓に強い人間を人為的に作り出したからだ。世界は彼らを人間ではないとし(個体と呼ぶことになる)、直ちに遺伝子操作を中止し、全ての研究成果を廃棄して研究者と個体を引き渡すよう要求する。
だがソンビアは拒否し、アメリカ軍が空爆とミサイルで壊滅的打撃を与えた結果、ついにソンビア政府は屈服したのだ。そして科学者と改造された2万人の個体たちを引き渡すと告げる。旗艦の空母にやってきたイータ博士は、翼のある仔馬をプレゼントとして持参していた。仔馬の愛らしさに艦隊の軍人たちは喜ぶが、司令官の将軍は鋭く追求する。引き渡された個体の人数が少ない。倍以上いる証拠があると。傲慢な空母の艦長と違い、将軍は実はこの戦争には懐疑的だった。世界は過剰反応していると考えていた。だが任務には忠実に従う。隠されている2万の個体の居場所も見当がついている。引き渡さなければそこに爆撃機が向かうだろう。
イータ博士はその通告をソンビア政府に伝えると言い、去り際に「アフリカから去れ」と言い残した。翌日、改造された2万の個体が、艦隊に襲いかかる――。最新鋭の兵器で武装した艦隊に、携帯武器しかもたない個体たちが人海戦術で向かっていく。だが彼らには羽があり、天使のように空を飛ぶことができるのだった。
戦いの描写は凄まじい。それは巨大な戦艦が航空機部隊に翻弄された時代を再現するかのようなものだが、相手は航空機どころか一人一人の人間なのだ。これまた現代戦の高度なテクノロジーが敗北する物語であり、そして未来の多様な人類の姿を見届ける物語でもあるといえるだろう。
「運命」は作者が大好きな恐竜がテーマのショートショート。宇宙船に乗ってハネムーンに出かけた二人が、未知の小惑星を発見する。それは地球に衝突するコースに乗っていた。だが地球への連絡がなぜかできない。二人は何とかしようと宇宙船の後部エンジンを切り離して小惑星にぶつけ、軌道を変えることに成功する。地球は救われた。しかしなぜ地球は沈黙しているのか。
ネタバレになるが、二人は知らない間に過去へワープしてしまったのである。それに気づいて現代へ戻った二人が見たものは――。
まあ想像がつくでしょう。あの小惑星はあの小惑星で、二人は歴史を変えてしまったのだ。結末は楽しいが、決着はついていない。はたして二人の存在は認められるのだろうか。
「鏡」はシリアスな社会的問題を扱っていて、傑作といっていい。刑事が長官にあり得ない事件の報告をしている。地方組織の全体に関わる汚職のネットワークについてその秘密を知った者がおり、それを曝露されないよう調査していたのだが、そのターゲットの男がこちらの手の内を完全に知っているというのだ。そこへ当のターゲットから電話がかかり、長官のライターが部屋のどこにあるかまではっきりと指摘してみせる。長官の上着のポケットに何が入っているかまで。彼には全てがお見通しなのだ。
彼の名は気象エンジニアの白冰(バイ・ビン)。彼は気象予報のための超弦コンピュータ(ブリーフケースに入るくらいの大きさだという)を盗んで自分のものとし、そして何と宇宙創成から現在までのあらゆる事象を現実の通りにシミュレーションするシステムを作り出したのだ。
これはT・L・シャーレッド「努力」、デーモン・ナイトの「アイ・シー・ユー」、さらにクラーク&バクスターの『過ぎ去りし日々の光』など昔から傑作の多いアイデアをいたって現代的に描いたものである。このアイデアを実現するため、最初に量子力学が変貌して確率論ではなく決定論になったというトンデモな設定が書かれているが、それはともかくとして、過去の傑作同様にあらゆるものが白日の下にさらされるということの良い面と暗黒面が描かれ、それが中国の現在の政治・社会状況ともつながっている。
『三体』の文化大革命のシーンにも通じるものがあるが、それだけではなく、真実の曝露が必ずしも正義ではないという議論は、善か悪かの二者択一の思考を批判するものであり、今のSNSや表現の自由論争のようなところへも関わってくるものだろう。
「フィールズ・オブ・ゴールド」も傑作。製薬会社のオーナーであるミラーは冬眠薬を開発し、それを宇宙飛行に使おうと考えた。しかし冬眠薬が必要な恒星間宇宙船など夢のまた夢。ミラーはまず火星を目指すロケットを自社開発することにしたが資金不足で月まで向かう1人乗り宇宙船の開発がやっとだった。
その宇宙船〈フィールズ・オブ・ゴールド〉に乗り込むのはミラーの一人娘、20歳のアリス。ところがその打ち上げでトラブルが発生し、〈フィールズ・オブ・ゴールド〉は帰還不能となって太陽系を果てしなく飛び続けることとなる。冬眠薬は20年分を搭載していたので、それが切れるまでアリスは薬を使いつつどこまでも慣性飛行ができるのだ。
この宇宙船にはインターネットにつながる回線があり、起きているときの彼女は(寝ているときもだが)地球の一般の人々とVRを通じて姿を見たり話したりすることができる。ただし次第にタイムラグは大きくなる。18歳の青年マイクはVRで彼女の姿を見て以来彼女に恋をしてしまった。それから19年。何度もの失敗の後、ついに〈フィールズ・オブ・ゴールド〉に追いつくことの出来る宇宙船〈オリオン〉が開発され、アリスの救援に向かった。今のアリスは天王星の軌道にいる。アリスが19年かかったその距離を〈オリオン〉は3ヶ月で追いついた。マイクは〈オリオン〉へVR接続する。4時間のタイムラグも気にならない。〈オリオン〉のクルーたちがアリスの画像を見ているスクリーンが見える。そして思いがけないことが起こる――。
宇宙船の名前の、そしてタイトルの意味が明らかとなる時、そこには絶望と希望の両方がある。思わず涙するような感情と、静かな、だがとても深い希望がある。この叙情性――。何とも見事な作品である。
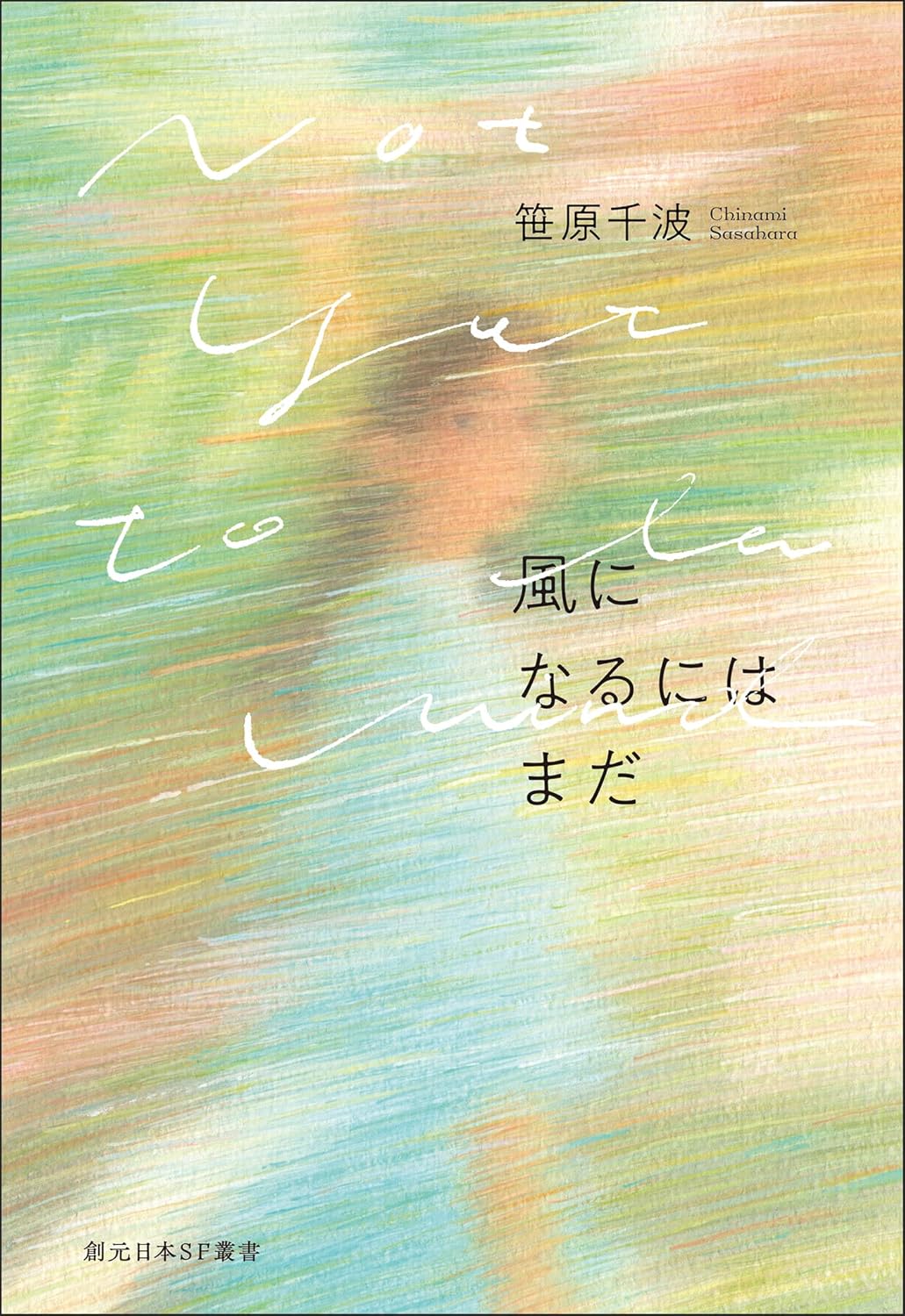 笹原千波『風になるにはまだ』 創元日本SF叢書
笹原千波『風になるにはまだ』 創元日本SF叢書2022年第13回創元SF短編賞を受賞した著者の初短編集。2025年8月刊行。書き下ろし3編を含む6編が収録されている。いずれも仮想現実の世界と現実の世界の関係性をテーマにした作品で、連作短編となっている。
創元SF短編賞の受賞作「風になるにはまだ」は、人格をすべてデジタル化して仮想空間にアップロードすること(肉体は失われる)が普通にできるようになった世界で、仮想空間に生きる女性、小春が、かつての友人たちのパーティに生身で参加しようと、現実世界に生きる主人公、あたしの体を借りる話。
あたしはバイトとして小春の依頼を受け、彼女の指示通りにパーティに参加し、その現実世界での肉体感覚を提供するのだ。体を借りるといっても相手の肉体や意識の操作はできず、あくまで相手が目や耳や肉体で感じる感覚を受け取ることができるだけである。二人のコミュニケーションはイヤホンとスピーカーにより言葉でなされる。スピーカーでは自分の声を発することもできる。
こういった限定的な(ダウンロードや憑依して意識が同居するというのとは違う)関係は、他でもあったかも知れないが面白いと思った。相手の肉体感覚をリアルタイムに受け取れることを除けば、スマホで遠隔地の相手と話をしているのとさほど変わらない。
物語は小春とあたしの二つの視点で交互に描かれる。ときおりどちらが視点人物か混乱するところがあるが特に問題はない。現実世界はほとんど今の日常のままなのだが、小春にすれば懐かしく、あたしを通じた感覚も新鮮だ。小春が仮想世界におり、今目の前にいるのは別人の体だとわかっている友人たちの反応も人によって異なる。
仮想世界に行ってしまった小春と彼らの関係、小春と、特にやりたいこともなくぼんやりと生きているあたしとの関係が、主に会話と心の声によって深みをもって描かれている。洋服や人の手に触れたときなどの感覚描写も解像度高く描かれていて、その場景が瑞々しく伝わってくる。確かに受賞に相応しい作品である。
「手のなかに花なんて」では仮想世界に生きる祖母の早季子(さきこ)を孫の優花(ゆうか)が自分そっくりなアバターを使って訪問する。
優花は家族にあまり親しみを覚えず、いつも味方をしてくれる祖母をとても慕っていた。その祖母が認知症を患い、ゆっくり時間をかけてリハビリしながら回復を待つため、情報人格となることを決断したのだった(このあたり、情報人格への移行の仕方がよくわからないのでSFとしてはやや曖昧さが残る)。現実世界の早季子は死に、家には骨壺もある。優花は早季子の仮想世界への移住にもわだかまりを抱いている。だがアバターとして訪れた仮想世界の祖母はときおり認知症の症状はあるものの、やはり優花のおばあちゃんだった。
表題作の題名にもあるように、仮想世界の情報人格は不死ではない。いつか人格の情報が散逸して風(ノイズ)となってしまう(エントロピー増大の法則か)。優花は何度も祖母のもとを訪ねて刺激を与えることでそれを遅らせようとしているのだ。
仮想世界というが、それはほぼ現実世界と同じである。優花は祖母の家から外に出て仮想世界の街を歩き、そこの人たち(高齢者が多い)と交流をもつようになる。ここでも若い(現実世界の)優花と仮想世界の人々の関係性、会話、ふるまい、見聞きすることがとても繊細に描かれていて心に染みる。表題作の小春もその中に登場する一人だ。ただ、その観点から見たときに仮想世界と現実世界の違いは溶け去り、全てが同じレイヤーの中にあるようにも感じる。
「限りある夜だとしても」は仮想世界ではなく現実世界で物語が進む。
独り身のカメラマンである主人公の榛原(はいばら)は、学生時代の友人で、今は同性結婚していて養子の子供もおり大手メーカーに就職している三森(みもり)から相談を受ける。彼は学生のころからみんなの注目を集める存在だったが、ぱっとしない榛原に何かと親しくしてくれ、そこから断続的ではあるが長いつきあいが始まったのだ。
その三森があと三年の命だという。そこで肉体を捨てて仮想世界への移住を考えているのだが、幼い子供たちのことを考えると決断がつかないというのだ。仮想世界へ行けば自分はもっと生きながらえることができるが、子供たちの手を握ったり抱きしめることができなくなる(12歳になるまではVRでの面会が許可されないのだ)。仮想世界へ行っても不死になるわけではなくいずれは散逸するのだが、今の仕事は続けられ、配偶者とはVRで会える。現実に残った場合は死ぬまで入院して子供たちにも会えなかったり苦しんでいるところを見せることになるだろう。そう考えれば情報人格となるのが一番いいように思えるのだが――。でも幼い子にはいっしょに同じ空間で暮らし体全体を使ってコミュニケーションすることが大事なのでは。
決断に苦しむ三森に、榛原は家まで付き添ってやるという。この二人の関係がとてもいい。頼り切るでもなく、結論を示すでもなく、心を通わせて会話につき合う。結末のほのかなユーモアが温かい。
「その自由な瞳で」では仮想世界に移住した映(はゆる)とトオルのカップルが描かれる。
トオルは現実世界では十二歳で肢体不自由となり人工呼吸器を着けた寝たきりの生活を送っていたが、その饒舌な瞳が視線入力でテキストを打ち込み自分の意思を発信していた。
映は裕福で愛情いっぱいの家庭に育った少女だったが、高校で友だちだと思っていた相手にいいように利用されていたことを知り、引きこもりになってしまった。彼女がトオルを知ったのはSNSだった。映はテキストだけのコミュニケーションで彼に恋した。
彼は二十歳の年齢制限に達したら、不自由な肉体を捨てて電脳移住する。映もいっしょに行きたいと思った。それまでの間、彼女は家族の協力を得て生身の彼とも面会し、愛情を深めていく。トオルにはITの才能があり、視線入力だけで3DCGをプログラムし、様々なものを作り出して見せてくれた。家族とは話し合って情報人格になることを受け入れてもらった映だが、トオルの母親は彼女のことを思い健康な肉体を捨てることに強く反対した。それでもいっしょに暮らしたいという映を最後には応援するようになる。
そして今、二人は仮想世界の仮想の家で暮らしている。作品冒頭で、二人のとろけるような生活が描かれるが、電脳存在は互いの感覚を共有し、重ねて感じることもできるようだ。ほのかにエロティックです。
トオルは仮想世界のルールを破るようなことも平気でやる。仮想世界ではできるだけ現実世界と同様にすることがルールなのだが、トオルは(映にしか見せないが)現実には存在しないおかしなものを生みだして見せる。地下室に広大な平原を作ったり、不思議な動物を作り出したり。
二人は「手のなかに花なんて」に出てきた人々とも会うが、高齢者でも重い病気でもない映に不審を抱く人もいる。そんな人も最後には打ち解け合うのは、この世界に住むことになった人々が結局はみな仮想の存在であるという(本人にとっての)リアルを共有しているからだろうか。
「本当は空に住むことさえ」は仮想世界に移住した著名な女性建築家、敷島綾女(あやめ)と、その構造設計を手伝うことになったこの世界での平凡な建築家である古谷誠治(せいじ)、それに現実世界にいながら仮想世界での建築素材やモデリング・ソフトの専門家である勝村基(もとい)による仮想建築の物語である。
彼らに現実には存在しない素材を用いた建築を実験として依頼したのは、仮想世界が生まれて最初に移住した世代の生き残りで、ここの役所に勤めている並木翼(つばさ)だ。この世界では散逸を恐れて現実を大きく逸脱するようなことは御法度なのだが、それに疑問を持ち、もう少し自由でもいいのではないかと考えている。
60歳を越えて移住した綾女がこの実験に最も積極的で、持ち前の想像力を発揮し、鉄のようでガラスのような素材とか、生物ではない金魚とか、様々な素材の製造を基に依頼する。基も嬉々としてそれに応じる。とはいえ、基は綾女の自由さにいささか危険なものを感じてもいて、時には反対意見も述べるのだ。誠治は現実世界に家族がおり、綾女のやることに興味はあって平凡な生活から一歩踏み出そうとはしているが、なかなか飛び出せない。綾女や基の作り出すものに驚くばかりである。その誠治が最後に綾女に提案するのだ。この世界での人々を中心とした新たな街作りを――。
ストーリーそのものは建築というリアルでかつアートでもあるものへの思いを重ねていく、現実でもありうる物語だが、それが仮想世界で展開するところには、「その自由な瞳で」と同様なSF的な視線がはっきりと現れているようだ。
「君の名残の訪れを」は三十年前、仮想世界がまだ試験運用だったころに不治の病で移住し、すでに散逸してしまった神澤理知(りち)という女性と、彼女の幼なじみで、一緒に移住したが生き残ったわたし(「本当は空に住むことさえ」に出てきた並木翼その人だ)の物語だ。
初期の時代はまだ散逸が知られておらず、理知は仮想世界でプログラムを作ってまるで魔法のようなことを次々にやってのけた。現実世界から参加した勝村基という青年も仮想世界ならではのアート作品を作り出し、理知はそれを喜んだ。理知はまたわたしに特別な部屋をプレゼントしてくれた。片方から入ると秋の世界、もう片方から入ると春の世界となる部屋だ。その理知が突然散逸した。彼女の断片がノイズとして漂っていたことからそれがわかった。
仮想世界の法律も変わり秋と春の部屋も違法となったが、非公開で所有しているだけなら許容されることになった。その部屋の中で風が吹く時、わたしは思う。「いいよ、入って」と。
これは並木翼がなぜ実験的な建築づくりを綾女に依頼することになったかの物語であり、仮想世界には現実を越える自由があって良いと思うようになったかの物語である。それはまた風となった理知の物語でもあるのだ。短いが印象に残る短編だ。
 天沢時生『すべての原付の光』 早川書房
天沢時生『すべての原付の光』 早川書房2025年4月刊行。第2回ゲンロンSF新人賞(2018)を本書に収録の「ラゴス生体都市」で受賞してデビューした著者の初単行本である(一部の作品は以前に電子出版されている)。5編を収録。
「すべての原付の光」では滋賀県近江八幡市(著者の出身地でもある)に暴走族の取材に行った記者が体験する恐るべき(笑うしかないがぞっとする)物語である。
記者が訪れたのは田んぼの中にあるさび付いたトタン屋根の巨大なガレージだった。その中ではキャタピラのない戦車のような謎めいた機械の傍らに中学生の少年が縛り上げられて宙づりになっていた。凡庸な田舎のヤンキーを取材しに来たつもりだった記者に、暴走族の幹部である不良は「ガチで半端ねえ機械なのさ」という。粋がって原付で国道を暴走した罪で、これからこの機械で中坊を処刑するのだと。しょうもねえヤツがしゃしゃって来たら原付取り上げて落とし前つけさす「原付狩り」なのだそうだ。中坊を機械の弾倉に込めてガレージの奥にある的に向け射出すると、砲身の中にある入墨機構(タトゥーマシン)が働いて中坊に刺青をほどこし、高速回転させながら発射するのだという。まさにガチで半端ねえ機械だ。
何と恐ろしいことをと恐怖する記者の前で不良は中坊を装填しマシンを稼働させる。そして発射――ところが的に当たるはずの中坊が消滅する! 何と刺青された図像が座標となって、異世界に転移(ワープ)したのだ。びっくり。
滋賀の田舎から想像力がいきなりインフレーションするが、それでも田舎のヤンキーから世界が広がるわけでもなく、あくまで視点はローカルなまま。さらに結末ではもう一つの異様な展開があって驚かされる。すごいとしか言い様がない。
「ショッピング・エクスプロージョン」は傑作といっていい。タイトルからわかるようにギブスン『ニューロマンサー』へのオマージュであり(ルビの多用もそう)、渾沌とした巨大ディスカウントショップ「ドンキホーテ」(ここでは「サンチョ・パンサ」)への愛であり、制御不能となってひたすら自己増殖し、世界中を食い潰していく自動装置(まさに『横浜駅SF』を思わせるような)への恐れと憧憬であり、もう一つ言えば今は仮想存在となった「サンチョ・パンサ」の創業者に見られる「関西のおばちゃん」のかっこよさを描く作品でもある。
創業者が亡くなって野生化した「サンチョ・パンサ」は暴走して世界を埋め尽くしていく。ここハリウッドも風前の灯火だ。主人公の少年ハービーは警備ロボット「鋼鉄店員(メタルクラーク)」がうろつく店内にもぐり込んで商品を万引きするのを生業としていた。見つかって素早く逃げられなければ鋼鉄店員に殺される危険な稼業だ。
ハービーはあるとき闇市で欲しかった「トランスフォーマー」のフィギュアを手に入れる。ボタンを押すたびにトラックとロボットに変形するやつだ。変形させて遊んでいるうち、その中にスティック型の拡張素子(プラグインチップ)が隠されているのを見つける。これは拾い物だ。彼はギャングの大物にそれを売りに行くのだが――。
これがとてつもないもの〈創業者のお宝〉の手がかりだとわかって彼は命がけの冒険に巻き込まれる。凄腕のトレジャーハンターであるセロニアスとタッグを組んで、「サンチョ・パンサ」の奥深く、渾沌の店内へともぐり込んでいくのだ。そして――。
おしゃべりなAI自動車が義体化した敵を排除したり、数限りなく襲ってくる鋼鉄店員との死闘、セロニアスとハービーの冒険がモーレツにかっこ良く、スピード感ある楽しいエンターテインメントとなっている。サイバーパンクなSF的趣向も面白い。セリフもいちいち決まっている。
店の深奥まで来てステージが変わり、また別の展開が現れるのだが、そこもいい感じで堪能した。
「ドストピア」は任侠ギャグSF。笑える。宇宙時代に弾圧された滋賀のヤクザが場末のスペースコロニーに住み着き、そこで細々と「タオリング」を興業している。これは濡れタオルで相手をぶちのめす格闘技だ(作者によれば本当にあるらしい)。このスペースコロニーには田んぼが広がり、小さな山には組長が濡れタオルで掘ったという(本当かしら)磨崖仏がある。ほとんど日本の田舎の風景だ。
そこへ林家パー子みたいな派手な格好の夫婦がやってきて住み着くことになる。どうやら二人は「カタギ警察」であり、ここがヤクザの巣窟であることを探って、「銀河マル暴」へ通報しようとしているらしい。「銀河マル暴」はとてつもなく恐ろしい存在なのでコロニーの連中はこの二人を警戒する。
だが若頭の坂田は、二人と親しくなってつい心を許し、磨崖仏を操作して光学迷彩に隠されたトンネルへと案内してしまう。そこで本性を現した林家夫妻だが、そのとき現れたのが原磯組組長。そして――。
といった密度と熱気とパロディ度の高い任侠SFである。面白かったけど、どうせならもっとぶっ飛んで欲しかったなあ。他の作品に比べ結末がちょっと大人しすぎる気がする(任侠ものとしてはこれくらいでちょうどいいのかも)。
「竜頭」は他の作品とちょっと雰囲気が違って、ホラー味のあるシリアスな作品だ。
のどかな田舎に住む少女しのみが語る、幼なじみの辻田尽郎(じんろう)のもとに深夜現れるようになった謎の存在、龍頭(りゅうず)の物語である。
龍頭は夕方に尽郎の部屋の扉をたたいてはダッシュで逃げ、夜中に窓の外で奇声を発したり、駄菓子や不要品などを残して行く。姿ははっきりせず、学生服かスーツ姿の男のようではあるが、街灯の下でくねくねと踊っている。まるで都市伝説に出てくるような存在だが、尽郎にとっては実在だ。
その尽郎は高三になり、バイクを買って一人で日本百名山チャレンジを始める。いきおい地元の仲間と遊ぶ機会は減り、付き合いの悪い奴ということになる。高校を卒業し、しのみは京都の大学へ、尽郎は自衛隊に入隊。やがてしのみは知り合った男性と同棲するようになるが、ある日母からの連絡で尽郎が地元に戻り、鬱になって引きこもっているという。懇願されて久しぶりに地元に帰ったしのみが見たものは――。
この後、龍頭の正体が明らかとなり、何ともおぞましい閉鎖的なコミュニティの闇が立ち現れて、そういうイヤな人間関係を描いたリアルな小説かと思いきや、読者は唐突に非現実な異界へと引きずり込まれるる。
「友達のため、動けるときは動くべき。たとえどれだけ馬鹿げたことのように思えたとしても」と何度も繰り返される言葉がよみがえり、男女を超えた友情と信頼、そして力強い戦いの物語となるのだ。ホラーであり、SFであり、奇想ファンタジーだといってもいい。何であれ、とても読み応えのある一編だった。
「ラゴス生体都市」は未来のナイジェリアを舞台にしたサイバーパンク風な作品である(やっぱりルビが多い)。本書で一番長い中編だ。そしてギブスンがそうであったように、リアルなスペキュレーションよりも神話的な魔術世界へと向かう作品である。
主人公の出自からしてそうだ。落雷で割れた聖なる木の底、赤土の中から生まれてきたというのだ。眉間に稲妻形の傷があり、皮膚の内側に鉄板が埋まったままだった。部族の呪術師(ウンガン)によってアッシュと名付けられたその男の子は12歳で村を追い出され、ハイエナのエサになりかけていたところを兵士を引き連れた若い娘に助けられる。彼女こそ、マジェスティック。9年にわたる長い戦争の後、再興したナイジェリアの首都、生体都市ラゴスの支配者である。アッシュは彼女に忠誠を誓い、反政府活動を取り締まる保全局のエージェントとなって頭角を現す。
この未来のラゴスは「遺伝子操作技術、クローン技術、ヴードゥー死者蘇生術の粋を結集して生み出された」〈貯蔵体(ネオモート)〉を核とする〈生体都市〉であり、そこでは人々の出生から天気、食事、仕事、人間関係や感情まで全てが制御され、セックスも、子どもをつくることも法律で禁止されている。
そんな社会で反体制の旗印となったのは「ポルノ」である。男女がキスする写真だけでも過激な「ポルノ」と呼ばれて弾圧されるのだ。アッシュはそんなポルノを摘発し、反政府活動を取り締まる有能な焚像官(リムーヴァー)となった。そんなところへポルノをプロパガンダとする〈映画監督〉が大規模な上映会を開催するという情報が入り、マジェスティックはそこへ集まる連中をミサイルで攻撃し、反体制的な労働者たちが暮らす水上都市マココを空爆する作戦をエージェントたちに命ずる。アッシュも怪しげな「ポルノ」売人のところへ向かうのだが――。
実はアッシュには二つの顔があった。体制に忠実で有能な焚像官としての顔と、裏社会とつながるもう一つの顔が。彼はある店で謎めいたディスクを発見する。そして……。
物語は管理社会側と、それに対抗する側との、いわば魔術的な闘争を描いていく。エキゾチシズムに溢れる魔術的な展開が面白くて魅力的だ。ただ、管理者側と裏世界の側の人々は生き生きと(現代のわれわれとさほど変わらぬ感性で)描かれているのに対し、普通に生活しているはずの大多数の人々の姿が見えてこない。それは、この物語の設定にかなり無理があるからではないかと思う。そもそも〈生体都市〉がどのように成立したのかという疑問、それが世界の他の国々とどう関係しているのか、いや、ナイジェリアの他の地方とどう関係しているのか、そういうダイナミズムがあえて捨て去られているように思うのだ。ともあれ、完成度が高くとても面白かった。この世界の外側に何があるのか、それはきっとまた別の物語なのだろう。