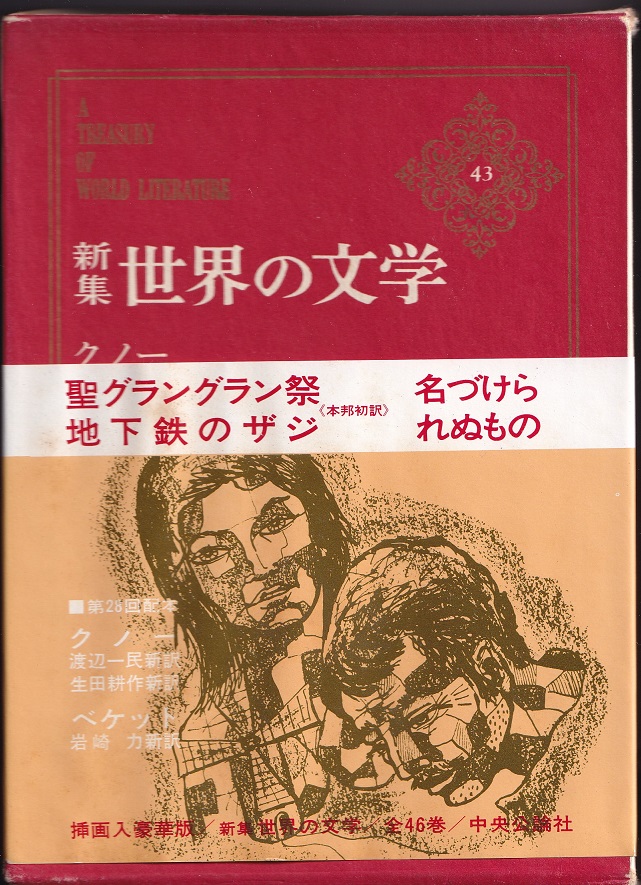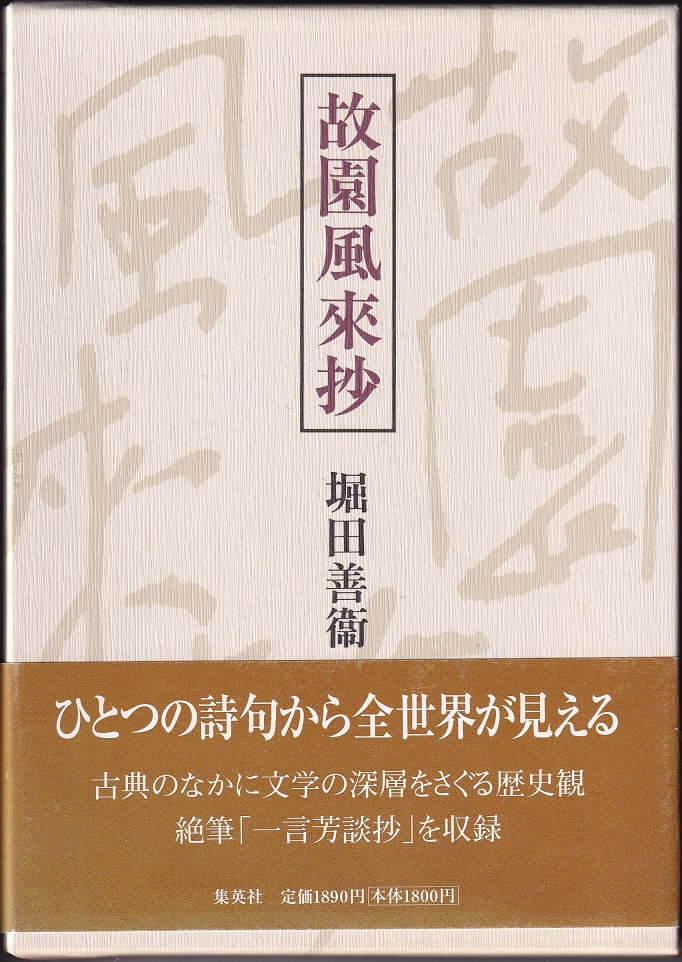前回もあいかわらず誤字脱字だらけだったけれど、大田南畝編宇田敏彦校注『万載狂歌集 江戸の機知とユーモア』は、「タイトルからして『千載和歌集』のもじりで、「万歳/万載」で」と書いているので「万歳狂歌集」と書いた間違いに気がついてない。われながらさすがにダメでしょう。
それはそれとして、自分が書いた四方赤良のロリエロ狂歌の解釈を読んだら、また妄想が湧いてきて、「十三夜」なんだから当然「十五夜の満月」が意識されるよねえ。となれば、「数え十五」で「小娘」は「おとな」になって「月経」もあるし、雲が懸かって雨が降って「濡れてる」かも。そういや現役時代、鎮守府長官官舎の担当をしてたとき、官舎の奥座敷を使って正月15日頃と中秋の名月の頃にナントカ流の茶会をひらいてもらってたんだけれど、先生が「片見月」というのを教えてくれて「十五夜」だけじゃなく「十三夜」もみるのがいいんです、とか云っていたなあ。で、妄想は野口雨情の「雨降りお月さん」に結びついてしまい、「雨降りお月さん 雲の蔭 お嫁にゆくときゃ 誰とゆく ひとりで傘(からかさ) さしてゆく 傘(からかさ)ないときゃ 誰とゆく シャラシャラ シャンシャン 鈴付けた お馬にゆられて 濡れてゆく」(Wikiより)を見て、これは四方赤良/大田南畝のロリエロ狂歌を雨情が読んでいたに違いないとおもったのでした。←んなわきゃないだろ。
2月9日(日)の朝日新聞に、「ニューヨーク・タイムズから読み解く世界」という同紙掲載記事の翻訳があって、今回は麹を使ったウィスキー「タカミネ式」が取りあげられていたんだけれど、その冒頭に「高峰譲吉という日本人化学者が米イリノイ州ピオリア(訳注:play
in Peoria〈一般受けする〉という英語の成句でも知られる)に列車で到着した」という一文があって、当方の目は「play in Peoria〈一般受けする〉」に釘付けになった。
で、なにをおもったのかと云うと、そうか、キング・クリムゾンのカセットテープ録音ライヴと云われているアルバム「アースバウンド」収録の、ピオリアで演奏したインプロ風セッション曲のタイトル「Peoria」はこの成句を反映したタイトルで、実は〈一般受けする〉というジョークだったのか、半世紀以上経って初めて知ったぞ、ということだった。Wiki を見ると、
テスト市場としてのピオリア
米国では、ピオリアは、その代表的な人口構成と、一般に主流と認識されている中西部 の文化のため、長い間、典型的なアメリカの都市とみなされてきた。その結果、ピオリアは伝統的に国内有数のテスト市場の1つであった。1980年代から90年代にかけて、サム・キニソンのようなコメディアンや、ボブ・ディラン、ロバート・プラント、メタ リカ、フィル・コリンズなどのミュージシャンは、すべてピオリアでコンサートツアー を完成させ、開始した。(自動翻訳)
とある。「アースバウンド」が出た1972年でもアメリカ人には常識だったのかなあ。
 昨年のハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作品のもう一方、犬怪寅日子『羊式型人間模擬機』は150ページ足らずの長編。でも気に入ったという意味では『コミケへの聖歌』と違って何の文句もない。あるとすればやはり「SF」としては境界的な作品だったこと。
昨年のハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作品のもう一方、犬怪寅日子『羊式型人間模擬機』は150ページ足らずの長編。でも気に入ったという意味では『コミケへの聖歌』と違って何の文句もない。あるとすればやはり「SF」としては境界的な作品だったこと。
当方の感想も審査員の神林長平や菅浩江のそれと一緒で、これが山尾悠子的な幻想小説とファンタジー大賞の受賞作に多いリアリズムで描かれるエンターテインメントスタイルとの間にあるような作品に仕上がっている。『羊式型人間模擬機』というタイトルが内容を現しているのかどうかはやや疑問。表紙の下に英文タイトルがあって「The Android Slaughters Human Sheep」。これだとSFっぽい響きが強く内容に対してやや味気ない感じがする。
冒頭に家系図が置かれていて、読み終わったあとに見返せば、これが語り手であるメイドアンドロイドの出自から現在までに仕えたこの家系の構成員回顧録であることが判る。
この物語にいわゆる筋書きがなく、この作品における現在は、大旦那様が御羊様(おひつじさま)になったのを語り手が発見して、4人の孫をはじめとする現存する一族に料理として供するため語り手が御羊様を解体しているところで終わる、わずか2日間しかない。この2日間の現在だけだと確かに英文タイトルに近いかも知れない。
しかし実際の作品世界はこの一族の屋敷と周囲の土地だけで、その点でこれは拡がりのある現実の世界ではなく幻想世界のつくりだ。語り手は一族のメイドとして作られ、語り手の視野には一族と屋敷の周辺しか存在しない。極端に狭い世界と視野だけれど、だからこそ成立させることが出来たとも云える。
作品世界は閉じているけれども読み手には開かれている。「SF」かどうかはともかく好みであることは確か。
 岡本俊弥さんの書評を見て面白そうだなあと手を出したのが、馬伯庸(マー・ポーヨン)『西遊記事変』。タイトル通り三蔵法師とその弟子が天竺へお経を取りに行く冒険譚を、その舞台裏があったらこんなものだったかもという想像力の遊びで料理した1作。作者が楽しんで書いていることがよくわかるノリの良い物語になっている。
岡本俊弥さんの書評を見て面白そうだなあと手を出したのが、馬伯庸(マー・ポーヨン)『西遊記事変』。タイトル通り三蔵法師とその弟子が天竺へお経を取りに行く冒険譚を、その舞台裏があったらこんなものだったかもという想像力の遊びで料理した1作。作者が楽しんで書いていることがよくわかるノリの良い物語になっている。
西遊記の舞台裏で冒険譚の演出を支えたのが主人公の、原題にもあるように、太白金星こと李長庚。ここでは道教の仙人として年寄り扱いだが、読んでいるとそれほどの歳とは感じられない。
三蔵法師の取経は本来仏教説話だけど西遊記は道教重視で作られているため、ここでは三蔵法師担当の観音の話によれば、仏祖と天帝の間で李長庚が観音と一緒に三蔵法師の81の劫難の作成を担当することになったというところから始まる。ということで、李長庚とは因縁のある孫悟空をはじめとする3匹の弟子や天界地上界の仙人・仏弟子・妖怪どもを巻きこみ、李長庚が中間管理職的苦労を嘗めながらテンヤワンヤを展開していく。
ポケット・ミステリから出ているし、帯には「孫悟空は偽物だった!?」とか書いてある上「華文ミステリ」と謳ってはいるけれど、どうみても奇想ファンタジーだよね。
当方は『西遊記』そのものを読んだことはなく、最初は小学生の時に手塚治虫が参加した東映の長編アニメで知って、大人になってからは邱永漢の文庫8巻セットを読んだ。その後中野美代子の概説書も読んだので一応の内容は知っている。中野美代子訳の岩波文庫も読むべきとは思うが、もう遅いか。
 現物を手にしてその薄さにビックリしたのが、ハヤカワ文庫SFから出たデュナ『カウンターウェイト』。韓国SF。200ページしかない。
現物を手にしてその薄さにビックリしたのが、ハヤカワ文庫SFから出たデュナ『カウンターウェイト』。韓国SF。200ページしかない。
韓国企業の超富豪が中心となって宇宙エレベータがインドネシア近海の島国に実現している時代、視点人物はその企業の対外業務部長としてトラブルシューティングを担当。この時代の人間は脳にナノテク機器をいれている。
様々な政治的錯綜も含めて一種の企業内諜報合戦のような趣があり、『攻殻機動隊』第2巻の世界を髣髴とさせる。もっとも物語としては『攻殻』のような電脳世界でのドラマには行かず、あくまでも現実世界の複雑な仕掛けとしてテクノロジーは駆使されている。サイバーパンクともいえないけれど、そういう時代を経た後の現代SFエンターテインメントになっていることは確かだ。
文庫の裏表紙にある内容紹介を見たら「アクションSF」とあった。そうだったのか。
 創元文庫SFから山本弘『時の果てのフェブラリー』が未完の「宇宙の中心のウェンズデイ」とセットで再刊されたので読んでみた。
創元文庫SFから山本弘『時の果てのフェブラリー』が未完の「宇宙の中心のウェンズデイ」とセットで再刊されたので読んでみた。
山本弘追悼出版という意味合いがあるのは大森望の解説を読めばよく分かる。なお当方はリアルタイムでは本書を読んでない。当時は新井素子に代表されるスタイルの作品はピンと来なかったので敬遠していた。栗本薫さえほとんど読んでない。そういう意味で山本弘もなかなか視野に入らなかったのは確かである。
いま読むとSFならではのエンターテインメント性は抜群だけれど、この(疑似)親子関係のベッタリ具合は鬱陶しい。続編の方はウェンズデイと男子ふたりの朗らかセックスが却って邪魔かも。続編の方が中断したのは、ハードSFを自負する作家として、この4半世紀の揺れ動く宇宙論にもっともらしい理屈が付けにくくなったことも影響しているのではと思いました。
 まったく聞いたこともない作家のSFがいきなりハヤカワ文庫SFで出た。それも古澤嘉通さんの訳で。
まったく聞いたこともない作家のSFがいきなりハヤカワ文庫SFで出た。それも古澤嘉通さんの訳で。
それがA・J・ライアン『レッドリバー・セブン・ワン・ミッション』。タイトルからではどういう話なのかまったく予想が付かない。
取りあえず読み始めたら、目覚めた視点人物がいきなり銃声のようなものを聞いたと思って周囲に目をやると、頭を吹き飛ばした男の死体が船べりに見えた。ここはどこ、俺は何者だ・・・。
と云うことで、五里霧中の語り手は自分が船に乗っており周りは赤い霧で何も見えないが、船/ボートには他人がいることを知り、警戒しながらなんとか話を通じさせることが出来た。乗員は自殺した男を含め7人。残りは女が3人で男も3人。船は自動操縦でどこかに向かっているらしい・・・。
ここまで読めば、タイトルの意味はかなりハッキリしてくる。すなわちこれは何らかの任務に就かされた7人ということだ。
読み進めると、大まかな設定として、人間はもちろん生物を凶暴化させる、コロナ禍がヒントになったような、何かが世界中に蔓延して、ここではその発生地を目指して赤い霧が覆う河に向かっていることがわかる。すなわち「レッドリバー」。
ここまでくれば、これはストレートなジェットコースター型の冒険SFで、最初に死体があるように皆殺しタイプのそれである。
牧眞司さんが書評でホラー系の作家を引き合いに出したように、一枚一枚扉を開けていくホラーな叙述スタイルが顕著だ。個人的にはホラー不感症なので結末は感心したけれど、視点人物に引き込まれるような感覚は無かった。あと、自分の名前を失った7人の腕にはそれぞれ有名作家名が入れ墨されているけれど、その割にはシルヴィア・プラスの名を割り当てられた女ぐらいしか名前にふさわしい行動をしていないように思えた。
タイトル的には、「荒野の七人」とそのご先祖「七人の侍」が思い浮かびました。
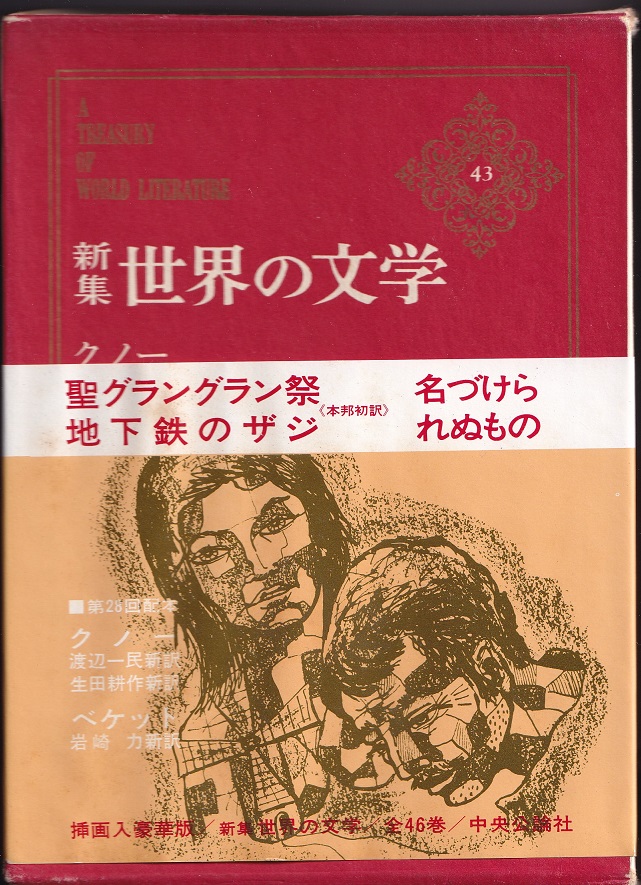 今回は薄い本ばかりでやや余裕があったので、もう10年以上も枕元で積ん読になっていた中央公論社版『新編世界の文学43 クノー/ベケット』収録の『聖グラングラン祭』と『地下鉄のザジ』を読んでみた。昭和45年12月刊。
今回は薄い本ばかりでやや余裕があったので、もう10年以上も枕元で積ん読になっていた中央公論社版『新編世界の文学43 クノー/ベケット』収録の『聖グラングラン祭』と『地下鉄のザジ』を読んでみた。昭和45年12月刊。
『聖グラングラン祭』は渡辺一民訳で、40年後に水声社のレーモン・クノー・コレクション同訳者による改訳版が収録されている(訳者はその2年後に歿した)。『地下鉄のザジ』の方は生田耕作訳でいまでも中公文庫で現役のようだ。ただし改訳はされているだろう。この翻訳では「めっかち」「めくら」「片輪」をはじめ当時は普通に使われていたが、現在は避けられる言い回しが満載だから。なお新訳版が2011年にやはり水声社のコレクションに収録されていて、生田訳と比較をしながら新訳版を推奨したHP「Riche Amateur」もある。
『聖グラングラン祭』は1948年刊行で『地下鉄のザジ』は1959年刊。前者はリアリズム小説からまったく離れた完全な奇想小説で、当時としてはシュールレアリスム的な作品だったかも知れない。一方『地下鉄のザジ』は、表面的には悪ガキ娘が大活躍するドタバタ喜劇で、ベストセラーになり、2年後にルイ・マルが映画にしてこれまた大ヒット。現在でも『地下鉄のザジ』をググると映画の方がヒット数が多い。解説によると作者はベストセラーになったことに大いに失望したらしい。
『聖グラングラン祭』を読んでから『地下鉄のザジ』を読むと確かにその教育的効果が読み手に伝わるようになっている。
 『聖グラングラン祭』は、〈ふるさとの都〉の市長の役立たずの長男が〈異国の都〉で通訳の修業をさせられていたが、その長男は水族館で魚に〈水在〉を認めて哲学的思想に目覚め、故郷へ帰ることにしたところから始まる。〈ふるさとの都〉は〈聖グラングラン祭〉が始まって市長が機関銃で何万という陶器を粉砕して取り巻きの喝采を受けるが、この市長は〈雲追い石〉で〈ふるさとの都〉に晴れの日だけが続く天気をもたらした男だった。そしてせっかく〈奨学金〉を工面したのに学業を蹴って帰ってきた長男に失望した市長は長男を追い出す・・・。
『聖グラングラン祭』は、〈ふるさとの都〉の市長の役立たずの長男が〈異国の都〉で通訳の修業をさせられていたが、その長男は水族館で魚に〈水在〉を認めて哲学的思想に目覚め、故郷へ帰ることにしたところから始まる。〈ふるさとの都〉は〈聖グラングラン祭〉が始まって市長が機関銃で何万という陶器を粉砕して取り巻きの喝采を受けるが、この市長は〈雲追い石〉で〈ふるさとの都〉に晴れの日だけが続く天気をもたらした男だった。そしてせっかく〈奨学金〉を工面したのに学業を蹴って帰ってきた長男に失望した市長は長男を追い出す・・・。
大枠だけでストーリー構成を単純化すると、市長は長男に始末されて銅(ではないが)像となり、長男が後を襲って市長になると〈雲追い石〉が外されてずっと雨が降り続くようになる。それに我慢ならない有力者達が市長職を次男に継がせ、市長だった長男は雨で溶けた市長の像を石に刻む彫刻家になる。年がめぐって雨の中の『聖グラングラン祭』が終わると、最終的には一番下の3男が、隔離されていた奇妙な妹を連れて戻ると、新しい市長になり、〈ふるさとの都〉に晴れ間が射してきて幕となる。
実際の物語のディテールは解説にもあるとおり造語だらけで、多数の登場人物が出入りし、細かいエピソードが積み重ねられていく。また時代的には映画が発明されて新規なものとして流行している。たとえば次男は映画の中の女優に熱中し、たまたまその女優がこの都を訪れたとき次男は一目惚れで結婚してしまうのだった(すなわち女優は市長夫人になる)。
作品としてはそれ自体が小説であることに自覚的に作られていて、いわゆるリアリズム小説が齎すような感想を読者に抱かせようとしているのではないことはよく分かる。面白いかといわれれば面白いし、何かわかるかといわれれば何も分からないというしかない。
なお、開巻1ページ目に聖グラングラン祭は「フランスの民間伝承で、けっしてはじまらない想像上の祭のこと」と訳注がある。
 『地下鉄のザジ』の方はWikipediaがあるくらいの有名作なので、内容や特徴についてはそれを見ればいいんだけど、一応簡略なストーリーを紹介しておこう。
『地下鉄のザジ』の方はWikipediaがあるくらいの有名作なので、内容や特徴についてはそれを見ればいいんだけど、一応簡略なストーリーを紹介しておこう。
母が愛人と過ごすため、一緒に田舎町からパリにやって来た口の悪い腕白小娘(10才!)ザジが、伯父のガブリエル夫婦の借家に預けられると、早速逃げ出してパリをさまよう。伯父とその周囲の大人や見知らぬ大人たちは変人ばかりではあるものの、その大人たちがザジに振り回される。地下鉄に乗りたくてやって来たザジなのにスト中で乗れず、一晩の間に街で冒険しおえたザジは、せっかく再開した地下鉄に乗せられて母の元に返ったときは白河夜船で寝ていて地下鉄に乗った記憶は無いままだった。というぐらいの話だとは、映画のヒットもあって年寄りのヒトには、なんとなく見当が付くだろうけど、これは『聖グラングラン祭』で見せたクノーの手管がそこら中に張り巡らされているかなり謎めいた1篇(そのこともWikiに説明がある)。
ザジにホモかと問い詰め続けられる伯父ガブリエルは、タクシー運転手の友人とともにパリは初めてというザジをエッフェル塔に連れて行くが、友人はザジをおいて塔を下りてしまいザジには二度と会いたくないと云って去ってしまう。一人になったガブリエルは作中でも「芝居がかった」といわれるこんなセリフを吐いている。
「ガブリエルは(すばらしい)幻、ザジは夢の(あるいは悪夢の)幻、そしてこの物語はすべて夢のまた夢、幻の幻、たかだか間抜けな小説家が(おっと!失礼)タイプで打ちまくったうわごとにすぎない」
これはむしろ『聖グラングラン祭』にふさわしい言い分だけれど、クノーは一応のミエは切って見せている訳だ。しかし一番印象に残るセリフはザジの口癖「けつ喰らえ」だろう(新訳版は見ていないが、先に紹介したHPを見ると「オケツぶー」らしい)。
『聖グラングラン祭』は上下2段組で200ページ、『地下鉄のザジ』はたったの130ページ。翻訳はどちらも素晴らしい出来で、時代的制約はあるけれど、年寄りの当方にはあまり違和感がなかった。なおベケットは読んでない。
 |
 |
東京創元社海外文学セレクションとして出た、こちらも古澤嘉通さんの訳になるR・F・クァン『バベル オックスフォード翻訳家革命秘史』は、ハヤカワ文庫SFの薄いのと違って、ハードカヴァー上・下巻合わせて750ページ以上という大長編。ぱっと見には上巻が450ページで下巻が300ページ余り、なんでと思ったけれど、読めばその理由は分かるのだった。というか値段が高くなるのを別にすれば1冊本でも良かったかも。
プロローグは1829年の広東でコレラが流行して多数の死者が出たとき、母親を失い孤児となった少年をオックスフォードにある王立翻訳研究所「バベル」の教授が連れだしてイギリスに向かうところから始まる。この少年は英語の家庭教師に鍛えられ英語は堪能だったが、渡英にあたり教授によって英国風の名前を考えさせられ、その答えが「ロビン・スウィフト」、すなわち主人公である。なお、ロビンは白人との混血児であり、教授が父ではないかと疑うようになる。
と云うことで始まる本編は、ロビンを視点人物にして教授の家での徹底した語学教育(古代ギリシャ語・同ラテン語)が施される。そしてオックスフォードに入学を果たしたロビンは、運命を共にしてもいいと思うくらいになるロビンと同じ才能を持つ同期生、インド系の少年とハイチ系の黒人女性そして兄の代わりに入学したというイギリス白人女性に出会い、この4人がロビンにとって学生生活の中心になる。実際彼らの大学生活がこの長い物語の前半を形づくっている。なぜか下巻の腰巻にある「友情と相克、そして青春の終わり」ですね。
しかし、そこに暗い影を落とすのが、あるとき「バベル」から盗みを働く自分そっくりの男を見てロビンはなぜかその盗賊の行為を手伝ってしまい、後にその盗賊から自分はロビンの異母兄であると知らされ、かれが属している反「バベル」秘密組織「ヘルメス」に協力するよう求められロビンが迷いながらも頷いてしまう。このことでロビンは「バベル」での多言語翻訳者養成が最終的に大英帝国の侵略的性格を支えるためのものであると知る・・・。
このドラマ部分では、前半においてロビンは受け身のキャラクターとして描かれ、この小説世界の案内役を果たしている。物語進行のパターンはヴォネガットいうところに「シンデレラ」パターンを繰り返しながら、その振り幅が大きくなっていくタイプに見えて、エンターテインメントの王道を行くが、上巻の最後に起きる事件によって、ロビンは主体的にならざるを得なくなり、下巻に入ると「シンデレラ」パターンは振り切れてしまい元に戻らなくなって、先の読めない展開になる。
そのような物語の進行の一方で、この物語を魅力的なものにしているのが、上巻のダストジャケット見返しの設定紹介「銀と、ふたつの言語における単語の意味のずれから生じる翻訳の魔法によって、大英帝国が世界の覇権を握る19世紀。」という設定上の大枠である。この小説の魅力は「銀」の棒の裏表に彫られる言葉の意味の重なりと違いの「意味のずれ」が帝国を支えるほどのエネルギーを生み出すというある意味バカげたアイデアであり、しかしその尤もらしさを支えるために投入された膨大な言語(主に単語)に関する歴史的な蘊蓄の山なのだ。「バベル」の翻訳者養成はこのエネルギーを大英帝国の力の源泉とするため行われており、反「バベル」組織「ヘルメス」はこのシステムとどめを刺すことを目的として一度は「バベル」に籍を置いたメンバーで作られていた。すなわち副題の「翻訳家革命秘史」である。それがどのように成就するのかしないのかは下巻を読んでのお楽しみだけれど、作者が中国出身であることもあっていわゆるアメリカ人には出来ないと思われるやり方で作られている。
訳者の古澤さんが、『アンドロイドは電気羊の夢をみるか』のあの有名な浅倉さんのあとがきを引用したくらいの作品なので、その面白さはいわゆるエンターテインメント以上のものがある。
とはいえ、当方も手放しでその出来の良さを納得している一方で、じつは読後感を反芻している内に、これはファンタジーだから成り立つ話であってSFとしては説得力を持たせられないかもと思い出した。この作品は設定の面白さ、それを支えるディテールの凄さ、そしてドラマのハラハラドキドキが予定調和しない結末のへの驚きなどほぼ満点の出来だけれど、「銀の棒に刻まれた同じ意味持つと同時にまったく違う意味を持つふたつの言葉の懸隔からエネルギーが発生する」というのは「魔法」のアイデアでとしては素晴らしいけれど、SFにしたら説得力が無いように思われるのは「書き文字と発音の関係は必然性がない」というのが言語学の常識のように思われるからだ。
どういうことかというと、「新しい」を「あらたしい」と読まずに、「あたらしい」と発音することは「新」の読みとしては明らかに間違っているけれども、発音としてはそれが正しいと認められて既に数百年が過ぎていてもはや直す意味が無くなっており、最近だと中世由来の「一所懸命」が元の意味を失って訛った発音である「いっしょうけんめい」に「一生懸命」と当てて怪しまないということだ。すなわち、いくら厳密に書き文字の言語的変化を調べ上げても「正しい読み/発音」は存在しないので、2千年以上前の言語の文字や世界中のローカルな書き文字から「正しい読み/発音」を導くことは出来ない。
「正しい読み/発音」とは単なる権威主義に過ぎないわけで、それが銀の棒に刻まれた文字のエネルギー発生を発語によって開始するということに理屈は付かないだろうと思われる。第一書き文字を持った文明は限られている。発音とその意味は人類の歴史が始まって以来、千差万別に存在したろうが、書き文字はそうではなく、文字は解読可能性が残されているけれども、その発音は類推でしか体系化出来ないだろう。書き文字はたとえ読めなくてもそこに意味が込められていると推測できる、というかそれだから文字だと認めるわけだけれど、発話は聞く側に同じ言語システムが組みこまれていないと単なる雑音にしか聞こえない。それが長い間「バルバロイ/野蛮人」の判断基準なってきたわけだ。
ウーム、そうすると発音することでそれに対応する現象が起きると設定するには相互理解が前提になるのか。だから言語SFは大抵(でっち上げの)言語体系が問題にされているワケか。単に呼びかけるだけである現象が発生するのは魔法/ファンタジーなんだ。
なぜか今回は長編ばかりだったなあ。
ノンフィクションを2冊。
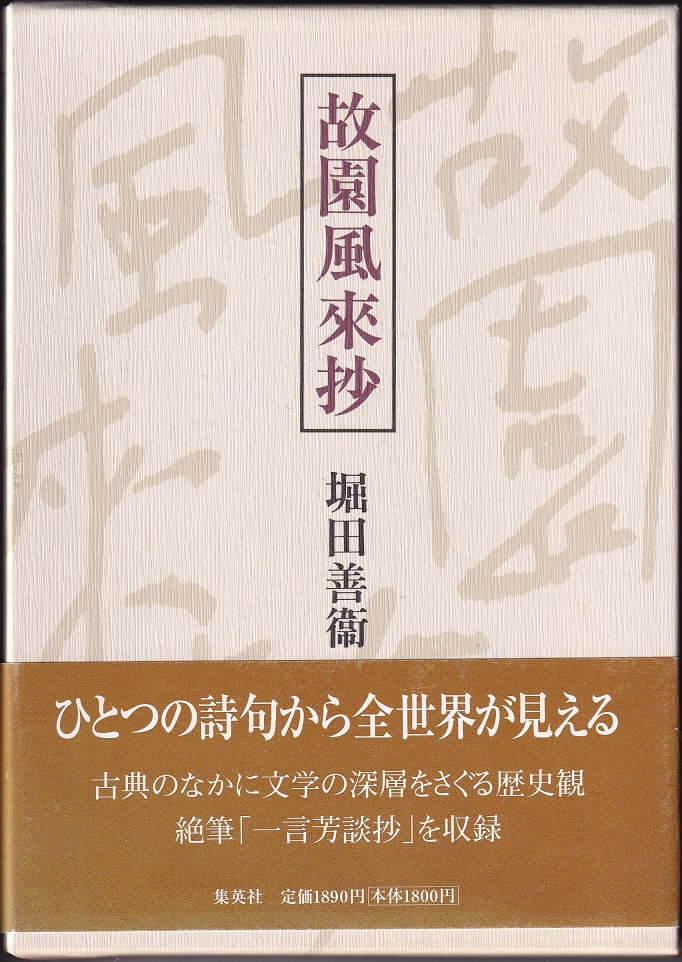 広島市の繁華街にある行きつけの古本屋には、やや離れた裏筋に廃業した古書店を居抜きで引き継いだ支店がある。そこはカープグッズ買い取りを謳い文句にした店なのでいつもはあまり立ち寄らないのだけど、久しぶりに店の軒下に並べてあるいわゆるワゴンサービス本を眺めていたら、えらくキレイな函入り本が光って見えたので抜いてみた。
広島市の繁華街にある行きつけの古本屋には、やや離れた裏筋に廃業した古書店を居抜きで引き継いだ支店がある。そこはカープグッズ買い取りを謳い文句にした店なのでいつもはあまり立ち寄らないのだけど、久しぶりに店の軒下に並べてあるいわゆるワゴンサービス本を眺めていたら、えらくキレイな函入り本が光って見えたので抜いてみた。
これが堀田善衛『故園風来抄』だった。帯が僅かに破れていてテープ止が目に付いたが、箱も帯もヤケシミなしで、函を下に向けても抜け落ちないが振ると少し本体が顔を出す。これはと思い本体を出すとまったくの手つかず状態。パラフィン紙は掛かってないもののほぼ新品である。奥付は1999年6月。初刷りの集英社本。で、値札を見たら殴り書きで「110」とあった。さすがに驚いたけれど、110円ならゴミ本でも気になれば買ってしまう値段。さっそく店の奥のレジで110円出して入手した。
『故園風来抄』自体は、「冷泉家時雨亭叢書」月報に連載した短い古典文学にまつわるエッセイを収録、巻末に絶筆となって未完となったエッセイを収録したもの。買った当初は、読む気は無かったのだけれど、手元に置いていたらなんとなくその気になって読んでしまった。堀田善衛の著作はたぶん読んだことがない。『方丈記私記』とか『定家明月記私抄』など古典に関する著作は有名だけれど当方は手は出してない。あと『ゴヤ』とか『ミッシェル 城館の人』とかのヨーロッパものの大作もちょっと気にはなったけどね。そういや岩波新書の『インドで考えたこと』は椎名誠がパロディタイトル本を書いていたっけ。 このエッセイは本編が時代順だったせいか、『懐風藻』など平安漢詩集からはじめて『古事記』『万葉集』から『古今和歌集』『源氏物語』そして定家を通って、西行・実朝へ行き、『徒然草』『方丈記』の中世文学と戦国の史書へ、最後は一休禅師で閉じて、絶筆エッセイになる。エッセイ自体はテーマとなる作品や作者にかなりヒネったスポットを当てるものになっていて読めば面白い。
たとえば『古事記』『万葉集』のところでは、戦争末期の海軍将校の死出の旅を前にした宴会の荒れっぷりを投げ捨てられた『万葉集』に見て、また神国日本の『古事記』神話に怖気をふるって堀田善衛は長い間この2冊をちゃんと読むことが出来なかったという。 しかしこのエッセイでは、日本創世神話には旧約聖書の創世神話を重ね、『源氏物語』にはプルーストを、『梁塵秘抄』に「カルミナ・ブラーナ」を重ねて、式部にプルースト並みの強烈な自意識を、中世俗謡にヨーロッパのそれを当てて見せるのは、やはり戦前に教養を築いて戦争をくぐり抜け(堀田善衛は中国にいた)、戦後はヨーロッパで西欧文化の知見を深めた、あの時代の典型的な知識人/作家だなあという感じがする。
でも、この連載を始めるまで一休宗純「狂雲集」を読んだことがなかったというのはホンマかいなとおもったけれど。森女とのセックス満載、男色も歌うエロ漢詩集は当方も何十年か前に読んでその解説にビックリしたので、堀田善衛の興奮振りはよく分かる。
堀田善衛も、今後は宮崎駿の尊敬する作家ということで話題になるくらいで、忘れられていくのだろう。
 小川原正道『西郷従道―維新革命を追求した最強の「弟」』は昨年8月刊の中公新書。この手の本も現役時代ならすぐに読んだろうけど、もはや気が向けば程度になってきた。 西郷従道は西郷隆盛の15歳下の弟。9歳の時に両親が死亡、隆盛が親代わりだった。従道は「つぐみち」と読むことになっているが、本人は「じゅうどう」と自称していたという。名前に関しては幼い頃から薩摩藩主の茶坊主をしていたこともあり、隆興というのが本名だったらしい。18才で茶坊主を止めて還俗後信吾と名乗った割には、戸籍を作るときに隆興(りゅうこう)が訛って従道(じゅうどう)と書かれ登録されたとか。まあ当時としてはよくある話である。
小川原正道『西郷従道―維新革命を追求した最強の「弟」』は昨年8月刊の中公新書。この手の本も現役時代ならすぐに読んだろうけど、もはや気が向けば程度になってきた。 西郷従道は西郷隆盛の15歳下の弟。9歳の時に両親が死亡、隆盛が親代わりだった。従道は「つぐみち」と読むことになっているが、本人は「じゅうどう」と自称していたという。名前に関しては幼い頃から薩摩藩主の茶坊主をしていたこともあり、隆興というのが本名だったらしい。18才で茶坊主を止めて還俗後信吾と名乗った割には、戸籍を作るときに隆興(りゅうこう)が訛って従道(じゅうどう)と書かれ登録されたとか。まあ当時としてはよくある話である。
従道が明治13(1880)年に東京の目黒に建てたという接客用の2階建て洋館(維新の元勲達はあちこちに別荘を持っていた。京都南禅寺界隈にもいっぱいある)は、現在明治村に移築されて重要文化財になっているので、見た人も居るだろう。
この人物は薩摩出身の大物政治家の信望が厚く、兄隆盛が西南戦争の首魁となった時は、東京で政府軍側のバックアップを担当し、その後は陸軍・海軍・農商務・文部・内務の大臣(卿)を勤めた。特に海軍大臣は足かけ10年に及んで明治20年代の海軍拡張を担当したこともあって、呉をはじめとする鎮守府の初期の歴史には欠かせない人物だった。
と云うことでちょっと期待して読んだのだけれど、従道の一生を追う形になっている新書なので海軍関係はあまり面白い話がないのだった。
この本には書いてないが、呉との関わりでは、日清戦争で広島に大本営があったころ、足かけ8年のヨーロッパ派遣から帰ってきて当時の海軍造兵部門のホープだった山内万寿治(やまのうちますじ)少佐が海軍大臣の従道に伴われて伊藤博文首相の宿を訪ね、山内が直接首相に向かって艦艇搭載兵器の国産(造兵)の必要性を説いた。首相の部屋を出た直後、従道は汗をふきふき山内に「イヤどうもまことに御苦労で御座りました」と云ったとか。
この時の演説が効いたのか、山内は日清戦争が終わった明治28年に後に呉工廠となる造兵施設の建設責任者として呉にきて、その後14年間呉に居住し、最後は呉鎮守府司令長官になった。一度も軍艦の艦長も艦隊司令も経験せずに鎮守府長官になった海軍唯一の人物という。また山内はシーメンス事件で検察に収賄について訊問され海軍と関係を絶った後、没年(59才)の大正8(1919)年に自費で日本初の地熱発電用蒸気噴気孔を別府で試掘した。現在は日本で最初の地熱発電開発者として、地熱発電の歴史解説のトップに出てくることで知られる。なお、日本で地熱発電が行われるのは戦後になってから。
山内は海兵6期のクラスヘッドだったけれど、首相経験者で内大臣(宮内大臣)の時に二・二六事件で暗殺された斎藤実とは同期で親友だった。明治19(1886)年に従道が海軍大臣として欧米視察に出たとき、斎藤はアメリカの駐在武官だったが、アメリカにいてもお役に立てないから日本へ返してくれと従道に頼んだという。従道は英語に堪能な斎藤を伴ってヨーロッパへ行き、斎藤はロンドンで山内に再会している(ちなみに斎藤は21年に帰国した)。
あと、初代横須賀鎮守府長官を務めた後に初代呉鎮守府長官となった佐賀藩海軍出身の中牟田倉之助が、明治23(1890)年に呉に天皇を迎えての開庁式を無事終えたその夜、謹厳実直を絵に描いたような中牟田が宴会で酔っ払っているのを見た従道が、中牟田の赤い顔をからかっている。
ちなみに中牟田は従道より6才年上。幕末は上海で高杉晋作の通訳をしたり、維新の時は官軍の船の艦長として榎本武揚の旧幕府海軍と箱館沖で戦い船を喪っている。
この半世紀の内に近代史の人物研究は、書簡類を始めとした生資料を駆使して書かれることが普通になったけれど、この従道伝もその手の資料を博捜して書かれている。なお西郷従道は明治35(1902)年に59才で歿したが、同年に簡易な伝記が出たほか、いまから45年前に孫が書いた厚い1冊がある。どちらもデジコレで可読。憲政資料室の従道関連書簡類もかなり読めるようだ。
この本は内扉の著者名が誤植になっていることで一時話題になったけれど、誤植訂正のお詫びスリップが入っている。あとがきで謝辞を捧げられている編集者は可哀想というしかない。
『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ
THATTA 442号へ戻る
トップページへ戻る
 昨年のハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作品のもう一方、犬怪寅日子『羊式型人間模擬機』は150ページ足らずの長編。でも気に入ったという意味では『コミケへの聖歌』と違って何の文句もない。あるとすればやはり「SF」としては境界的な作品だったこと。
昨年のハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作品のもう一方、犬怪寅日子『羊式型人間模擬機』は150ページ足らずの長編。でも気に入ったという意味では『コミケへの聖歌』と違って何の文句もない。あるとすればやはり「SF」としては境界的な作品だったこと。