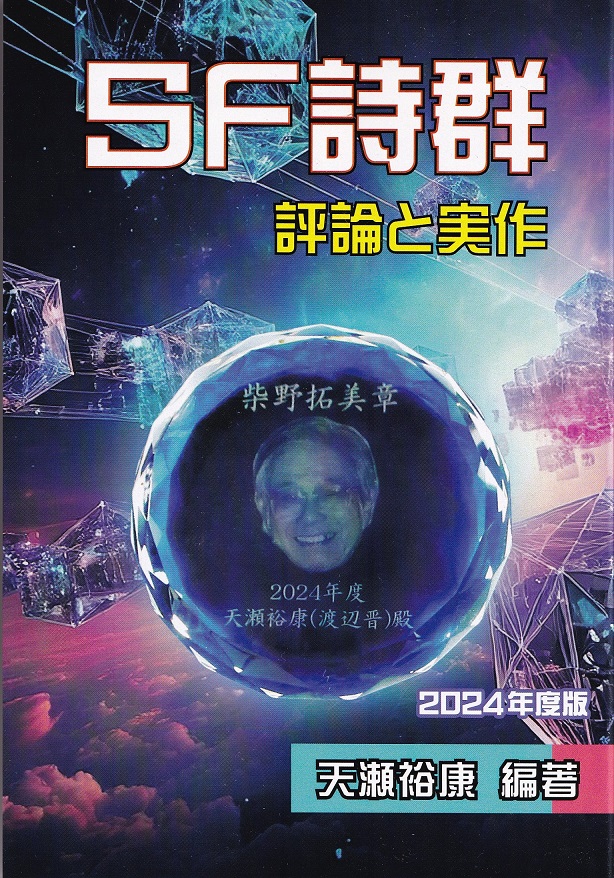 |
 |
|
続・サンタロガ・バリア (第267回) |
筒井康隆『敵』が映画化されて、東京国際映画祭三冠受賞の話題もあって、どれどれと公開早々広島まで見に行ってきた。土曜の昼と云うこともあってなかなかの入。
映画の『敵』の出来は上々で、30年近く前の原作のイメージをアップトゥデートした形で、スタンダードサイズモノクロ画面の効果が活かされた作品になっていた。パンフの長塚京三インタビューにもあったけれど、冒頭で暫く続く主人公の日常生活が丁寧に作られていて、特に自炊して食べる毎日の料理がウマそうに見えるが素晴らしい。安部公房『箱男』の映像化を思うとこちらの見事さには感心させられる。そうか、『箱男』もスタンダードサイズモノクロ画面で撮っていれば印象が違ってたかも。
後半主人公が見る夢/妄想の映像では「押し寄せる難民」がギャグっぽくて、当方の趣味とややズレているけれど、全体の出来の良さからすれば無問題でしょう。
終映後、かなりの人数の観客が無言でゾロゾロと出て行ったのを見ると、みなさん感じるところがあったのかなと思いました。
そういや昔読んだときにここに感想文を書いたなと思い、大野万紀さんが毎回更新してくださるReview Indexから当時の掲載号を見てみたら、ちゃんと褒めているではないか。もっとも当時当方はまだ40代後半だったから、古稀を迎えた現在とは感じ方が変わっているだろうけれど、筒井康隆が60代に入って以降に書いた作品としては最高の部類に入る1作ではあったと今でも思う。しかしわれながら「博物誌」という感想は何だったのだろうと思う。いま見た映画からはそんな感想は湧かないけど。
あと『SF詩群』2024年度版が無事発行されたので一応渡辺直己の歌碑にご挨拶に行ってきたのだけれど、肝心の『SF詩群』を忘れたのは申し訳なかった。と云うことで再度行って証拠写真を撮っておきました。『SF詩群』の表紙は「やねこんR」で天瀬裕康さんが受賞した柴野拓美賞のメダルです。ちなみに天瀬さんは、渡辺晋名義で先にこの章を受賞しておられ、2度目の受賞とのこと。表紙デザインは同人誌『イマジニア』の表紙画及びデザインも担当されてる泉尾祥子さんです。
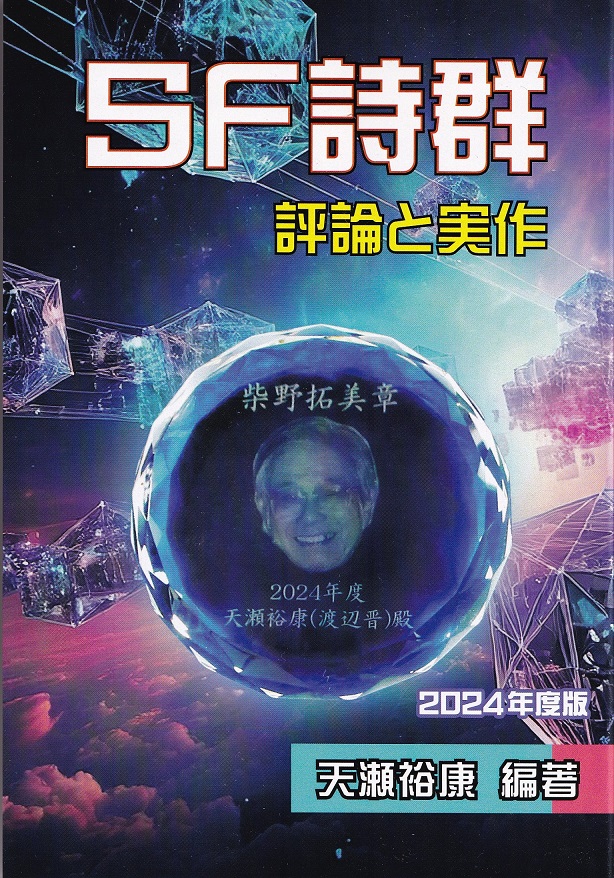 |
 |
今回取りあげた作品は昨年出版のものがほとんど。
 マーガレット・アトウッド『老いぼれを燃やせ』は昨年9月刊の短編集。視点人物が高齢女性の作品がほとんど(高齢男性の場合もある)だけれど、原書は2014年刊で、1939年生まれ作者がこれを書いたのは60代から70歳になった頃と思われる。
マーガレット・アトウッド『老いぼれを燃やせ』は昨年9月刊の短編集。視点人物が高齢女性の作品がほとんど(高齢男性の場合もある)だけれど、原書は2014年刊で、1939年生まれ作者がこれを書いたのは60代から70歳になった頃と思われる。
最初の3篇「アルフィンランド」「蘇りしもの(レヴェナント)」「ダークレディ」は、連作で1話では、若き日無名詩人の男と同棲していた女性老ファンタジー作家が視点人物。 若さに任せたセックスだらけの日々だったが、女は生活費稼ぎに表題のファンタジーを書き、それが後に人気作となる。しかし男が浮気して分かれ、女はファンタジー作家として活躍、家庭も築いた。男の方はようやく出した詩集が評価されその後は文学者となる。夫も亡くなり一人の生活の中で詩人との思い出が日々の生活と交互に語られる。
2話になると、元大学教授となった詩人はかなり年下の女(おそらく文学部の講師)と暮らしつつ、若き日の彼の作品を研究する学生たちがいて、女の紹介で来た女子大学院生の相手をする。詩人は退屈したような対応を見せるが、実は大学院生の研究テーマは女性ファンタジー作家であり、自分はその研究の一材料であったことを知る。
3話では、話の中心が詩人が浮気した女に移り、詩人が亡くなった後、彼と関係したファンタジー作家、詩人の未亡人、女子大学院生そしてこの女が勢揃いしてドタバタになる。
ファンタジー作家の視点が一番強いせいもあって、途中からこれはル・グィン書いた作品だと勘違いしながら読んでしまった。ル・グィンにしては性的な話題でのドライであからさまな書き方に違和感があったけれど。
「変わり種」は10ページの掌編。語り手は女の子として生まれたがいつの間にかヴァンパイアになってしまった娘。飄々とした語り口で自らの生い立ちから滅びまでを語る。
「フリーズドライ花婿」も奇譚で、視点人物は中身を見ずに倉庫を買い取るギャンブルみたいな商売をしているが、新しく3棟をセリ落としてひとつひとつ検分していったら、最後の1棟に入っていたのは・・・というもの。そりゃビックリするよね。
「わたしは真っ赤な牙をむくズウィーニアを見た」は、仲良しリタイア女性3人組のおしゃべりで紡がれた1篇。「ズウィーニアの夢を見たの」で始まる。訳者解説(鴻巣友季子)を読むと、これは1993年の作品『寝取る女』のスピンオフとのこと。この3人はズウィーニアに夫を寝取られたらしい。
「死者の手はあなたを愛す」は若き日に書いたエンターテインメント作品がその後の作家生活を支えたという意味で、冒頭のファンタジー作家や詩人と重なる。こちらは貧乏学生が数人でアパートメントを借りる中、家賃の分担金も払えない作家志望の若者が遂に1作をものにしたところ、それまでの借金の形として他のメンバーに均等に著作権を分配してしまったことで、その後その作品がベストセラーとなった青年が年取ってから著作権分配を解消しようと試みる。面白い。
「岩のマットレス」は、老齢を迎えて北極圏めぐりの観光船に乗った裕福な女が、たまたま同乗してきてお近づきになった男が、若き日の彼女をレイプしてボロきれのように棄てた男だと気づいたとき脳裏に浮かんだのは完全犯罪だった。女はコワイ、といったら怒られるか。
巻末の集中一番長い表題作「老いぼれを燃やせ」は、裕福な老人たちが入居する高級サ高住で暮らす高齢女性の視点で、サ高住で仲良くなった男性との暮らしぶりから、顔の見えない高齢者排除集団がサ高住になだれ込んでくるまでを語る1篇。構成だけなら映画『敵』と似てないこともないけれど、こちらはホラー度が高い。
 人間六度『推しはまだ生きているか』は10月刊、ノヴェレット5編を収録したSF短編集。各篇はそれぞれ全くテーマが違うのに作品としては似通った雰囲気がある。
人間六度『推しはまだ生きているか』は10月刊、ノヴェレット5編を収録したSF短編集。各篇はそれぞれ全くテーマが違うのに作品としては似通った雰囲気がある。
と書いたところで、『本の雑誌』の大森望ページを見たら、世代宇宙船テーマの冒頭の「サステナート314」と巻末の高齢者が怪物化する砂漠の惑星を舞台にした「福祉兵器309」は世代宇宙船と、行った先の惑星の関係にあるんじゃないかとあって、そうなのかと思った次第。そういえばタイトルのつくりが同じだ。まあ読んですぐ内容を忘れるトリ頭なので博覧強記の人の云うことは信じましょう。
基本的にはディストピアSFとしての基調があり、他の3篇のタイトル、表題作の「推しはまだ生きているか」「完全努力社会主義」「君のための淘汰(とうた)」もタイトルを見るだけでそのような感じを与える。
表題作「推しはまだ生きているか」は当方の嫌いな「推し」がはいっていることもあり、内容自体も視点人物が、地上は生活できないほど大気汚染が進んでほとんど人がいなくなった地下の密室で、唯一生き残っているラジオ放送のアイドル番組が沈黙したことでアイドルの危機を感じ取り、ぜったいにアタシが助けると思い詰めてアイドルが居る場所へと外出する話になっている。
一応視点人物にはシアワセが訪れるが、読者からするとどう見ても地獄のようなディストピアである。
これは冒頭の「サステナート314」でも「福祉兵器314」でも物語構造としては同じパターンを取っていて、ディストピアでの視点人物はささやかな報いを得るものの、それはディストピアの酷薄さを強調している。これは能力に応じての努力が点数化される「完全努力主義」も同じだ。まあデートする度に相手の本性を見抜く寄生生物を宿す女性が主人公の「君のための淘汰」のハッピーエンドは、ハッピーエンドを迎えた女性が本人なのかという疑問はあるけど、ちょっと毛色が違う。
でもこの短編集は各作品のディテールを離れて眺めると、とてもオーソドックスな、ある意味昔ながらのSFのアイデアが活かされているように思える。
 前回積み残した坂崎かおる『箱庭クロニクル』は6篇を収める短編集。基本的に女性視点で女性同士の繋がりを描くものが多い。なお表題作がないのでその理由は何だろうと思っていたら、岡本俊弥さんがご自身のBookreview Onlineの書評で解いていました。
前回積み残した坂崎かおる『箱庭クロニクル』は6篇を収める短編集。基本的に女性視点で女性同士の繋がりを描くものが多い。なお表題作がないのでその理由は何だろうと思っていたら、岡本俊弥さんがご自身のBookreview Onlineの書評で解いていました。
冒頭の「ベルを鳴らして」は、視点人物の回想になっており、高女卒業後邦文(和文)タイピストになろうとタイピスト養成学校に入ったら、先生が中国人だったと云うところから始まる。たぶん大正の終わりから昭和の初めころのエピソード。マジメで努力家の主人公は超絶技巧の先生に追い付こうとする一方、彼女にすり寄ってくる不器用な女性にはイライラさせられる・・・。時代が時代なので話は急転するけれども、どうやら実際の歴史とは少しずれた世界らしきことが浮かんでくるので、SFなのかも。ちなみに「ベル」は和文タイプの行末に来たとき鳴るのベルこと。
「イン・ザ・ヘヴン」はアメリカのふたりの少女の物語。主人公の母親は狂信的なキリスト教保守主義者で焚書運動のリーダー。娘はその圧政に辟易しているが、親友の黒人少女と一緒にクラスでは最底辺組。母親の行き過ぎた行為がきっかけで主人公は学校を止めてなかなか理解力のある家庭教師の男性を付けられるが・・・。結末はタイトルが皮肉であることを示す。でも少女たちは生きていく。
「名前をつけてやる」は、商品デザイン部の女性がなぜか、300円均一の店で売るバグチャルというネパールの子供向けゲームの名づけを営業部から任されるが、営業部のチャラ男やデザイン部に新人として入ったクイズ研出身の無口な女の子に振り回される1篇。最終的には女性とクイズ研出身女性の話に落ち着く。
「あしながおばさん」は、娘に先立たれた中年女性が、カツ丼屋のアルバイト店員の女子学生を気に入っていろいろ気を回すけれど、あることがきっかけでその子と縁切りしてしまう。とはいえこれも縁切りしたはずの女の子と中年女性に新しい場面が用意されて終わる物語。
「あたたかくもやわらかくもないそれ」は、急病人かなにかで止まってしまった新幹線で視点人物の女性が、小学校3年生の時ゾンビパンデミックという流行病があって先生もいなくなる事態になった頃、仲良しとマツモトキヨシで薬を売っているという噂をきいて二人でマツモトキヨシに行ったことを思い起こしながらボンヤリしていると、通路を挟んだ席の女性がペパーミントキャンディを差し出してきた。女性は名札を付けていて幼馴染みと同じ「くるみ」だったため、視点人物がくるみとのエピソードを回想しながら、目の前の女性を少女時代のくるみと思いつつ「くるみ」と会話する・・・。二重の喪失の物語かもしれないがそういう終わり方ではないようだ。
巻末「渦とコリオリ」は、「徳島新聞」に掲載されたという10ページの掌編。話の方は、バレエ教室で子供たちを教えるバレリーナが、バレエの天才少女だった姉の意地悪な視線を常に感じながらバレエをやってきたことが語られ、子供時代の姉を知る先輩から鳴門の渦潮を見に行ったとき、姉が「渦はコリオリの力が原因だ」と知ったかぶりしていたことを教えられて終わる。
これらの作品を象徴しているのは、確かに総タイトルと日常的な生き物をシュール化した表紙絵かも知れない。
 レイ・ブラッドベリ『10月はたそがれの国〔新訳版〕』は正月に読もうと思って取っておいたのだけれど、結局ゼラズニイを読んでしまったので、後回しになった。
レイ・ブラッドベリ『10月はたそがれの国〔新訳版〕』は正月に読もうと思って取っておいたのだけれど、結局ゼラズニイを読んでしまったので、後回しになった。
『10月はたそがれの国』は、56年前、中学3年生だったときに読んだ最初のブラッドベリ。『2001年宇宙の旅』の再上映をテアトル東京で見たあと、2学期から広島の田舎中学校へ転校して間もない頃で、毎日場違いな感覚におびえながら強風の吹く寒い夜に読んだものだから、「風」の恐怖譚がとても人ごとには思えず布団を引き被って読んだ覚えがある。
いま中村融さんの新訳で読むと、もはや当時のナイーヴな感覚は蘇ってこないけれど、「みずうみ」や「群集」をはじめとするブラッドベリの初期短篇が、いかにインスタントクラシックぶりを発揮していたかがよく分かる。「集会」なんか何回読んでもいいもんな。
この新訳がいまの中学生たちの手にも届いて欲しいと思うこと切である。
なお、ボロアパートから掘り出した旧版は、1969年6月7版刷り定価240円。新版でムニャイニ/マグナイニの挿絵がシャープになったことは嬉しいけれど、旧版の表紙絵が口絵になって拡大トリミング状態になったのは残念。
 チョン・セラン『J・J・J三姉弟の世にも平凡な超能力』は、160ページしかない長中編。2014年の作。早川書房から掌編集も出たのだけどこちらを読んだ。
チョン・セラン『J・J・J三姉弟の世にも平凡な超能力』は、160ページしかない長中編。2014年の作。早川書房から掌編集も出たのだけどこちらを読んだ。
三姉弟は長女と長男それに長男より10歳下の次男で、長女は大田の企業研究所で働き、長男は中近東のある国で砂漠の中のプラント建設現場に設計担当として働き、次男はまだ高校生でアメリカの片田舎にホームステイする。タイトル通り、それそれがささやかな超能力とも云えるモノを得るが、長女は超絶硬い爪が生え、長男は危険があるところを見ると視野が赤くなり、次男のそれはエレベーターを呼び寄せる力を授かる。だけど、平原しかないアメリカの田舎では何の役にも立たない。
長女は母親とのあれこれ、同僚とのあれこれをこなしながら、硬いツメの利用法を研究に潜り込ませ、母を救い同僚を助ける。長男は、ヒョンな事から危機に陥っていた外国の少女を救い、次男はカルチャーショックでうつむき加減になったけど、結局アメリカの田舎でのホームステイを楽しめるようになる。
チョン・セランはほんとうにささやかな魔法を使うことが出来る作家だなあと今回も楽しく読ませてもらった。
 前回積み残した宮内悠介『暗号の子』は、作者あとがきで昨年4月から5月に書いたという中篇の表題作をはじめ8編を収める。表題作以外は短いのが多い。
前回積み残した宮内悠介『暗号の子』は、作者あとがきで昨年4月から5月に書いたという中篇の表題作をはじめ8編を収める。表題作以外は短いのが多い。
作者が解題しているし、スマホでもその部分が読めるようになっていたので、あまり云うことは無いかも、というか早くも内容を忘れてしまって、表題作さえ思い出せず、適当にページを開けて読んだら語り手は女性だった。ウーム、大丈夫じゃないな、オレ。
「暗号の子」は、その語り手の女性がオンラインのASD(自閉スペクトラム症)の自助グループからブロックチェーン技術を使った完全自由主義的なコミュニティに参加して、居所を発見する。しかしそのコミュニティもやがて・・・。様々な考察がなされているものの基本は視点人物の想いにある。
次の「偽の過去、偽の未来」は8ページの掌編。Webマガジン『Kaguya Planet』初出というから再読だったかも。これは解説で表題作と対を成すと云っているけれど、たしかに視点人物はITに強い女性だしちょっと距離を置いてる父親も出てくるし、云われればそうだなあ。
「ローパスフィルター」は、ステレオ系だと音をなめらかにする効果だけれど、ここではSNSの投稿に掛けられるフィルターらしい。なかなか不幸な話だけれど、作者も云うようにSNSの引き起こす悲惨さは2025年の現在、この作品が書かれた2019年をはるかに上回っているなあ。
「明晰夢」はデジタルLSDの出現とその消長を語った1作。解説に『新ナポレオン奇談』からの引用云々とあるけれど、以前楽しく読んだ記憶があっても引用には気づけなかった。
「すべての記憶を燃やせ」は12ページの掌編。『SFマガジン』誌上の企画ものとしてAIにSFを書かせるというのがあったけれど、これもその1作。
自殺した作家/詩人の作品を引用しながらその詩人の足跡を追いつつ語り手も最後にシュールな世界の存在であることが明かされる。作品が不気味なのは作者が指定した素材がそうだったからで、それが宮内悠介の作品かと云われるとやや違う感じがする。血が通ってなくても面白ければそれでいいのか。
「最後の共有地」も忘れていたので、パラパラとめくり返している内に、こういう話だったと改めて気がつくのだけれど、それで思ったのが、この短編集の作品には物語の主因となる人物/仕組みが最終的に不在であるパターンが多いなあ、と云うことだった。
この作品はイーサリアムという現実にある仮想通貨の一つをモデルにしているけれど、タイトルが意味しているのはヒトの内面だ。人の心はそれこそ千差万別だけれど、ヒトの心の問題は常に孤独であることを反省してしまうことにある。即ち生物学的にはほぼ同一で同じプログラムで出来ているのに、個体の意識はすべて独立/孤立していて内省してしまうのだから始末に負えないと云うことなんだろう。
そういう意味では「行かなかった旅の記録」も、解説を読むと「不在」がテーマであり、作者の想いがフィクションの企みを通じて作品化される形を取っている。
「ペイル・ブルー・ドット」は、解説によると以前、実在の雑誌である『トランジスタ技術』誌を破りまくる短篇「トランジスタ技術の圧縮」を出版社に無断で発表したことで、当該雑誌の方から連絡があって、その縁で昨年12月号に掲載された作品だというから新しい。
話の方は他の収録作と違って、小型衛星開発会社のソフトウェア部門にいる視点人物が理系少年に出会い、視点人物が社内企画にする彷徨で技術畠の人間を巻きこんで少年が超小型衛星の制作に挑むのを手伝うという、前向きの明るい1編。藤井大洋を思わせる。
いい短編集だけど、話をすぐ忘れるのは当方が理系の概念操作が苦手なせいか。
 年末に出たのが劉慈欣『時間移民』は、大森解説によるとここに収録された作品で既発表短篇はすべて訳されたとのこと。若い頃は短篇をいっぱい書いていた小松左京やバラードやヴォネガットに較べるとやはり少ないか。劉慈欣の場合は発表先も限られていたろうし。もっとも名を成して大物/年寄りになると短篇を書かなくなるのが一般的な傾向だ。その点筒井さんはもともと短篇型で最後まで短篇を書き続けているし、そういう意味ではデビュー当時からいわれていたようにシェクリイ型だったのかも。
年末に出たのが劉慈欣『時間移民』は、大森解説によるとここに収録された作品で既発表短篇はすべて訳されたとのこと。若い頃は短篇をいっぱい書いていた小松左京やバラードやヴォネガットに較べるとやはり少ないか。劉慈欣の場合は発表先も限られていたろうし。もっとも名を成して大物/年寄りになると短篇を書かなくなるのが一般的な傾向だ。その点筒井さんはもともと短篇型で最後まで短篇を書き続けているし、そういう意味ではデビュー当時からいわれていたようにシェクリイ型だったのかも。
標題作「時間移民」は〈典型的な1950年代の英語圏SF短篇〉とでも称されるお手本通りのよくできた冷凍睡眠/時間航法ジャンルの1編。ただしスケールはでかい。作者のSF大好きぶりがよく分かる。
「思索者」は、時空の眩暈を長い人生で出会えるのが数回しかない男女の出会いに重ねたSFの手練れとなった作者の1編。最後の1行は劉慈欣マークだろう。
「夢の海」は、氷の彫刻家がふと空を見上げたとき「低温アーティスト」と名乗る声が頭に響き、空に巨大な何かがいるのが目に映った・・・。ということでこの「低温アーティスト」が惑星単位で超巨大スケールの水/氷彫刻を創り出す。その結果は眼前に広がる干上がった海だった・・・地球迷惑一番な話。
「歓喜の歌」となれば第九で、これ全編「歓喜の歌」が響く。国連総会コンサートにはリチャード・クレイダーマン(!)が招かれていたが、その夜大空にはもうひとつの地球が出現した。こちらも超巨大スケールの鏡が出現したという「超巨大モノ」。しかも鏡は「私は音楽家です」としゃべるので「低温アーティスト」と並ぶ〈巨大芸術家〉シリーズとも云うべき1篇。
ここから『三体』シリーズにも出て来た天才/異常科学者ディン・イー(丁儀/丁一)がメインの短篇が4作続く。
「ミクロの果て」は粒子加速器を使って大統一理論を証明しようをするディン・イーが引き起こした事件の顛末。作品中で紹介されるクラークのバカSFのアイデアをそのまま実行した1篇。
「宇宙収縮」もディン・イーのビッグバン実験の結果宇宙が収縮、それに伴い時間も反転する・・・。大昔の筒井康隆や星新一を思わせる稚気満々の1篇。
「朝(あした)に道を聞かば」も、ディン・イー一家が地球スケールの加速器の中を旅しているところから始まるが、ディン・イーの科学理論最優先は全宇宙に災厄をもたらすものなのでどこからかリスク排除官が現れる。最後は取り残されたディン・イーの妻子のその後を描いてシンミリさせる。劉慈欣はトコトン自作のキャラに肩入れしない作家だ。
「共存できない二つの祝日」は丁一が出てくる8ページの掌編。1961年頃のソビエトで初の有人宇宙船打上げを成功させたコロリョフのもとに宇宙人を名乗るAが人類が地球を初めて出た日が記念すべき日だと告げる。一方2050年の未来では丁一たちがブレイン・マシン・インターフェース開発に成功するが、そこへやはり宇宙人Aがいてその発明の行き着く先を星空の沈黙として説明する。
これって最近当方が考えてるデジタルワールドはSFの行き止まり説みたいだなあ。
「全帯域電波妨害」はIT技術の塊で戦う時代の戦場においてレーダーに対するECMジャミングが全帯域で行われると戦闘はどうなるかという思考実験モノ。ロシア側の総司令官の科学者となった息子と総司令官配下の部隊に属する美人士官の恋愛を絡めて悲劇的に展開する。ホントにこの作家はキャラクターに思い入れがない。
「天使時代」はアフリカの架空の国が舞台の戦争物。その国では遺伝子操作研究でノーベル賞を取った科学者が違法なヒトゲノム改変テクノロジーを開発したが、国連の一切の勧告を無視したのでアメリカの空母部隊が戦闘に入る。アフリカの小国の軍隊など一蹴出来ると踏んでいた司令官は空から天使の群れがやって来るのを目にして・・・。
太平洋戦争当初、日本の航空機部隊がイギリス東洋艦隊の戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスをマレー沖海戦で沈めて以来、艦隊は航空攻撃に勝てないことになったわけで、これはその有翼人バージョン。
「運命」は、地球衝突コースの小惑星の破壊からワープ航法の影響で発生するタイムトンネル効果、恐竜が人類に取って代わった世界までを若い男女カップルの冒険として仕上げた1篇。いかにもこの作者らしいスケールのデカい一方で、荒っぽくてやや古めかしいタイプのSF。
「鏡」はタイトルだけからすると「歓喜の歌」の「鏡」を思ってしまうけれど、実はこの作者には珍しい本格的社会派SF。中国共産党を思わせる巨大組織の地方部局の省で、組織の腐敗したネットワークを見つけた若手官僚は長官に報告した後に投獄される。そこへすべてをお見通しという気象シミュレーション担当の若者が面会に来る・・・。
これは量子論的な全世界観測システムが仮想空間上に再現されることで、時間軸の操作によりすべての事象の成り行きを観察できるようになるという、かなり強引なアイデアで押し切ったサスペンスもの。現実が再現できる装置のアイデアは昔からSFに取り込まれていて正義が勝つのだけれど、なんと劉慈欣は正義感から「悪」を告発するだけでは人間社会を上手く動かせないのだという長官側の視点にも重点を置くというオトナな物語構成をして見せている。
巻末に置かれているのが、現在のところ劉慈欣が発表した最後の短篇で、2017年に執筆、翌年英訳版が単行本に収録されたという「フィールズ・オブ・ゴールド」。このタイトルだとどうしてもスティングの名曲が聞こえてくるのは仕方が無い。
ここでは表題は宇宙船の名前として使われている。この作者の作品としては叙情性を湛えた悲劇として見事な仕上がりを見せた1作。ちょっと見直した。
全体的に超スケールのSFコントが多いけれど、「全帯域電波妨害」「鏡」「フィールズ・オブ・ゴールド」の3作はシリアスなSFとしても見事な出来を示している。
今年出たのを1冊だけ。
 第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作のひとつ、カスガ『コミケへの聖歌』の読後感は、東浩紀の選評で置き換えられるのでその点では何も云うことは無い。
第12回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作2作のひとつ、カスガ『コミケへの聖歌』の読後感は、東浩紀の選評で置き換えられるのでその点では何も云うことは無い。
しかし作品自体はエンターテインメントとして充分完成されているにしろ、新人発掘のためのSFコンテスト受賞作としては、当方はこの作品に否定的である。否定の元はいわゆる「SF」観にあって、当方の古い感覚からすると、塩澤もとSFM編集長のそれとは正反対だ。
SF新人賞は、まず型破りが第一で、完成度は二の次だと思う。たとえば『標本作家』のような作品に当方は高い評価を与えてはいないけれど、そのアイデアを書いてしまう蛮勇は十分に評価されるべきなのだ。だから『コミケへの聖歌』と『標本作家』なら「SF」としては『標本作家』を取る。
「SF」に期待するのは「完成度」じゃなくて「ヘンさ」なのだ。完璧に面白いエンターテインメントを書ける作家は各ジャンルに常に存在する。だからこそそのジャンルは多くの読者を抱えている。でも「SF」は、多くの読者がもとめるすっごく面白いエンターテインメントでなくても、ビックリさせられれば、もしくはその「ヘンさ」に呆れることが出来ればそちらを取るようなジャンルだったとおもっている。
だから『コミケへの聖歌』は、その結末のシーンから始まる少女たちの未知への旅立ちとその後が「SF」になったはずだし、もしくは最後の方に出てくる大叔父の日記の中身が本来のSFだったはずと思ってしまう。
とはいえ『コミケへの聖歌』自体は良作であり、面白いことにかけては全く文句を言われる筋合いのない作品であることは確かだ。ただそういう観点からは文中のSFへの目配せが鬱陶しかったことは付け加えておこう。
 読まなくてもいいんだよ、と思いつつ手を出してしまって、その浅薄さについつい上の空になっていつまで経っても読み終わらなかったのが、ジェイムズ・P・ホーガン『ミネルヴァ計画』。
読まなくてもいいんだよ、と思いつつ手を出してしまって、その浅薄さについつい上の空になっていつまで経っても読み終わらなかったのが、ジェイムズ・P・ホーガン『ミネルヴァ計画』。
目次を見ずに読み始めたので、2部構成とは思っておらず、いつになったらタイトルと話が繋がるんだろうと思いつつ、テューリアンが人類の暴力性向の謎について悩むのを読む度に、おマエらは人類がサルだということを知らんのかっ、とツッコミを入れてしまうのが止められず、ページを閉じてしまうのだった。
ホーガン晩年のハードSF風スペースオペラに文句を付けても仕方が無いのは分かっているけど、第1作を大傑作だと思ってしまった想い出はいかんともしがたいのでる。
ということで人間がサルだということがいまだに常識になっていないようなので、脱線しておこう。「類人猿」とか「霊長類」とか他のおサルさんに失礼な名称をいまだに使い続けているんだから。
有史以来の人類史が同種間の殺し合いの記録になっていて、それを楽しめることがエンターテインメントの一大源泉であることは誰しも思い当たるだろう。その原因が群れを作るサルの社会システムから、すなわち「ナワバリ」から来ていることも明らかなのに表だっては誰も云わない。「政治とは敵を作ることである」と誰ぞや有名な政治学者が言ったけど、これは「ナワバリ」の言い換えだろう。基本的に「ナワバリ」は敵を攻撃するか妥協するかしかない。「ナワバリ」集団の中では生存維持システムがヒエラルキーと協力体制の破綻を防いでいるが、外に対してはそれがない。
人間が知性を持って一番やっかいなのは「神」と「正義」を発明したことだ。どちらもヒトの心にあっては、その効用は無類だけど、それが外に出て集団の意思形成に関わってしまうと、とたんに「ナワバリ」維持のための免罪符と化す。もう一度書くけど、文字を使うようになって以来の人類が「神」と「正義」のための同族殺しを記録に留めてきた。そしてそれは「オモシロイ」のである。もっとも「神」と「正義」を御旗にしなくても単に「ナワバリ」拡大を目指して同族殺しをやった例も夥しくあるけれど。どちらにしてもそれは面白いドラマなのだ。
ということで人類が本当に「ホモ・サピエンス」なのかどうかは怪しいモノだ。基本的に暴力史としての人類史は「ナワバリ」を否定できないことの証しとしてある。旧約聖書の預言書にはヤハウェが「万軍の主」と同義として出てくるけれど、ヤハウェは自らを祀った民を外敵から守ってやると云っているから「万軍の主」と褒め称えられているわけだ。でもその約束が空しかったことはその後の歴史が示すとおりだけど。とはいえヤハウェには強力な言い訳がある。それは民たちがヤハウェを正しく信仰していないからだ、というものだ。預言書を読んでいると、ヤハウェの言い訳も、まあ、分からんでもない。
脱線が長くなったなあ。
タイトル通りの話は第2部で実現する。とても古めかしい戦争話でE・E・スミスのスペースオペラもかくやという印象がある。とはいえこれで「巨人たちの星」シリーズも一応の完結ということで、メデタシだったのかな。
 ノンフィクションとして鹿野司『サはサイエンスのサ〔完全版〕』は9月刊だったけれど、最近ようやく入手した。『本の雑誌』別冊の鏡さんのベスト10を見て、嗚呼これがあったと思ったのでした。
ノンフィクションとして鹿野司『サはサイエンスのサ〔完全版〕』は9月刊だったけれど、最近ようやく入手した。『本の雑誌』別冊の鏡さんのベスト10を見て、嗚呼これがあったと思ったのでした。
今回は、堺三保・白土晴一・松浦晋也とり・みき各氏の追悼文を読んで、本文の方をアチラコチラ適当に開いたところから読んでみた。だから全文を読んだとは云えないし、たぶんいつまで経っても全文読了はしないのだろう。
そうやって読んでいていろいろ思うことはあったのだけど、取りあえず印象的だったのは、柴野さんのSF論義に限っての強い攻撃性が鹿野司の記憶に強く印象づけられていたことだった。当方はSF大会などで柴野さんと偶然居合わせたことはあっても、話をしたことがない。となればあのニコニコ顔がトレードマークのイメージしか無かった。でも考えてみればプロフェッショナルを矜持とした福島正実との対立があそこまでキツかったのは、やはりSFにかけた執念のなせるワザだったと云うことなのだろう。それが鹿野司の性格もあって、柴野さんみたいになったことは若気の至りとしているけれど、やはり反面教師とした所はあったのだと思われる。
それにしても当方よりも若くして亡くなるというのは残念至極ではある。
 渡辺直己から離れようと読んだ小林ふみ子『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』が面白かったので、おなじく角川ソフィア文庫から年末に出た大田南畝編宇田敏彦校注『万歳狂歌集 江戸の機知とユーモア』も読んでみた。解説は小林ふみ子。
渡辺直己から離れようと読んだ小林ふみ子『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』が面白かったので、おなじく角川ソフィア文庫から年末に出た大田南畝編宇田敏彦校注『万歳狂歌集 江戸の機知とユーモア』も読んでみた。解説は小林ふみ子。
解説にあるとおり、これは1990年に社会思想社から現代教養文庫で上下巻として出たものを1冊にまとめた再刊。やはりNHK大河ドラマの影響なんだろうな。
しかし小林ふみ子の概説書と違い、これは大田南畝が選して収めた748首の狂歌を活字に起こして語句の解説と解釈および狂歌の拠った本歌や当時はやった言い回しなどを博捜して付けただけのモノ。
当方は現役時代に近世地方文書もかじったけれど、地方文書は基本定型文書なので、少々読めなくても見当は付いたモノが多かった。だけど、これは室町時代から大田南畝の同時代人までの狂歌アンソロジー。勅撰和歌集はもちろん漢詩をはじめとする中国の古典の知識も当たり前な文芸好き達が、当世流行の言い回しなども入れて、ヒネリにヒネった三十一文字にデッチ上げた歌が並べられていて、シロウトが読むにはかなり難しい。読み終わるのにひと月かかった。
タイトルからして『千載和歌集』のもじりで、「万歳/万載」でもちろんバンザイで、目出度さを言祝いでいるというもの。
そのわからなさの例を一つだけあげておこう。「巻第五 秋歌 下」に入っている233番目の狂歌。作者は四方赤良ですなわち大田南畝。
「十三てはつかりはれし空われに月のさハリの雲もかヽらす」
ぱっと見に前半の句がサッパリ分からない。「十三」は十三夜で「はつかり」は初雁だから秋の季語、十三夜の初雁、晴空に月が雲にも邪魔されず煌々と照っている風景が浮かぶけれど、これは狂歌なので、素人目には何のことやら分からないが、じつはロリエロ和歌なのである。
どういうことか。語句解説によると「十三て」は「十三で」、「はつかり」はもちろん「初雁」で秋の季語だけど「ばっかり」と読んで現代風なら「バックリ」と読み、「はれし」は「は」を「わ」に読んで「割れし」あるいはそのまま「腫れる」と読んでもいいかも、「空われ」は「から割れ」と、ここまでくれば「月のサハり」は「月の障り」ですなわち「月経」。「雲もかヽらす」はそのまま「雲も掛からず」。
通しの意味は、数え13才の小娘のアソコは膨らんでバックリ空割れしたろうが、月経はまだ来てないから汚れてはいない、ということになる。ここまでエロな狂歌は748首に類は無いけれど、屁を歌った尾籠なヤツはいっぱいあるしキンタマ系も複数ある。
もちろん爽やか系やお涙頂戴もあるけれど、一番多いのはやはり見立てともじりで本歌取りしておかしみを出すタイプ。あと狂歌を読むときに使う狂歌師名(ペンネーム)がヴァラエティ豊かで、本業を反映しているものもあり、ダジャレに過ぎないものもある。たとえば「元木網(もとのもくあみ)」は妻も狂歌師で「智恵内子(ちえのないし)」というんだけれど、これは「智恵」が無い「子」とへりくだる一方、宮中の女官の役職「内侍(ないし)」に掛けて結構しょった名前にしてある。夫の方は湯屋が本業だったが剃髪後狂歌の門人を多数抱えたという。
読んで楽しいのと読む苦労とが半々な1冊ではあった。