

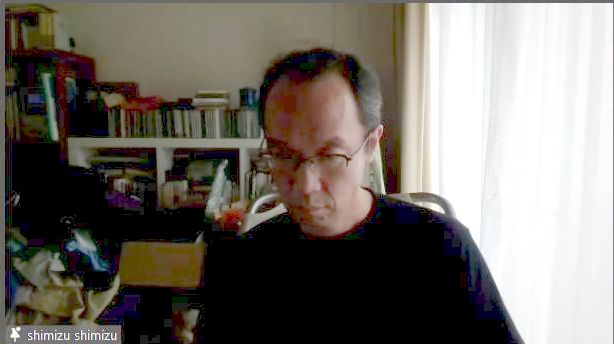
内 輪 第373回
大野万紀
 |
 |
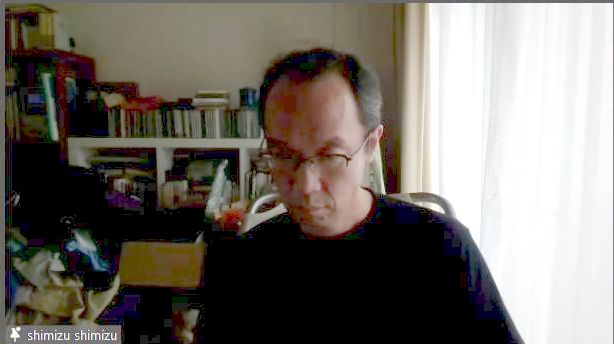 |
| 岡本さん | 芝田さん | 清水さん |
9月のSFファン交流会は9月18日(土)に、「Sto lat!スタニスワフ・レム」と題して、スタニスワフ・レムの生誕100周年を記念し、国書刊行会の〈スタニスワフ・レム・コレクション〉第Ⅱ期の話を中心に行われました。ちなみに「Sto
lat!(スト・ラート)」はポーランド語で「(特に誕生日)おめでとう」の意味だそうです。
司会進行は岡本俊弥さん。国書刊行会の清水範之さんと翻訳家の芝田文乃さんがゲストです。(岡本さんのページにも詳しい内容がありますので参照ください)
芝田さんからは、ポーランドのクラクフではレム年としてイベント「未来学会議」が開催され、街のあちこちにレムの本の看板が表示されたり、「レム対ディック」という演劇が上演されたりしているとの報告。ちなみに、レムの文学以外にも科学技術やIT、現代音楽などのイベントも同時開催され、二次創作やレムにかこつけての色んなディスカッションをやっているとのことです。
岡本さんが年表をもとに日本でのレムの出版について。短篇では「泰平ヨン」が62年のSFマガジンに翻訳され、長篇は『金星応答なし』が61年に映画との関連でハヤカワSFシリーズに入ったのが最初。その後『ソラリス』がSFマガジンに連載され、ハヤカワSFシリーズを経て68年の世界SF全集に『砂漠の惑星』と共に収録されたと。レムは当初から大変高い評価を得ていたのですね。
ちなみに、この世界SF全集版はぼくも確か高校に入ったばかりのころに読んで(図書館にあったのかな)、衝撃を受けた記憶があります。どちらも凄いと思ったけれど、どちらかといえば『砂漠の惑星』の方に鮮烈な印象がありました。芝田さんも同じような話をされてびっくり。好みが(歳も?)近いのかしら。しっかりSFの人ですね。なお『砂漠の惑星』は今度、国書刊行会から『インヴィンシブル』としてポーランド語からの翻訳で出るとのこと。
清水さんからは国書刊行会のレムコレクション第一期の話。沼野さんがレムはポーランド語から訳さないといけないと言われたので、思い切って始めたが、ソダーバーグ版の映画上映に間に合わせる予定だった『ソラリス』も沼野さんの翻訳が遅れて間に合わない。でも、まあそれでもいいかと思ったとのことでした。そうですね、それでいいんです。
第二期もレム100周年に合わせたわけではなく、本当はもっと早く出るはずだったとのこと。第二期の目玉の一つが初期の長編『マゼラン雲』。これはかつてのレムが翻訳されるのを拒否していたという作品ですが、その拒否していた理由というのが、この作品には当時の政治状況でやむを得ず共産主義を礼賛するような記述があり、非共産圏の読者がそれを読んで誤解して共産主義者になったらイヤだから、という話。レムはイデオロギーとしての共産主義には距離を置いていたのですね。レムが亡くなって版権管理者が代わり、翻訳できるようになったとのことでした。
それから芝田さんがポーランドに留学してレムと会った話など、面白い話がたくさんありましたが、メモが追いつかなかったので割愛。映画の話や、「泰平ヨン」の訳語についての話など、なるほどと思ったのですが(「泰平ヨン」はショーロホフの「静かなドン」のポーランド語でのもじりだとか)。
次回のSFファン交流会はラファティがテーマということで、これまた楽しみです。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『テスカトリポカ』 佐藤究 KADOKAWA
『テスカトリポカ』 佐藤究 KADOKAWA
直木賞受賞作。3月に買っていたのだが、ようやく読んだ。残酷でグロテスクでとてつもない内容だが一気に読める。確かに傑作。圧倒的な迫力と熱気がすさまじい。でも乾いた文体がそのむごたらしさをねちっこくなく描写しているので、恐怖とおぞましさにも止まることなく読み続けることができる。
メキシコの麻薬カルテルに君臨した麻薬王バルミロ。彼は幼いころ兄弟と共に祖母からアステカの神々の話を聞いて育った。しかし麻薬戦争に破れて兄弟も妻子も皆殺しにされ、一人逃れた先はインドネシア。そこで日本人の心臓外科医末永と出会い、彼を犯罪仲間として新たなファミリーを立ち上げる。末永は知的エリートであり心臓手術が何より好きなスポーツマンタイプの医者だが、中身は怪物だ。日本で事件を起こして医学界を追放され、今は東南アジアと日本をつなぐ臓器売買のコーディネーターをしている。やがて二人は日本に渡り、川崎に拠点をもうけ、無国籍孤児を集めて、自分の子への臓器移植を求める海外の裕福な親たちにその心臓や臓器を販売する闇のビジネスを着々と準備していく。
一方、メキシコ人の母と日本の暴力団幹部の父の間に生まれた少年コシモは、まともな教育も受けずに育ったが、手先の器用さと心の純真さを持ちながらもその巨体と肉体の力を自分で制御しきれない少年となった。その力のあまり両親を殺害してしまった彼は少年院に送られるが、17歳になって退所したとき組織の目にとまり、知らぬ間に犯罪に巻き込まれていく。バルミロは彼の圧倒的な潜在力を見いだしていたのだ。彼は祖母の話してくれたアステカの神々の話をコシモに伝えようとする。
この小説は徹頭徹尾、悪の側から描かれる。警察や一般人の視点はほとんど無視される。孤児たちに愛情を注ぐ女性も登場するが、彼女も麻薬中毒者であり、一般人とはいえない。バルミロの組織は強い結束を持ち、敵や裏切り者には容赦なくむごたらしい制裁を加える。バルミロからは暗号名で呼ばれるこのファミリーの強さは半端ではない。それはもう少年ジャンプのヒーローマンガを思わせる強さだ。一方で、臓器売買をビジネスとして進める彼らの仕事ぶりはきわめてシステマティックで、合理的だ。最先端のテクノロジーを駆使し、グローバルな広がりをもつ。まさに現代のグローバル資本主義、凶悪だが影の支配者がいるわけではなく、悪知恵のある奴らがバラバラに、金儲けという一点で創発的に開拓していく闇の資本主義のおぞましさが凝縮しているといえる。末永は実際それを体現している人物だ。バルミロもそのリアリズムを血肉としつつ、一方でアステカの神話世界をも同時に生きている。血まみれの生贄を求めるその神話世界は、犯罪社会のリアリズムと拮抗し、しだいに物語全体を侵食していく。
結末はちょっとあっけなく感じたが、そこには救いがあり、アステカの神とは別の、もう一つの神話世界が立ち現れる。とはいえ、本書の全体はもうはっきりとアステカの神々の物語だったといって間違いない。血と暴力と死をエネルギーとする神々の神話。SFといえるかどうかはわからないが、現代の最先端の資本主義世界によみがえったむごたらしいアステカ神話であり、ある種の怪奇幻想小説であり、かつての半村良の伝奇SFに通じるものである。バルミロにも末永にも強烈な悪の魅力があるが、本書で最も印象的なのは聖別された子供であるコシモだ。彼は日本神話のスサノオのように、幼な子のように純真で、凶暴な英雄である。最後に描かれたもう一人の幻視者である少年とともに、彼の物語はまだこれからも続いていくだろう。
 |
 |
『帝国という名の記憶』 アーカディ・マーティーン ハヤカワ文庫SF
2020年のヒューゴー賞長編部門受賞作で、ビザンチン帝国の専門家でもある著者の長編デビュー作である。遠い未来の銀河帝国を舞台にした宮廷陰謀劇だ。スペースオペラの要素はあるものの、ほぼ帝国首都と宮廷内で物語は進み、絢爛たる文明――皇帝がおり貴族がおり、古典文学の引用や詩がそのまま政治となるような優雅でみやびな「文明」――にあこがれる田舎者(野蛮人ともいう)の大使の視点から描かれた物語である。
強大なテイクスカラアン帝国が銀河を支配している時代。採鉱ステーションの集合体からなるルスエル・ステーションは、重要なスペースゲートを抱え、独立した国家としての地位を保っていたが、テイクスカラアンから急遽新しい大使の派遣を要請される。そこで帝国の文化に心酔していた若いマヒートが選ばれて派遣されることになったのだが……。
ルスエルには帝国にはない国家機密の重要技術があった。それはイマゴマシンという脳インプラントで、そこには個人の記憶と人格がダウンロードされており、それを埋め込んだ者はその人格と会話し、経験を継承することができるのだ。マヒートは前任の大使イスカンダーのイマゴを移植されたが、本来の彼は帝国へ行ったきり消息不明なので、そのイマゴは15年前に記録された時遅れのものだった。マヒートはこのうるさい脳内存在とあーだこーだ言いながら二人三脚で(いや肉体は一人だが)やっていくものと思ったら……。
帝国の首都惑星に着いてみると、前任大使イスカンダーはすでに死亡していたことがわかる。アナフィラキシーによる事故だと伝えられたがそれは怪しい。明らかに何かの陰謀に巻き込まれて殺されたのだ。マヒート脳内のイスカンダーは自分の死体を見て錯乱し、以後ほとんど何もコミュニケーションしなくなる。知りたい情報も得られなくなる。イマゴ自身の問題なのか機械の故障なのか、いずれにせよこれではイマゴの意味がない。帝国情報省からマヒートの案内係(そして監視役)として常に同行することになったスリー・シーグラスと共に、マヒートは前任者の死の真相を追って帝国を揺るがす権謀術策の中に飛び込んで行くことになる。それは帝国の中枢、そして皇帝その人にまでつながる巨大な陰謀だった。いったいイスカンダーは何をしでかしていたというのか……。
上下巻本だが、上巻の最後になってようやく謎の全体像が見えてくる。それまでは本当に五里霧中というか、誰が敵で誰が味方かもわからないまま手探りで進んでいくことになる。おまけに、アステカとビザンチンの文化が合わさったような帝国の文化はとてもエキゾチックで、いやエキゾチックといえば聞こえはいいが、固有名詞や用語が独特なので読んでいてとても悩ましい。ぼくは読み終わるのにずいぶんと時間がかかってしまった。装飾的で華麗な文章はイメージ豊かだが、アステカといえばアステカ神話をモチーフにした作品を読んだばかりで、ついそれと比べてしまう。ビザンチンはともかく、この小説におけるアステカ味というのはショッキングな一面もあるが、かなり表面的なものに思えた。一方、詩を政治的に用いる文化というのは、平安時代の貴族が和歌でやりとりしていたのを思うとわかりやすい。人名には数字が使われているなど、コードウェイナー・スミスみたいで面白いのだが、それが英語だというのは何か変な気がする。どうなっているのだろう。どこかに説明があったかしら。
言い忘れたが、本書の主要人物はほとんどが女性である。だがこの話で性差が意味を持つことは全くないので、物語上はそれは大きな問題ではない。物語の外から見ると、まさに現代的でジェンダーフリーなSFだといえる。
解説で鳴庭真人氏が書いているが、本書で一番印象に残るのは、主人公マヒートと、彼女の案内人であるスリー・シーグラスの関係である。百合といってもいいのかも知れないが、ここでは性差は意味ないので、これは生死を共にするバディ同士の友情であり、愛情だ。特にスリー・シーグラスがいい。彼女は知的でユーモアがあり、真面目だがとても可愛らしい側面もあり、すごく魅力的だ。彼女の昔からの友人である情報省のトウェルブ・アゼイリア(こちらは男性)とのやりとりも微笑ましくて好ましい。
物語の全体像が見えてきてからの流れはスムーズになり、どんどん読めるようになる。背景にある人類とは別の強大な敵の存在も明らかになってくる。ところが面白くなってきたところで本書は終わってしまう。これはもう、続編を早く出してもらわなくちゃね。
 『階層樹海』 椎名誠 文藝春秋
『階層樹海』 椎名誠 文藝春秋
どうやら地球とは別の惑星らしい。巨大な樹海が垂直方向にも水平方向にも広がっていて、様々な生物がその中で生き、うごめいている。人間たちはいくつもの部族に分かれ、高度によって階層化された樹林の中で狩猟採集の生活をしている。そんな部族の少年スオウは、12歳になり、部族の住む階層から時々は外へ出かけて行っても良いことになった。さっそくスオウは遠くへ出かけて食料となる無数の虫や動物、寄生植物――木肌トビマル、ヨジノボリ、トビキリヤモリ、などなど――を眺めたり捕まえたりするのだが、危険な目に合って兄のところへ戻ってくる。どうも階層樹海に何か異変が起ころうとしているのだ。部族の”学者”であるコンゾさんによると、樹海の遥か上空には古代の人々が打ちあげた偵察球が周回しており、世界を観察しているのだという。そして彼らの残した映像と言葉を投射する機械が、階層樹海の崩壊を警告しているのだと。
スオウは樹海の上へと一人で探検に出かける。ところが〈虫の川〉に巻き込まれ動けなくなったところを、どこからか飛んできた飛行機械に乗った男に救われる。男は自分をアインシュタインと名乗り、スオウをこの階層樹海の最下層、水面に近い村へ連れて行く。スオウがそこで知ったことは……。
作者自身がオールディスの『地球の長い午後』がイメージの下地にあったと述べている。また実際に行ったアマゾンのジャングルでの体験が反映しているとのことだ。樹海の世界、未知の、エキゾチックな生物たち。〈樹海もの〉には圧倒的な魅力がある。たくさんのSFがそのイメージを描いてきた。日本でいえば「ナウシカ」の腐海もそうだし、最近では酉島伝法の作品や上田早夕里の作品でも描かれていた。深い森とむせかえるような濃密な生命の息吹。そして森の民。
本書にもそんな魅力が満ちていて、そこにSF的な背景がほのめかされている(それは他のシーナ・ワールドともどこかつながっているようだ)。ただその背景に関する説明はごくあいまいで、想像するしかない。雰囲気があって面白かったが、ところどころつじつまが合わないと思えるところもあり、また主人公が知らないはずのことを知っていたりと、よくわからない所があった。椎名さんはその辺はもうあまり気にしないのかな。まあ、あえて気にするほどのことではないが。
児童書のような、プリミティブアートのような挿絵がたくさん入っていて、それも雰囲気を出している。