



|
続・サンタロガ・バリア (第151回) |
誕生日がめぐってきて、とうとう還暦に。通常の新年会に誕生会兼送別会で飲んでばかり。でもネーム入りの万年筆やブックカバーのプレゼントをいただいたりして、本(仕事では資料)ばっかり読んでいるオヤジとしては結構喜んでいるのである。4月になれば会えなくなってしまう人もいれば、相変わらずつきあっている連中もいるだろうが、とりあえずは経済的な変化に対応せねばならんなあ。
ブラジル音楽はマルコス・ヴァーリとカエターノ・ヴェローゾを追いかけている。
 |
 |
 |
 |
1月に聴いたうち、マルコス・ヴァーリは『サンバ・ジマイス』64年作、『ヴィオラ・エンアラルーダ』68年作、『プレヴィザォン・ド・テンポ』72年作それと『マルコス・ヴァーリ』74年作の4作。すべてEMIオデオン・レーベルで発売されたもの。
『サンバ・・・』はデビュー作ということでボサノヴァまっただ中。ただし、自作は半分で、あとは他人の曲をカヴァー。ジャケットは白シャツのちょっと神経質そうな好青年が木陰をバックに写っている。アレンジのエウミール・デオダートと初顔合わせ。デオダートはヘンリー・マンシーニの編曲法を学んだというだけあって洒落ている。ボサノヴァ/行儀のいいブラジリアン・ポップが心地よく、きらめきを持つ歌が好ましい。アントニオ・カルロス・ジョビンを1曲目に持ってきて、自作のボサノヴァを2曲目で披露。強心臓だが、確かにボサノヴァの骨法を会得していることがわかる。中にはジョビンのメロディをアレンジしたようなのもあるけれど。なお、マルコス・ヴァーリは曲作りのヒトで、歌詞は基本的にパイロットが本業の兄パウロ・セルジュが書いている。『ヴィオラ・・・』もゲスト作詞家があるものの、大半は兄の作詞である。1曲目が「月夜のヴィオラ」という意味のアルバム・タイトル作で、歌詞は国安真奈の訳詩が掲載されているので引用すると「ヴィオラォンを弾く手は必要なら戦争もする」で始まる一種のプロテスト・ソングなんだけれど、マルコスのつける曲はどこまでもポップで、デオダートもそのメロディを引き立てる。2曲目のタイトルなんかは「陽子・電子・中性子」といって、歌詞は核開発を行うマッドな科学者を非難するものなのだ。「なんと理想的な破壊的爆発だろう/どこかの実験室では変な人たちが/巧妙にも勤しんでいる」なんていう歌詞にポップなメロディが付いて女性ヴォーカルとデュエットしたりしている。『プレヴィザォン・・・』は訳せば「天気予報」。表題曲はインストである。72年作ということで、エレキにエレピにシンセなエレクトリック・ポップだけれど、ここでも歌詞は苦くともメロディやアレンジは心地よく、特にアナログ・シンセのオブリガートが快感。このシンセのリアリティは今の音楽から失われたものの一つだ。74年のオデオン最終作となったセルフタイトル作は一種の総決算で、この後アメリカに渡り、80年代に入るまでアルバムがなくなる。
マルコス・ヴァーリはデビューから10年で10枚あまりのアルバムを残した。そのうち半分を聴いたわけだが、その個性は明確で、時代に合わせて洗練されたサウンドを作っているけれども、趣味のよいメロディ作りは一貫していて、どのアルバムも飽きずに聴いていられる。兄の作る歌詞はかなり辛辣だけれども。解説でブライアン・ウィルソン/ビーチ・ボーイズを引き合いに出していたけど、頷けるとこだろう。
 |
 |
 |
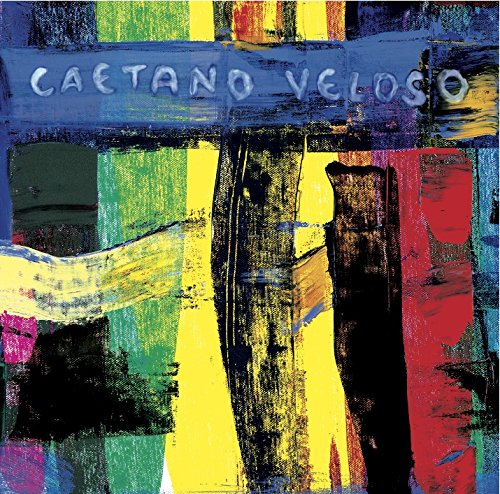 |
カエターノ・ヴェローゾの方は、通称『ホワイト・アルバム』68年作、通称『フェラ・フェリーダ』87年作、『シルクラドー』91年作それに『リーブロ』97年作の4枚。幸せなメロディストのマルコス・ヴァーリと違って、常にその時々のリアリティを作品化するカエターノのアルバムは一つ一つ印象が異なる。
デビュー3作目の『ホワイト・・・』の原題はセルフ・タイトルで、カエターノにはこれがいくつもあるのでどれも通称がつけられているのだ。『ホワイト・・・』はジャケットを見れば白地に名前だけのデザインで、当然ビートルズのそれにちなんで通称が付けられている。中身も前作『アレグリア・アレグリア』よりずっと同時代的なロック・アレンジがされていて、英語詩では歌い方もジョン・レノンを思わせたりするので、音楽的にもビートルズの強い影響下にある。しかし、このアルバムの特徴は、ジルベルト・ジルとともに反政府的言論活動で逮捕された後に、行動の制限をされる中、ジルベルト・ジルのアコギ1本の伴奏で基本トラックを作っていることだろう。そこに後期ビートルズ的なアレンジがかぶせられているので、ある種のサイケデリック・フォーク・ロックみたいな感じが出ている。アルバム後半では、シコ・ブアルキやジルベルト・ジルの曲をカヴァーしているが、基本的な感触は変わらない。これが20年後の『フェラ・・・』(原題は『カエターノ』)に跳ぶと60年代の名残はみじんもなく、今聴いても同時代かと思わせるかっこいいサウンドと歌詞が満載。コンテンポラリイ・ワールド・ミュージックなんである。青い海と空に黄色い砂浜そして波打ち際の黒人と色彩豊かな海辺を描いたジャケットにヒゲ面メガネのオッサンなカエターノの横顔が大きく描かれ、ユーモアとしゃれっ気が同居している。『シルクラドー』は当時玄人受けしていたアート・リンゼイをプロデューサーに迎えた2作目で坂本龍一やマーク・リボーなどリンゼイ人脈も参加して、1曲目から日本人女性の日本語で「新世界の無秩序」なんていうリフレインが歌われる、当時のとんがった1枚。でも途中で寝てしまうんだよねえ。その時代にとんがっていたはずのサウンドは時折退屈でもあるのだった。今回の再発シリーズでは一番の最近作『リーブロ』は、オリジナル・アルバムとしては『シルクラドー』以来7年ぶりで、カエターノと深いつきあいのチェリスト/アレンジャーであるシャギス・モレレンバウムが参加した、いかにもコンテポラリイな作品で、カエターノの曲作り・ヴォーカルそしてアレンジが三拍子そろったカエターノらしいといえばカエターノらしいアルバム。『フェラ・・・』ほどポップな感じはないけれど、これはこれで十分聴かせる。
カエターノはもう少し聴いてみないと好きかどうかも含めてまだよくわからない。
 高山羽根子『うどん、キツネつきの』は表題作が第1回創元SF短編賞佳作を得た著者のデビュー短編集。収録5編中、表題作と「母のいる島」が既読。前半の作品からは、女性作家には珍しいのほほんとしたユーモアが感じられるが、2014年中に書かれたらしい後半の2作からは緊張感を伴うスタイルに変化している。これがヴァラエティなのか本来の持ち味なのかはわからないが、できれば「のほほん」とした作品が読みたい。
高山羽根子『うどん、キツネつきの』は表題作が第1回創元SF短編賞佳作を得た著者のデビュー短編集。収録5編中、表題作と「母のいる島」が既読。前半の作品からは、女性作家には珍しいのほほんとしたユーモアが感じられるが、2014年中に書かれたらしい後半の2作からは緊張感を伴うスタイルに変化している。これがヴァラエティなのか本来の持ち味なのかはわからないが、できれば「のほほん」とした作品が読みたい。
 新☆ハヤカワ・SF・シリーズのマデリン・アシュビー『vN』は読みやすさが取り柄のカナダ出身新人作家のデビュー長編。アシモフ・ロボット三原則バリエーションのアンドロイドものだが、少女アンドロイドが祖母ちゃんを食ってムクムクと成長してしまうまでが、超スピードで展開するので、残りの逃亡者物語は、読めない展開であるけれど、思ったほどの広がりを出せていないように感じた。大森望の解説にもあるように日本アニメのタッチがそこここに現れていてほほえましいといえばほほえましい。SF/倫理的なアイデアはよいけれど、その分世界の空気が薄いような気がする。
新☆ハヤカワ・SF・シリーズのマデリン・アシュビー『vN』は読みやすさが取り柄のカナダ出身新人作家のデビュー長編。アシモフ・ロボット三原則バリエーションのアンドロイドものだが、少女アンドロイドが祖母ちゃんを食ってムクムクと成長してしまうまでが、超スピードで展開するので、残りの逃亡者物語は、読めない展開であるけれど、思ったほどの広がりを出せていないように感じた。大森望の解説にもあるように日本アニメのタッチがそこここに現れていてほほえましいといえばほほえましい。SF/倫理的なアイデアはよいけれど、その分世界の空気が薄いような気がする。
 第2回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作という柴田勝家『ニルヤの島』は、ヒトの人生を丸ごと記録し再生できる技術が成立して、死後の世界は存在しないというのが当たり前になった時代に、ミクロネシア経済連合体(ECM)の島を舞台に展開する3パートのドラマとECM内のある場所でチェスに似たゲームをしながら対戦者の一方が他方にこの世界をレクチャーする《Checkmate》-弑殺-というパートで構成されている。「主観時間」というタームとその説明が出てくるが具体的には何なのかよくわからない。またミーム・コンピュータという概念もよくわからないし、ヴァチカンが死後の世界を否定したなどということをさらっと流しているあたりで、設定に疑問を感じて読むのに苦労した。表題の「ニルヤの島」が彼岸とどう違うのかもわからず、設定に対する疑問の方が物語を読み進める力に勝るような1作だった。
第2回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作という柴田勝家『ニルヤの島』は、ヒトの人生を丸ごと記録し再生できる技術が成立して、死後の世界は存在しないというのが当たり前になった時代に、ミクロネシア経済連合体(ECM)の島を舞台に展開する3パートのドラマとECM内のある場所でチェスに似たゲームをしながら対戦者の一方が他方にこの世界をレクチャーする《Checkmate》-弑殺-というパートで構成されている。「主観時間」というタームとその説明が出てくるが具体的には何なのかよくわからない。またミーム・コンピュータという概念もよくわからないし、ヴァチカンが死後の世界を否定したなどということをさらっと流しているあたりで、設定に疑問を感じて読むのに苦労した。表題の「ニルヤの島」が彼岸とどう違うのかもわからず、設定に対する疑問の方が物語を読み進める力に勝るような1作だった。
 同コンテストの最終候補作という神々廻楽市『鴉龍天晴』の方は受賞作と違って、エンターテインメントに徹した改変幕末維新時代劇アクションもの。明るい作風にもかかわらずイマドキ珍しい「皆殺しの歌」をやって見せた、ハドリー・チェイスが好きだった人間には嬉しい1冊。字で書いたマンガには違いない。手間暇掛けて造形された主人公扱いのキャラクターたちが実は忍術合戦のバトルのコマとして消尽されてしまう贅沢さには参った。そりゃまあSFコンテストでは大賞には選べないだろうが、金を出して読むだけの楽しさはあるので、これを出版したのは正解だろう。「画竜点睛」のひねり方はうまいがペンネームは苦しい。
同コンテストの最終候補作という神々廻楽市『鴉龍天晴』の方は受賞作と違って、エンターテインメントに徹した改変幕末維新時代劇アクションもの。明るい作風にもかかわらずイマドキ珍しい「皆殺しの歌」をやって見せた、ハドリー・チェイスが好きだった人間には嬉しい1冊。字で書いたマンガには違いない。手間暇掛けて造形された主人公扱いのキャラクターたちが実は忍術合戦のバトルのコマとして消尽されてしまう贅沢さには参った。そりゃまあSFコンテストでは大賞には選べないだろうが、金を出して読むだけの楽しさはあるので、これを出版したのは正解だろう。「画竜点睛」のひねり方はうまいがペンネームは苦しい。
 1巻目が楽しく読めたので、池内紀・川本三郎・松田哲夫編『幸福の持参者 日本文学100年の名作第2巻1924-1933』も読んでみた。500ページ足らずに15作を収録。収録作家は中勘助・岡本綺堂・梶井基次郎・島崎藤村・黒島伝治・加能作次郎・夢野久作・水上滝太郎・龍胆寺雄・林芙美子・尾崎翠・上林暁・堀辰雄・大佛次郎・広津和郎。この中では、黒島伝治と加能作次郎が知らない名前だが、黒島は大正時代にロシア革命に乗じた日本のシベリア出兵に従軍した作家。まだ習作時代だった大学予科の時に招集されシベリアでの悲惨な兵隊生活を経験したという。収録作「渦巻ける鴉の群」はその経験を元にしたフィクションで、雪深いシベリアで懲罰的に斥候に出された先遣隊が遭難、春になって鴉が舞っている下には・・・というのが表題の意味だが、それよりも現地の貧しいロシア人との情けなくも人間らしい付き合いやしがない兵隊の消耗品扱いが印象的だ。アンソロジーの表題作に選ばれた加能作次郎の作品は、貧しいサラリーマンの奥さんがささやかな贅沢としてコオロギを1匹買って帰り、最初は夫と風流を愉しんだが元気な鳴き声を毎日聞かされイライラが募り・・・というもの。解説を読めば、そう言えるけれど、どうということもない小品。集中随一は林芙美子「風琴と魚の町」。いわゆる「尾道もの」の1編。作家自身の少女時代を思わせるヒロインと親夫婦がはじめて尾道に着いてそこに居着き始めた時の話。林の筆は尾道/瀬戸内の風情をとらえてよどみなく明るく、悲惨な貧乏生活も全く暗さを感じさせず、ヒロインが小便をして自らの股間をのぞき込むところなど笑ってしまう。梶井・龍胆寺・尾崎・堀のモダニズムも楽しい。とくに龍胆寺「機関車に巣喰う」は斬新なエロティシズムでビックリさせられる。また岡本綺堂「利根の渡」や広津和郎「訓練されたる人情」の強い話作りには感心する。
1巻目が楽しく読めたので、池内紀・川本三郎・松田哲夫編『幸福の持参者 日本文学100年の名作第2巻1924-1933』も読んでみた。500ページ足らずに15作を収録。収録作家は中勘助・岡本綺堂・梶井基次郎・島崎藤村・黒島伝治・加能作次郎・夢野久作・水上滝太郎・龍胆寺雄・林芙美子・尾崎翠・上林暁・堀辰雄・大佛次郎・広津和郎。この中では、黒島伝治と加能作次郎が知らない名前だが、黒島は大正時代にロシア革命に乗じた日本のシベリア出兵に従軍した作家。まだ習作時代だった大学予科の時に招集されシベリアでの悲惨な兵隊生活を経験したという。収録作「渦巻ける鴉の群」はその経験を元にしたフィクションで、雪深いシベリアで懲罰的に斥候に出された先遣隊が遭難、春になって鴉が舞っている下には・・・というのが表題の意味だが、それよりも現地の貧しいロシア人との情けなくも人間らしい付き合いやしがない兵隊の消耗品扱いが印象的だ。アンソロジーの表題作に選ばれた加能作次郎の作品は、貧しいサラリーマンの奥さんがささやかな贅沢としてコオロギを1匹買って帰り、最初は夫と風流を愉しんだが元気な鳴き声を毎日聞かされイライラが募り・・・というもの。解説を読めば、そう言えるけれど、どうということもない小品。集中随一は林芙美子「風琴と魚の町」。いわゆる「尾道もの」の1編。作家自身の少女時代を思わせるヒロインと親夫婦がはじめて尾道に着いてそこに居着き始めた時の話。林の筆は尾道/瀬戸内の風情をとらえてよどみなく明るく、悲惨な貧乏生活も全く暗さを感じさせず、ヒロインが小便をして自らの股間をのぞき込むところなど笑ってしまう。梶井・龍胆寺・尾崎・堀のモダニズムも楽しい。とくに龍胆寺「機関車に巣喰う」は斬新なエロティシズムでビックリさせられる。また岡本綺堂「利根の渡」や広津和郎「訓練されたる人情」の強い話作りには感心する。
 ノンフィクションはなんといってもマイク・アシュリー『SF雑誌の歴史 黄金期そして革命』。いやあ、これを読んでると至福の時が流れているような気分に襲われる。リアルタイムには全く知らない時代のアメリカとイギリスのSF雑誌の編集者や経営者や掲載作や作家たちの話がかくも面白く読めてしまうのはいったい何なだろう。6割以上の話題は聞いたこともない雑誌にまつわるもの(雑誌自体、編集者、出版社、作家、作品それにイラストレーター)だけれど、全く飽きない。ここで言及されている膨大な作品の中から60年代にSFマガジンやハヤカワSFシリーズや創元SF文庫で紹介された作品群が、今から見ても確かな選択眼で取捨選択されていたことがわかる。そしてそういう作品の翻訳を読んで育った人間が今になって当時の知らなかった米英SF(雑誌)界の事情を知ることが出来るというのはすばらしいことだ。長生きはするもんだねえ、牧眞司さん。
ノンフィクションはなんといってもマイク・アシュリー『SF雑誌の歴史 黄金期そして革命』。いやあ、これを読んでると至福の時が流れているような気分に襲われる。リアルタイムには全く知らない時代のアメリカとイギリスのSF雑誌の編集者や経営者や掲載作や作家たちの話がかくも面白く読めてしまうのはいったい何なだろう。6割以上の話題は聞いたこともない雑誌にまつわるもの(雑誌自体、編集者、出版社、作家、作品それにイラストレーター)だけれど、全く飽きない。ここで言及されている膨大な作品の中から60年代にSFマガジンやハヤカワSFシリーズや創元SF文庫で紹介された作品群が、今から見ても確かな選択眼で取捨選択されていたことがわかる。そしてそういう作品の翻訳を読んで育った人間が今になって当時の知らなかった米英SF(雑誌)界の事情を知ることが出来るというのはすばらしいことだ。長生きはするもんだねえ、牧眞司さん。
 2を読んだので川田稔『昭和陸軍全史1 満州事変』も読んでみた。2の後書きにあった1を読んでなくとも読めるように書いた、というのはかなりの誇大広告であった。この1を読んでようやく2の陸軍のバカ/エリートがなんであんな動きをしているのかが分かるし、まねごと議会制民主主義のゲームメイカー元老西園寺の動きが、政界と天皇周辺と軍部との駆け引きや陸軍のはねっ返りたちの陰謀工作などいくつもの流れが重なって結局キャスティングボートが陸軍統制派の手に転がり込んでいく筋立てが分かる。それにしてもこんな連中を育てた大正時代って何なんだ。ウーン、ミームってか。
2を読んだので川田稔『昭和陸軍全史1 満州事変』も読んでみた。2の後書きにあった1を読んでなくとも読めるように書いた、というのはかなりの誇大広告であった。この1を読んでようやく2の陸軍のバカ/エリートがなんであんな動きをしているのかが分かるし、まねごと議会制民主主義のゲームメイカー元老西園寺の動きが、政界と天皇周辺と軍部との駆け引きや陸軍のはねっ返りたちの陰謀工作などいくつもの流れが重なって結局キャスティングボートが陸軍統制派の手に転がり込んでいく筋立てが分かる。それにしてもこんな連中を育てた大正時代って何なんだ。ウーン、ミームってか。
 最後は昨年12月に読んでいたのに感想を書くのを忘れていた片岡義男『音楽を聴く』1998年初刷東京書籍刊。これは近所の古本屋で見つけた1冊。片岡義男の小説は1編たりとも読んだことがないのにエッセイには興味を引かれる。長文の音楽エッセイは3部からなっていて、どれも強いタイトルが付されている。いわく第1部「過去という膨大な財産の蓄積が 小さくて横柄な現在を抑制し、均衡をはかる アメリカのことだが」第2部「世界の各地はどこもみなエキゾチックか 真にエキゾチックなのは、自分だけではないのか」第3部「戦後の日本人はいろんなものを捨てた 歌謡曲とともに、純情も捨てた」。ホント、ハードなヒトだなあ、片岡義男という人間は。第2部のタイトルなどJ・G・バラードみたいだ。
最後は昨年12月に読んでいたのに感想を書くのを忘れていた片岡義男『音楽を聴く』1998年初刷東京書籍刊。これは近所の古本屋で見つけた1冊。片岡義男の小説は1編たりとも読んだことがないのにエッセイには興味を引かれる。長文の音楽エッセイは3部からなっていて、どれも強いタイトルが付されている。いわく第1部「過去という膨大な財産の蓄積が 小さくて横柄な現在を抑制し、均衡をはかる アメリカのことだが」第2部「世界の各地はどこもみなエキゾチックか 真にエキゾチックなのは、自分だけではないのか」第3部「戦後の日本人はいろんなものを捨てた 歌謡曲とともに、純情も捨てた」。ホント、ハードなヒトだなあ、片岡義男という人間は。第2部のタイトルなどJ・G・バラードみたいだ。
基本的には片岡義男自身が聴いてきた音楽を考察したエッセイだけれど、グレン・ミラーならグレン・ミラーのレコーディング史をきっちり押さえながら、その音楽がどんなものだったかを語る。第1部の結論は「個人が徹底しておこなう勉強や修練。その上に組み上げ広げていく、工夫や独創、そして創意。ブルースから出発してたとえばジャズへと発展していくプロセスは、実は科学そのものなのだ。個人がきわめて科学的に、ひとりで立つ世界。そのようなひとりひとりが集まり、競争のなかでひとつの価値を創り出す。そのプロセスのなかにある、解放された確実な前進の快感。ぼくが聴いてきたのは、これだった」あとは推して知るべし。