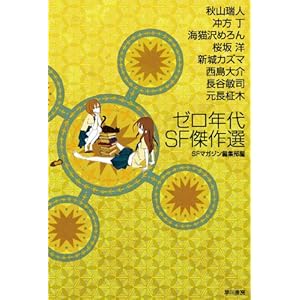内 輪 第235回
大野万紀
よしながふみ『大奥』の1巻と2巻のアメリカ版(1、2)が、このたび2009年度のジェイムズ・ティプトリー・ジュニア賞を受賞しました。ジェンダーにまつわるSFを対象とする賞ですが、マンガが受賞するのは初めてとのこと。確かに男女が逆転したパラレルな江戸時代を舞台にした、ジェンダーにまつわるSFに違いはないですね。嬉しいニュースでした。
さて、年度末。あっという間に時間が過ぎていきます。職場で、学校で、生活に変化が訪れる季節。ぼくはまあ、相変わらずです。
今月はけっこう忙しかったにも関わらず、8冊も読めてしまった。忙しくて時間がない方が、かえってたくさん読めるのだろうか。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『天地明察』 冲方丁 角川書店
『天地明察』 冲方丁 角川書店
歴史小説。これが圧倒的に面白い。水鏡子は本書をさして、SFジャンルの小説ではないが〈サイエンス・フィクション〉だといった。
江戸時代に、それまで8百年続いていた暦を改め、新しい独自の暦を作り上げた渋川春海の物語。泰平の世に、戦ではなく知力で戦った男。でも全然暑苦しい話ではなく、ユーモアあり(算術の塾に毎回行商のおばちゃんから魚を買って行くエピソードとか)、ほのぼのとした恋あり(神社で掃除をしていた武家娘との出会い、うーんかなりの萌えキャラ)、サイエンスあり(天文、和算、関孝和との算術勝負)、幕府と藩と朝廷の政治あり(老中酒井忠清、会津の保科正之、水戸光圀、土御門家や陰陽師)、碁の勝負あり、とにかく登場人物たちがみんなキャラが立っている。さすが冲方丁だ。
テーマは改暦であり、和算であり、また一つの大プロジェクトをやりとげる情熱であるわけだけど、サイエンスが主題なわりにはほとんど説明的な文章は出てこない。本書ではそれで良かったと思えるが、本当はもっと語りたかったのではないかなあ。最近数学に関わる小説やマンガを続けて読んだのだが、面白いからつい数式で語りたくなってしまいがちだ。数式を出さないまでも、和算の術と現代数学の関係とか、暦の天文学的な基礎とか、いくらでも語れる深さがあるし、サイエンス好きにはそこにロマンを感じるわけだけど、本書ではごく軽く触れられるだけで、ばっさりと切り捨てられている。SFファンとして、多少の物足りなさはあるのだが、そこを切り捨てたおかげで、本書は人間ドラマとしての成功をとげたと思える。
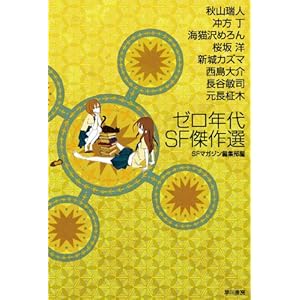 『ゼロ年代SF傑作選』 SFマガジン編集部編 ハヤカワ文庫JA
『ゼロ年代SF傑作選』 SFマガジン編集部編 ハヤカワ文庫JA
ゼロ年代のSFマガジンに掲載された作品を中心に(書き下ろし1編を含む)、若手作家の作品8編を収録。
解説で〈リアルフィクション〉という言葉が多用されているが、ぼくにはあまりリアリティのない言葉だ。これはSFマガジン前編集長の塩澤さんが作ったキャッチフレーズで、ライトノベルと、SFやSF寄りの普通小説(スリップストリーム)との融合を意図していたようなのだが、作品としての共通性はなく、あまりこの言葉には意味を見いだせないように思える。
それはさておき、現代SFとして読み応えのある作品の多い、注目すべき短編集である。正直ピンと来ない作品もあるが、全体として外れは少ない。中でも印象に残ったのは、SFM読者賞を受賞した秋山瑞人の「おれはミサイル」。これは確かに傑作だ。その昔「人間以外――人間の登場しないSFアンソロジー」という文章を書いたくらいで、ぼくはこの手の話は大好きだ。冲方丁は『天地明察』を読んだばかりだが、「マルドゥック・スクランブル"104”」はやっぱり面白い。海猫沢めろん「アリスの心臓」も若々しいはったりが効いていて面白く読めた。
 『紫色のクオリア』 うえお久光 電撃文庫
『紫色のクオリア』 うえお久光 電撃文庫
ベストSF2009で10位に上がっていたライトノベル。量子力学・多世界SFだというので読んでみた。帯に「少し不思議に日常系ストーリー」とあるけど、ええっ?。全然日常系じゃないや。
何というか、相当に不思議な小説で、登場人物はほとんど3人(後半で4人)の女の子だけ。ゆかりという「人間がロボットに見える」という少女を中心に、語り手の少女と彼女との関係性が全てといっていい物語である。確かに量子力学SFで、並行宇宙で多世界で、人の意識の不思議さが描かれている――というか、まさに宇宙レベルの広がりを見せるものすごいSFとなるのだけれど、これだけの壮大な大宇宙レベルの物語が、主人公とゆかりの関係性のためだけに存在しており、それ以外は全く眼中にない、というのには、おじさんビックリです。セカイ系というけれど、これってウチュウ系?
人がロボットに見えるというところから、逆にロボット(モノ)も人だとなるのは面白く、なかなか読み応えはあると思うが、後半の展開にはちょっとついていけない感じがある。果てしない繰り返しのむなしさ、恐ろしさは、涼宮ハルヒのエンドレスエイトの方が強烈だった。本書のもつ、何というか万能性は、ぼくにはもうひとつピンと来なかった。
 『リックの量子世界』 デイヴィッド・アンブローズ 創元SF文庫
『リックの量子世界』 デイヴィッド・アンブローズ 創元SF文庫
これまた量子論・多世界SF。妻の交通事故をきっかけに、並行世界の自分自身に乗り移ってしまったリック。こちらの世界では妻は生きており、自分の職業も異なっている。なぜこの世界に入り込んでしまったのか、果たして元の世界の自分に戻ることができるのか。
というわけで、確かに量子論・多世界SFではあるのだが、物語の中心は二重人格ミステリ。一人の男の中に二つの人格が存在し、さらに彼らはコミュニケーション可能だという設定。そうして、少しずつ異なる因果律の中での、家族や夫婦の有り様が描かれる。妻の浮気、良き友人との破局、そういう日常的な人生の悲劇がこれでもかと彼を見舞う。そこからどうやって脱出することができるのか。
えーと、小説としては普通に面白いので、さくさくと読むことができる。だけど、SFを読んだ気があまりしないというのも確かだ。ディック的悪夢という面については、そういう雰囲気もないわけではないが、逆に本書ではSFとしての理屈をきちんと通しているので、ディック的な不条理感、あいまいでもやもやした気分というものはあまり感じられない。本当にしっかりSFしているにもかかわらず、あんまりSFっぽくないという、ちょっと変わった作品でした。
 『セピア色の凄惨』 小林泰三 光文社文庫
『セピア色の凄惨』 小林泰三 光文社文庫
短篇4編を額縁小説でくるんだ連作集。ホラーである。特別に超自然的な存在が出てくるわけではない、異常心理的なホラーで、生理的な不快感をこれでもかと畳みかけるイヤなホラー。しかもひたすら理屈っぽい。不快で邪悪で、救いがなく、おぞましい。というと、けなしているように聞こえるかも知れないが、そうじゃない。これは誉め言葉だ。あまりの不快さに笑えてくる。
それにしても、額縁小説となっている探偵と依頼人の会話のぶち切れそうな理屈っぽさ。こんな探偵はすぐにたたき殺しておくべきです。あの黒光りするしつこい害虫と同じです。おぞましさでは「ものぐさ」と「安心」が双璧をなしているが、巻末の「英雄」はちょっと違ったタイプで、昔の筒井康隆っぽいスラプスティックな味わいがある。スプラッタなスラプスティック・コメディ(言いにくい)。熱いぜ。熱血ホラーだ。
 『アホの壁』 筒井康隆 新潮新書
『アホの壁』 筒井康隆 新潮新書
『バカの壁』ならぬ『アホの壁』。しかしお笑いの本ではなく、けっこうシリアスな、フロイト流の解釈を中心に、人はなぜアホなことをしてしまうのか、色々と考察している本である。
「人間は、考えるアホである」というのは良い言葉だなあ。それほど目新しいことが書いてあるわけではないのだが、ちょうど筒井さんが肉声で語っている感じの文章で、TVに出ている筒井さんの顔を思い浮かべながら読むと大変面白い。文章では真面目にりっぱなことを語っているように見えながら、「いや、ホンマにアホやねえ」とあの声で言われたら、ホンマですわ、アホですわ、と頷くしかないわなあ。
巻末の言葉が滅茶苦茶素晴らしい。「人類はやがて滅亡するだろうが、そしてそれは最終戦争以外の理由であるかもしれないが、その時はじめてわれわれはアホの存在理由に気づくだろう。アホがいてこそ人類の歴史は素晴らしかった、そして面白かったと」「アホとは何と素晴らしいものであろう。アホ万歳」凄い。凄すぎる。アホや〜。
 『日本SF精神史 幕末・明治から戦後まで』 長山靖生 河出書房新社
『日本SF精神史 幕末・明治から戦後まで』 長山靖生 河出書房新社
ノンフィクションをもう1冊。評価の高い本だが、なるほどこれは素晴らしい。ぼくは古典SFというものにさほど興味がなかったのだが、本書は、昔にこんな面白い話が書かれていたんですよ、という横田さん流の古典発掘・紹介ではなく、幕末からの日本SF史を実にまっとうに、丹念に描いていく。もちろんそんな時代に「SF」という言葉もジャンルもないわけだから、SF史というより「SF精神史」なのである。つまり、SF精神、SF心、SFファンがこれはSFだ!と思うあれだ。センス・オブ・ワンダーを愛する気持ちというものは、百五十年も前からこの日本に脈々と受け継がれていたということなのだ。
明治の時代に、欧米のSFをほとんどリアルタイムに読み、広めていたというのにも驚かされる。ぼくらのじいさんのじいさんたちも、ぼくらと同じようなことをやってたのね。今の日本SFが手塚治虫から始まったと感じているぼくの意識では、古典SFと現代SFには大きな断絶があるように思っていたのだが、それは間違いだということがわかる。
本書の終わりは1970年代にまで及んでいるが、ぼく自身がSFにのめり込んでいった時代でもあり、そこはさすがに生々しい印象があるなあ。これももうすでに歴史の一幕なのか。
 『天冥の標 II 救世群』 小川一水 ハヤカワ文庫
『天冥の標 II 救世群』 小川一水 ハヤカワ文庫
〈天冥の標〉シリーズの第2巻は、1巻とはがらりと趣を変えて、ほぼ現代の日本を舞台にしたパンデミック小説となった。
ミクロネシアのリゾートで発生した未知の感染症。国立感染症研究所の児玉圭吾と矢来華奈子は現地で生き残った日本人の少女、千茅と現地人らしき男性を保護する。WHOを始めとする国際的な努力にもかかわらず、疫病は世界に広がり、パンデミックの危機が人類に迫る……。
本書では、圭吾ら、感染症と闘う医師の視点と、千茅ら、生き残った患者の視点、そしてパンデミックのような危機的状況に対処する、ある種冷たい政治的、防疫的な立場の視点が入り交じって、多角的に危機が描かれる。とりわけ千茅らの患者たちの描き方が印象的だ。それは短篇「白鳥熱の朝に」と同じ問題意識であり、今現在も続いているインフルエンザ禍の、マスコミや大衆やネットの中に置かれた患者一人一人を見守る視点ともつながっている。小松左京の『復活の日』とは違い、人類が絶滅するような疫病ではないが、むしろウイルスを宿したままの多数の生き残りが生じることが、社会的な問題を大きくしている。とてもリアルな、そして現実の社会とつながる小説であり、パニックだけを描くものではない。
本書を読んで、小松左京の真の後継者となるのは小川一水ではないか、という気がした。それは人類は何てアホなんだろう、でもそんな人類が愛おしいというような、基本的にオプティミスティックな視点だけでなく、ある種の理想論とのバランスの取り方、科学への信頼、そして日常にこだわりながらも宇宙につながるような巨視的なまなざしといったものだ。もちろんそれらは多くのSF作家に多かれ少なかれ共通するものだが、著者の場合、小説としてのバランスよりも、そういったテーマ性により惹かれ、重視する傾向があると思う。それってまさに(良い意味でも悪い意味でも)小松左京的なものではないだろうか。
そして、本書のマンデーンなリアリズムとそぐわない、情報生命体のちょっと唐突なSFっぽさ。それがシリーズ全体を結びつけていくのだろうか。いよいよ面白くなっていきそうだ。続巻への期待が高まる。
THATTA 263号へ戻る
トップページへ戻る
 『天地明察』 冲方丁 角川書店
『天地明察』 冲方丁 角川書店