クラークが亡くなった。長生きしたし、ジャック・ウィリアムスンほどじゃないけれどずっと半現役だった。20世紀を代表するSF作家だったのは衆目の一致するところだね。 もう何度も書いたような気がするけれど、出会いは中学校2年の夏、親父に連れて行ってもらってテアトル東京のロードショーで見た「2001年宇宙の旅」。親父は500円の一般席だったが、どう思ったのか1000円の指定席を買ってもらえた。すると制服姿の案内嬢が絨毯の敷いてある席まで案内してくれた。立川の南口にあった3番館ではよく一人で007映画(「殺しの番号/ドクターノオ」とか「サンダーボール作戦」とか)なんかを見に行っていたが、都心の映画館は初めてだった(その前は小学生の時に親父に連れられてジョン・ヒューストンの「天地創造」のロードショーを都心のどこかで見たはずだが何も覚えていない)し、案内嬢と効き過ぎの冷房と本物のシネラマ超横長スクリーンで展開される映像の衝撃に見終わった後はボーッとしていた。それ以来伊藤さんが訳していたソフトカヴァーの『2001年宇宙の旅』を繰り返し読み、親に見つからないように夜中布団の中にスタンドを引きずり込んで『地球 幼年期の終わり』を読んで滂沱の涙を流し、翌年の夏今度は一人でテアトル東京のアンコール上映を見に行って、立川の3番館ではカメラ持参でスクリーンの映像に向かってシャッターを切っていた(当時は天文&カメラ小僧だったので、スローシャッターで撮れば映画やテレビの映像が写せることを知っていた)。 こうしてSF人生が始まったわけだが、自分の小遣いで最初に買ったのは何故か『第二段階レンズマン』だった。なんでそんな中途半端な巻を買ったのかはまったく覚えていないけど、十分に楽しんだことは覚えている。
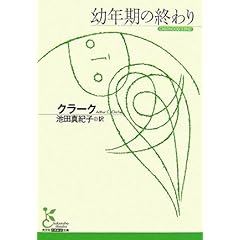 そんなこととはつゆ知らず、正月に読もうとしていて3月初めにずれこんだのがクラークの新訳版『幼年期の終わり』。初読以来40年ぶりということで、かなり覚えているはずだったのに、第二部以降がずいぶんあやふやになっていたことが判明。第三部で地球の変貌を地上から中継する最後の人間が、記憶では黒人の少年に化けていたことに驚愕。クラークがそんな登場人物を用意するわけがないよなあ。いまとなっては世界のとらえ方が非常にシンプルであることがよくわかるけれど、クラークが希求したものが、この時代にあってさえ強いロマンティシズムとして感動を呼び込むだけの力をもっていることにうれしさを感じる。
そんなこととはつゆ知らず、正月に読もうとしていて3月初めにずれこんだのがクラークの新訳版『幼年期の終わり』。初読以来40年ぶりということで、かなり覚えているはずだったのに、第二部以降がずいぶんあやふやになっていたことが判明。第三部で地球の変貌を地上から中継する最後の人間が、記憶では黒人の少年に化けていたことに驚愕。クラークがそんな登場人物を用意するわけがないよなあ。いまとなっては世界のとらえ方が非常にシンプルであることがよくわかるけれど、クラークが希求したものが、この時代にあってさえ強いロマンティシズムとして感動を呼び込むだけの力をもっていることにうれしさを感じる。
 ハードカヴァーでは買わなかったけれど、長らく気になっていたピアニスト安川加壽子の評伝、青柳いづみこ『翼のはえた指 評伝安川加壽子』が9年ぶりに白水Uブックスに落ちたので、早速読んでみた。読んでびっくりさせられたのは、その晩年のピアニストとして残酷ともいえる運命とその運命をものともせず動き回った安川加壽子の姿だった。この話も前に書いたけれど、今から30年前に京都市交響楽団のソロイストとしてショパンの協奏曲(1番か2番か覚えていない)を聴いたとき、とてもピアノから出ているとは思えないほどフワフワと宙を漂っていく音に驚かされた。その光景と音の印象は今も眼底と耳底に焼き付いている。そんな超絶的といってもいい音を持つ不思議なピアニストが、その後大活躍することもなくまた大家として数多くのレコードを残すこともなく、消えたような印象がつきまとっていたが、この本を読んでその理由がよくわかった。安川加壽子は進行性のリューマチのため80年代に入ってまもなく引退を余儀なくされていたのだった。京響で聴くことが出来た安川加壽子は、だから好調を維持していた最後の時期の演奏だったのだ。安川加壽子のCDは未だに聴いたことがないが、京都で聴いたあの音が記憶にある限り聴かなくてもいいような気がする。
ハードカヴァーでは買わなかったけれど、長らく気になっていたピアニスト安川加壽子の評伝、青柳いづみこ『翼のはえた指 評伝安川加壽子』が9年ぶりに白水Uブックスに落ちたので、早速読んでみた。読んでびっくりさせられたのは、その晩年のピアニストとして残酷ともいえる運命とその運命をものともせず動き回った安川加壽子の姿だった。この話も前に書いたけれど、今から30年前に京都市交響楽団のソロイストとしてショパンの協奏曲(1番か2番か覚えていない)を聴いたとき、とてもピアノから出ているとは思えないほどフワフワと宙を漂っていく音に驚かされた。その光景と音の印象は今も眼底と耳底に焼き付いている。そんな超絶的といってもいい音を持つ不思議なピアニストが、その後大活躍することもなくまた大家として数多くのレコードを残すこともなく、消えたような印象がつきまとっていたが、この本を読んでその理由がよくわかった。安川加壽子は進行性のリューマチのため80年代に入ってまもなく引退を余儀なくされていたのだった。京響で聴くことが出来た安川加壽子は、だから好調を維持していた最後の時期の演奏だったのだ。安川加壽子のCDは未だに聴いたことがないが、京都で聴いたあの音が記憶にある限り聴かなくてもいいような気がする。
 その厚さにビックリしたジョン・スラデック『蒸気駆動の少年』に収められたいささかバラエティの富みすぎな作品群は、多彩とは言い難いスラデックの書き癖みたいなものが感じられる。一つ一つがどんな話だったか早くも忘れてしまっているけれど、昔読んだ表題作や「教育用書籍の渡りに関する報告書」(キセルさんの黒縁眼鏡を思い出す)などは今回も面白く読めた。それにしてもヒネた思考力の持ち主だったなあ。
その厚さにビックリしたジョン・スラデック『蒸気駆動の少年』に収められたいささかバラエティの富みすぎな作品群は、多彩とは言い難いスラデックの書き癖みたいなものが感じられる。一つ一つがどんな話だったか早くも忘れてしまっているけれど、昔読んだ表題作や「教育用書籍の渡りに関する報告書」(キセルさんの黒縁眼鏡を思い出す)などは今回も面白く読めた。それにしてもヒネた思考力の持ち主だったなあ。
 著者15年ぶりと謳われた野阿梓『伯林星列』は、昔の傑作群を期待して読むと肩すかしを食らわせられる著者の趣味が汪溢した一作。話の半分は美少年調教と被虐の宴に費やされ、二・二六事件が成功した改変歴史上でのナチス・ドイツとソ連との秘密裏の提携を探る諜報戦という本来のストーリーは、その面白さが十分に発揮されているとはいいがたい。文体はこの作者らしい華やかさを持ってはいるが、コリン・ウィルソンもいったように、ポルノを書けばポルノ以外の話が無駄になる可能性は大きく、この作品もその弊害を免れてるとは思えない。それにポルノが(これは個人的な趣味の違いが大きいが)その本来の機能を果たしてくれないとなると、作者が意を注いでいるだけに残念という印象が強くなる。姉川孤悲がいたぶられた話は好きだったのに、少女の姿をした美少年がいたぶられても何も感じないのはこちらが年を取ったからというだけのことなのか。
著者15年ぶりと謳われた野阿梓『伯林星列』は、昔の傑作群を期待して読むと肩すかしを食らわせられる著者の趣味が汪溢した一作。話の半分は美少年調教と被虐の宴に費やされ、二・二六事件が成功した改変歴史上でのナチス・ドイツとソ連との秘密裏の提携を探る諜報戦という本来のストーリーは、その面白さが十分に発揮されているとはいいがたい。文体はこの作者らしい華やかさを持ってはいるが、コリン・ウィルソンもいったように、ポルノを書けばポルノ以外の話が無駄になる可能性は大きく、この作品もその弊害を免れてるとは思えない。それにポルノが(これは個人的な趣味の違いが大きいが)その本来の機能を果たしてくれないとなると、作者が意を注いでいるだけに残念という印象が強くなる。姉川孤悲がいたぶられた話は好きだったのに、少女の姿をした美少年がいたぶられても何も感じないのはこちらが年を取ったからというだけのことなのか。
本来は音楽の雑談で書くところだけれど、『本の雑誌』の青山南のエッセイで延々と続くジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』話が4月号で「1980年の映画『ハートビート』」をとりあげている。その文章を眼にしたとたん、八〇年代キング・クリムゾンの第2作「ビート」が思い出され、久しぶりにCDをひっぱりだしたら、やっぱり「ビート」はこの映画および同名原作と『オン・ザ・ロード』に触発されて出来たコンセプト・アルバムだった。アメリカ趣味の青山南コラムでは(半分アメリカ人がいるとはいえ)ブリティッシュ・プログレが話題になることはないんだろうな。
THATTA 239号へ戻る
トップページへ戻る
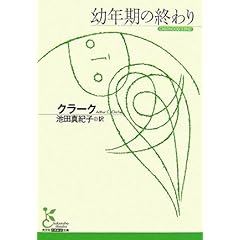 そんなこととはつゆ知らず、正月に読もうとしていて3月初めにずれこんだのがクラークの新訳版『幼年期の終わり』。初読以来40年ぶりということで、かなり覚えているはずだったのに、第二部以降がずいぶんあやふやになっていたことが判明。第三部で地球の変貌を地上から中継する最後の人間が、記憶では黒人の少年に化けていたことに驚愕。クラークがそんな登場人物を用意するわけがないよなあ。いまとなっては世界のとらえ方が非常にシンプルであることがよくわかるけれど、クラークが希求したものが、この時代にあってさえ強いロマンティシズムとして感動を呼び込むだけの力をもっていることにうれしさを感じる。
そんなこととはつゆ知らず、正月に読もうとしていて3月初めにずれこんだのがクラークの新訳版『幼年期の終わり』。初読以来40年ぶりということで、かなり覚えているはずだったのに、第二部以降がずいぶんあやふやになっていたことが判明。第三部で地球の変貌を地上から中継する最後の人間が、記憶では黒人の少年に化けていたことに驚愕。クラークがそんな登場人物を用意するわけがないよなあ。いまとなっては世界のとらえ方が非常にシンプルであることがよくわかるけれど、クラークが希求したものが、この時代にあってさえ強いロマンティシズムとして感動を呼び込むだけの力をもっていることにうれしさを感じる。

