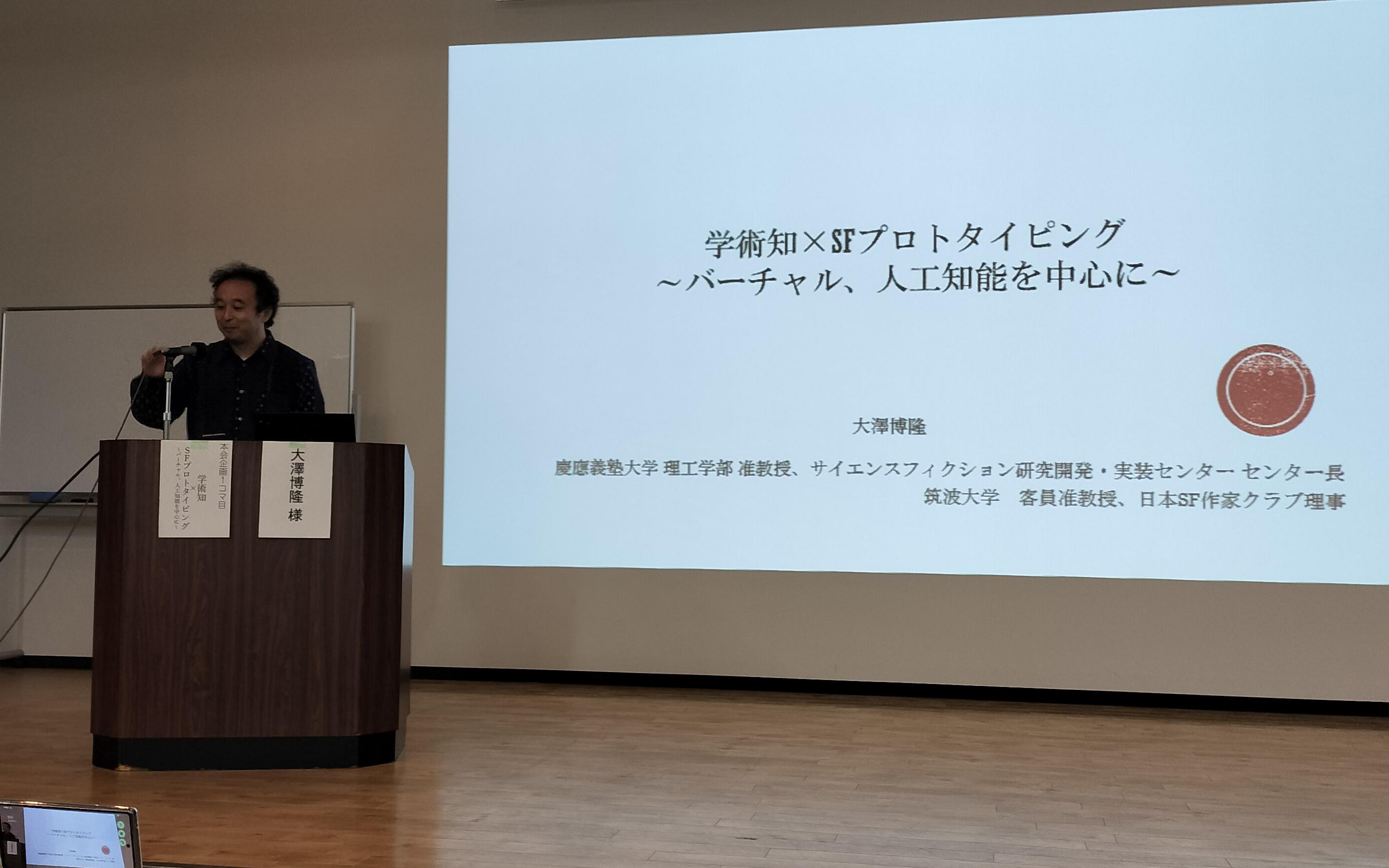 最初の企画は日本SF作家クラブの会長も務められたことのある、慶応大学理工学部管理工学科准教授の大澤博隆さんによる「学術知×SFプロトタイピング~バーチャル、人工知能を中心に~」。
最初の企画は日本SF作家クラブの会長も務められたことのある、慶応大学理工学部管理工学科准教授の大澤博隆さんによる「学術知×SFプロトタイピング~バーチャル、人工知能を中心に~」。 今年の京都SFフェスティバルは10月11日(土)から12日(日)に昨年同様、合宿を伴うリアル企画として開催されました。会場は京都駅から徒歩5分ですが、昨年と違いYIC京都という専門学校の会議室。場所がちょっとわかりにくく、正面からは入れず裏にまわって入る必要があって、ちょっと戸惑いました。
今年はこれまでのようなプレス制度はなく、THATTA用に写真を撮らせてくださいと頼んだところ、出演者の了承があればOKですとのこと。そこで各企画でそれぞれお願いしましたが、みなさん快くOKしていただきました。
以下は、メモと記憶に頼って書いています。もし間違いや勘違い、不都合な点があれば、訂正しますので連絡してください。
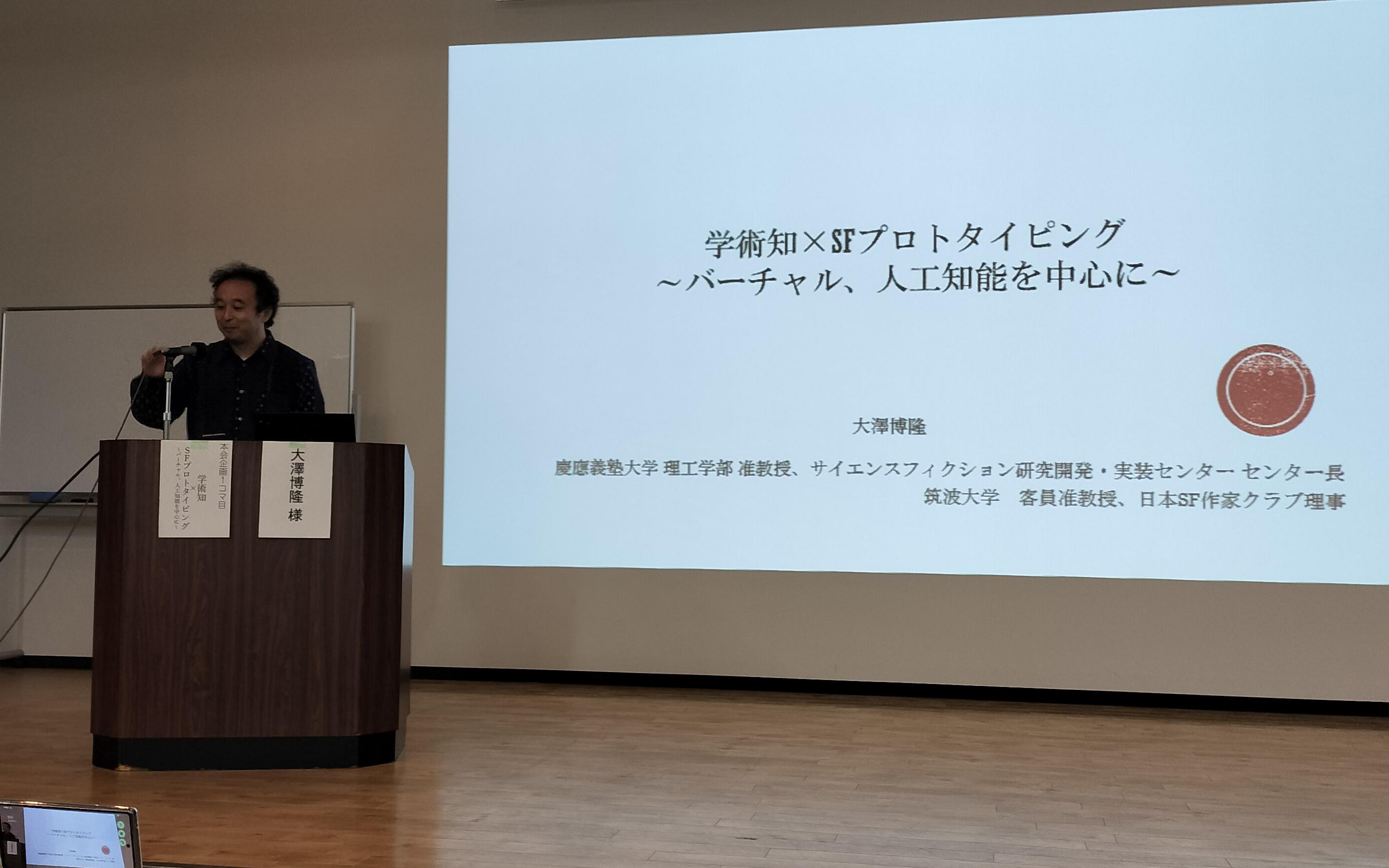 最初の企画は日本SF作家クラブの会長も務められたことのある、慶応大学理工学部管理工学科准教授の大澤博隆さんによる「学術知×SFプロトタイピング~バーチャル、人工知能を中心に~」。
最初の企画は日本SF作家クラブの会長も務められたことのある、慶応大学理工学部管理工学科准教授の大澤博隆さんによる「学術知×SFプロトタイピング~バーチャル、人工知能を中心に~」。
まず大澤さんが研究されている「ヒューマンエージェントインタラクション」の話から。そこでは人工知能はどのように擬人化されるべきなのか(「人工知能学会誌」の表紙が女性差別と問題になったように)とか、長崎のハウステンボスにありロボットが働く「変なホテル」でのエージェントの社会影響調査などをされていたそうです。
また、何が知能を育てるのかというテーマでは相手の意図を探る必要がある「人狼ゲーム」を取り上げてゲームやシミュレーションを分析。さらに「星新一賞」に見られるようにAIが小説を書くようになった今、長谷敏司さんとの共同研究でSFにおけるAIや、SFが描く未来社会のイメージ(およびその影響)を学術的に議論されました。
SFにおけるAIの分析として、AIを「人間型」、「バディ型(『雪風』など)」、「機械型」、「インフラ型(『声の網』など)」に分け、それを「人間らしさ」と「知能」の軸でマッピングした図が面白かったです。
AI自身にAIのリスクを分析させてみたところ、SFに登場するAIは大体ヤバイという結論になったとか、日本のサイバーパンクは身体に執着する傾向がある(例えば大原まり子、柾五郎など)という話もありました。
サイバーパンクとVR/AR技術のテーマでは、士郎正宗「攻殻機動隊」、磯光雄「電脳コイル」などが取り上げられ、さらに今のVR文化との関係では暴力とも子「VRおじさんの初恋」も上げられていました。
そういったSF的「物語」についての研究もあります。「物語」は人々の意見をまとめ共有するのですが、昨今の物語をめぐる状況の変化(人口減少、多様化・国際化、ユーザ主導型のコンテンツ、生成AI・・・)があり、多くの企業で未来技術よりもその社会への受容こそが現場で求められているとの話。コロナ禍が企業にSFを求めさせたといえます。そこから「SFプロトタイピング」の話へ。
企業の中で、自分たちがSFを創る。小説的な面白さより価値観を変えることを重視する。未来を予測するというより、未来像をフィクションとして作り出し、そこに専門家が加わって創作そのものではない別の価値を見いだすことを目的とする。従来のシナリオ型技法に比べ、SFプロトタイピングは挑発的で楽しいが、リアリティには乏しい面がある。しかし、ビジネスにとってはリアリティよりもむしろ楽しさ、挑発性、新規性、直観性の方が重要だ、ということでした。
その後の質疑応答で、SF的ビジュアルが新しいアイデアの支障にならないかという質問に、生成AIが出してくるビジョンは結構保守的。生成AIでアイデアを出させるとそれに引きずられがちだという問題が確かにあるとのこと。
また、ASI(人工超知能)についてどう思うかという質問には、知能はスケールがないと測れないので、ASIのスーパーインテリジェンスというのは定義が難しいという回答でした。
大澤さんの話は膨大なプレゼン資料をどんどん説明していくので追いつくのが大変でしたが、いずれもまさに現代的なテーマで、それがSFと重なっていくところが刺激的でした。
 午後一番、2つ目の企画は、天沢時生さんと十三不塔さんの対談で「ヤンキーとドストエフスキーでSFはできるか――地方、古典、サイバーパンク」。
午後一番、2つ目の企画は、天沢時生さんと十三不塔さんの対談で「ヤンキーとドストエフスキーでSFはできるか――地方、古典、サイバーパンク」。
白い服の若い天沢さん(滋賀県出身)と、黒い服のちょっとおじさんっぽい十三さん(名古屋の人)の対比がいい。どちらも古典とヤンキーという共通点があるとのことです。(本人がヤンキーだったというわけではありません)。
以下、対談部分は当日のメモから抜粋して記載します。メモが元なので実際の発言通りではありません。もし間違いや不適切な部分があれば修正しますのでご指摘ください。
天沢:周囲にヤンキーっぽい連中が多かったが、その中で自分はいわばハカセ役のポジションだった。
十三:天沢さんの『すべての原付の光』は地元のコミュニティの中での関係性を描いているのではないですか。
天沢:あれはかなり実体験で、そこに一歩下がったハカセ視点を加えたもの。コミュニティの中で何がが起きてその中で完結する話です。
十三:名古屋市の西の方はちょっとガラが悪いんですが、そこを舞台にほぼ実話のヤンキー小説を書いたことがあります。そこには喧嘩が茶飯事だった伝説のライブハウスがあってその風景を書いた。そんな不良小説集をいつか出してほしいなと思います。
不良というのは暴力性だけではないんです。何でも改造したがるのが不良で、学ランやバイクをやたら改造するのがヤンキー。その改造は機能性や効率性を度外視して美学へと向かう。改造したら高い車でももう売れなくなって、資本主義からは外れるんです。
歴史改変SFもまた改造だといえる。オリジナルをいじって楽しむ。古典をアレンジして作り替える。カッコイイものをダサいものに作り替える――。
天沢:SFよりもドストエフスキーを読んでいました。SF創作講座にたまたま入ったのでSFを読むようになりました。
十三:SFに特別な愛着はないんですね。淡白な人だ。
天沢:ジャンル意識はあまりないです。
十三:古典にはそもそもジャンルがないんですね。カテゴリー分けできないものをSFとしておけば、SFという箱には何でも入る。夏目漱石は夏目漱石であってジャンルは色々。天沢さんの『すべて原付』も、カフカ『流刑地にて』のオマージュでした。
天沢:古典をSFにする。創作講座で堺三保さんがSFの黎明期について話すというので、マーク・トウェイン『アーサー王宮廷のヤンキー』を読んだ。SFとして書かれてはいないがSF。今書いているものもそんな感じです。
十三:古典からパクると誉められる。今の作家からパクると怒られる。青空文庫は宝の山だ。
天沢:十三さんは古典が血肉化していると思います。
十三:むしろサンプリング感覚です。広く浅く。昔、批評文を読んでいたので、その屁理屈がSFのロジックに使える。柄谷行人、浅田彰、蓮實重彦、村上龍が好きだった。〈群像〉の新人賞には当時批評部門があったので、〈群像〉でデビューしたいと思っていました。
二人の今後の予定など。
天沢:今書いているのは、アーサー王宮廷とシド・ヴィシャスを合わせてヴィクトリア時代へ行く話。
十三:カクヨムネクストにライトノベルを書きました。ロボット工学者が転生してゴーレムを作る話。それと一般小説に近いほぼ外国人のチームの定時制のバスケ部の話。これは実際に愛知県であった話を元にしています。
天沢:集英社で連載中の「キックス」という普通小説も出る予定です。
二人の話はあちこちと飛ぶのですが、地元愛と古典愛が感じられて面白かったです。でもサイバーパンクの話はあまりなかったような。
 3つめはベテラン翻訳家のお二人、鍛治靖子さん(『精霊を統べる者』など)、原島文世さん(『フォース・ウィング』など)による、「英米ファンタジー翻訳家対談:2024年の話題作を語る」。
3つめはベテラン翻訳家のお二人、鍛治靖子さん(『精霊を統べる者』など)、原島文世さん(『フォース・ウィング』など)による、「英米ファンタジー翻訳家対談:2024年の話題作を語る」。
以下、パワポに表示された質問事項を見ながらのお二人の対談をメモから抜粋したものです。
英米でのファンタジーのジャンル定義について。
原島:学生のころ児童文学の研究をしていたんですが、井辻朱美先生の下で『ファンタジー百科事典』の翻訳に関わりました。そこでは「ファンタジーは心の願望の物語である」と書いてあります。かつては神話や伝説、妖精物語のようなものがファンタジーの源流だったところが、ある時点で児童文学として子供部屋へ追いやられてしまったと。それがイギリスのファンタジー。ただアメリカのファンタジーはちょっと違って、パルプマガジンの秘境冒険ものも入っている。イギリスで出たトールキンの『指輪物語』がアメリカで人気が出て、そこが今の基本。
鍛治:ファンタジーは大人向けと子ども向けとはっきり分かれている感じがありますね。
原島:いま日本で読まれているファンタジーは、なろう系、ラノベ系が中心のように思います。『フォース・ウィング』はそれにちょっと近い。読者の反応などを見てもそんな気がします。
翻訳の仕事について。あるある話。
鍛治:ヒマがあったら翻訳しています。
原島:朝起きて訳して、ご飯を食べて訳して、とにかく長いものはずーっと訳していないと終わらない。一時期、一週間靴を履かずに実家にいて翻訳していたことがあります。
鍛治:いつまでも終わらない翻訳が辛いですね。何で終わらないんだろうと思いながらやっていますけど。楽しいのはピタリとはまる表現ができたとき。
原島:自分が訳したものが本になったとき読み返すのが好きなんですけど、元々読むのが好きなんで、読み返すのがけっこう楽しかったりします。
鍛治:わたしはあんまり読み返さないですね。読み返すと辛いことが多いんで。
翻訳の昔と今、世代の違いについて。
鍛治:わたしが初めて訳した本は原稿用紙に手書きでした。それからワープロ専用機、何冊か訳した後にやっとWindows95、パソコン通信の時代になりNiftyを始めましたが、まだインターネットはありません。『ドラキュラ紀元』は人名辞典が売り物になっているんですけれど、インターネットなしにどうやって作ったのか記憶にありません。原島さんはわたしより若いので、最初からワープロですか。
原島:卒論をワープロで書いたのは覚えています。テーマは『指輪物語』だったんですが先生は誰も『指輪物語』を知らなかった。大学院でパソコンを知って、仕事はパソコンとインターネットでやってます。原稿はメールで送ってます。
翻訳とAIについて。
鍛治:AIは嘘をつく。DeepLは信用してはいけません。あいつはわかんないところは全部抜いて訳します。使った場合は必ずチェックが必要。
原島:そうですね。わたしも使う時はここの部分だけとか細切れにして使うんですけど。
鍛治:嘘ついてるのか間違ってるのかバカなのかわからないですけど、まあちょっと参考にするくらいはいいけど信用しない方がいいです。まだ小説の翻訳には使えません。だからわたしたち、まだ安泰です。
原島:最近はPDFを開くと要約しますかとか言ってくるんですけど、AIはあら筋のリーディングには使えるかも知れませんね。
P・ジェリ・クラーク『精霊を統べる者』について、原島さんから鍛治さんへの質問。
翻訳で単語にルビを振る基準はどういうふうに決めていますか?
どの程度まで実際のエジプト史やアラビア語を確認されましたか?
女性同士の恋愛を男性作家が書くことについて、はやりなんでしょうか?
鍛治:わたしはSFではルビを多用するけど、ファンタジーではできるだけルビを使わない方針としています。『精霊を統べる者』についてはSFだと思っていたんで、アラビア語が使われているとルビをつけました。色の名前がたくさん出てくるんですが、カタカナだけではわかりにくい。それで漢字にしてルビを振るということにしました。
アラビア語は読めないんで英語サイトで調べました。歴史はこの戦いは本当にあったのかとか、Wikiで調べました。歴史改変は〈ドラキュラ紀元〉で慣れているんで大丈夫です。インターネットは本当に便利ですね。
女性同士の恋愛はわりとあっさり書かれていて違和感はありません。女性主人公の話が多いみたいです。女性で黒人とか、意識して書かれているようです。
レベッカ・ヤロス『フォース・ウィング』について、鍛治さんから原島さんへの質問。
ドラゴン、グリフォン、ワイヴァーンの違いを日本の読者は理解できるでしょうか? アメリカではどうでしょうか?
かなり濃厚なラブシーンがありますが、訳していて照れませんか?
カタカナのルビをつけるものとつけないものの基準はありますか?
原島:ファンタジーだとグリフォンはわりと出てくると思います。読者にもグリフォンはイメージしやすいと思うのですが、ワイヴァーンはあまり出てこないようです。この作品でのワイヴァーンははっきり定義されていて、人工物で2本足です。普通のファンタジーのワイヴァーンとは違います。
ラブシーンについては無の境地です。昔そうい場面の出てくる作品を訳したことがあって、どっちかいうと男性同士の話でしたが、露骨に訳すとムードがないと言っていかにぼかすかと、技術的な話になってしまいます。『フォース・ウィング』は本屋大賞をいただいてしまったので、80歳超えた親戚に読んだよと言われて、ありがたいんですけど、あそこも読んだのかなと。
ルビについてはファンタジーではつけないことが多いんですけど、この作品では竜の名前などすごく長くて、日本語にしても英語にしても収まりが悪いので苦肉の策として漢字にルビで対応しました。また「レリック」や「シールド」は訳語を作ってルビを振りました。「シールド」なんてそのままカタカナだとSFになっちゃう。
ファンタジーの面白さについて。
鍛治:ファンタジーもSFも、ないことがいっぱい出てきてその訳語を考えるのが楽しく、面白い。
原島:どこか別の世界の話が好きだったんです。妖精物語(フェアリー・テイル)についてフェアリーは妖精というだけでなく、その背後にある妖精の国も示していると昔読んだ本に書いてありました。それはここではない所。そうじゃない所、別の世界を目指すんです。SFだとそれは科学になるのかも知れませんが、ファンタジーではもっと逃避というか、この現実から抜け出したいという気持ちがあるんじゃないかと思います。
 最後の企画は円城塔さんと十三不塔さんによる「物語と「翻案」」。
最後の企画は円城塔さんと十三不塔さんによる「物語と「翻案」」。
以下、、めちゃくちゃ面白かったのでいっぱいメモを取ったため、ちょっと長くなります。
十三:「翻案」というちょっとぼんやりした話なんですけど、ぼくは何で呼ばれたんだろう。歴史物、『長安ラッパー李白』の関連ですかね。
司会:もともと「翻案」という話が出たのが某ロボットアニメをSF研の会員で見ていたとき、アレンジという話で盛り上がり、そのテーマで京フェスに誰かお呼びしたいとなったんですが、歴史とアレンジという話が面白いと、それで『長安ラッパー李白』に作品を載せていらっしゃる先生を呼ぼうと。
円城:『長安ラッパー』の依頼が来たときどうでした? ぼくはちょっと困ったんですけど。
十三:ぼくはかなり前からお話をいただいていて、編者の大恵さんとも親交があったんで困ったんですけどまあ何とかなりました。
円城:中国で歴史というと、おおってなりません? 何か改変したら罰せられるという話があったので悩みました。日本で出るだけならいいけど翻訳されるでしょう。
十三:ぼくが聞いたのは、国のトップが変わるとその辺の厳しさが変わるということで。やっぱり近代に近いほどやばい。唐くらい昔ならほぼOKだろうと話をしていました。
円城:その辺の危ないところを狙うべきなのか、狙わないべきなのか、かなり悩んで、最悪翻訳が出せなくてもいいですかと一応聞いてから書きました。
ぼくが書いたのは唐の初期の話なんですが、唐はそもそも北方民族が立てた国だと。でも今の中国ナショナリズムからするとそれを書いたらまずいんじゃないかと思ったんですが、どうやらバトルものとして読まれたようでした。
『文字禍』を書いた時も、チベット語の文字コード領域を漢字が埋め尽くすという話を書いたらどのくらい怒られるのだろうか、中国のアニメの原作の仕事ができなくなるんだろうかとか色々考えたんですけど、SFならちょっと頑張らなくてはいけないのではという気がして。まあわからないんですけどね。
十三:ぼくは処女作の『ヴィンダウス・エンジン』が近未来の中国が舞台の話で、それって共産党的には完全にヤバイなと思ったんですが、長安、唐代はノーマークでした。円城さんほど考え込むことはなかったですね。
円城:どれだけ素直に書いていいか悩むんですよ。実際ナショナリズムとBLを混ぜると捕まる。どうすればいいのか。ロシアならはっきりしているが、中国ってスタンスがわからない。SFってけっこうそういうところを突っ込んで行くじゃないですか。
十三:どこまで危ないところまで行くかという話では、あえて行きたいなという部分もありますね。
「翻案」という意味で歴史というものをもう一度見直すということについては、先ほど天沢くんと話をしていて、ヤンキーというか、不良みたいなのがテーマだったんですが、ヤンキーって物事を改造するやつらだなって。制服だとか車だとかバイクだとか。ぼくもそういう元ネタがあってそれをカスタムする、改造するみたいな感覚で書いているんです。
円城さんはそれで言うと『ゴジラS.P.』なんかはリブートというかリメイク、あと『雨月物語』とか『怪談』とかは現代訳や翻訳、それと『去年、本能寺で』みたいな歴史ものと、3パターンくらいあるのかなと思ったんですが。
円城:アニメの仕事は基本的に監督・プロデューサーが主体なんで。大きなお金も動くし、意思決定の仕方が全然違う。基本、監督のオーダーに応じている。もっと円城塔ぽくと言われたら円城塔ぽくするし、それが円城塔ぽくないと言われても困るし。もともとそんなガチにするつもりはなくて、ゴジラもゴジラ細胞でいいんじゃないか、毎年夏には台風のかわりにゴジラが来る、今年もゴジラが来たねでいいんじゃないかと思っていた。でももっと円城塔らしく理屈をつけてと言われてそうした。雇われ脚本家だから。
『雨月物語』などはぼくががんばるところは何もないので、ちゃんと仕事します。
自分の書く小説は円城塔ぽくとか考えないので素直に書きます。でも最近考えるのは文章と構想と全然違うように書いていると思うようになりました。『長安ラッパー』でもそうですが、検閲に引っかからないように意識して違うことを書くようになりました。だから本当にヤバイところへは行かない。
『コード・ブッダ』を書いたときも、日本の仏教の歴史を書いていたんですけど、日蓮の前で止める。これが仏教史じゃなくてイスラム史だったら本当に命の危険があるじゃないですか。イスラム史で機械カリフとか出したら面白そうだと思うけど、誰を怒らせるかわからない。イスラムアンソロジーの話が来たらどうしよう。けっこうヤバイですね。かなり考え込むと思います。
十三:イスラムアンソロジーはヤバイですね。ご辞退させていただくかも知れない。
円城:文学系だとパレスティナアンソロジーとかあるでしょうし、依頼されたらどうしよう。ガザとかだと立場を明確にすればいいんでしょうが、イスラムとか言われたらどこまでやっていいのか。
十三:それは仏教でもあるでしょうね。ぼくはそこまで考えていませんでしたが。
円城:歴史的なことに関して言うと、みんな自分が思っている歴史への思い入れが強いんで。ぼくは北海道生まれなんですが、今大阪に住んでいます。そこで17年間あまり、日本の歴史観の違いに日々戸惑っています。近畿の人は本当に大和朝廷を信じているのが怖い。実感として違う。歴史を考えるようになったのは関西に来てからです。
十三:ぼくもずっと名古屋なんでそういう感覚はないですね。移動がないと土地ごとの歴史観みたいなのはあまり感じなくて。愛知の歴史観でいえば尾張の歴史は信長からとか。それより昔というのはあまり感じないですね。
円城:関東だと戦国時代以前は縄文になったりとか。
十三:静岡なら登呂遺跡がありますね。ところで、『去年、本能寺で』では固有名詞に英訳的なルビが振ってあったりするんですが、あれは異化効果を狙うといった意味でそうされているんでしょうか?
円城:あれはWikipediaからです。異化効果もあるんですが、それよりも日本史をどう翻訳するか問題というのがぼくの中でずっとあって、例えば鎌倉幕府についてどうコンパクトに説明するかというと、幕府が、将軍が、北条が天皇が、と難しい。もっとざっくり書けないか。でも英語で書くとああ書くしかないんです。
十三:何かあの書き方ではまた別のパラレルワールドの歴史かなと思わせるサインになるとか、色々考えたんですけどね。
円城:実際そうなんですけど、海外から見るとああなるし、ChatGPTに訳させるとたぶんあの単語はああ訳すでしょう。そう読まれてしまう。
『文字禍』を書いている時、まず日本語は中国語方言なんだなというのをずっと意識するようになってしまった。日本語には漢語と仏教用語がいっぱい含まれていて、結局それがないと日本語が書けない。それが気持ち悪くて何となく日本語を変えていけないかと。Wikipediaの言葉を入れてみたり。和語だけで書こうとしても書けないことが多いじゃないですか。そこで歴史にからめて日本語が勝手に違うことを語り出すようになると。
十三:『コード・ブッダ』でも、今日のテーマになりますが、仏教自体がどんどん「翻案」されている。色んな宗派に分かれていく。円城さんの仏教への関心についてお聞きしたい。
円城:ぼくは仏教の宗派とか歴史とか全然知らなかったんです。興味はあったんですが全然わからない。で『ゴジラS.P.』の後、ネットの評判とか見てちょっと疲れたんでこの辺で仏にすがろうかと。でもすがれなかった。
十三:『去年、本能寺で』には「タムラマロ・ザ・ブラック」にシェークスピアの『オセロー』が重なっていたりとか、何か別のものをぶつけたりということがあるんですが、その辺の狙いは?
円城:『去年、本能寺で』ではフェイクにならないようにしよう。フィクションだとわかるようにして、絶対に本当じゃないとわかるようにしようと。これはフィクションであってフェイクではないというラインをちゃんとしておかないと、ありそうなことを書いて歴史がぐちゃぐちゃになるという危機感がある。あの小説を生成AIが書いてきたらきっと編集で落とされる。そこに人間がいる価値がある。俺がいるから通るんだと。その辺をねらわないと厳しいなと思うようになった。Sora2なんて勝手なニュースを勝手に報道している。ああいうのにどう対抗していくんだろうと。
大森望(会場より):坂上田村麻呂黒人説ってすごいアメリカで流行ってるぽいじゃないですか。
円城:あれはアメリカで黒人はいかに偉大であるかというのを宣伝しなくちゃいけないから、もう何でもいいから昔誰かが書いたものが残っていたのを引っ張ってきているわけです。だからゲームの「弥助問題」なんかも起こるわけですよ。
日本は海外から見るとかなり謎の国なんです。田村麻呂黒人説なんかもそう。
十三:ぼくの小説の舞台には色々な国があって、実際に行ったところが多いんですが、一番深く入り込んだのは留学していた中国ですね。あとは旅で行ったり調べたりなんですが、そこはぼくもちょっと危険だと思っています。ちょっとエキゾチシズムみたいな形で消費してしまったりとか。日本とのギャップとか面白いのでそういうのを取り込んじゃいたくなるんですけど。
円城:ぼくが最近日本が舞台の作品ばかり書いているのにもそんな気持ちがあります。ヨーロッパの歴史なんか無理だなと思うようになりました。謎ヨーロッパになってしまう。転生ものの謎ヨーロッパがマンガ化された時の何ともいえない感覚。
「翻案」の小説は今は予定がありませんが、だんだん難しくなっていくんでしょうね。今アイヌの小説を書いているんですけど、アイヌの固有名詞は勝手につけちゃダメなんです。だからアイヌの人が出てこないアイヌの小説を書くという無茶なことになっています。ちょっと失敗しそうなので、書き終わったら専門家に助けてもらうつもり。翻案ものにはいざという時に助けてもらえるよう、偉い専門家をアドバイザーにしておく必要があるのでは。
十三:そうですね。『長安ラッパー』も大恵さんがいないとめちゃくちゃになっていたかも。大恵さんがかなり綿密にチェックしてくれるので安心して書けるというところがあります。
円城:でも古代史とか、偉い専門家でもけっこう俺の考えた歴史、みたいな方がいて、ほぼ全部間違っていたけど偉い人とかいるので難しいですね。
これからフィクションはどこへ行くんだろうなとか考えるんですが。ぼくはAIに書けない方向のものを書いていこうと思っています。ちょっと突拍子もなくしますとかいうのは、あいつらやりそうな気配がするので、やられちゃわないよう、違う方違う方へと向かって行って、でも生き延びるのは辛かろうなと。
このあたりで時間となり、会場との質疑応答もありましたが対談は終わりに。十三さんも言ってたけど、すごくためになる対談でした。とりわけ、「フェイクにならないようフィクションに徹する」というのはなるほどと感心しました。
夕食後、合宿所へ。今回の合宿は昨年と違う旅館で、近江屋旅館。会場からは昨年同様歩いて行けます。古いけれど普通にちゃんとした旅館でした。中はやっぱりダンジョン。ディーラーズとなった広間でファンジンを買う。大広間はあったけれど、合宿の注意などが放送であっただけで、特に集まって何かするということはありませんでした。
合宿企画は見たいものが重なっていて、どうするかと迷ったのですが、まずは神戸大SF研つながりで後輩の木下充矢さんと本城雅之さんの「同人誌の持続可能性を考える」へ。水鏡子と岡本俊弥もいっしょに。人は少なめで、ほとんどSF研の同窓会みたいになっていました。
まずは古いファンジンの話。本城さんらの「Vitamin SF」は和文タイプライターで作られた最後のもの。当時のPCのプリンタはしょぼかったからずっと立派な本になった。
本城さんも訳したTHATTA文庫を回覧。手書き原稿を渡して米村秀雄がワープロ化、印刷・製本までしたものです。懐かしい。
翻訳同人誌と創作同人誌の難しさの違いについて。翻訳同人誌はすでに定評のある作家なら売れます。話題のある作品は評価が高いという強みがあるが、版権を取るのが大変。エージェントのWEBサイトもあるが、作者にダイレクトアタックするのがいい。エージェントに関しては以前大森望さんのファンジンで「たった一つの冴えたやり方」を個人で版権をとろうとタトル・モリ エージェンシーと交渉した人の話を聞いたことがあります。
蛸井さんがキース・ロバーツ『モリー・ゼロ』を訳したときは、代理人からファンジンの版権を取ったとのことですが、本城さんが今度訳したイアン・ワトスン『地球の鏡の中で イアン・ワトスン奇想短編集』の場合、1年前にワトスンのWEBサイトにあったメールアドレスにダイレクトアタックしたとのこと。そのワトスンは今スペインに住んでいるようです。版権についてワトスンには同人(non-commercial)ではなくスモールプレスとして話をし、5年間で10万ほどで契約できたそうです。
『地球の鏡の中で』(内容紹介はこちら)は、AmazonKDPとカドカワウォーカーでの販売を計画。EPUB変換は「でんでんコンバーター」サイトで楽に出来たが、縦組み・横組みの混在に対応しておらず、HTMLを手編集することで対応した。
ところがKDPはアマゾンのロイヤリティが高いので「ちょ古っ都製本工房」に切り替えた。KDPでは紙も色々選べないがここならできる。KDPだと採算を考えるとどうしても2000円になってしまうところを1000円に抑えられたとのこと。
短編集を編むに当たり、まずワトスンの作品リストを作った。翻訳作品集成のAMEQさんと木下さんはパソコン通信時代にやりとりしていたことがあり、本城さんがそれをもとに追加・補完して作品リストを作成。とりあえず手に入ったものから読んで面白かったものを選ぶ。翻訳にAIはあてに出来ない。短いフレーズではなく長いものを訳例として使い手修正する。電書はOCRの誤植が多かったので紙の原書も参照した。
この次は、白亜紀テーマのビショップとウォルドロップの短編があったので、テーマアンソロジーを作りたいと本城さん。
木下さんからは創作同人誌について。権利関係はノープロブレム。読者にダイレクトに買ってもらえる。でもまあ売れない。2桁売れたら嬉しい。さらに中身を知ってもらわないと届かない。そして在庫が溜まっていく――。
オンデマンド(KDPなど)は楽だが値段も高い。WEBに載せるのは簡単だが競争が強烈。
木下さんの所属する創作サポートセンターは大阪・京都・東京の文学フリマで同人誌とワトスンやノヴァ・クォータリー(岡本が在庫を全部放出した)を売るとのことでした。
次の合宿企画は、「もっと聞きたい!SF入門いまむかし」に。
東京創元社の河内舟月さん、翻訳家の鯨井久志さん、それに大森望さんによる『紙魚の手帖 Vol.24』の座談会「まずはここから!SF入門のための10の名作短編」をネタに語る企画でとても面白かった。
河内さんは96年生まれ。文庫の『虐殺器官』を中2で買った。『年刊SF傑作選』(大森望)を読んでいた。鯨井さんも96年生まれ。星、筒井は小学生から読んでいた。ゲームをやっていたので小中学で「メタルギアソリッド」のノベライズを読み、『ハーモニー』も読んだ。大森望は61年生まれ。小5か6のとき星新一「ぼっこちゃん」を図書館で読んでからずっと50年間SFを読み続けている。高知図書館には銀背(ハヤカワ・SF・シリーズ)が300冊そろっていたがそれは1人の人が寄贈していたものだった。
『紙魚の手帖』のSF入門で、中村融さんと大森さんは同じポジションにいる。大森さんは自分の好きな物というより年代的にある程度バランスをとって10本選んだ。でも若い人はもっと自由に選んでいる。
鯨井さんが海外編で1位に選んだコニー・ウィリス「魂はみずからの社会を選ぶ」は異常論文といってよく、文学部学生向けでとても入門とはいえないのでは、と大森さん。
さらに、フェッセンデンのようなアイデアストーリーはバカバカしさと紙一重。ティプトリーならもっと初期のバカバカしいものがいい。ル・グインの「オメラス」など今読むとどこがSFなのかと言われる。ディストピアものはSFなのかといえば、韓国ではSFだが、日本では(村田沙也加のように)純文となる。
あなたの読んでいるこれは「SF」なんですよ、と言ってあげたい。男女バランスも考える。国によってSFと思われている作家が違う。ヴォネガットはアメリカではSFと思われていない。
日本編に伊藤計劃や円城塔がなぜ入っていないんですかと鯨井さん。大森さんは、現代作家でSF作家と言われているものはあえて外したという。香月さんや大森さんはオールタイムベストの上位に入っているものも外している。同じになってしまうので、新しめなものしか選んでいない。
そこから次に読むものは何かを考えると河内さん。鯨井さんは、入門とは何か。SFを読まない人にどうすれば入門したと言えるのか。そこで今読んで面白いものを選んだ。それが面白ければまたそんなものを読むだろう。
大森さんは、昔のSFも意外に面白い。テーマへの入り口となる。SFをある程度読んでいる人にはこれも読んでみればと連作ものの1つを入れている。そこから読んでみる。
鯨井さんは昔のSFの問題点を指摘。クラークの「太陽系最後の日」は宇宙人も人類と同じ考えなところに引っかかった。ソラリスの呪縛は強い。野尻さんが言うようにコミュニケーションできない話は1つあればそれでいい、と。
柞刈湯葉「人間たちの話」みたいにコミュニケーションについては面白い話がまだ書ける。筒井康隆「関節話法」も結局コミュニケーションしているし。コミュニケーション不能な宇宙人をきちんと書くのは難しいと大森さん。
河内さんが各世代の人に入門として何を読んだか聞きたいといい、部屋にいた人たちが話す。
0年代の学生さんたち。スティーブン・バクスター『プランクゼロ』を父から渡されて読んだ。センスオブワンダーがあって面白かった。神林長平『狐と踊れ』をSFと意識しないで読んだ。また別の人は伊藤計劃の映画評を中2くらいで。そこから円城塔や神林へ。
90年代生まれ。SFとして意識して読んだのは高2で『虐殺器官』『ハーモニー』。隣にあった円城塔を読んだらわからなかった。小学生で筒井・小松を読んだがSFと思っていなかった。これがSFだと気づく瞬間が重要。別の人は、小学生で星などを読んでいたが意識したのはジャック・ヴァンスをアンソロジーで読んだ中3くらい。そこから〈未来の文学〉へ。紹介文が面白い。
叢書やSF全集のようなまとまりが重要、とこれも90年代生まれの鯨井さん。
80年代生まれ。大澤さんが、親の本棚に星さんがあった。祖母のもっていたメリルの『年間傑作選』を読む。図書館でSFを読んでいく。大学の読書会でイーガンを読んですごいと思った。石亀さんは、小学校の児童文学SF。「まんがサイエンス」、『2010年宇宙の旅』を図書館で読んで次にベンフォード。科学への興味とSFへの興味が重なる。ハヤカワ、創元を知らない問題。林さんは、SFを読む、見るというのは今では「どらえもん」など多くの人が知っている。それと自分がSFファンだとわかる瞬間が重要。アイデンティティを知る。
河内さんは「まんがサイエンス」のようなセンスオブワンダーの上澄みを集めたようなものが必要と話す。
入門系のアンソロジーも作ったが、いくつか何これと引っかかて印象に残るものを入れたい。バランスが難しいが、と大森さん。大澤さんは、テーマ別アンソロジーが良いとのこと。
23時前には終了となった。自分が読んでいたものがSFだと知る瞬間が重要というのは確かにと思う。ぼくの場合は手塚治虫の単行本にあった福島正実の解説などだろうか。60年前も今もあまり変わらないのかも知れないと思った。「まんがサイエンス」(あさりよしとう)が科学のワンダーとSFを結びつけたという話も納得。ぼくの時代ではあさのりじ「発明ソン太」あたりがそうだし、もちろん藤子・F・不二雄もそうだろう。とても面白くて刺激になった企画だった。
今年も京大SF研はすばらしかった。頑張るところは頑張り、適当でいいところは適当に無理なく進めて、それでちゃんとやり遂げたのはすばらしい。拍手。
関係者の皆様、今年もすばらしい京フェスをありがとうございました。
※これまでの京都SFフェスティバルレポートは下記インデックスページにまとめてあります。