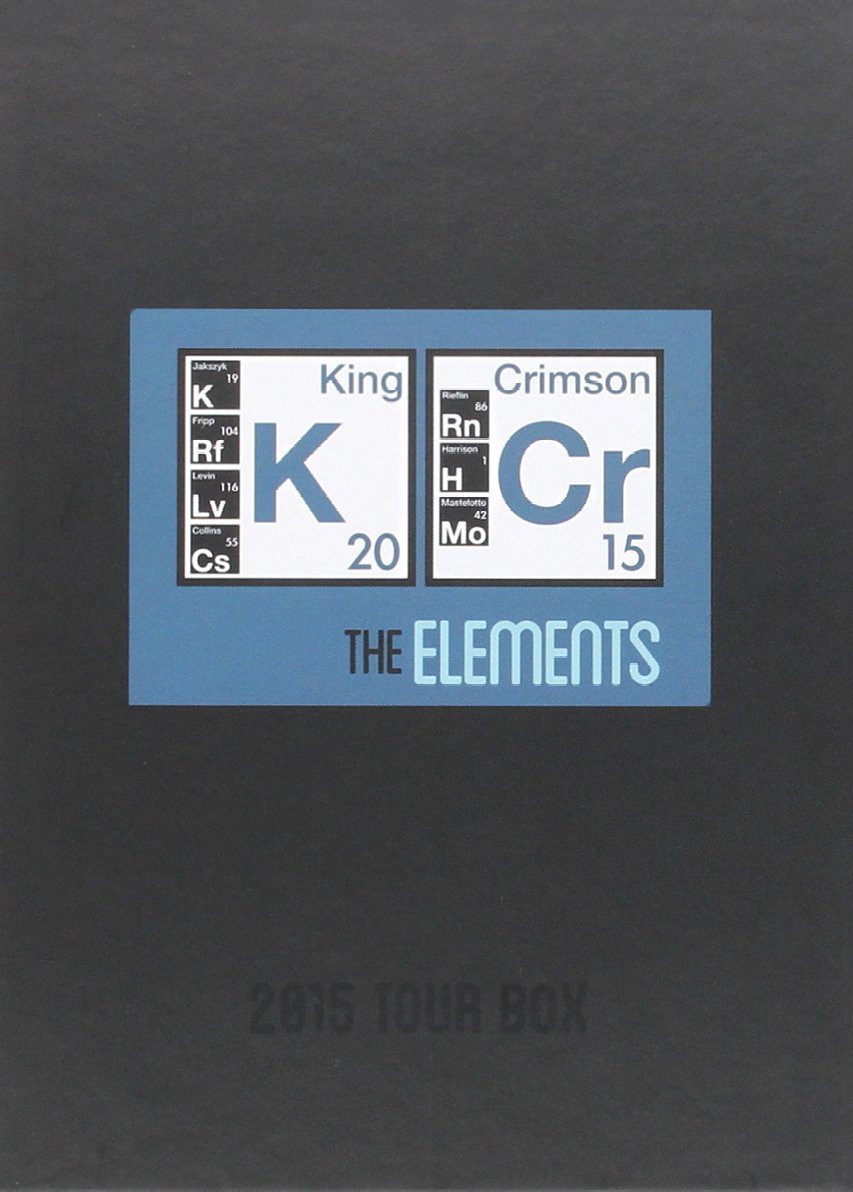3月になって急に暖かい日が続いたけれど、まだ寒の戻りがあるようで、いやだなあ。とはいえ今年の冬はあまり寒くなかったような気がする。
アンディ・ウィアー『火星の人』をリドリー・スコットが映画化した『オデッセイ』を見た。まあ、原作を適当に(特に後半)端折ってて、割とよくできている。サウンドトラックにあのディスコ音楽がそのまま使えて、笑える。デヴィッド・ボウイはやり過ぎだけれど(タイミング良すぎ)。映画になって一番感心したのはラストで軽量化された脱出機の姿。いかに大気が薄く重力が弱いとはいえ、あんなのに乗って救助船の軌道を目指したのか。文章だけだと分からないけれど視覚化されると驚く。
『SFマガジン』の表紙がデヴィッド・ボウイだったのにも驚いた。本屋の雑誌コーナーで最初自分が何を探しているのか分からなかった。丸善ジュンク堂じゃ音楽雑誌のコーナーにも置いてあった。それにしても過去『SFマガジン』がデヴィッド・ボウイにそんなに関心を示していたかなあ。
 BUMP OF CHIKEN『Butterflies』が出たので聴いてみた。BUMPも「天体観測」で引っかかって以来シングルもアルバムもかなり聴いてきたが、ここ数年はシングルを買うのやめていた。YouTubeで見ても引っかかるものがないからだけれど、このアルバムを聴いても最初は2曲目くらいで寝てしまい、気がついたら無音・・・。ほって置いたらいつものオマケ歌が始まった。なかなかゴージャス。ということで2回目に挑戦した。1曲目から7曲目まではまったく魅力を感じなかったが、8曲目「大我慢大会」から耳が集中しだした。9曲目10曲目と初期のBUMPが持っていたリアリティが戻ってきて、終曲「ファイター」で泣いてしまった。この4曲だけで買った価値はあったかな。
BUMP OF CHIKEN『Butterflies』が出たので聴いてみた。BUMPも「天体観測」で引っかかって以来シングルもアルバムもかなり聴いてきたが、ここ数年はシングルを買うのやめていた。YouTubeで見ても引っかかるものがないからだけれど、このアルバムを聴いても最初は2曲目くらいで寝てしまい、気がついたら無音・・・。ほって置いたらいつものオマケ歌が始まった。なかなかゴージャス。ということで2回目に挑戦した。1曲目から7曲目まではまったく魅力を感じなかったが、8曲目「大我慢大会」から耳が集中しだした。9曲目10曲目と初期のBUMPが持っていたリアリティが戻ってきて、終曲「ファイター」で泣いてしまった。この4曲だけで買った価値はあったかな。
 『CDジャーナル』が割と力を入れて紹介していたので、ちょっと気になっていたジャズ系の若手テナー・サック奏者カマシ・ワシントン『The Epic』に手を出したら、なんと3枚組。でも値段は安かった。フライング・ロータスのエッジの効いた作品にエレクトリック・ベースで参加していたサンダー・キャットとその兄のドラマー、ロナルド・ブルーナー・ジュニアも加わったかなりの大所帯バンド(ボーカルにストリングスまで入っている)。
『CDジャーナル』が割と力を入れて紹介していたので、ちょっと気になっていたジャズ系の若手テナー・サック奏者カマシ・ワシントン『The Epic』に手を出したら、なんと3枚組。でも値段は安かった。フライング・ロータスのエッジの効いた作品にエレクトリック・ベースで参加していたサンダー・キャットとその兄のドラマー、ロナルド・ブルーナー・ジュニアも加わったかなりの大所帯バンド(ボーカルにストリングスまで入っている)。
それなりに構えてステレオの前に座っていたら、出てきた音にひっくり返る。なんなんだコレ。ハードバップからフュージョン時代(1950年代半ばから70年代)までのジャズを今に蘇らせたかのような非常に安いフレーズを4ビート・スタイルでゴージャスに鳴らす。だたし、ピアノとオルガン・エレピが同時に鳴るし、エレキベースとウッドベースも同時に鳴って、その後ろで昔風のゴージャスな(安い)ストリングスとバック・コーラスが流れる。ただし、ドラムとパーカッションは現代スタイルだ。
とにかく笑える。3枚のCDのどれを聴いても笑える。女性ヴォーカルが2曲入っているけれど、オリジナルもスタンダードの「チェロキー」もすんごいオーソドックスなビリー・ホリデイ以来のスタイルで歌っている。ドビュッシーの「月の光」までやっているのだけれど、これがまた徹底して安いニューオーリンズ・スタイルのアレンジで笑ってしまう。ここでのカマシ・ワシントンは、ジョン・コルトレーンやファラオ・サンダースを思わせるテナーの音色を多用しているし、トランペットやトロンボーンもハードバップ時代以来のサウンドを踏襲しているように聞こえる。しかし、この若い西海岸のジャズ・ミュージシャンたちは昔のジャズをパロっているわけではないようだ。この演奏に衒いやイヤらしさは全く感じられず、聴いてる方が素直に笑えるような楽しさにあふれている。彼らにとってジャズの遺産がおもしろいと思えるから、このような演奏が出現しているのだろう。ここにはエレクトリック・マイルスや後期コルトレーンやオーネット・コールマンはいないけれど、彼らにやる気があればそれをやれることは間違いない。ま、そんなことに関心はなさそうだが。
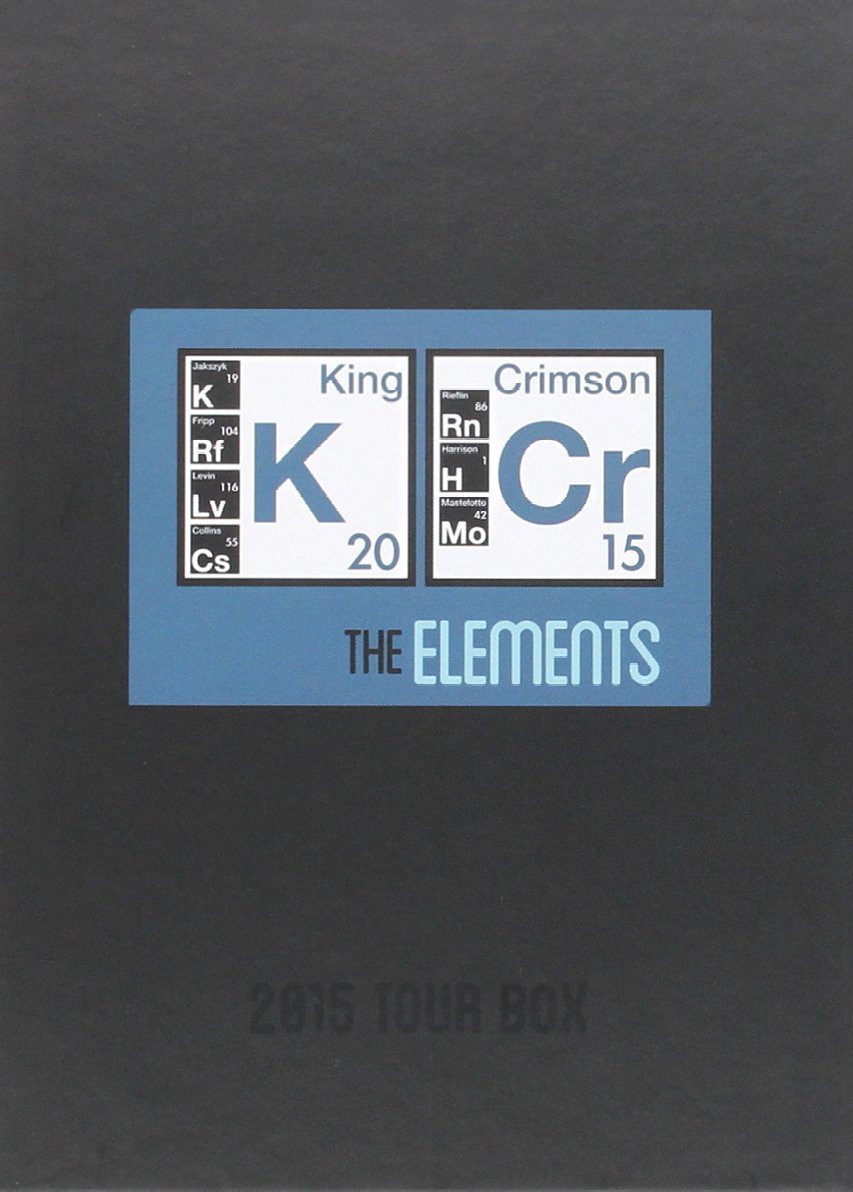 King Crimsonの「THE ELEMENTS TOUR BOX 2015」は、ライヴを聴く前に聴いていたらあまり感銘を受けなかったかもしれないけれど、今聴くと嬉しい1枚。『クリムゾン・キングの宮殿』から80年代ディシプリン時代までがCD1、90年代以降がCD2と一応時代区分されている。しかしCD1でも曲によって最新ミックス・デモだったり2014年の演奏だったり、いろいろ工夫が凝らされている。ライヴを見る前に聴いたときはなんだかよく分からなかった2014年のライヴ音源が、いまでは強いリアリティを持っていて、集中して聴くことができる。
King Crimsonの「THE ELEMENTS TOUR BOX 2015」は、ライヴを聴く前に聴いていたらあまり感銘を受けなかったかもしれないけれど、今聴くと嬉しい1枚。『クリムゾン・キングの宮殿』から80年代ディシプリン時代までがCD1、90年代以降がCD2と一応時代区分されている。しかしCD1でも曲によって最新ミックス・デモだったり2014年の演奏だったり、いろいろ工夫が凝らされている。ライヴを見る前に聴いたときはなんだかよく分からなかった2014年のライヴ音源が、いまでは強いリアリティを持っていて、集中して聴くことができる。
 前回紹介の、かおるさんに借りたLeniniのCDは2015年作の最新盤で、タイトルは『CARBONO(炭/素)』でした。ジャケットが木炭で描いたレニーニの肖像だから。
前回紹介の、かおるさんに借りたLeniniのCDは2015年作の最新盤で、タイトルは『CARBONO(炭/素)』でした。ジャケットが木炭で描いたレニーニの肖像だから。
 70歳を過ぎてともにデビュー50周年のカエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルが、それぞれギター1本持ってデュオ・コンサートを開いた。その時のライヴが出たので注文したらコレを書いている最中に届いたので、早速聴いてみた。いやあ、すばらしいコンサートだったことがよく分かる録音だった。以前も書いたけれど、歌うことに専念したときのカエターノはすごかった。そしてすでに何十年も前に作った自分の歌を歌うことに専念しているこのステージは、たとえ70歳超という年齢からくる声の衰えがあっても、やはりすごいのだ。それに加えてたった2本のギターが刻むサンバのリズムがこれまた効く。カエターノは普通のナイロンギターっぽいが、ジルの方はマイク内蔵のナイロンギターで、それぞれがソロをとるときは自分のギターが主体だが、デュオではリズムを刻むだけで見事なアンサンブルが聞こえてくる。2枚組で、1枚目はカエターノの曲が主体、2枚目がジルの曲主体だけれど、合作やスタンダードな他人の曲も含めて全28曲。聴衆のコーラスを残して終わるエンディングも感動的。タイトルは『Dois Amigos, Um Seculo De Musica』。これからは、ジルベルト・ジルの1000盤も集めてみようか。
70歳を過ぎてともにデビュー50周年のカエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルが、それぞれギター1本持ってデュオ・コンサートを開いた。その時のライヴが出たので注文したらコレを書いている最中に届いたので、早速聴いてみた。いやあ、すばらしいコンサートだったことがよく分かる録音だった。以前も書いたけれど、歌うことに専念したときのカエターノはすごかった。そしてすでに何十年も前に作った自分の歌を歌うことに専念しているこのステージは、たとえ70歳超という年齢からくる声の衰えがあっても、やはりすごいのだ。それに加えてたった2本のギターが刻むサンバのリズムがこれまた効く。カエターノは普通のナイロンギターっぽいが、ジルの方はマイク内蔵のナイロンギターで、それぞれがソロをとるときは自分のギターが主体だが、デュオではリズムを刻むだけで見事なアンサンブルが聞こえてくる。2枚組で、1枚目はカエターノの曲が主体、2枚目がジルの曲主体だけれど、合作やスタンダードな他人の曲も含めて全28曲。聴衆のコーラスを残して終わるエンディングも感動的。タイトルは『Dois Amigos, Um Seculo De Musica』。これからは、ジルベルト・ジルの1000盤も集めてみようか。
 ちくま文庫から突然出た、企画協力日本SF作家クラブという表示で、おそらくちくま文庫編集部が編集したと思われるテーマ・アンソロジー『あしたは戦争 巨匠たちの想像力〔戦時体制〕』は、江戸川乱歩や海野十三の戦前の作品から91年に英訳作品として発表された荒巻義雄の作品まで収録しているけれど、基本は第1世代のSF作家たちの60年代から70年代にかけての作品である。小松「召集令状」や筒井「東海道戦争」、星「ああ祖国よ」などは40年ぶりに読んだけれど、年寄りになった今の方が焦燥感が感じられて、10代の頃読んだのとは感じ方がだいぶ違うようだ。収穫は海野十三「地球要塞」で、ガーンズバックばりのSFとしておもしろく読める。コレに熱中していた少年が戦後SFを書いたのも無理はない。
ちくま文庫から突然出た、企画協力日本SF作家クラブという表示で、おそらくちくま文庫編集部が編集したと思われるテーマ・アンソロジー『あしたは戦争 巨匠たちの想像力〔戦時体制〕』は、江戸川乱歩や海野十三の戦前の作品から91年に英訳作品として発表された荒巻義雄の作品まで収録しているけれど、基本は第1世代のSF作家たちの60年代から70年代にかけての作品である。小松「召集令状」や筒井「東海道戦争」、星「ああ祖国よ」などは40年ぶりに読んだけれど、年寄りになった今の方が焦燥感が感じられて、10代の頃読んだのとは感じ方がだいぶ違うようだ。収穫は海野十三「地球要塞」で、ガーンズバックばりのSFとしておもしろく読める。コレに熱中していた少年が戦後SFを書いたのも無理はない。
 続いて出た同シリーズ(?)の企画協力日本SF作家クラブ『暴走する正義 巨匠たちの想像力〔管理社会〕』も読んでしまった。こちらも小松・筒井・星の御三家を収録。星「処刑」が懐かしくてちょっとうれしかった。あの「銀の玉」の感触だけが長い間残っていたんだなあ。あと山野浩一の「革命狂詩曲」がSFマガジン掲載時に「レボルシオーンNO.5」のタイトルで読んだときのロマンティックなノスタルジーに浸れる。こちらの収穫は水木しげる「こどもの国」と安部公房「闖入者-手記とエピローグ-」かな。
続いて出た同シリーズ(?)の企画協力日本SF作家クラブ『暴走する正義 巨匠たちの想像力〔管理社会〕』も読んでしまった。こちらも小松・筒井・星の御三家を収録。星「処刑」が懐かしくてちょっとうれしかった。あの「銀の玉」の感触だけが長い間残っていたんだなあ。あと山野浩一の「革命狂詩曲」がSFマガジン掲載時に「レボルシオーンNO.5」のタイトルで読んだときのロマンティックなノスタルジーに浸れる。こちらの収穫は水木しげる「こどもの国」と安部公房「闖入者-手記とエピローグ-」かな。
 円城塔に藤井大洋に宮内悠介に森見登美彦が入っているとなれば読んでみようと思うのが当たり前の、小説トリッパー編集部編『20の短編』。20人の作家が400字詰原稿用紙20枚で20をテーマに「小説トリッパー」誌に書き下ろした作品を集めたアンソロジーらしい。上記4人は期待通りの作風で仕上げており、特に宮内が軽いタッチで嬉しかった。しかし、そのほかの作家もそれなりにおもしろくて、冒頭の朝井リョウこそ普通のサラリマン話だったけれど、2つめの阿部和重は紛争地帯でのハードな拷問と絶望的な状況をリアリスティックに書いて見せている。ただこれをシリアスに読んでしまうと、なぜ日本人作家が日本の読者に向けてコレを書いて見せているのか、エンターテインメント長編の1シーンならよく分かるが、などという余計な感想がわいてくる。作家の性別は男10人女(木皿泉を含む)10人だけれど、新潮文庫の100年の名作シリーズでも明らかなようにここでも女性作家の方がパワフルだ。江國香織「蒸籠を買った日」がちょっとした鉄道ファンタジーで、川上弘美「20」は児童もの、桐野夏生「マダガスカル・バナナフランベを20本」は意地の悪い視線でかかれたカップルの別れ(ようと試みる女の)話。どれも強い印象を残す。なかでも津村記久子「ペチュニアフォールを知る二十の名所」が、アメリカを舞台に、観光ガイドの説明からその土地のブラックな歴史を浮かび上がらせて、秀逸なブラック・ユーモア・コメディ短編に仕上っている。
円城塔に藤井大洋に宮内悠介に森見登美彦が入っているとなれば読んでみようと思うのが当たり前の、小説トリッパー編集部編『20の短編』。20人の作家が400字詰原稿用紙20枚で20をテーマに「小説トリッパー」誌に書き下ろした作品を集めたアンソロジーらしい。上記4人は期待通りの作風で仕上げており、特に宮内が軽いタッチで嬉しかった。しかし、そのほかの作家もそれなりにおもしろくて、冒頭の朝井リョウこそ普通のサラリマン話だったけれど、2つめの阿部和重は紛争地帯でのハードな拷問と絶望的な状況をリアリスティックに書いて見せている。ただこれをシリアスに読んでしまうと、なぜ日本人作家が日本の読者に向けてコレを書いて見せているのか、エンターテインメント長編の1シーンならよく分かるが、などという余計な感想がわいてくる。作家の性別は男10人女(木皿泉を含む)10人だけれど、新潮文庫の100年の名作シリーズでも明らかなようにここでも女性作家の方がパワフルだ。江國香織「蒸籠を買った日」がちょっとした鉄道ファンタジーで、川上弘美「20」は児童もの、桐野夏生「マダガスカル・バナナフランベを20本」は意地の悪い視線でかかれたカップルの別れ(ようと試みる女の)話。どれも強い印象を残す。なかでも津村記久子「ペチュニアフォールを知る二十の名所」が、アメリカを舞台に、観光ガイドの説明からその土地のブラックな歴史を浮かび上がらせて、秀逸なブラック・ユーモア・コメディ短編に仕上っている。
 昨年出た作品の読み残しの中から王城夕紀『マレ・サカチのたったひとつの贈物』を読んでみた。坂知稀が量子病という、本人の意志にかかわらず地球上をあちこち跳んでしまう病(作中でもテレポートとどこが違うか議論されている)にかかって、そのジャンプ中の体験の様々な物語に、時々マレが学生時代に受けた(量子論を含む)物理学の講義が挟まるという構成。時代は世界が政治的に崩壊することもあり得るくらい混乱していて、物語の後半で一人の超富豪が進める人類電脳世界移住計画にマレも協力するが、最後の決断は・・・というのがタイトルの由来。基本的には現実世界を生きることには何の意味があるかを問い、その答えを示しているわけだが、人間嫌いを人間好きに変えるのは生半可なことでは難しそうだ、とは思う。もちろん希望としてこの結論はそうあるべきだけれど。なお、表紙絵のマレ・サカチの表情がいかにもそれらしくて作品に似合っている。
昨年出た作品の読み残しの中から王城夕紀『マレ・サカチのたったひとつの贈物』を読んでみた。坂知稀が量子病という、本人の意志にかかわらず地球上をあちこち跳んでしまう病(作中でもテレポートとどこが違うか議論されている)にかかって、そのジャンプ中の体験の様々な物語に、時々マレが学生時代に受けた(量子論を含む)物理学の講義が挟まるという構成。時代は世界が政治的に崩壊することもあり得るくらい混乱していて、物語の後半で一人の超富豪が進める人類電脳世界移住計画にマレも協力するが、最後の決断は・・・というのがタイトルの由来。基本的には現実世界を生きることには何の意味があるかを問い、その答えを示しているわけだが、人間嫌いを人間好きに変えるのは生半可なことでは難しそうだ、とは思う。もちろん希望としてこの結論はそうあるべきだけれど。なお、表紙絵のマレ・サカチの表情がいかにもそれらしくて作品に似合っている。
 個人的にはユーモア系の方が好きな宮内悠介『アメリカ最後の実験』は、長編第2作で音楽演奏を物語の軸にしたちょっとシリアスな作品。連作短編集『ヨハネスブルグの天使たち』のテーマもちょこっと入っているように感じられる。主人公は失踪した天才音楽家の息子で、その才能を受け継いだのか醒めた目で音楽を演奏するタイプだが、母を裏切った父の消息を追って、父が在籍したアメリカの有名音楽学校を受験しようとしている。それとは別にその頃、「アメリカ第一の実験」に端を発する殺人事件が起きている。ということで、最後まで読んでいつものようにずらっと並ぶ参考資料を眺めていると、宮内悠介の問題意識とそれを物語に翻訳する構築力との関係が初期よりも窮屈になってきているじゃなかろうかとの思いがだんだん強くなってきた。読んでいて退屈しないはもちろんだし、最後まで読めばそれなりの結末にたどり着くわけで、それで十分なのだけれど、何かしっくりこないんだよねえ。
個人的にはユーモア系の方が好きな宮内悠介『アメリカ最後の実験』は、長編第2作で音楽演奏を物語の軸にしたちょっとシリアスな作品。連作短編集『ヨハネスブルグの天使たち』のテーマもちょこっと入っているように感じられる。主人公は失踪した天才音楽家の息子で、その才能を受け継いだのか醒めた目で音楽を演奏するタイプだが、母を裏切った父の消息を追って、父が在籍したアメリカの有名音楽学校を受験しようとしている。それとは別にその頃、「アメリカ第一の実験」に端を発する殺人事件が起きている。ということで、最後まで読んでいつものようにずらっと並ぶ参考資料を眺めていると、宮内悠介の問題意識とそれを物語に翻訳する構築力との関係が初期よりも窮屈になってきているじゃなかろうかとの思いがだんだん強くなってきた。読んでいて退屈しないはもちろんだし、最後まで読めばそれなりの結末にたどり着くわけで、それで十分なのだけれど、何かしっくりこないんだよねえ。
 翻訳の方は新作は読まずに新訳ばかり。まあ、そういう季節だよね。クリフォード・D・シマック『中継ステーション』は山田順子新訳。高校生か浪人時代に銀背のSFシリーズで読んだと記憶しているが、もはや偽造記憶かも。40年以上前に読んだときは、1964年のヒューゴー賞受賞作なんだからまだ発表されてから10年もたっていなかったんだが、その時でさえちょっと古い感じがしたことは覚えている。実際は田舎が舞台の話なので、それを古くささと思ったのかもしれない。今読むと当時のアメリカに漂っていた最終戦争への懸念が色濃く漂い、シマックの故郷であるウィスコンシンの田舎風景の描写は失われる可能性のあるフレイルなものとして置かれている。中継ステーションと星々を結ぶ宇宙人転送網に、もはやSF的なおもしろさはないけれど、主人公の孤独感は印象的だ。作品構成としては、冒頭の情報部員と科学者との会話で示される謎の設定と物語のメインストーリーとの絡みがあまりスムーズではなく、エンターテインメント小説としての完成度はいまひとつ。
翻訳の方は新作は読まずに新訳ばかり。まあ、そういう季節だよね。クリフォード・D・シマック『中継ステーション』は山田順子新訳。高校生か浪人時代に銀背のSFシリーズで読んだと記憶しているが、もはや偽造記憶かも。40年以上前に読んだときは、1964年のヒューゴー賞受賞作なんだからまだ発表されてから10年もたっていなかったんだが、その時でさえちょっと古い感じがしたことは覚えている。実際は田舎が舞台の話なので、それを古くささと思ったのかもしれない。今読むと当時のアメリカに漂っていた最終戦争への懸念が色濃く漂い、シマックの故郷であるウィスコンシンの田舎風景の描写は失われる可能性のあるフレイルなものとして置かれている。中継ステーションと星々を結ぶ宇宙人転送網に、もはやSF的なおもしろさはないけれど、主人公の孤独感は印象的だ。作品構成としては、冒頭の情報部員と科学者との会話で示される謎の設定と物語のメインストーリーとの絡みがあまりスムーズではなく、エンターテインメント小説としての完成度はいまひとつ。
一方、同じ1964年のヒューゴー賞候補に雑誌連載版が対象となって翌年単行本版で受賞したフランク・ハーバート『デューン 砂の惑星』は、酒井昭伸新訳ということもあり、かなりの訳語変更があって、わが記憶にあるあの『砂の惑星』とは別物のような感じがする。まあ矢野さんの訳が白黒ワイドスクリーン版だとしたら、酒井訳は4Kデジタルハイビジョン立体映像版というところだろう。
こちらも40年ぶりに読んだわけだけれど、新訳のせいも手伝ってか、ハーバートの作り出した大パノラマ大舞台劇には舌を巻くばかりである。先日、もとSFファンの業者に新訳版を読んだ話をしたらすぐ「クイサッツ・ハデラッハ!」と反応が返ってきたその「クイサッツ・ハデラッハ」も「ムアドディブ」もわが愛しの「エイリア」ちゃんもいなくなってしまって寂しいが、作品の方の迫力は読み手を圧倒する。よくもまあこれだけのからくりをほぼ破綻無く読者に読ませるだけの力がハーバートにあったことよ。改めて読むとハーバートは、物語の大半を各人物の独白や台詞に費やしていた。それでも記憶に残る大スペクタクルはちゃんとあるのだ。
これが出版から50年経ってもアメリカのSFファンにとってずっと最高のアメリカSFであり続けている理由は、今回再読してよく分かった。水鏡子も解説しているようにハーバートがこれだけバランスよく大作を書き切れているのは珍しい。少なくともジャンプ・ドア・シリーズやこのコラムの表題となっている『サンタロガ・バリア』を読む限り、『デューン 砂の惑星』はハーバートの作品中でも異色なものだと思える。
今回読み返してみて、「スター・ウォーズ」も「ナウシカ」もこの作品にヒントを得ていることは間違いないと思った。現代SFは『デューン 砂の惑星』と『ソラリス』の間で“黄金の道”を歩んでいるのかも。
 八世界全短編集の2巻目、ジョン・ヴァーリイ『さようなら、ロビンソン・クルーソー』は、発表年代が後期の作品を収録したというだけあって、青春物語っぽいさわやかさが特徴だった1巻目よりもシビアなテーマが据えられて、書き方もそれに合ったものが多い。表題作や最後の「ビートニク・バイユー」はそれでもまだ青春(以前?)物語の形をとっているけれど、喪失感が強く、さすがに甘酸っぱさという感覚はなくなってきている。冒頭の「びっくりハウス効果」は内容をすっかり忘れていたこともあって、まさにびっくりハウス効果だった。
八世界全短編集の2巻目、ジョン・ヴァーリイ『さようなら、ロビンソン・クルーソー』は、発表年代が後期の作品を収録したというだけあって、青春物語っぽいさわやかさが特徴だった1巻目よりもシビアなテーマが据えられて、書き方もそれに合ったものが多い。表題作や最後の「ビートニク・バイユー」はそれでもまだ青春(以前?)物語の形をとっているけれど、喪失感が強く、さすがに甘酸っぱさという感覚はなくなってきている。冒頭の「びっくりハウス効果」は内容をすっかり忘れていたこともあって、まさにびっくりハウス効果だった。
 ノンフィクションは、まず佐伯泰英『惜櫟(せきれき)荘だより』がちょっとびっくりする内容だった。これも坪内祐三が『週刊文春』で、そのびっくりする所以を紹介していたから読んだ1冊。
ノンフィクションは、まず佐伯泰英『惜櫟(せきれき)荘だより』がちょっとびっくりする内容だった。これも坪内祐三が『週刊文春』で、そのびっくりする所以を紹介していたから読んだ1冊。
佐伯泰英といえば書き下ろし文庫時代劇小説のベストセラー作家。当然1冊も読んだことはない(テレビドラマは見たことがある)。そんな作家に興味の湧くはずもないが、坪内の紹介で、「惜櫟荘」が岩波茂雄が熱海に建てた建築家吉田五十八の手になる近代数寄屋の別邸であり、それを紆余曲折の結果佐伯泰英が買い取って、なおかつ自費でレストアしてしまう(だから「岩波現代文庫」)話の間に、なんとスペインで永川玲二(丸谷才一と一緒にジョイスの『ユリシーズ』を訳した人)と付き合ったり、堀田善衛夫妻の付き人をやったりという、相当風変わりな経歴が綴られていることを知り、読んでみた。
作家としては岩波と縁もゆかりもない佐伯泰英は、作家になる前はスペインに在住して闘牛写真を撮る写真家だった。その時大学助教授を辞してスペインにいた永川玲二と知って付き合い、その変人(ボヘミアン)ぶりを描写している。また写真家だけでは食えないので、やはりスペインで知り合った堀田善衛家の付き人(運転手)をやっている。その間に永川玲二を堀田家に案内して飯を食わせたら、永川のマナーの下品さに辟易した堀田夫妻からひどく叱られたというエピソードを披露している。そしてスペインに在住したまま亡くなった(ハイパー)リアリズム画家磯江毅(いそえつよし)まで出てきたのには驚いた。磯江は数年前に広島でも回顧展があり、それを見に行ってかなり強い印象が残っている。
メインは、佐伯泰英がどうして「惜櫟荘」を買うことになったか、そして自費で文化財修復を行うことを決心してその修復の経過報告するものなのだが、どうしてもスペイン体験に興味がいってしまうのである。佐伯泰英のスペイン経験は70年代ということもあって、かなり神話的な雰囲気が漂う。
 もう1冊は文京洙『新・韓国現代史』(岩波新書)。まあ、日清・日露戦争および朝鮮戦争の関係資料で前にもいくつか朝鮮半島の近代史の断片を読んだこともあり、新聞の読書欄で小さく取り上げられていたのを目にして、その後の韓国(北のことは書けないだろう)も知っておこうと読んでみた。
もう1冊は文京洙『新・韓国現代史』(岩波新書)。まあ、日清・日露戦争および朝鮮戦争の関係資料で前にもいくつか朝鮮半島の近代史の断片を読んだこともあり、新聞の読書欄で小さく取り上げられていたのを目にして、その後の韓国(北のことは書けないだろう)も知っておこうと読んでみた。
これは日本敗戦後から今日の朴政権までの現代史を、政治史を中心にコンパクトにまとめた1冊。戦後の韓国といえば軍政のイメージが強い。全斗煥時代まではまさに軍政だったけれど、韓国はその軍政期に高度成長を成し遂げている。60年代の高度成長は日本だけでなく韓国にもあったらしい。軍政は1988年に盧泰愚が大統領になるまで続いていたんだから、韓国の戦後史は日本のそれ以上にジェットコースター的なめまぐるしさである。その後盧武鉉政権までは革新系が取ったけれど、李明博・朴槿恵で保守系に戻ってしまった。作者は民主主義的革新派に同情的で、保守政権には厳しいが、それでも急変しやすい韓国の状況に希望は持っているようだ。
先月積み残した3冊は、鍛代敏雄『戦国大名の正体 家中粛正と権威志向』(中公新書)、落合弘樹『秩禄処分 明治維新と武家の解体』(講談社学術文庫)、渡辺尚志『百姓の力 江戸時代から見える日本』(角川ソフィア文庫)だった。
もはや書く気力がなくなったので、『百姓の力』がこれまで読んだ中では一番バランスよくコンパクトに江戸時代の百姓身分の実態を現在の研究水準に合わせて紹介しているので良かったということだけにしよう。
THATTA 334号へ戻る
トップページへ戻る
 BUMP OF CHIKEN『Butterflies』が出たので聴いてみた。BUMPも「天体観測」で引っかかって以来シングルもアルバムもかなり聴いてきたが、ここ数年はシングルを買うのやめていた。YouTubeで見ても引っかかるものがないからだけれど、このアルバムを聴いても最初は2曲目くらいで寝てしまい、気がついたら無音・・・。ほって置いたらいつものオマケ歌が始まった。なかなかゴージャス。ということで2回目に挑戦した。1曲目から7曲目まではまったく魅力を感じなかったが、8曲目「大我慢大会」から耳が集中しだした。9曲目10曲目と初期のBUMPが持っていたリアリティが戻ってきて、終曲「ファイター」で泣いてしまった。この4曲だけで買った価値はあったかな。
BUMP OF CHIKEN『Butterflies』が出たので聴いてみた。BUMPも「天体観測」で引っかかって以来シングルもアルバムもかなり聴いてきたが、ここ数年はシングルを買うのやめていた。YouTubeで見ても引っかかるものがないからだけれど、このアルバムを聴いても最初は2曲目くらいで寝てしまい、気がついたら無音・・・。ほって置いたらいつものオマケ歌が始まった。なかなかゴージャス。ということで2回目に挑戦した。1曲目から7曲目まではまったく魅力を感じなかったが、8曲目「大我慢大会」から耳が集中しだした。9曲目10曲目と初期のBUMPが持っていたリアリティが戻ってきて、終曲「ファイター」で泣いてしまった。この4曲だけで買った価値はあったかな。