 みだれめも
第214回
みだれめも
第214回
 みだれめも
第214回
みだれめも
第214回
水鏡子
 |
 |
 |
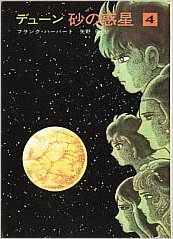 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
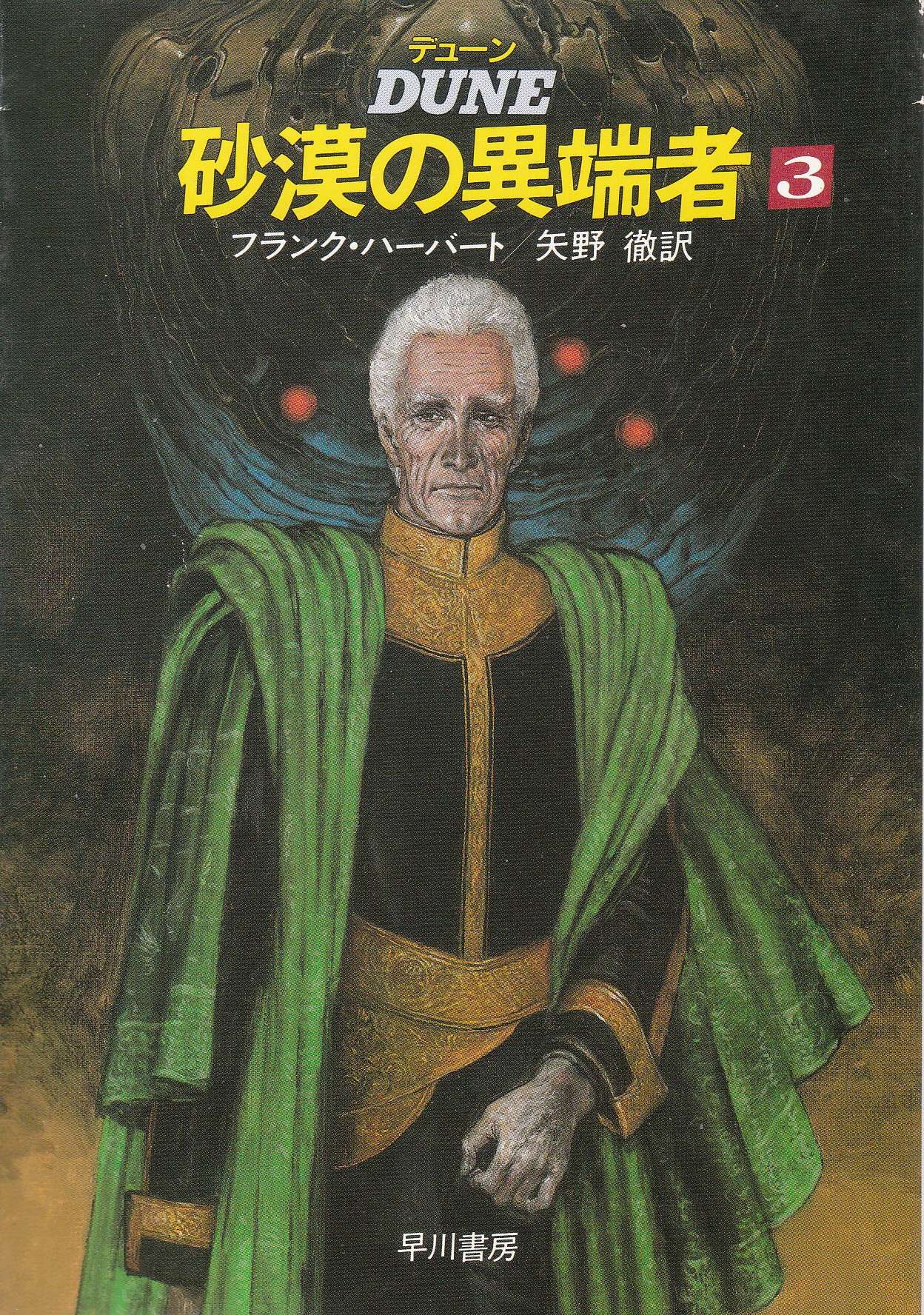 |
 |
 |
 |
ひさしぶりに〈デューン〉を読み返す機会を得た。SFマガジン2月号の「ハヤカワ文庫SF総解説」である。
『砂漠の異端者・解説』、『SFハンドブック』、『公家アトレイデ・解説』そして今回の「総解説」と10枚前後の文章をこれで4回書いたことになる。ほかにも『砂丘の大聖堂』のブックレビューとかもやっているし、〈デューン〉とのおつきあいは意外と多い。そもそもSFオールタイムベストの1位には昔からずっと『鞭打たれる星』をあげているのである。
読み返しながら、気がついたこと、改めて再確認したことがいくつかある。
○まず、贔屓の作家であるのだけれど、この作家を英米SFの流れの中で位置づけようとしたことがじつは一度もないことに気がついた。これはぼくにしては珍しい。ラファティやコードウェイナー・スミスのような作家であっても総体としての英米ジャンルSFとの関わりを常に意識してきた人間としてなんでだろうと考えこんだ。現代SFは〈デューン〉から始まったとか、生態学SFの世界を切り開いたとか、そんな文章はいっぱい見るのだけれど、なんかそういう文章には、英米SF史のなかでフランク・ハーバートをどう位置づけるかがあまり見えない。最初に思い浮かんだのはハーバートがSFの保守本道を歩いている作家でありすぎて、言及する意味がないと考えたりしたせいと思ったが、いやいやそんなことはない。アシモフとかアンダースンとか自分なりにいろいろ位置づけして遊んだ王道作家はごろごろいる。
そう思っていくつかの本を読み返してみると、ジョン・クルート編集の『SF大百科事典』では、「かれの作品には、他の大半のアメリカ作家と違った雰囲気がある」と書いている。ピーター・ニコルズ編集の『SFエンサイクロペディア』(1979『砂丘の子供たち』までの刊行時点)は「彼の長篇群は現代SFでも比肩しうるものの少ない思弁的知性の産物である」と持ち上げると同時に「その作品を、批評・分析の対象にした例は驚くほど少ない」と締め括る。『砂の惑星』刊行から15年を経ているのに。やっぱりSF界と少し距離があったのかなとか思いながら『一兆年の宴』を見ると後期〈デューン〉」を絶賛したうえ、SF界への多大な影響について記述しているブライアン・オールディスがいる。
「〈デューン〉は疑いもなく大叙事詩である。この連作は、独特の手法でそれまでのモデルが失敗したことをなしとげた。現在の物語を未来へ移しかえただけのものではない。権力幻想をはるかに超えたものである。〈レンズマン〉の宇宙や〈ファウンデーション〉の宇宙とちがい、奥行きがある。これらの初期のモデルとちがって、未来には現代と異なる行動様式があり、現代と異なる動機づけがあることを把握している。一見中世風の設定にもかかわらず、徹頭徹尾未来を志向した小説なのである。」
そして、「この連作の存在は、若い作家たちに影響を与え、彼らを鼓舞して、より複雑な構成に向かわせた」としてその代表にブルース・スターリングとグレッグ・ベアをあげる。言われると『スキズマトリックス』には通底するものがある気がしてくるが、ベアというのはわからない。あと少なくともブライアン・ハーバートとケヴィン・アンダースンには継承されてる気がしない。
それにしても『スキズマトリックス』というのは盲点だった。SFは内容面ではなくリテラシイ・レベルにおいて、30年代から80年代くらいまで明らかに<進歩>を重ねてきた。時代時代に作られたコンポジションがある。80年代以降にも進歩が続いているのかどうかは実感としてつかめない。進歩しなくなったのか、ぼくのほうがその時点で止まってしまったのかどっちだかわからない。ただ21世紀に入ってからの読み応えのある力作は、押し並べて複雑な文法結構を備えているように思えるので、また1ランクレベルアップしている可能性がある。単純にこちらの読解力が劣化しているだけかもしれないが。
40年代文法で構築された『非A』が、60年代文法で『デューン』にグレイドアップされ、80年代文法にブラッシュアップされて『スキズマトリックス』を生み出したという発展図式はどうだろう。作風面は別にして。
と、昔ながらの持論を持ちだしてきて気がついた。代表的SF作家に数えられ、かなりの作家に影響を与えながらあんまりSFエスタブリッシュメントの形成に組み込まなかった作家がもうひとりいる。いわずとしれたA・E・ヴァン・ヴォークトである。
○『デューン』の組み立ては『砂の惑星』、『砂漠の救世主』、『砂丘の子供たち』でひとつの結実をみ、『砂漠の神皇帝』という緑のアラキスの物語が屹立し、再び砂漠の星に戻って『砂漠の異端者』、『砂丘の大聖堂』そして書かれなかった『デューン7』となるというのが常識的な見方である。かなめに位置する『神皇帝』を挟んで初期3部作と後期3部作が対になるわけである。『子供たち』と『神皇帝』の間で3500年の歳月が流れるし、『神皇帝』と『異端者』も1500年をはさむ。妥当な分け方だと思う。おまけに日本版では『子供たち』までが石森章太郎の表紙と挿絵で『神皇帝』から加藤直之と交代する。題名的にも『レンズの子ら』で大団円を迎える某著名スペース・オペラもある。そう読むのがむしろ普通だろう。
ところがオールディスの捉え方は違うのだ。彼は『砂の惑星』と『救世主』をポウルの覚醒と終末を描いた前後篇の物語、『子供たち』と『神皇帝』をレト3世の前後篇の物語、『異端者』と『大聖堂』をマイルズ・テグの前後篇の物語とする。
うーん。
言われてみると、なるほどと思うところもある。発表年も『救世主』と『子供たち』の間は7年空いているけど、『子供たち』と『神皇帝』の間は5年しか空いていない。
しかし、その先入観から『異端者』と『大聖堂』を他の2つと同じ意味での前後篇とみなして結末に不満をこぼしているのは、オールディスにはあるまじき読み間違いといえる。なぜならこの二つは明らかに、話が1冊で終わらず分かれただけのものだから。その証拠にこの2冊だけが発表年がつながっている。『異端者』、『大聖堂』が前篇、『デューン7』を後篇と考えるのがおそらく正しい。
○SFMでも書いたように、ローカスのオールタイム・ベストはこの半世紀ずっと『デューン』が首位を占め続けている。ただこの『デューン』がシリーズ〈デューン〉を指しているのか『砂の惑星』を指しているのか判然としない。正直、シリーズ中でいちばん平板な『砂の惑星』のことのような気がするところが気に食わない。このシリーズは、あとにいくほど進化していくというのが、オールディスやジーン・ヴァン・トロイヤーの、そしてぼくの意見であるのだが、どうもそういう人間は少数派のようである。たとえば『SF大百科事典』では、「『救世主』、『神皇帝』といった、多数のデューンのあれこれは、第1作ほどの傑作とはいえず、いくつかは刺激も趣もないただの討論会と化している」とさんざんである。この評言には、まず〈デューン〉をひとつの大河小説として捉える視点が欠けており、同じ惑星を舞台に、違う登場人物、異なる時代で展開されるそれぞれの物語としてしか読んでいないきらいがある。例えれば〈パーンの竜騎士〉のように。ちなみに、「『救世主』、『神皇帝』といった、多数のデューンのあれこれは、」といった言い回しは、紹介することを割り振られた作品について、じつは読んでなかったりしたときに使う常套手段であったりする。
ただし、この担当者はハーバートに対してむしろ畏敬の念を抱いている。
「人間も、ハーバートの作品も、たゆまぬ努力を続けている。あるめんでは導師として、あるめんではコールリッジの老水夫として、フランク・ハーバートは我々にSFによって思考する術を教えているのである。」というシメの文章は、この〈デューン〉に対する評価の低さをよく補っている。
僕の水先案内人ジュディス・メリルの『SFに何ができるか』は、歯に衣を着せぬという意味では一番に手厳しい。「これは部分的にはすぐれたところもあるけれども、まったくありきたりの未来歴史小説で、独創的あるいは思弁的な内容というよりも、複雑な構成が見どころの大作である。ほかの作家に刺激や影響を与えるものは、皆無といっていい」
とまあ、けちょんけちょんであるけれど『砂の惑星』の評価としてはわからなくもない。この本の段階ではまだ『救世主』にも言及されていないことだし。あと発売直後の書評(『砂の惑星』訳者あとがき)では絶賛しているのだけれど、みんながあんまり誉めるのでへそを曲げたようでもある。
 メリルの時代は忌憚なく批判もできた〈デューン〉だが、さすがに半世紀不動の首位という実績を積み重ねるとさすがに面と向かって否定するのは腰が引けるようであり、マイク・アシュリー『SF雑誌の歴史 ②』などは一見否定していることがわからない。
メリルの時代は忌憚なく批判もできた〈デューン〉だが、さすがに半世紀不動の首位という実績を積み重ねるとさすがに面と向かって否定するのは腰が引けるようであり、マイク・アシュリー『SF雑誌の歴史 ②』などは一見否定していることがわからない。
「「デューン・ワールド」は、やがて予期せぬ大ヒットとなる。その価値が知れ渡るまでは時間が必要だった。四十年後の今日でさえ、この作品をSFの最高作にあげる読者と、ほとんど興味を示さない読者とに二極化されている。」
この文章に前後して、「デューン第1部」雑誌掲載時のロイ・タケットの批判的投稿や、60年代の「多くの作家によって、超能力や疑似魔法が作品に取り入れられ、誌面に横溢するようになる」、著者が若干の憂いを込めて「SFの幻想小説化」と呼ぶトレンドの先駆けとしての指摘など、なんとなく著者が「ほとんど興味を示さない読者」であることを示唆しているように見える。そもそも、わざわざ「ほとんど興味を示さない読者」との2極化を強調すること自体、奇異な指摘であるわけで。
それにしても、この本はめちゃくちゃ面白い。50年代60年代というぼくらが実体験的に読んできた時代について、雑誌や本の目録目次と作品内容から積み重ねてきた世界像が、作家、編集者、出版社、取次間の軋轢競合、原稿料、売上高などの商業データの数々で、どんどん上書きされていく。『SF雑誌の歴史 ①』だって同じことをしてたのだけど、あちらはもともと基礎的知識が少ない。そうなんですか、お勉強させていただきますの世界だったのだけど、こっちはもろに積み上げてきた基礎教養に変更を強いてくる。とくに衝撃的だったのは、ハリスン、マルツバーグ、テッド・ホワイトの編集時代のアメージング、ファンタスティックが売上高が激減した同誌最大の混迷期だったというくだり。この時期のアメージングといえば、SFスキャナーで二流雑誌から脱却し新生を果たしつつあるもっとも目覚ましい雑誌として絶賛されていて、英語を読めないこのぼくが、何冊も買い込んで目次を楽しんでいたものなのだ。じっさいぱらぱら見直しても、ノスタルジアの霞はかかっているとはいえ、やっぱりいい目次だと思う。ハリスンが処女作だと主張するジェームズ・ティプトリー・ジュニアの「断層」の載ったファンタスティックもちゃんと持っている。
幸いなことに作品評価の部分とかにはそれなりに首をかしげるものも多くて、おかげで是々非々のポジションをとらせてもらえているのだけれど、若い読者はこれが当時の英米SFについての基本テキストになっていくんだろうなあ。
そういえば、こんな文章がある。
「〈宇宙都市〉は〈レンズマン〉や〈武器店〉からの自然な発展であり、これがさらに未来の作品、もっとも有名なのはフランク・ハーバート〈デューン〉シリーズへとつながっていく」
〈宇宙都市〉、〈レンズマン〉、〈武器店〉、〈デューン〉、全部好きな作品だけど、この繋ぎ方はさっぱりわからない。
○マガジンでも少し書いたように、アラキスの生態学的設定を絶賛する人たちが、ほぼ一様にベネ・ゲセリットの優生学的神秘主義には一様に口を噤んでいる気がする。ここにはもしかすると、アスタウンディングを席巻したサイオニクスやダイアネティクス騒動への忌避感が働いているのではないかという気もするし、血によって過去の先祖と意識を共有できるとするたわごとは非科学性のきわみではある。(そういえば、ヴァン・ヴォークトもたしかこのダイアネティクス渦中に巻き込まれたはずである。)
以前にも紹介したことがあるのだが、『SF大百科事典』には「シャスタは、ハーバートのダイアネティクスに関する最初の本を没にした」という誤植があって、けっこう楽しんだのだけど、第1部がアスタウンディングに発表された『砂の惑星』には、あるいはやっぱりそんな風潮の余波もあったのかもしれないと思ったりする。もっともこのひとのユマニズムには宗教に傾く気配は毛ほども見いだせない。(その意味ではヴァン・ヴォークトも同じ気がする)
生態学的世界設定と優生学的神秘主義というのはハーバートの意識のなかでは同じ根から生まれたひと固まりではないのかと思う。それは学者的な体系的思考ではなく、雑学系新聞記者上がりのフィールドワーカーが多種多様な知識、そのなかにはダイアネティクスをも含むSFへの造詣も含まれて、非科学的な発想も自由に盛り込んでしまう博物学的思考によって生み出されたものではないか。
同様に生態学的世界観を反映させた作品を書くル・グインや、アンダースンやクレメントの世界が機械的力学的ダイナミズムを付与されているのと逆に、ハーバートの作品は生理的動物的ダイナミズムが付与されているのでは。世界観の根本が、システム的なものか、個々の動物性の積み上げにあるのでないか、という分け方ができないか。そしてそんな作家がもうひとり。博物学系動物学者シートンの影響を強く受けたA・E・ヴァン・ヴォークトである。考えてみるとスターリングにもそんな面がなくもない。なんとなく、ぼくのきらいなニュー・サイエンスとかと重なる部分がありそうで少しいやなのだけど。ほかに非システム的生物ヴィジョンが特徴的な作家というとだれだろう。ヴァーリイとかティプトリーとかそういう側面はないだろうか。
機械的力学的ダイナミズムに支配されたSFの系譜と生理的動物的ダイナミズムSFの2項対立というのはちょっとおもしろいかもしれない。
 ○「官能性と暴力性と破天荒」というのはぼくのハーバート理解のキイ・イメージでそれが彼とヴァン・ヴォークトをきっちり結びつけているのだが、その発端となったのが『鞭打たれる星』である。
○「官能性と暴力性と破天荒」というのはぼくのハーバート理解のキイ・イメージでそれが彼とヴァン・ヴォークトをきっちり結びつけているのだが、その発端となったのが『鞭打たれる星』である。
ネタばれするよ。
人類がジャンプドアと呼ばれるシステムによって銀河一円に広がった時代。サディスティックな性癖を持つ大富豪(女性)が鞭打ちのお相手(!)としてカレバンと呼ばれる謎の存在と契約を結ぶ。彼らの行為は最終的にカレバンの死につながる可能性が高い。連絡を受けたサヴォタージュ局(システムが円滑に働くことで世界が非人間化しないよう、物事の円滑化を妨げる政府機関!)局員ジョージ・X・マッキーは調査を開始するなかで、衝撃的な事実に辿りつく。ファニー・メイという名のカレバンの正体はじつは一個の恒星(!)であり、彼女の死はジャンプドアにコネクトしたことのある全ての人間の死と結びついていたのだ!
何十年か読み返していないので記憶違いがあるかもしれない。個人的変態行為が銀河文明崩壊につながるのが凄いし、サヴォ局という発想がすばらしい。こんな話がハードボイルド探偵ものの筆法で、しかし尋ね歩く関係者が、文化規範が異なってまともな会話が成り立たないいろんな異星人たちという、まああまり類を見ない傑作である。怪作と呼ぶ人の方が多いかもしれない。
こんな話を書く人はやっぱりへんだろう。位置づけをしてこなかったと言ったけど、いま思いついたのはこのてのへんさは60年代イフ、ギャラクシーのキャピキャピ宇宙小説やジャック・ヴァンスやコードウェイナー・スミスとも通底している気もする。さらにこの恒星生命のイメージは、神皇帝にもつながるのかな。そしてもちろん、ヴァン・ヴォークトにも。
デユーンを『非A』のグレイドアップ・ヴァージョンとし、ダンカン・アイダホをギルバート・ゴッセンに重ね合わせているのだけれど、あるいは「神皇帝」は『非A』の「機械」にあたるかもしれない。
○酒井さんの新訳で『デューン』が再刊されると聞いて喜んでいる。矢野さんの訳も頑張っていたのだけれど、なにより情報取材能力が限られていた時代にイスラム文化をベースにして書きあげられた大冊を訳すことは大変な努力を要したことは想像に難くない。今回読み返してみて、「ラマダン」などという単語がなんの注釈もなく出てきたのに少しびっくりした。『砂の惑星①』の訳者解説には、「ラハエル・ヤールソンの『沈黙の春』」といった文章があり、翻訳が数年前に出ていたにもかかわらず、この表記が訳者編集校正を通ってしまうくらい取材はたいへんな時代だったのだ。(その後、この表記はレイチェル・カーソンに改められている)
さらに、「プロットの中のプロットの中のプロット」などというハーバートの好んで使うタームはかれの小説作法にも適用されていて、ときには次の本にならないと詳細があきらかにならない謎や伏線もことかかない。リアルタイムに訳出していくことは相当な難行だったと思われる。
今回の新訳はどこまで行われるのか。できることなら、『異端者』『大聖堂』さらには、例の、息子たちの手による『デューン7』まで訳していただければ助かるのだが。
いや、訳さないであらすじを『大聖堂』のあとがきで詳しく書いてもらったほうがもっといい。