|
続・サンタロガ・バリア (第146回) |
ほとんど雨と曇りの8月だったけれど、暑いことには変わりなく、エアコンのない部屋で窓を閉め切ってCDを聴くのも大変で、もっぱらYouTubeのお世話になっていた。
さすがにギター姫やベース姫にも飽きて(というか「彼女」らも歳をとって新作がない)、ボーカロイドやダンスロイドも新鮮さは失せたし(最初の衝撃の映像は今でも新鮮だと思うけれど)。では何を見ているかというと、昔のジャズやロックとやはり昔の(日本での)洋楽ヒットチャートもの。クラシックもいっぱいあるけれどパソコン画面とオモチャみたいなスピーカーでは聴く気がしない。
ジャズはビリー・ホリディをいくつか見ていたら、チャーリー・パーカーの元気そうな映像を見つけてビックリ。マイルスはいっぱいあって、特に復活後亡くなるまでの10年間の映像はいくらでも見られる。あとMt.FUJI.JAZZ FESTIVALの映像が何年分かあって、ドン・プーレン/ジョージ・アダムズ・カルテットの演奏シーンにちょっと感動してしまった。
ロックもほとんど何でもありで、ピート・ブラウン率いるピブロクトーの演奏風景とか見つけてヘェーって感じ。プログレ系ロックに入れ込んでいた71年当時、日本ではピブロクトーの名前はすでに伝説的だったけれど、イギリスでは当然フツーに活動していたロックバンドの一つで、その後はクリームの前身バンドの片方だったにすぎないわけだ。
洋楽ヒットチャートものでは、少し前にマリスカ・ヴェレスが亡くなったショッキング・ブルーを片っ端から見ていた。あの印象的なイントロが実はアメリカのカントリーソングの前奏からとられていたらしいなどという映像があったりして、こちらもヘェーっだったが、今探すと見つからないなあ。
9月はパク・キュヒの新作CDが出るらしいので、たのしみ。
7月に読んだのに前回感想を書き忘れたフィリップK・ディック/レイ・ネルスン『ガニメデ支配』は、いかにもディックな考え方があふれているガラクタSF。60年代にディックの書いた傑作長編は多いが、ガラクタSFも多い。これは牧眞司の解説で引用されているようにディック自ら「ジョーク」と呼ぶ出来具合だが、主要キャラクターの思考はイモムシ体型のガニメデ人も含めてディック・タイプとしか云いようがないし、ガニメデ人の地球支配も60年代初期アメリカのSFテレビドラマのようなスケールだけれど、幻覚兵器の効果の描写にはドラッグ小説作家ディックの片鱗がうかがわれる。レイ・ネルスンはたぶんディックよりも常識的なスタイルの持ち主だったろうから、これはやはりディックの作品といっていい。あと、ディック独特の倫理観がこれだけグダグダなプロットでも表面に浮き上がってくるのは凄い。
話題の作家であることは知っていたけれど、まともに読んだことがなかったレイ・ヴクサヴィッチ『月の部屋で会いましょう』は、300ページ足らずの本に33編を詰め込んだ掌編集だった。奇想の作家といえばその通りだが、アサッテの方向への論理で書かれたタイプが多いので、人間くささのないスタージョンみたいな感じがする。そのほかいくつか感想や感銘がうまれたけれど、渡邊利通の解説に書いてあるので、まあいいか。
続いて読んだ短編集はケリー・リンク『プリティー・モンスターズ』。こちらも奇想系ではあるけれど、小説作法はオーソドックスであり、いわゆる名編が多い。解説でヤングアダルト向けに編まれた作品集となっているが、そんなことは意識せずに読むことができる。
「マジック・フォー・ビギナーズ」や「スペシャリストの帽子」はそれぞれ過去に出た短編集の表題作であるにもかかわらず、そして早川書房の出版物であるにもかかわらず、訳出されているのは訳者柴田元幸のこだわりがあったからだろうけど、ちょっとイヤミっぽい(「専門家の帽子」だもんね)。ただし、当方は読んだ作品をすぐ忘れる人間なので、再読させられても初読と同じくらい感心してたりするので、個人的にはOKだ。
ケリー・リンクの小説の基本はホラー寄りのファンタジーだけれど、小説自体がよくできているので、読んでいてホラー小説によくある芝居っけはほとんど感じられない。ヴクサヴィッチの作品にもホラー系統は多いが、乾いた感覚が強くコントに近い。リンクはウェット系で、下手をするとただのホラーになりかねないが、作者にはホラーが自分の伝えたいものを伝えるための効果的な手段であることを強く意識していて、ホラーを書くことが目的化していないように見える。
ある意味ベスト・オブ的な短編集といってよく、巻頭の「墓違い」から巻末の表題作までダレない。SFファン的にはエイリアンの襲来が背景になっている「サーファー」が愉しい。主人公の黒人少年のオヤジがSFファンで『伝導の書に捧げる薔薇』にさらりと言及されてるもんなあ。
読みたい翻訳長編SFがないこともあって、ヴィクトル・ペレーヴィン『ジェネレーション〈P〉』を読む。ソ連崩壊後のロシアでコピーライターとして身を立てようと頑張るタタールスキィ青年(本人はヴォーヴァと呼んでもらいたがっている。タタールスキィは日本語で発音してもちょっと古くさい)の物語。ちなみに〈P〉はペプシのPらしい(当然ペレーヴィンのPでもある)。
熱に浮かされたような現代ロシア社会の描き方は、ドストエフスキーを彷彿とさせるが、ソローキンのような大馬力とはだいぶ違う。問題は訳者後書きの初めに出てくる「あらすじ紹介」で、300ページあまりにわたって綴られたタタールスキィ君のグダグダな生活が最後の30ページで驚異の結末を迎えるのだが、あらすじ紹介の半分弱がこの部分にあてらているので、これを読んでからタタールスキィ君の冒険につきあった読者はかわいそうだ。ミステリイじゃないんだから、という感覚があったからかもしれないがこれはちょっとなあ。
椎名誠『埠頭三角暗闇市場』は20年ぶりの本格的SF長編。舞台となる東京は、イマドキの情勢を反映して中国・韓国連合の攻撃を受けて生じた廃墟になっている。そのことは背景として何度も言及されているが、後半にいたってようやく物語がレジスタンスに向かっていたことがわかる仕掛けは弱く、プロットにカタルシスはないので、結局このグチャグチャな世界のべっとりとした感覚を楽しむことが主眼だろう。
物語の展開を支える登場人物(ヒトじゃないものもいるが)はどちらかというと影が薄く、読後の印象は構築された世界の感触だけが尾を引く。椎名誠はもはや小説的キャラクターにあまり興味が無いのかもしれない。
第五回創元SF短編賞受賞作を読もうと『ミステリーズ!Vol.66』を買ってくる。高島雄哉「ランドスケープと夏の定理」という意味不明なタイトルになっていたけど、気にせずに読んだ。登場人物が語り手(若い男)とその姉(超天才宇宙物理学者)そして姉の共同研究者の青花(女)しかいない、いや、以前姉の実験台にされた語り手に生じた分離魂(女)も入れたら4人いるか。超天才姉の創り出したSF的設定はウルトラ・ハードだけれど、弟である語り手の目線はシスコン・ラノベ的で書き方もそんな感じである。
ハードSF的には、弟の魂が分裂した「量子ゼノン記憶転送実験」はまあそんなものかだけれど、インフレーション宇宙論に絡めた「ドメインボール」は宇宙誕生時に生じた無数の別宇宙がそのままこの宇宙に存在しているという理論で、もっともらしくて魅力的だ。ラノベ的な軽さとウルトラ・ハードSF理論の組み合わせが成功しているとは思えないけれども、これぞSFという作品ではある。
この作品だけで1200円は高いので、西條奈加と柴田よしきそれに西澤保彦の短編(前の2作は連作短編シリーズの一部)を読んだ。女性作家はどちらもホッコリ/ユーモアタイプで西澤はパズラー的1編。前2作は読めばそれなりにホノボノするが、パズラーはピンとこない。どちらにしてもこういう小説にあまり興味がわかないのは昔からだなあ。
小説が読めない分、ノンフィクション系ばかり読んだひと月だった。
前月紹介した日清戦争を概観した新書の影響で、では朝鮮側はどうだったのかが気になって、やはり岩波新書の趙景達『近代朝鮮と日本』2012年11月初刷(いまだに!)を読んでみた。著者は東京生まれの人。日本でいえば幕末頃から明治末の日韓併合までの時代にあたる朝鮮半島の歴史を「政治文化史」的視点から書いた1冊。
著者は日本生まれの朝鮮民族ということもあり、決して順調には推移するここのなかった朝鮮近代史を痛ましい想いで綴っている。朝鮮王国民衆の(朝鮮王国の圧政と日本政府の圧政に対する)抵抗に肩入れして、賢王の下で「民本主義」が行われる理想の朝鮮王国を常に宙に描きながら、現実の朝鮮王国の近代史は齟齬だらけであったことをこの著者は明らかにしている。
強国同士の草刈り場的な運命を担わされた朝鮮半島の人々には同情を禁じ得ないが、その世界情勢を全く認識できない仕組みを作り上げてしまった当時の王国は、日本でなければロシアが支配したことは明らかで、現在の目で見れば日本の行為は侵略そのものとはいえ、当時のパワーゲームの中で朝鮮半島に苦難を避けられるような国家体制がなかったことをこの本は教えてくれる。
山形浩生訳の一般理論が面白かったので、ケインズ『お金の改革論』も読んだ。あいかわらずボケ頭にはよくわからないことが書いているが、山形浩生の明快なハリセン解説によれば、要は「(ハイパーでない)インフレはデフレよりマシ」ということが書いてある。
金本位制がたまたまそれまでの時代にマッチしていただけで、金本位制なんてさっさと止めるがよろしい、などと云うことも書いてある(らしい)。
第1次大戦後のドイツで、1923年3月の紙幣価値を1として、8月には0.116まで下がった表などを見ているとゾッとする。なおその2年あまり前の紙幣価値は4.8だったというから、その間に紙幣価値は0.02まで下がったわけだ。トランクいっぱいに紙幣を詰め込んで買い物に出かけるドイツ人の映像を思い出す。
ちくまプリマー新書の橋本治『古典を読んでみましょう』は、明治時代以前の古典を読むと何かいいことがあるかという視点で書かれた手引き書。橋本治は古典を読むのは、今と違った日本語で書かれているし今とは違った常識で書かれているんだから、読むのは当然面倒くさい。面倒くさいことを前提にして、それでも「すでにある多様な日本語の表現を忘れてしまうのは、損」だから古典を読むことを勧めている。
以前、小林秀雄を材料にした本を紹介したときに書いたとおり、橋本治は自分が勝てる部分でしか勝負しない人なので、ここでも「古典を読む」ことに不安がなくなった勝利報告的な面が感じられる。それが愉しいかどうかは人による。
山田風太郎『戦中派復興日記』が出たのに気がついて読んだら、『戦中派動乱日記』と『戦中派闇市日記』も文庫になっていることを知って、アマゾンに注文してまとめて読んでしまった。「闇市」は2012年の発刊だが、初刷のままヤスリ掛けになっており、思ったほど売れてないんだなあと思ってしまった。このヤスリ掛けはページをめくるたびにペリペリと抵抗感のある音がして気持ち悪い。
「復興」から「闇市」へさかのぼる形で読んだけれど、おもしろさでは、新人作家としていつも高木彬光とツルんで酔っ払っている「復興」、意外な面が見られるという点では「闇市」が一番だ。風太郎が「余が医者たるは肉体的に精神的に性格的に適せず。乾坤一擲さっかたらんとす。(?)」と「動乱」昭和24年5月8日の日記に書いたことで、作家風太郎が誕生したことがわかるが、なぜ「探偵小説」を書き始めたのかは、「闇市」のどこにも書いていない。またあれだけクールな視点に立っていたはずの山田青年が「極東軍事裁判」での東條にあれほど(「東條は現存する日本人中、最大の人物には違いなかった」昭和23年11月12日)思い入れをしていたとはビックリだ。果たして風太郎は死ぬまでそう思っていたんだろうか。
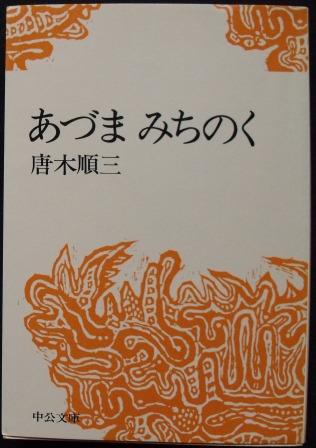 今月の積ん読のつもりで読んだ唐木順三『あづまみちのく』中公文庫昭和53年3月初刷は、よく考えたら買った当時読んだ記憶があった。まあ、36年ぶりの再読だから初読と一緒だ。
今月の積ん読のつもりで読んだ唐木順三『あづまみちのく』中公文庫昭和53年3月初刷は、よく考えたら買った当時読んだ記憶があった。まあ、36年ぶりの再読だから初読と一緒だ。
唐木順三が現在でも多くの読者を持っているかは怪しいが、昭和40年代の唐木順三はそれなりに強面のする文学/歴史評論家だった。今読むと最初に並ぶ「実朝の首」や「熊谷直実入道」に「頼朝の長女」といった歴史エッセイのおもしろさが実感される。実朝・大姫に共通する心を見いだし、現代的な心理に付会して鎮魂の一文をモノしたり、平家物語の有名キャラクターのひとり熊谷直実の強情っぱりを仏者蓮覚入道となった後も一生直らない性格として描いて見せたり、結構エンターテインメントしている。群書類従に納められているような古記録類を参照しながら、「みちのく(道の奥)」の在処の変遷とそこへ向かった、または思いをはせた古代平安朝の人々を描く後半もなかなか面白い。最後にある現地旅行記はちょっとダレるけど。真ん中に置かれた小説調の「将門記秘抄」もイマイチかなあ。
補遺 前回取り上げた『東京プリズン』の主人公がアメリカ留学した先はメイン州で、ド田舎だったんだけど、そのメイン州のド田舎ぶりが7月の『本の雑誌』の青山南のエッセイで取り上げられていたのに気がついた。シンクロニシティかと思ったが、たぶん青山南の陰の応援だったのだろう。