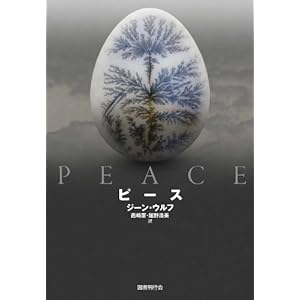|
���E�T���^���K�E�o���A�@�@�i��P�S�P��j
�Óc���v
|
�@�R���������̂悤�ɂ����Ƃ����Ԃɉ߂�����A�Ԍ������Ǝv�����炷�łɎU���Ă���B�����������Ă����̂��ȂǂƎv���o�����Ƃ��ł��Ȃ��B���~�{�ܓa���̂��ē���S��������A�C�M���X���痈�����N��肽�����R�_�_�ИA��čs�����肵���̂͊m����������B
 �@�ŋ߂̓W���Y�̂P�O�O�O�~�Ղ���ʂɏo�Ă��Ď��X�����Ă���̂����A�V���b�v�ł��낢�뒭�߂Ă�����A���N�ɂȂ��ă\�j�[���o�����V���[�Y�ɁA�A�[�g�E�t�@�[�}�[���uThe Time And The Place�v���������̂łт����肵���B
�@�ŋ߂̓W���Y�̂P�O�O�O�~�Ղ���ʂɏo�Ă��Ď��X�����Ă���̂����A�V���b�v�ł��낢�뒭�߂Ă�����A���N�ɂȂ��ă\�j�[���o�����V���[�Y�ɁA�A�[�g�E�t�@�[�}�[���uThe Time And The Place�v���������̂łт����肵���B
�@�S�O�N�قǑO�A�W���Y�����������ɔ������P��������ǁA�����Ղ������Ƃ͂����A�Ȃ�����Ȃ��̂��Ă����̂��S���v���o���Ȃ��s�v�c�ȔՂ��B�W���Y���Ă���l�ɂ��̃^�C�g���������Ă������Ă��́A�G�[�ǂ�ȃ��c���������Ƃ����邭�炢�e�̔����ꖇ�B�Q�l����ɉ������āA�O���[�t�F�̃Z�~�E�N���V�b�N�u�g�ȑ勬�J�i�O�����h�E�L���j�I���j�v����u�R�����s���v�����t���Ă������Ƃ��L���Ɏc���������ŁA���̌�͕������Ƃ��Ȃ������i�����O���[�t�F�u�g�ȑ勬�J�v�͂���Ȃ�ɗL���ȂŁA�A�[�T�[�E�t�B�[�h���[�ƃ{�X�g���E�|�b�v�X�ŕ����Ă����j�B
�@�I������o���ƁA�тɓ��{��CD���Ə����Ă���B���������W���P�b�g���݂Ȃ��甃���ċA��A�S�O�N�Ԃ�ɕ����ċ������̂��A���肪�����Ă������ƁB�^�����C���������̂ł���B��[�A��������Y��Ă����B���߂ăW���P�b�g�̏����ȉp�ꃉ�C�i�[�m�[�g�Ɠ��{������ǂނƁA����͂P�X�U�V�N�����Ńj���[���[�N��MoMA�i������p�فj�ł̃��C���Ƃ����G�ꍞ�݂������炵���A������������C���^�������悤�ɓǂ߂�B�������A�^���̓N�C���e�b�g�̃}���`���m�^���Ŕ��肪�^���X�e���I���ۂ��B�}�C���X�ꑮ�v���f���[�T�[�̃e�I�E�}�Z�����A�R���g���[����R�[���}����A�C���[���Ő�[��S���Ă�������A���ă}�C���X�����G���N�g���b�N�ֈڍs���O�Ƃ����Ƃ��ɁA�����Ƃ��Ă�����x��Ȃ���ȃW���Y�E���b�N���A���o���������Ă����Ȃ��B�܂������Ƃ������Ƃ��B��������Ƀt���[��A���@���M�����h��焈Ղ��Ă�����F�l�ɃI�X�X���I�Ə����Ă��邵�A���{�����ɂ͓��{���������D�]�������炵���Ɠ`���`�ŏ����Ă���B�I�[���h�E�X�^�C�������������W���Y�E�t�@���ɂ̓��e�������Ȃ��B
�@����Ȏ���������ߋ��ƂȂ������A�t�����[�Q���z�[�����S�̂��̃A���o���͌��\���ɐS�n�悢�B�����o�[�̓n�[�h�o�b�v����ɂ���Ȃ�ɖ����Ȃ��������o�[�A�W�~�[�E�q�[�X�̃e�i�[�A�E�H���^�[�E�u�b�J�[�̃x�[�X�A�~�b�L�[�E���[�J�[�̃h�����ɃV�_�[�E�E�H���g���̃s�A�m�ŁA���q�̂悢�i���o�[���D�����Ă���B�u�V���h�E�E�I�u�E���A�E�X�}�C���v�Ƃ��u���C�N�E�T�������E�n�b�s�[�v�Ƃ��̃|�s�����[�Ȃ��y���������Ă��ꂵ���B��\�ΑO�̎����ɂ͂��̊y�����͂킩��Ȃ������낤�Ȃƍ��ɂ��Ďv���B�ł�����͂����B
 �@����ɖ������߂āA������������킪�ň��̃W���Y�E�s�A�j�X�g�ł����W���[�W�E�E�H�[�����g���̂���܂��ň��̂P���uKnight Music�v���o�Ă��邩���Ǝv���A�O�O���Ă݂���Ȃ�ƂQ�N�O�ɂP�O�O�O�~�ՂɂȂ��Ă����̂��A����HMV�ɒ��������B
�@����ɖ������߂āA������������킪�ň��̃W���Y�E�s�A�j�X�g�ł����W���[�W�E�E�H�[�����g���̂���܂��ň��̂P���uKnight Music�v���o�Ă��邩���Ǝv���A�O�O���Ă݂���Ȃ�ƂQ�N�O�ɂP�O�O�O�~�ՂɂȂ��Ă����̂��A����HMV�ɒ��������B
�@�u�i�C�g�E�~���[�W�b�N�v�͂�����S�O�N�O�̘Q�l����A�����͂������������I�[�f�B�I�e�Ђ̃V���[�E���[�����n�V�S���Ă��āA�p�C�I�j�A�̃V���[�E���[���ł��܂����ɓ���A���̌��Ԃ̂��C�ɓ���ƂȂ����P�����B���̍��̓E�H�[�����g���Ȃ�Ēm��Ȃ����������t�̟��E���A���m�b�h�𒅂ĉ��t���Ă���s�A�m�E�g���I�̃C���X�g�̕��͋C�ɖ������ꂽ�B����CD�������ԓ��{�������Ȃ����ꂪ���{��CD�����B
�@�����Ă������̓��A��їE���CD�v���[���[�ɓ���A�����o��̂�҂B�n�܂����Ƃ���Ђ�����Ԃ�B��������́A�X�e���I�^�������B�ł�������o�X�h���A��ʂ��Ȃ��s�A�m�A����^���X�e���I�B�p�C�I�j�A�̃V���[�E���[���ɂ�����LP���^���X�e�������\���͂���B������X�e���I�邽�߂̃V���[�E���[���������̂�����B�����Đ̔�����LP���^���X�e���I�������\�����ۂ߂Ȃ��B�������A���Ɏc���Ă��鉹�̓��m�ł���A�n���ȃs�A�m�g���I�̉��̓o�����X�悭�����Ă����B��������ɓ����̘^���̃g���[�h�}�[�N'HIGH FIDELITY'�͂����Ă��A�X�e���I�\���͓��R�����B���f�B�E���@���E�Q���_�[���P�X�T�U�N�ɃX�e���I�^��������Ă�����������낤�i�Q���_�[�̏��X�e���I�^���͂P�X�T�V�N�R���Ƃ���Ă���j�B�����Ă���LP�͑S���X�̔��Α��ɂ�����ꂩ���̃A�p�[�g�̈ꎺ�ɕ��荞��ł���̂ŁA���������Ŋm�F�ł��Ȃ��B����ɂ��Ă�������^���X�e�ɂ����낤�B
 �@�Ȃ����Ղł͂Ȃ�����ǂ����ꖇ�������̂��A�}�C���X�E�f�C���B�X�uWe Want MILES�v�B�V�O�N�㔼�ɍ����G���L�o���h�����U���ĂT�N���܂��A���A���Ē���̃��C���E�A���o��������ǂ��A�����͕��A��P��uThe Man With
The Horn�v���Ă��܂�̃w�i�`���R�Ԃ�ɁA����ȍ~�̃A���o���͔���Ȃ������B
�@�Ȃ����Ղł͂Ȃ�����ǂ����ꖇ�������̂��A�}�C���X�E�f�C���B�X�uWe Want MILES�v�B�V�O�N�㔼�ɍ����G���L�o���h�����U���ĂT�N���܂��A���A���Ē���̃��C���E�A���o��������ǂ��A�����͕��A��P��uThe Man With
The Horn�v���Ă��܂�̃w�i�`���R�Ԃ�ɁA����ȍ~�̃A���o���͔���Ȃ������B
�@���������������́w�h���IJAZZ�m�[�g�x�i�u�k�Ё{�����ɂP�X�X�S�N�����j�ɁA�I�[�f�B�I�̂������ŗL���ȃW���Y�i���u�x�C�V�[�v�ɋߏ��̃W���Y�i���X�傽���ƒ����ɍs�����Ƃ��A���������͂��̉��̗ǂ��ɑł��̂߂��ꂽ�Ə����Ă���B���̎��������Ă������R�[�h�����̃}�C���X�̉��t�������B���ꂩ��wCD�W���[�i���x�ɃC���X�g�G�b�Z�C��A�ڂ��Ă���q��ǍK���A���������Ԃ�O�̂��Ƃ�����ǁA����CD�Ɏ��^���ꂽ�����V�h�ł̖�O���t���o�C�g�̋A��ɍ��˕����̋߂��Ŗڌ����A���������ɂȂ��ĉ��t����}�C���X�̎p��`���Ă����B���̓�̃G�s�\�[�h�����܂ł������痣��Ȃ������̂ŁA�����Ă݂��킯���B
�@�A�����J�ōs��ꂽ���A�X�e�[�W�ł̉��t�ł́A�}�C���X�̃g�����y�b�g�͌��\���C���悭�A�����ł̉��t�͊m���ɉ��������Ă����B�ł����A��P��̃X�^�W�I�Ղ��͂͂邩�Ɋy����������B�������A�����ł̉��t�̃��[�_�[�͂���̓}�C���X�ł͂Ȃ��ăx�[�X�̃}�[�J�X�E�~���[���B���̂��ƖS���Ȃ�܂ł̂P�O�N�ԁA�}�C���X�͑����̃��C�������Ȃ��A�V��X�^�W�I�Ղ��o������������ǁA����͎Ⴂ�W���Y�}�������̂��߂̊w�Z�������̂�������Ȃ��B
 �@�W���Y�̒I�����낶�댩�Ă�����A�p�b�g�E���Z�j�[�uFIRST CIRCLE�v���ڂɂ��āA����ς蒮���Ă��������Ǝv���Ă��܂������Ă��܂����B��{�땽�w�t�@�[�X�g�E�T�[�N���x�̖`���ɏo�Ă���P�P���q�̎蔏�q�����ڂ��̃^�C�g���Ȃ�����p����Ă���Ƃ������ꂾ���̗��R���B
�@�W���Y�̒I�����낶�댩�Ă�����A�p�b�g�E���Z�j�[�uFIRST CIRCLE�v���ڂɂ��āA����ς蒮���Ă��������Ǝv���Ă��܂������Ă��܂����B��{�땽�w�t�@�[�X�g�E�T�[�N���x�̖`���ɏo�Ă���P�P���q�̎蔏�q�����ڂ��̃^�C�g���Ȃ�����p����Ă���Ƃ������ꂾ���̗��R���B
�@�킪�Ƃɂ���p�b�g�E���Z�j�[�̉��t��������CD�͂����P���A��������㉹�y��匷�y�l�d�t�c�N���m�X�E�N�@���e�b�g�ɉ�����ăX�e�B�[���E���C�q�̋Ȃ��P�ȉ��t���Ă���Ƃ������m���B�v�̓��Z�j�[�ɂ͋������Ȃ��Ƃ������ƂȂ���ǁA�W���Y�D���Ȓm�荇���ɂ��m�F���Ă݂���A�ނ����Z�j�[�͑匙���Ƃ����Ă����B���Z�j�[�̉��ɂ̓W���Y�̂ɂ������Ȃ��̂��B
�@����͂Ƃ����������Ă���CD�͂P�X�W�S�N�̍�i�ŁAECM���[�x���ł̃��Z�j�[�̍ŏI��Ƃ̂��ƁBECM�Ƃ������Z���̍��A���R�[�h�X���ɗ�����Ă����G���s�̐_��I�ȋ����Ɏv�킸���ꂭ�������ƁA�Ȃ��݂̂��o����X���ɋ삯����Ă������u���^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�v�̃f�r���[����v���o���B���̌�̓`�b�N�E�R���A�ƃQ�C���[�E�o�[�g���́u�N���X�^���E�T�C�����X�v��}�C�i�[�ȂƂ���ł̓t���[�W�����n�M�^���X�g�̃e���G�E���s�_���̃A���o�����v���o�����B�v���f���[�T�[�̃}���t���[�g�E�A�C�q���[��I�X���̃X�^�W�I�Ř^���Ƃ����̂����̍��o�����B��������L�[�X�E�W�����b�g�́u�P�����E�R���T�[�g�v��ECM�����������B
�@���������̉��t�̓j���[���[�N�̃p���[�X�e�[�V�����E�X�^�W�I�ł̘^���ŁA���t�S�̂��ʂ�͓̂�ĉ��y�̕��͋C�ł���B�^�C�g���Ȃ̎蔏�q�͂������낢���z������ǁA���t���̂��̂̓T���o�E�t���[���@�[�̃t���[�W�����ŕ@�̓���̃C�[�W�[���X�j���O�ɋ߂��B�X���Ԃ̉��t�͐���オ��Ƃ�������邵�����͂Ȃ����A�R�O�N�O�̐��V���͂U�O�N�߂��O�̃n�[�h�E�o�b�v�̒�^�I�ȉ��t�̂������낳�����F�����ĕ�������B���ƂQ�O�N�������炱�̉��t���������낭��������悤�ɂȂ邩������Ȃ����A���̍��ɂ͂��������Ă���Ƃ��Ă��A������̎����������Ȃ��Ȃ��Ă����Ȃ��B
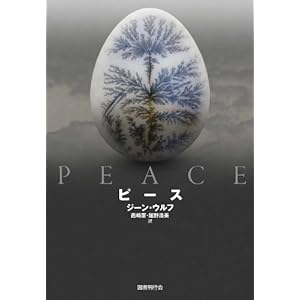 �@�|��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�|�����ǂ�ł݂��B�܂����W�[���E�E���t�w�s�[�X�x����B����u�M�p�ł��Ȃ�����v�����̑㖼���݂����ȃE���t�̍�i�����A��������̈�B���̍�i�ł͘V�N�ƂȂ�������̎q�������N����̏o����������q�ɂȂ��ĉ�z�����B�\�������E�\���̃G�s�\�[�h�͌Ï����U������Ï��X��̔������{�����肪�U���ƌ��j��b�����A�ő�̉R���͓��R���肾�낤�B�Ƃ��낪�A�s���ӂȓǎ҂ɂ͂��̎d�|���������ς�킩��Ȃ��B��҉���Ő��茛���u�E���t�͉R�����Ȃ��B�����`�ʂ��邾�����B�R�����l�Ԃ��B�v�ƁA���ɓI�m�Ɂu�M���ł��Ȃ�����v�̍������`���Ă���Ă���B�ł��{���N���ȓǎ҂͋C�����Ȃ���ˁB���ƂȂ����͋C���`��邾���ŁB�ł����ꂪ���̏�����ǂފy���݂��Ǝv�������B
�@�|��������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�|�����ǂ�ł݂��B�܂����W�[���E�E���t�w�s�[�X�x����B����u�M�p�ł��Ȃ�����v�����̑㖼���݂����ȃE���t�̍�i�����A��������̈�B���̍�i�ł͘V�N�ƂȂ�������̎q�������N����̏o����������q�ɂȂ��ĉ�z�����B�\�������E�\���̃G�s�\�[�h�͌Ï����U������Ï��X��̔������{�����肪�U���ƌ��j��b�����A�ő�̉R���͓��R���肾�낤�B�Ƃ��낪�A�s���ӂȓǎ҂ɂ͂��̎d�|���������ς�킩��Ȃ��B��҉���Ő��茛���u�E���t�͉R�����Ȃ��B�����`�ʂ��邾�����B�R�����l�Ԃ��B�v�ƁA���ɓI�m�Ɂu�M���ł��Ȃ�����v�̍������`���Ă���Ă���B�ł��{���N���ȓǎ҂͋C�����Ȃ���ˁB���ƂȂ����͋C���`��邾���ŁB�ł����ꂪ���̏�����ǂފy���݂��Ǝv�������B
 �@�O����ǂނ̂ɂ����ԂԂ����������̂ŁA���炭�ق����Ă������L���T�����EM�E���@�����e�w�ǎ��̕���U����d�݂ƍ����̓s�ɂāx�Ɏ���o�����Ƃ���A��͂萔�y�[�W�̃G�s�\�[�h���قǓǂ�ł͐Q�Ă��܂��B�Ƃɂ����{���d�����̂��i�l�i���������j�B�V�N���ƃo���G�e�B�ł͑O���̕����C���p�N�g���������悤�Ɏv�����A������͑傫�������āA�d�݂����H��ɂƂ��ꂽ���N�Ə�������n�܂�b�ƁA���̍d�݂��Č̓��֓n���D���ɂ܂��b�B�㔼�͌Â��s�Ɩ��i���j�_�q�W���r�̘b����̂��Ȃ��Ă���B��������̂܂Ԃ��ɏ����ꂽ�����ǂݑ�����g����̐i�s������B
�@�O����ǂނ̂ɂ����ԂԂ����������̂ŁA���炭�ق����Ă������L���T�����EM�E���@�����e�w�ǎ��̕���U����d�݂ƍ����̓s�ɂāx�Ɏ���o�����Ƃ���A��͂萔�y�[�W�̃G�s�\�[�h���قǓǂ�ł͐Q�Ă��܂��B�Ƃɂ����{���d�����̂��i�l�i���������j�B�V�N���ƃo���G�e�B�ł͑O���̕����C���p�N�g���������悤�Ɏv�����A������͑傫�������āA�d�݂����H��ɂƂ��ꂽ���N�Ə�������n�܂�b�ƁA���̍d�݂��Č̓��֓n���D���ɂ܂��b�B�㔼�͌Â��s�Ɩ��i���j�_�q�W���r�̘b����̂��Ȃ��Ă���B��������̂܂Ԃ��ɏ����ꂽ�����ǂݑ�����g����̐i�s������B
�@���̕���́A�b�̒��̓o��l�����o���������̘b���A���̑��肪�o��������肪�܂��b������Ƃ����A��҈�Ҏ�������Ƃ���́u���j�A�ȕ���v�Ŗc��ȒZ���G�s�\�[�h���ςݏd�˂��Ă���B�Q�O��ł��̍�i�����m�ɂ������@�����e�͂��������Z�ʂ̎����傾�B�o��l�������͍r�ꋶ�����Ƃ����邪�A��{�I�ɂ͐�捂ȕ���ł���A�����鋭�Ղȃ��B�W���������O����悤�ȌÓT�I�ȃt�@���^�W�[�Ƃ͈Ⴄ�B�܂����^�t�B�N�V�����I�Ȑg�U��͓��R����킯������ǁA������Z�I�Ƃ��Ă͈ӎ��������ʂĂ��Ȃ��G�s�\�[�h�̃����h��t�łĂ���B���̂��Ƃ́A��҉���ł́A����́u�܂��Ƃ��₩���v�ւ̎����������A�u�����Έِ��E�v�ł͂Ȃ��u�g�������v�̎���ƂȂ����Ƃ��Ă���B�܂��A�l�͕����I�Ɏ��ʂ��Ƃɑ���͂Ȃ��ɂ�������炸�A���̐؎��������u�g�������v�ɕ����Ă��܂��Ă��邢�܂̌����̌������B���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊��o�I�ɂ͗���������B�̓R���Ɓw�i���̂O�x�l�C�̓R�C���̕\���ł����Ȃ�����Ȃ��B
 �@���@�����e��ǂނ̂������Ƃ��i�܂Ȃ��̂ŁA���̊ԂɎ���o�����̂��t�B���b�v�E�J�[�w�Â��Ȃ鉊�x�B�����O���^�[���̑�Q��Ƃ������ƂŁA��P���ǂݓ����Ă��āA�S�O���Ă����̂�����ǁA�ǂ�ł��܂����B�P�X�T�O�N��s���̃h�C�c��ăA���[���`���Ɉڂ����T�O��̃O���^�[�̕���Ɛ�O�q�b�g���[�����͂���������I�����O�P�X�R�O�N��̕��ꂪ���݂Ɍ���A�㔼�̓O���^�[�̍��ł���P�X�T�O�N��ɏW���B�x�������O���삪�D���������̂ŁA�ǂ����Ă��P�X�R�O�N��̌��炸���O���^�[�Ɏ䂩��Ă��܂��B�b��B�K���������Ȃ��瑊�ς�炸�^�t�ȏ����сA�ꂢ�������}����s�N�̃O���^�[�����Ă܂������͂Ȃ����A��͂�O���^�[�͂P�X�R�O�N�ォ��S�O�N��̐l���낤�B
�@���@�����e��ǂނ̂������Ƃ��i�܂Ȃ��̂ŁA���̊ԂɎ���o�����̂��t�B���b�v�E�J�[�w�Â��Ȃ鉊�x�B�����O���^�[���̑�Q��Ƃ������ƂŁA��P���ǂݓ����Ă��āA�S�O���Ă����̂�����ǁA�ǂ�ł��܂����B�P�X�T�O�N��s���̃h�C�c��ăA���[���`���Ɉڂ����T�O��̃O���^�[�̕���Ɛ�O�q�b�g���[�����͂���������I�����O�P�X�R�O�N��̕��ꂪ���݂Ɍ���A�㔼�̓O���^�[�̍��ł���P�X�T�O�N��ɏW���B�x�������O���삪�D���������̂ŁA�ǂ����Ă��P�X�R�O�N��̌��炸���O���^�[�Ɏ䂩��Ă��܂��B�b��B�K���������Ȃ��瑊�ς�炸�^�t�ȏ����сA�ꂢ�������}����s�N�̃O���^�[�����Ă܂������͂Ȃ����A��͂�O���^�[�͂P�X�R�O�N�ォ��S�O�N��̐l���낤�B
 |
 |
�@���@�����e�Ƃقړ����ɓǂݎn�߂��������A�ǂނ̂ɂ��炭���Ԃ����������̂��A���@�[�i�[�E���B���W�w���̊U�̋�x�B��͂̒��S�ƊO���ŕ��������i��������Ȃ��݂����j���Ⴂ�A����ɍ��킹�Ďv�l���x��������E�������Ⴄ�Ƃ����w���e�R�ȉF����ɂ��Ĉ�ʃn�[�hSF�����A���ʕ��ʂِ̈��`��SF�i������̕�������̑啔���j�Ƃ����V�����m�B�w�ʼnʂĂ̋�͑D�c�x�͓ǂ�ł��邯��ǁA�O��́w�����_�X�̉��x�͓ǂo�����Ȃ��B���̂��߁u�u�a�͑��v�̋��Ђ����܂����s���Ƃ��Ȃ��i����͎�l���ɑ��Ĕ������N�����q������Ɠ������j�B�����ɏW���m���́q�S�ܑ��r�̐ݒ肪�悭�ł��Ă��Ă��A����Ă邱�Ƃ�l�������l�Ԃƕς��Ȃ��̂ŁA����܂�{�C�ɂȂ��ăX�g�[���[��ǂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�u���^�v�Ƃ����Ƃ���ɃJ���C�C�Ɣ�������l������ł��傤���A���[�g��SF�t�@���ɂ́u�z�[�J�v�ł��傤�B���ƁA�g�̉��ςɊւ���\�����قƂ�ǂȂ�����ǁA���͂����ɏo�Ă���l�Ԃ�S�ܑ��́w�n���[�T�}�[�E�O�b�h�o�C�x�Ɠ����悤�Ɏ��Ԃ͌������̕���ƑS�R�Ⴄ�\��������B�܁A���B���W�������܂ōl���ď������Ƃ͎v���Ȃ�����ǁB
 �@�R�j�[�E�E�B���X�w��P�x��x�̓x�X�g�Z�ҏW�̌㔼�����ŃV���A�X�҂Ƃ�������ǁA�̂���E�B���X�̃V���A�X���s���Ƃ��Ȃ��č����Ă���B�ǂݕ��Ƃ��Ă͔��ɓǂ݂₷���A����Ȃ�Ɋ��S����̂�����ǁA�����͂��Ȃ��B�u�i�C���Ɏ����v�����ǂ���������ǁA����ȊO�͍ēǁB�܂��A�\���͂����Ԃ�v���Ԃ�ɓǂ�ŁA���̊ԂɁq�j�w���V���[�Y�r���K���K���ꂽ�̂ŁA���\�Ȋ��S�������ēǂނ��Ƃ��ł�������ǁA�̐S�́u�Ō�̃E�B�l�x�[�S�v�ɂ͂��܂�S����������Ȃ��B����L�Ɏv�����ꂪ�Ȃ����ׂ��˂��B�u�}�[�u���E�A�[�`�̕��v�͓������g�ɂ܂���邪�A�����܂Ń����h�����P�ɂ�����邩�A�Ƃ����Ƃ���ł�����Ƌ^��B�t�^�͂������낢�B
�@�R�j�[�E�E�B���X�w��P�x��x�̓x�X�g�Z�ҏW�̌㔼�����ŃV���A�X�҂Ƃ�������ǁA�̂���E�B���X�̃V���A�X���s���Ƃ��Ȃ��č����Ă���B�ǂݕ��Ƃ��Ă͔��ɓǂ݂₷���A����Ȃ�Ɋ��S����̂�����ǁA�����͂��Ȃ��B�u�i�C���Ɏ����v�����ǂ���������ǁA����ȊO�͍ēǁB�܂��A�\���͂����Ԃ�v���Ԃ�ɓǂ�ŁA���̊ԂɁq�j�w���V���[�Y�r���K���K���ꂽ�̂ŁA���\�Ȋ��S�������ēǂނ��Ƃ��ł�������ǁA�̐S�́u�Ō�̃E�B�l�x�[�S�v�ɂ͂��܂�S����������Ȃ��B����L�Ɏv�����ꂪ�Ȃ����ׂ��˂��B�u�}�[�u���E�A�[�`�̕��v�͓������g�ɂ܂���邪�A�����܂Ń����h�����P�ɂ�����邩�A�Ƃ����Ƃ���ł�����Ƌ^��B�t�^�͂������낢�B
 �@�ŐV�C�^���ASF�Ƃ����̂�������ƋC�ɂȂ����̂œǂ�ł݂��_���I�E�g�i�[�j�w�����h�X�i�m�[���F�j�x�́A������Ƃ����Ռ���������P��BSF�I�ɂ͕ʂɐV�����A�C�f�A�͂Ȃ�����ǁA���E�̕`��������l���ݒ�ƕ���̓W�J�ɓ���SF�Ƃ͈�������G������A�ꌩ�V���A�X�ŃT�C�o�[�^�X�`�[���E�p���N�ȍ~�ȃX�^�C���Ɍ����邪�A���̓t�����XSF�R�~�b�N�̉e���������������A����͂Œ蒅�����Ă���Ƃ��낪���炵���B�ِ��̍������p��^�C���ōq�s���鋐��D�q���u���h�r����j�B�^�C�����j�b�g�͏���ɓ����o���A����ɏ���đD��E�o�����Q�l�̊͒��ƕ����̘b����n�܂�A���̓�j��������D�Ɋ֘A�������҂��S���łS�Ҏ��^����Ă���B�{���Q�S�O�y�[�W�Ƃ����R���p�N�g��������ǂ��A��ȃC���[�W�̍L�����G���^�[�e�C�������g�n�ł͖ő��ɂ݂��Ȃ���v�L�����̈�����������ۂ��c���B���̂̊��G�͂����镶�w�Ƃ������V���A�X�ȃR�~�b�N�����Ɗ������邯��ǁA������SF��������̂�������Ȃ��B����ɂ��Ă��q�X�r���g���^�C�g�������R��������̂ɂ͉�������낤���B
�@�ŐV�C�^���ASF�Ƃ����̂�������ƋC�ɂȂ����̂œǂ�ł݂��_���I�E�g�i�[�j�w�����h�X�i�m�[���F�j�x�́A������Ƃ����Ռ���������P��BSF�I�ɂ͕ʂɐV�����A�C�f�A�͂Ȃ�����ǁA���E�̕`��������l���ݒ�ƕ���̓W�J�ɓ���SF�Ƃ͈�������G������A�ꌩ�V���A�X�ŃT�C�o�[�^�X�`�[���E�p���N�ȍ~�ȃX�^�C���Ɍ����邪�A���̓t�����XSF�R�~�b�N�̉e���������������A����͂Œ蒅�����Ă���Ƃ��낪���炵���B�ِ��̍������p��^�C���ōq�s���鋐��D�q���u���h�r����j�B�^�C�����j�b�g�͏���ɓ����o���A����ɏ���đD��E�o�����Q�l�̊͒��ƕ����̘b����n�܂�A���̓�j��������D�Ɋ֘A�������҂��S���łS�Ҏ��^����Ă���B�{���Q�S�O�y�[�W�Ƃ����R���p�N�g��������ǂ��A��ȃC���[�W�̍L�����G���^�[�e�C�������g�n�ł͖ő��ɂ݂��Ȃ���v�L�����̈�����������ۂ��c���B���̂̊��G�͂����镶�w�Ƃ������V���A�X�ȃR�~�b�N�����Ɗ������邯��ǁA������SF��������̂�������Ȃ��B����ɂ��Ă��q�X�r���g���^�C�g�������R��������̂ɂ͉�������낤���B
 �@�Ō�܂Ŗ|���Ǝv���Ă�������ǁA���a���Ă��܂��A���߂ēǂލ�Ƃ�ǂ����ƃn���J��SF�V���[�YJ�R���N�V�����ŐV������w�k�����덑�l�x��ǂB�ǂނ�Ȃ������Ƃ����̂��A�Ƃ肠�����̊��z�B���Ǝ��Ɍ������Ă����͂��̏��q���w���������Ŗڂ��o�߁A�����ɂ͔������������킹�ɂ��邪�A����ɂ̓h�A�m�u�������A�����ɂ̓h�A�m�u������A�����ɂ͑��Ǝ����̎w�����������Ă���B�Ƃ����Ƃ��납��n�܂�̂����A�T�O�y�[�W�̒Z�҂̕\���̕���Ƃ��ĂȂ�A�t�[���ł����̂��A�u�����덑���v�Ƃ����o���G�[�V�����ɂ͂���ƍ�҂�������������̐ݒ肪�ϑz�̑������ɂȂ��ċ������Ă��܂��B�Ō�̃G�s�\�[�h�ɂ͂���Ȃ�̏������A���ꂱ�����w���Ɛ����炢�́A�܂��������V�N�Ȏ���ɓǂ߂Ί������邱�Ƃ��ł��悤���A���\�N���ǂނ��Ƃ̎h�������߂Ă����N���ɂ͗p���Ȃ��B
�@�Ō�܂Ŗ|���Ǝv���Ă�������ǁA���a���Ă��܂��A���߂ēǂލ�Ƃ�ǂ����ƃn���J��SF�V���[�YJ�R���N�V�����ŐV������w�k�����덑�l�x��ǂB�ǂނ�Ȃ������Ƃ����̂��A�Ƃ肠�����̊��z�B���Ǝ��Ɍ������Ă����͂��̏��q���w���������Ŗڂ��o�߁A�����ɂ͔������������킹�ɂ��邪�A����ɂ̓h�A�m�u�������A�����ɂ̓h�A�m�u������A�����ɂ͑��Ǝ����̎w�����������Ă���B�Ƃ����Ƃ��납��n�܂�̂����A�T�O�y�[�W�̒Z�҂̕\���̕���Ƃ��ĂȂ�A�t�[���ł����̂��A�u�����덑���v�Ƃ����o���G�[�V�����ɂ͂���ƍ�҂�������������̐ݒ肪�ϑz�̑������ɂȂ��ċ������Ă��܂��B�Ō�̃G�s�\�[�h�ɂ͂���Ȃ�̏������A���ꂱ�����w���Ɛ����炢�́A�܂��������V�N�Ȏ���ɓǂ߂Ί������邱�Ƃ��ł��悤���A���\�N���ǂނ��Ƃ̎h�������߂Ă����N���ɂ͗p���Ȃ��B
 �@����͖|����ǂނ̂Ɏ��Ԃ�������A�m���t�B�N�V�����͂P�������B����^�_�m���w�_�����{�̃g���f�����퐶���x�i�}�����Ɂj�́A�펞���́i���ɂ��Ă݂�j�A�z�o�J���W�߂��A�͂�����Ƃ�������v�z�Ɋт���Ă���P���B�J���[�}�ő����ŁA���߂Ă��̎�̎���������ǎ҂ɂ͂Ȃ��Ȃ��y�����{������ǁA���N�����Ɏ��グ��ꂽ�����������ɑ����Ă����l�����ɘb���Ă����҂ɂ͈������v���̂���P���ł���B�܂��A�펞���̐_������q�X�e���[��o���̂߂����Ƃ͍������炱���K�v�Ƃ������Ƃ͊m���B�ł��A���̚o���̂߂��ꂽ�_���������������Ȃ������̂������̐e�i�܂��̓W�C�`�����E�o�A�`�����j�ł��邱�Ƃ̋��낵�����w�ڂ��Ƃ���ɂ́A�s�����Ƃ��킴��Ȃ��B
�@����͖|����ǂނ̂Ɏ��Ԃ�������A�m���t�B�N�V�����͂P�������B����^�_�m���w�_�����{�̃g���f�����퐶���x�i�}�����Ɂj�́A�펞���́i���ɂ��Ă݂�j�A�z�o�J���W�߂��A�͂�����Ƃ�������v�z�Ɋт���Ă���P���B�J���[�}�ő����ŁA���߂Ă��̎�̎���������ǎ҂ɂ͂Ȃ��Ȃ��y�����{������ǁA���N�����Ɏ��グ��ꂽ�����������ɑ����Ă����l�����ɘb���Ă����҂ɂ͈������v���̂���P���ł���B�܂��A�펞���̐_������q�X�e���[��o���̂߂����Ƃ͍������炱���K�v�Ƃ������Ƃ͊m���B�ł��A���̚o���̂߂��ꂽ�_���������������Ȃ������̂������̐e�i�܂��̓W�C�`�����E�o�A�`�����j�ł��邱�Ƃ̋��낵�����w�ڂ��Ƃ���ɂ́A�s�����Ƃ��킴��Ȃ��B
THATTA 311���֖߂�
�g�b�v�y�[�W�֖߂�
 �@�ŋ߂̓W���Y�̂P�O�O�O�~�Ղ���ʂɏo�Ă��Ď��X�����Ă���̂����A�V���b�v�ł��낢�뒭�߂Ă�����A���N�ɂȂ��ă\�j�[���o�����V���[�Y�ɁA�A�[�g�E�t�@�[�}�[���uThe Time And The Place�v���������̂łт����肵���B
�@�ŋ߂̓W���Y�̂P�O�O�O�~�Ղ���ʂɏo�Ă��Ď��X�����Ă���̂����A�V���b�v�ł��낢�뒭�߂Ă�����A���N�ɂȂ��ă\�j�[���o�����V���[�Y�ɁA�A�[�g�E�t�@�[�}�[���uThe Time And The Place�v���������̂łт����肵���B