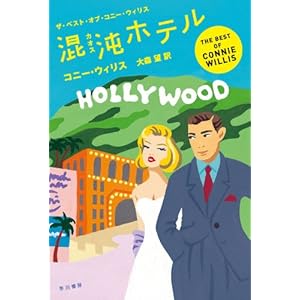内 輪 第282回
大野万紀
ソチの冬季オリンピックが終わりました。普段スポーツにはほとんど興味のない私ですが、オリンピックはそこそこテレビで見ていました。
梅田の例会でも、オリンピックの話題が出て、細美さんが「近所の弓弦羽神社が有名になって羽生結弦ファンがいっぱい来るよ」という話をしたところ、「羽生結弦って誰?」といった人がいて、一同びっくり。
その人は普段からスポーツのファンで、ネットの話題にもとても詳しい人だったので、ちょっと意外だったのです。こんな身近なところでも世界って分断され、セグメント化しているのだなと痛感しました。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『戦いの虚空 老人と宇宙5』 ジョン・スコルジー ハヤカワ文庫
『戦いの虚空 老人と宇宙5』 ジョン・スコルジー ハヤカワ文庫
久々の〈老人と宇宙(そら)〉シリーズの新刊。といっても出たのは10月だけど。
このシリーズは好きだ。とにかくごく普通の宇宙SF。先端的でもないし、深くもないけど、読むのが楽しいエンターテインメントだ。主人公はコロニー防衛軍(CDF)のハリー・ウィルスン。老化して死ぬ前にCDFにリクルートされ、サイボーグ化された緑の肌を持つ別の肉体に蘇った。ただしこの数年は兵士というより技術者として働いていたが、それでも生身の人間よりはるかに強い。その彼が、B級とランク付けされる女性大使のアブムウェらと、ろくでもない外交任務にかり出され、コロニー連合と異星人たちの連合であるコンクラーベ、それにコロニー連合に搾取されていた地球との複雑な政治的陰謀がからむ事件に巻き込まれていく。
ウィルスンの、おやじギャグを飛ばしながらやるときゃやる、いかにもアメリカン・ヒーローっぽいキャラクタがいい。そのまわりの情けない副大使シュミットや、鉄の女というべきアブムウェ大使、ウィルスンにシャトルをつぶされるのを気にしているコロマ船長、そしてコンクラーベの顧問官である異星人ソルヴォーラといった登場人物が、類型的ではあるが、魅力的に描かれている。
物語はとにかく陰謀によって死にかかったり死んだりという、みんなやたらとひどい目にあう話なのだが、テレビドラマ風に13のエピソードから構成されたというこの構成は、ちょっと冗長で、もっとすっきり書いていればずっと読みやすかっただろうと思う。そして、訳者も後書きで書いているけど、この宙ぶらりんな結末はないよな。大変な事件が起こって、これまでの謎は何も解決していない。続編が書かれるのは間違いないのだろうけど、いやはや。
 『テキスト9』 小野寺整 ハヤカワSFシリーズJコレクション
『テキスト9』 小野寺整 ハヤカワSFシリーズJコレクション
第一回ハヤカワSFコンテストの最終候補作。
新人のデビュー長編にしてはずいぶん分厚い。それに(とても読みやすいのだけれど)ストーリーは要約不能(と書いてある)で、SF的な飛躍が大きく、メタフィクション的というか、シミュレーション宇宙的というか、とても数学的で哲学的な言語SFというか(ちょっと円城塔の初期作品を思わせる)、自己言及バンザイというか、テーマは現代的で面白く、すごく興味あるのだけれど、なかなか手を出しづらいところだろう。読みやすいけどわかりにくい、というタイプの作品だ。いや、ぼくは好みです。
遙かな未来、田舎の惑星で〈仮定物理学〉を学んだカレンは、先生のサローベンとともに、この宇宙を支配するムスビメ議会に召喚され、宇宙を脅かす超テクノロジーを盗んだ女の追跡を依頼される。そこから始まる物語は、仮想も現実も、オリジナルもコピーも一緒くた、地球も本物の地球じゃなさそうだし、宇宙だっていっぱいあるという、いかにもハードSFの入った〈ニュー・スペースオペラ〉風な、派手でちょっとコミカルな展開となる。チャールズ・ストロスや、ジョン・C・ライトの大好きなぼくとしては大喜びで、とても面白かった。
ただ、最初の読みやすいということにも関わるのだが、作者(この言葉も最終的に特別な意味をもつ)は冒頭から、この文章がある種の翻訳であり、ずいぶん恣意的な翻訳もあり得ると語っている。ちょっとあからさますぎるな、と思ったが、実際「インディ・ジョーンズのような格好で」とか「未来世紀ブラジルみたいな世界」といった文章を読むと、ちょっとテンションが下がってしまう。でもそれが、世界を語るいくつものレイヤーや、そのシミュレーションが最終的にはどこで動いているのか、といった本書のメインテーマにも関わってくるので、あなどれない。
本書で何度も語られる重要なキーワードとして「トーラー」と「スタッシュ」という言葉がある。「トーラー」といえば普通モーゼの律法だが、本書ではこの世界のすべての秘密や謎、神林長平の帯にある「およそ言語化しうるすべての謎の答え」と言い換えても間違いじゃないだろう。一方「スタッシュ」は隠し財産を意味する英語からの作者の造語で、独自の生命と意識をもつ金融の(というかおそらくは経済活動すべての)ダイナミックな集合を表す。
複雑なシステムに独自の知性や意識が立ち表れるというのは、雰囲気としてよくわかる。道路の渋滞だって、そこに独自の意識があるのかも知れないよ(ねえ、菊池さん、堺さん)。
本書の終わり近くで、突然ストーリーに割り込んでくるスタッシュの起源の話があり、びっくり。えっ、じゃあ、あの論文を書いた謎の日本人って、彼だったの?!
彼だったの?!――大事なことなので二度いいました。
表紙の絵は好きだけど、本書との関係は――よくわからない。
 『サイバー・コマンドー』 福田和代 祥伝社
『サイバー・コマンドー』 福田和代 祥伝社
9月に出た本。積ん読になっていて、やっと読んだ。ハッカーによるサイバー攻撃とその防衛、民間企業のセキュリティ対策レベルの話と思っていたら(いや、そういう面もあるけど)、それどころかもっと強烈な国家間のサイバー戦争の話だった。
サイバー戦争って、何となくアノニマスの攻撃みたいな、民間企業のサーバがダウンしてサイトがアクセスできなくなったりするのが、ちょっと大規模になった感じ、と思うだろう。そうじゃなく、本当に戦争に近い、大勢の死者が出たり、いつまでも日常生活に影響を及ぼす非常事態が続く、そんな致命的なものだということだ。何が怖いって、社会が隅々までコンピュータ化されている現在、通信、電力、交通、金融、物流、医療、ガス・水道といったほとんどあらゆるインフラが目に見える武器を使わない攻撃の対象となるのだ。
本書では、自衛隊のサイバー防衛隊に属する若い天才ハッカーの青年が、裏社会と関わるロシアの悪意あるハッカーとの戦いに嬉々として参じていた時、突然、日本全国で深刻な通信障害が発生し、全国の工場では原因不明な稼働率低下が起こる。そしてついに、新幹線が致命的な衝突事故を起こすような事態となる。サイバー防衛隊で活躍するのが、主人公のまだ未熟な面のある明神海斗と、アメリカのセキュリティ企業出身でめちゃくちゃ切れ者の、しかし謎も多い出原しのぶ。いやー、しのぶさんといえば、パトレイバーじゃないですか。そういえば要員構成も特車二課とよく似ている。
大変面白く読んだのだが、実は、本書はとても身につまされるものだった。実際、自分の関わっていた某社で、本書の主人公みたいな若い技術者が、悪意あるハッカーによる攻撃をリアルタイムに防御していくのを身近に体験したことがある。それにしても、あらかじめ仕込まれたマルウェアによるインフラ攻撃って、恐ろしいよね。今時のシステムって、オフショア開発なんて当たり前だし(色々規制はあれど、現場はいいかげんだ)。
ところで、通信インフラが障害で使えない状態で、交通網も満足に機能しないとき、対策ソフトを全国に配布するって、いったいどうやったのだろう。
 『オニキス』 下永聖高 ハヤカワ文庫
『オニキス』 下永聖高 ハヤカワ文庫
第一回ハヤカワSFコンテストの最終候補作「オニキス」を含む書き下ろし短篇集。5編が収録されている。
「オニキス」では、タイムマシンやタイムトラベルがなくても、過去の改変は自然の内に、ひっきりなしに行われているというアイデアが面白い。ただ、それだけだと無数の並行世界が自然に存在しているというだけのことで(意識や記憶の連続性がなければ、書き換えられていく世界の中での自己同一性が担保できない)、それを転移した後も「以前の」世界の記憶を少しだけ残せるという超技術を持ち出すことによって、並行世界を独立した存在ではなく、情報を引き渡すことができる連続性のあるものとして扱っている。ぼくの興味としては、本当はそこをもっとSF的に突き詰めて欲しかったと思うのだが。しかし「集合的無意識」なんて色んな意味で手垢のついた言葉を使うのには、もっと注意深くあるべきだろう。
ストーリー的に一番面白かったのは、「オニキス」と同じ世界観が出てくる「三千世界」だ。ここでは並行世界間の移動を、いかにもリアリティの乏しいナビというスマホみたいなガジェットを使い、どこでもドア的にゲートをくぐり抜けることで実現する。こうなるともうSF的な理屈を突っ込むのが野暮となる。ここではどうしようもなくせこい悪のキャラクターたちがだましだまされ、まさに三千世界を渡り歩いての追いかけっこを繰り返すわけだが、その変化した日本の描写がとても魅力的だ。とりわけ、巨大な鳥居のある並行世界の京都や、長野の小都市での祭の情景など、色とりどりの色彩が目に見え、和太鼓の音が聞こえてきそうな感覚がある。
「神の創造」も面白い。平凡な男のマンションの部屋の中、日常的な家具や食器などが散らかる中に、妖精発生装置という謎のガジェットによって、様々な小世界が発生する。もっともこのファンタジー世界と現実との関係がよくわからないのだが、幻覚みたいなものではなく、ある程度の物理的な相互作用をもつ存在らしい。それはともかく、ファンタジー世界も次第に一貫性をもってきて、独立したSF的、ファンタジー的な物語を語り始める。これが迫力があって面白く、それだけ独立したSFとして読みたかったと思わせる。思うに、これは作家と作品との関係性を暗示しているのだろう。もっともここでの「神」は本当に最小限の干渉しか及ぼすことはできないのだが。
「猿が出る」は日常の風景の中に、猿の幻影が現れ、それが次第に進化しつつ現実感を増していくという、幻想的なSF。普通に面白かったが、むしろあんまり理屈をつけないほうが良かったのでは。
「満月」は小品だが、もしかしたら作者の実体験が反映しているのかも知れない、スマトラ沖地震を題材にしたリアルと幻想の混淆する話。でも、このパラレルワールドに入り込んでしまったのかも知れないという感覚は、阪神大震災を経験したぼくにも納得のいくものである。
 『レッドスーツ』 ジョン・スコルジー 新ハヤカワSFシリーズ
『レッドスーツ』 ジョン・スコルジー 新ハヤカワSFシリーズ
シリーズものではなく、2012年の単独長編で、ヒューゴー賞とローカス賞の受賞作である。とはいえ、現代SFの先端を行くようなエッジのきいた作品ではなく、かといってガチガチのミリタリーSFや表紙から想像されるようなスペースオペラでもない。大文字で「SF」としか言えない作品だ。SFファンが大喜びし、かつSFをTVや映画やマンガで知ってはいるが、あまり読まない人にも勧められる、「面白くてひねりがあって感動的な」小説である。
いやあ、スコルジーって、本当にいいSF作家になったなあ。すっかりベテランの味が出てきた。どの作品も安心して読める。
話は〈スタートレック〉のような古いSFドラマのパロディとして始まる。25世紀、銀河連邦の宇宙艦隊旗艦イントレピッド号には、何かとんでもなくおかしなところがあった。科学探査や惑星間の紛争解決など、様々な任務におもむくイントレピッド号だが、艦長をはじめとする特定の上級士官たちはいつも危機一髪なところで助かるのに、名もない一般乗員たちは悲惨な死を迎える率が異常に高いのだ。新任少尉のダールは、その謎を解くべく、同期の仲間たちと調査を始める。
このあたりはまさに古いスペースオペラのパロディを見るようで、コミカルではあるが今どきのリアリティには乏しく(まさにそこが謎というわけだが)、スコルジーにしてはもう一つじゃないの、と思わせる(さすがにアクションは迫力満点だが)。ところがその謎が解明されるとびっくり。解説でもすでに「メタフィクション」という言葉が出ていて、勘のいい人にはそれだけでネタバレだとは思うが、うっかりすると「現代SF」になりそうなところを、そんなややこしさは一切感じさせずに、ひたすらストレートに話は進んでいく。
舞台が21世紀に移って、謎はいったん解決し、ハッピーエンドを迎える。ところが、ハッピーエンドのその後に、また別の観点からの物語が続く。それは人間的な「感動」の物語なのだが、感動の押し売りではなく、しみじみと「いい話」なのであって、前半のドタバタしたストーリーとつながると、何とも気持ちよく読み終えることができる。ちょっとあざといけど、うまいよね。訳者のブログによれば、これをTVドラマ化するという話もあるそうで、実現すればまさにメタメタやね。
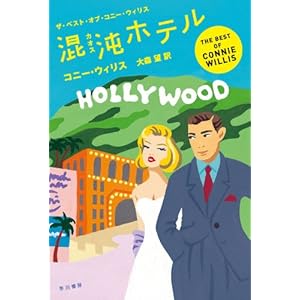 『混沌ホテル』 コニー・ウィリス ハヤカワ文庫
『混沌ホテル』 コニー・ウィリス ハヤカワ文庫
ヒューゴー賞・ネビュラ賞の受賞作のみを収録した短篇集THE BEST OF CONNIE WILLISの翻訳前編。ユーモア編という位置づけで5編が収録されている。後編『空襲警報』はシリアス編という位置づけだ。
表題作は「リアルトホテルにて」の改題・改訳。5編はいずれも既訳があるが、それぞれ作者のエッセイつき。
冒頭の献辞に「公共図書館に」とあって、まずはそこで関心し、にやりとする。つづく序文が、もう古いSFファン(ぼくのことだ)は感涙もの。ハインラインからはじまって、ディック、コーンブルース、ウィリアム・テン、キット・リード、シャーリイ・ジャクスン、ミルドレッド・クリンガーマン、ウォード・ムーア、そしてボブ・ショウ……。有名な名前もあるが、あまり知られていない、でも昔から読んできた人間には忘れられない名前が次々に出てくる。もうこれだけでうるうるしてしまう。
「混沌ホテル」と「インサイダー疑惑」はハリウッドもの。賑やかで華やかでドタバタで、背景に観客の笑いが絶えないテレビドラマのような作品だ。
とりわけ「インサイダー疑惑」は大好きな作品。アンチ・オカルト、アンチ・トンデモがテーマなのに、実在の懐疑論者の霊とチャネリングしてしまうという、とっても困った話だが、何よりも「現実とは思えないほど素晴らしい」ヒロインが魅力的で、とても楽しいロマンチック・コメディである。アンチ・オカルトなのに霊の存在が明らかになってしまうというパラドックスについては、正直あまりうまく解決しているとは思えない。ウィリスはこの作品に限らず、どうもSFが大好きな割にSF的なロジックの詰めが甘いというか、あんまり重視していないように思える。でもまあ、楽しいからかまわないのだ。
「混沌ホテル」は量子論コメディとあるが、そこを真剣に考えてはいけない。吉本風の繰り返しギャグと無茶ぶり(おっと、そこが量子論なのか)が楽しいのだ。
「女王様でも」は女性が生理から解放された近未来を扱いながら、家族や親族のコミュニケーションをテーマに、いささか戯画化された教条的フェミニスト(というか、これは何より自然がイチバンのトンデモ・エコロジストだろう)を肴にしたコメディだ。ここでも、非合理で排他的で、変化を認めない硬直した思考への、ウィリスの批判は一貫し徹底している。
後半の2編、「魂はみずからの社会を選ぶ」と「まれびとこぞりて」(SFM初出時は「もろびと大地に坐して」)は、面白かったけれども、文学的・文化的背景のないぼくには苦手なタイプの話だ。よく難しいハードSFで、わからないところは飛ばして読んでも面白いというが、わかったらもっと面白いんだろうな、と思うようなもので、悔しい感じがする。
「魂は――」は、詩人のエミリー・ディキンスンがウエルズの『宇宙戦争』に遭遇していた(火星人の侵略に出会っていた)ことを論証しようとするパロディ論文で、親切な注が原注・訳注ともたくさんついているのだが、それでも本当の面白さがよくわからないのは、ぼくが文学史や詩にうといせいだろう。もともと架空論文は好きなんだけどなあ。ル・グィンの「アカシア種子文書の著者をめぐる考察」なんか大好きだったし。
「まれびとこぞりて」はウィリスおとくいのクリスマス・ストーリーで、聖歌隊の歌声が謎めいたアルタイル星人とのファースト・コミュニケーションを果たす話。ここでも人の話を聞かない登場人物たちとのディスコミュニケーションが笑いを呼ぶ構造になっている。人間同士で会話できないのに、異星人との意思疎通ができるわけないよね。何をしているのかさっぱりわからない、いつも怒っているような表情のアルタイル人たちがいい。怖い叔母さんに例えられているけど、ハシビロコウみたいと思った。だけどこの作品のポイントは、聖歌や聖書の言葉にどれだけ意味をのせ、ずらし、遊ぶかというところにあるので、やっぱり置いてけぼり感が残ってしまうのだ。
それにしても、ウィリスは大長編もいいけど、疲れるので、こういう中短篇の方が好きだな。
 『ファースト・サークル』 坂本壱平 ハヤカワ文庫
『ファースト・サークル』 坂本壱平 ハヤカワ文庫
第一回ハヤカワSFコンテスト最終候補作の長編。これで出版されたハヤカワSFコンテストは全部読んだぞ。
SFというよりはかなり私的なタイプの幻想小説なのだが、トポロジー的な並行世界を思わせたり、数字の噴き出すシミュレーション宇宙を思わす場面があったりと、部分的にはSF的な要素もある。
大きくは2つの物語が語られており、ひとつはテレビを見ていたら、複雑で奇妙な手拍子に導かれ、頭をなくして胴体だけの存在になった(でも目も見えるし、内面的には少しも変わらない)私が、警官の格好をした奇怪な二人組と、言葉を話す黒猫と共に、自分の頭を見つけようとする話。
もうひとつは、精神科医の満ちるの話。入院していた少年の手のひらに突然穴が空き、そこからどことも知れない青空が見えるようになる。少年の主治医と共に、満ちるたちはやはり奇妙な手拍子のリズムに誘われ、病院の屋上から謎の空間へと飛ばされる。そこにはずっと前に死んだ満ちるの愛犬がいた。
ファースト・サークルという言葉とともに、ふたつの物語はやがて重なり合う。登場人物はほぼこれだけであり、手拍子の音以外は静かで、ほとんど何もなく何も起きないシュールな世界が描かれる。大きな白い大きな犬と小さな黒猫、ドーナツの穴にドーナツ自身が吸い込まれていくような、崩壊するファースト・サークル。時おりの情景描写にははっとするような美しさがある。ただ、語り口は、特に首無し男のナレーションは、くどくどと自己韜晦して冗長で、一言でいえば面倒くさい。
物語の基底にあるのは、つまらない日常的な作業からの逃避、逃走であり、しかし登場人物たちはその先にある世界を本当に目指し、信じているわけでもない。だから最後は日常に回帰してしまう。たとえ小さなバグがそこに存在しているとしても、それはやはり日常であり、本当にそれでよかったのかと思ってしまう。
「ファースト・サークル」というタイトルと、複雑な手拍子のリズムというと、パット・メセニー・グループの代表曲「ファースト・サークル」である。ネットで検索すると本書と同じくらいヒットするのですぐわかる。手拍子についてはここの解説が詳しいです。
で、そういう複雑なリズムが異世界へ誘うというのはいいとして、それがどうして「私」や「満ちる」を、主治医や少年を、犬や猫を同じ世界の創成に立ち向かわせるのかというところが、何の説明もなく、いや説明はなくてもいいけど、読者を納得させるようなイメージなりダイナミクスなりが描き切れていないので、もうひとつ物足りない。しかし、デビュー長編でここまで書けるなら、期待大といっていいでしょう。
THATTA 310号へ戻る
トップページへ戻る
 『戦いの虚空 老人と宇宙5』 ジョン・スコルジー ハヤカワ文庫
『戦いの虚空 老人と宇宙5』 ジョン・スコルジー ハヤカワ文庫