 結城充孝『躯体上の翼』は書きたいところだけ書いたという意味で潔い1冊。生体兵器の少女が唯一言葉で繋がることのできた相手の居場所を守る為に孤独な戦いを延々と続ける。ロマンチックといえばロマンチック。作品世界の設定やヒロインの持つ情念はSF的なアニメやラノベから生まれてきているようにおもえる。プロローグが示す面白そうな展開にはなっていないが、それは無いものねだりかな。
結城充孝『躯体上の翼』は書きたいところだけ書いたという意味で潔い1冊。生体兵器の少女が唯一言葉で繋がることのできた相手の居場所を守る為に孤独な戦いを延々と続ける。ロマンチックといえばロマンチック。作品世界の設定やヒロインの持つ情念はSF的なアニメやラノベから生まれてきているようにおもえる。プロローグが示す面白そうな展開にはなっていないが、それは無いものねだりかな。|
続・サンタロガ・バリア (第140回) |
前回、菊池さんの「SFから遠く離れて」とビートルズ話がシンクロしたのにはビックリ。あのモノ・ボックスが出た当時もの凄い評判になっていたのは確か。ステレオ盤セットよりも枚数が少ない(「アビー・ロード」のモノ・ミックスがない)のにお値段ははるかに高かった。でも評論家達はモノ・ボックスを絶賛していた。まあ、こちらにはあまり関係なかったので、フーンという程度だったけれど。
前回ビートルズのCDは買ってないと書いた後で、CD棚を見ていたら「BBCライヴ」の十字屋のバッタモンと「ビートルズ・アンソロジー1」があった。「BBC」は昔奥さんが誕生日にくれたモノで、貰った時はちょっと間違ってるぜと思ったっきり全く聞いてなかったし、「アンソロジー1」は仕事場のアルバイト女子がベスト盤と思って間違って買っちゃいましたというので買ってあげたけれど、そのまま棚に入れたままになった。今聴いてみると、どちらも結構楽しく聴ける。ライヴ・バンドとしての初期ビートルズにはパワーがある。でも、ここでもやっぱり黒人音楽っぽさはあまり感じられないんだなあ。それが世界中で受け入れられやすかった理由なのかも。
コスト・パフォーマンスが高かった廉価版は「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド」買った後、店から消えてしまったので、HMVで輸入盤の「ホワイトアルバム/ビートルズ」を買ってみたのだけれど、なぜか面白さが足りない。値段的には廉価版より少し安いけれど楽しくないんだなあ。国内版であの値段でビートルズ・クラブの解説があるところが魅力だったのか。「ホワイトアルバム」を聴いたら、バンドとしての活力は「サージェント・・・」で終わっている様な気もするし、とりあえずビートルズはこれで打ち止め。
キング・クリムゾンのコレクターズ・シリーズが4枚まとめて出たので聴いてみたけれど、こちらもイマイチ燃えない。6人編成クリムゾンのラスト・ライヴなんか、本来感涙モノのはずなんだけどなあ。初めて聴いた「ザ・パワー・トゥ・ビリーヴ」ツアー・ライヴは面白かったけど。その点ロックにしろクラシックにしろパワフルな音楽を聴いた後で、パク・キュヒの「最後のトレモロ」アルバムから数曲聴くと、興奮が売りの音楽の後で熱気をスゥーっと冷ましてくれる。次のアルバムが待ち遠しい。
 結城充孝『躯体上の翼』は書きたいところだけ書いたという意味で潔い1冊。生体兵器の少女が唯一言葉で繋がることのできた相手の居場所を守る為に孤独な戦いを延々と続ける。ロマンチックといえばロマンチック。作品世界の設定やヒロインの持つ情念はSF的なアニメやラノベから生まれてきているようにおもえる。プロローグが示す面白そうな展開にはなっていないが、それは無いものねだりかな。
結城充孝『躯体上の翼』は書きたいところだけ書いたという意味で潔い1冊。生体兵器の少女が唯一言葉で繋がることのできた相手の居場所を守る為に孤独な戦いを延々と続ける。ロマンチックといえばロマンチック。作品世界の設定やヒロインの持つ情念はSF的なアニメやラノベから生まれてきているようにおもえる。プロローグが示す面白そうな展開にはなっていないが、それは無いものねだりかな。
 なんかえらく間が空いた日下三蔵編『日本SF全集3 1978〜1984』は、これまで読まずにいた作家が多く収録された巻。新井素子のデビュー作は初めて読んだ。当時これを小松左京や筒井康隆が評価するのは難しかったろうなと、いまにして思う。小松・筒井にとってこの内容は、このふたりが築き上げてきた技量に対して失礼なレベルというようなものだったかもしれない。しかし星新一は内容ではなく、いや内容も含めて、この感性と文体に感心してみせた。それは小松・筒井には引っかからない何かだったわけだ。30年以上も経ってしまうと、当時の新鮮な文体はその用字や言葉遣いが中途半端に古い。
なんかえらく間が空いた日下三蔵編『日本SF全集3 1978〜1984』は、これまで読まずにいた作家が多く収録された巻。新井素子のデビュー作は初めて読んだ。当時これを小松左京や筒井康隆が評価するのは難しかったろうなと、いまにして思う。小松・筒井にとってこの内容は、このふたりが築き上げてきた技量に対して失礼なレベルというようなものだったかもしれない。しかし星新一は内容ではなく、いや内容も含めて、この感性と文体に感心してみせた。それは小松・筒井には引っかからない何かだったわけだ。30年以上も経ってしまうと、当時の新鮮な文体はその用字や言葉遣いが中途半端に古い。
栗本薫のグインサーガものを読むのは初めてだったが、びっくりさせられたのはそのひらがなの使い方だった。そうかこういう風にひらがなを使ってこの国籍不明なファンタジーを紡いでいたのか。バタ臭い線のマンガを思い出した。リーダビリティの高速化と王道というかデータベースというか、そのようにして取り出されるプロットが人気の秘密か。
この巻の収録作はいわゆる50年代アメリカSF短編を髣髴とさせるモノが多い。その頂点が水見稜「オーガニック・スープ」だろう。これが50年代後半または60年代前半のF&SFか「ファンタスティック」誌から訳されたといわれても信じてしまいそうな出来具合。いまでもこのまま英訳してアメリカのアンソロジーに入れられそうだ。
集中一の強力作はやはり野阿梓「花狩人」で、初読時の印象はもう忘れたけれど、今回読んでイメージの凝集力に感心した。話の運びはいまひとつピンとこないところもあるし、単純にのめり込むことはできないけれど、インパクトは強い。
巻末座談会では牧真司のツッコミが楽しい。
 第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作のうちハヤカワSFシリーズJコレクションから出た小野寺整『テキスト9』は、その一種イージーな文体と物語と、タイトルの強面(メタフィクション的仕掛け)がミスマッチな1作。ずっと付きまとう変な感じは『みずは無間』や『ファースト・サークル』とよく似ている。これらの作品は個人的なリアリティのウラオモテ/客観現実の固さと脆さを捉える感性においてある程度共通認識があるんじゃないかと思う。現実は脳が翻訳している世界の表象だが、人間同士のコミュニケーションもそうなのか。科学理論はミクロもマクロも解析してその物質世界の成り立ちを解いていくが、自己言及を免れ得ない意識同士の関係は結局世界対個人に置き換えられてしまうのか。「テキスト9」ねえ。
第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作のうちハヤカワSFシリーズJコレクションから出た小野寺整『テキスト9』は、その一種イージーな文体と物語と、タイトルの強面(メタフィクション的仕掛け)がミスマッチな1作。ずっと付きまとう変な感じは『みずは無間』や『ファースト・サークル』とよく似ている。これらの作品は個人的なリアリティのウラオモテ/客観現実の固さと脆さを捉える感性においてある程度共通認識があるんじゃないかと思う。現実は脳が翻訳している世界の表象だが、人間同士のコミュニケーションもそうなのか。科学理論はミクロもマクロも解析してその物質世界の成り立ちを解いていくが、自己言及を免れ得ない意識同士の関係は結局世界対個人に置き換えられてしまうのか。「テキスト9」ねえ。
 同じく第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作となった短編を表題作とした短編集が下永聖高『オニキス』。こちらはハヤカワ文庫JAから出た。表題作はアイデアがすっきりしていて候補作中一番わかりやすい。他の収録作も一つのアイデアをしつこく展開して見せて、読者に作者が想う世界の成り立ちを伝えようとする。その意味では昔のSFが持っていたアイデア・ストーリーの現在形とも言える。ただそのキーワードが平行世界であったり、自分だけに見える何かであったりすることで、他の候補作や受賞作の作者に通じる感性が作品世界に漂っているのだ。巻末の「満月 フル・ムーン」は作者の体験だけで書かれている様な作品だが、ここにも他の4編と共通する現実の捉え方が窺える。
同じく第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作となった短編を表題作とした短編集が下永聖高『オニキス』。こちらはハヤカワ文庫JAから出た。表題作はアイデアがすっきりしていて候補作中一番わかりやすい。他の収録作も一つのアイデアをしつこく展開して見せて、読者に作者が想う世界の成り立ちを伝えようとする。その意味では昔のSFが持っていたアイデア・ストーリーの現在形とも言える。ただそのキーワードが平行世界であったり、自分だけに見える何かであったりすることで、他の候補作や受賞作の作者に通じる感性が作品世界に漂っているのだ。巻末の「満月 フル・ムーン」は作者の体験だけで書かれている様な作品だが、ここにも他の4編と共通する現実の捉え方が窺える。
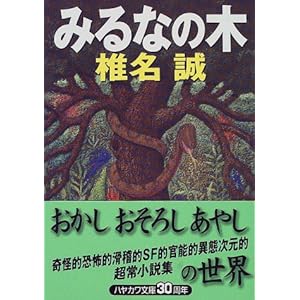 突然読む気になって積ん読棚から取り出したのは、椎名誠『みるなの木』。2000年4月発行のハヤカワ文庫JA。250ページの薄い短編集で14編を収録して1編1編も短いのだが、そこに現れる世界はかなり鞏固なイメージを持っている。特に作者が長編『武装島田倉庫』の世界を使って書いたという90年代前半の作品が素晴らしい。言葉遣いもまるで酉島伝法のご先祖様みたいだ。と、絶賛しながらも椎名誠の他の作品が読みたくなるかというとそうでもないところが、この作家に対して何かしら疎遠なモノを感じているということだろう。好きな作品集だが、好きな作家とは限らないということか。
突然読む気になって積ん読棚から取り出したのは、椎名誠『みるなの木』。2000年4月発行のハヤカワ文庫JA。250ページの薄い短編集で14編を収録して1編1編も短いのだが、そこに現れる世界はかなり鞏固なイメージを持っている。特に作者が長編『武装島田倉庫』の世界を使って書いたという90年代前半の作品が素晴らしい。言葉遣いもまるで酉島伝法のご先祖様みたいだ。と、絶賛しながらも椎名誠の他の作品が読みたくなるかというとそうでもないところが、この作家に対して何かしら疎遠なモノを感じているということだろう。好きな作品集だが、好きな作家とは限らないということか。
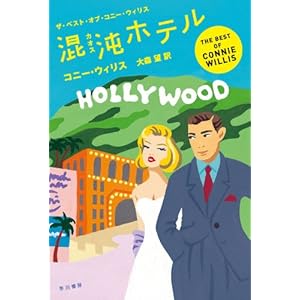 今月も翻訳成分が足りないと思いつつ、読んだのがコニー・ウィリス『混沌ホテル』では、なにをかいわんやである。まあ、再読ばかりだし、読めば面白いのは分かっているのだが、その面白さが歯がゆさにも繋がる。「まれびとこぞりて」なんかがその典型。異星人の表情や単純な動きには言及されるものの異星人の具体的なイメージはなく、人間側のテンヤワンヤだけが描かれ、それが面白いんだがそれだけだ。それで十分、まだほかに必要なものがあるか、といわれりゃ文句の付けようもない。でもなあ・・・。
今月も翻訳成分が足りないと思いつつ、読んだのがコニー・ウィリス『混沌ホテル』では、なにをかいわんやである。まあ、再読ばかりだし、読めば面白いのは分かっているのだが、その面白さが歯がゆさにも繋がる。「まれびとこぞりて」なんかがその典型。異星人の表情や単純な動きには言及されるものの異星人の具体的なイメージはなく、人間側のテンヤワンヤだけが描かれ、それが面白いんだがそれだけだ。それで十分、まだほかに必要なものがあるか、といわれりゃ文句の付けようもない。でもなあ・・・。
 ということで読んだのが、シギズムンド・クルジジャノフスキイ『未来の回想』。もう充分に話題になった作品なので、ビックリ度が下がってしまったのは残念だったけれど、東欧的/ソヴィエト的寒さがたっぷり感じられて、その点では満足の1冊。作者は、たぶん発表さえできないということを予想しながらも、ウェルズの向こうを張って時間旅行ものを書こうという意欲が湧いてくるのを止められず、そして書いてしまった。エンターテインメントとして読むのが本来の作品だったかもしれないけれど、作者が主人公の運命に自らを重ねずにはいられなかったろうと思うと、ここに持ち帰られた未来の記憶の抹殺がフィクション以上の効果を持つ。
ということで読んだのが、シギズムンド・クルジジャノフスキイ『未来の回想』。もう充分に話題になった作品なので、ビックリ度が下がってしまったのは残念だったけれど、東欧的/ソヴィエト的寒さがたっぷり感じられて、その点では満足の1冊。作者は、たぶん発表さえできないということを予想しながらも、ウェルズの向こうを張って時間旅行ものを書こうという意欲が湧いてくるのを止められず、そして書いてしまった。エンターテインメントとして読むのが本来の作品だったかもしれないけれど、作者が主人公の運命に自らを重ねずにはいられなかったろうと思うと、ここに持ち帰られた未来の記憶の抹殺がフィクション以上の効果を持つ。
 翻訳成分の補給ということでまたブラッドベリに手を出しかけたが、思い直してチャールズ・ボーモント『予期せぬ結末2 トロイメライ』を読む。ボーモントの持ち味はある程度知っているので、ここに集められた短編を愉しく読んでいたのだけれど、「集合場所」以下の後半5編を読んで、ボーモントの暗い情念がひどく応えた。青少年時代を50年代に過ごし、ヴェトナム戦争に深入りするアメリカと自らの健康状態に強い不安を持ちながら、1967年に38歳で他界したボーモント。なんかC・M・コーンブルースを思い出した。
翻訳成分の補給ということでまたブラッドベリに手を出しかけたが、思い直してチャールズ・ボーモント『予期せぬ結末2 トロイメライ』を読む。ボーモントの持ち味はある程度知っているので、ここに集められた短編を愉しく読んでいたのだけれど、「集合場所」以下の後半5編を読んで、ボーモントの暗い情念がひどく応えた。青少年時代を50年代に過ごし、ヴェトナム戦争に深入りするアメリカと自らの健康状態に強い不安を持ちながら、1967年に38歳で他界したボーモント。なんかC・M・コーンブルースを思い出した。
 SFを離れると、まずはノンフィクションのつもりで読み始めて、第2話を読むまでそれが小説だったことに気がつかなかった帚木蓬生『蠅の帝国 軍医達の黙示録』。手記の書き手の名前がないのがおかしいと思い、巻末解説を読んではじめて短編集であることをしりちょっとショックだった。
SFを離れると、まずはノンフィクションのつもりで読み始めて、第2話を読むまでそれが小説だったことに気がつかなかった帚木蓬生『蠅の帝国 軍医達の黙示録』。手記の書き手の名前がないのがおかしいと思い、巻末解説を読んではじめて短編集であることをしりちょっとショックだった。
医大を出たばかりの若き軍医達の経験を数多くの軍医たちの手記を基にした短編が15編。手記集を編集した経験からすると、知的な一人称が物語る言葉はあまりにも整いすぎていて肩透かしを食らったが、語られた内容そのものからは、北方領土から沖縄までの内地や中国大陸から南洋までの外地の体験がよくわかる。かれらは生還した。そしてその経験を書いた。それらはより届きやすい言葉に直されてここに収められた。それ以上にいうことはない。
ちなみに親父は戦中短い間だったが陸軍軍医をしていた。その時のことは滅多に口にしなかったが、山田風太郎が数年違いの後輩だったらしい。
 由良君美『みみずく古本市』が文庫で出たので読んだ。学生時代に気にはなったが素通りした由良君美。読んでみると、やはり学生時代に気にはなったが素通りした書物が数多く取り上げられている。クルティウスとかケネス・バークとか日夏耿之介とか。読んでいた本もいくつかある。林達夫とかコルタサルとか山口昌男とか蓮實重彦とか。実際はここに取り上げられたほとんどは、名前だけ知っていて読まなかった本ばかりといっていいんだけれど、それでも70年代半ばに大学生協の本屋で眺めたタイトルが並んでいて懐かしい。今さら読めないのは確かだが。生田耕作といい由良君美といい篠田一士を口を極めて罵っているのがおかしい。篠田一士が参加した集英社の『世界文学全集』がなかったら、学生時代にラテンアメリカ文学を読むことはなかったかもしれない。
由良君美『みみずく古本市』が文庫で出たので読んだ。学生時代に気にはなったが素通りした由良君美。読んでみると、やはり学生時代に気にはなったが素通りした書物が数多く取り上げられている。クルティウスとかケネス・バークとか日夏耿之介とか。読んでいた本もいくつかある。林達夫とかコルタサルとか山口昌男とか蓮實重彦とか。実際はここに取り上げられたほとんどは、名前だけ知っていて読まなかった本ばかりといっていいんだけれど、それでも70年代半ばに大学生協の本屋で眺めたタイトルが並んでいて懐かしい。今さら読めないのは確かだが。生田耕作といい由良君美といい篠田一士を口を極めて罵っているのがおかしい。篠田一士が参加した集英社の『世界文学全集』がなかったら、学生時代にラテンアメリカ文学を読むことはなかったかもしれない。
 考古学をやっている息子がオヤジの積ん読本の上に放り投げていたので、読んでみたのが岡谷公二『神社の起源と古代朝鮮』平凡社新書。どっかで聞いた名前だなあと思ったらミッシェル・レリス『幻のアフリカ』とかレーモン・ルーセル『ロクス・ソルス』の訳者だった。本業は民俗学系の研究者らしい。この新書は、神社の起源を求めて新羅系神社を北陸や琵琶湖周辺、奈良を含めて出雲や九州を巡り、朝鮮半島南部にたどり着くというもの。神社は社ではなく、森に囲まれた場所そのものだというのがどうやらそれらしき結論で、言われてみれば、厳島神社のある宮島でも、古くは島そのものがご神体だったと観光客相手のパンフで簡単に解説されているんだが、まともに考えた事はなかったなあ。
考古学をやっている息子がオヤジの積ん読本の上に放り投げていたので、読んでみたのが岡谷公二『神社の起源と古代朝鮮』平凡社新書。どっかで聞いた名前だなあと思ったらミッシェル・レリス『幻のアフリカ』とかレーモン・ルーセル『ロクス・ソルス』の訳者だった。本業は民俗学系の研究者らしい。この新書は、神社の起源を求めて新羅系神社を北陸や琵琶湖周辺、奈良を含めて出雲や九州を巡り、朝鮮半島南部にたどり着くというもの。神社は社ではなく、森に囲まれた場所そのものだというのがどうやらそれらしき結論で、言われてみれば、厳島神社のある宮島でも、古くは島そのものがご神体だったと観光客相手のパンフで簡単に解説されているんだが、まともに考えた事はなかったなあ。
新羅については、古代に先進技術を持った人々が朝鮮半島から日本に何度も渡ってきたことは当然で、その名残がいまでも各地に見られることもわかるが、その前から日本に住んでいた人々は神様をどう祀っていたんだろうか。やはりご神体は不在で岩座などを神聖視していたのか。
 幕末系では家近良樹『江戸幕府崩壊 孝明天皇と「一会桑」』が面白かった。これまで薩長の倒幕という視点で語られてきた明治維新に向かう歴史の流れを、孝明天皇を中心とした宮中政治と京都にいる会津/松平容保とその弟率いる桑名藩そして一橋慶喜に焦点を当てて読み解くというもの。元は新書だったこともあり、説明不足で食い足りないところもあるけれど、ついに薩長/明治政府が喧伝した倒幕神話に異議を申し立て、その神話によって何が覆い隠されたかを説き始めたという点で画期的な読み物になっている。ようやく薩長の増長慢が明治以降の夜郎自大意識を日本にもたらしたと、まだ弱腰ながら表明したことは素晴らしい。
幕末系では家近良樹『江戸幕府崩壊 孝明天皇と「一会桑」』が面白かった。これまで薩長の倒幕という視点で語られてきた明治維新に向かう歴史の流れを、孝明天皇を中心とした宮中政治と京都にいる会津/松平容保とその弟率いる桑名藩そして一橋慶喜に焦点を当てて読み解くというもの。元は新書だったこともあり、説明不足で食い足りないところもあるけれど、ついに薩長/明治政府が喧伝した倒幕神話に異議を申し立て、その神話によって何が覆い隠されたかを説き始めたという点で画期的な読み物になっている。ようやく薩長の増長慢が明治以降の夜郎自大意識を日本にもたらしたと、まだ弱腰ながら表明したことは素晴らしい。