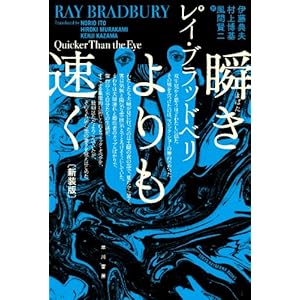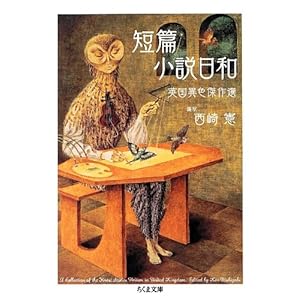歳のせいか何ということもなく気分が沈んでいる。ダウナー気分にはダウナーな曲をぶつけようと、ついにフルトヴェングラーの「トリスタンとイゾルデ」に手が伸びる。「前奏曲と愛の死」だけは生演奏でも録音でも聴いたことがあったけれど、全曲を聴いたのは初めてだ。
歳のせいか何ということもなく気分が沈んでいる。ダウナー気分にはダウナーな曲をぶつけようと、ついにフルトヴェングラーの「トリスタンとイゾルデ」に手が伸びる。「前奏曲と愛の死」だけは生演奏でも録音でも聴いたことがあったけれど、全曲を聴いたのは初めてだ。
今年2月に出た岩波文庫リクエスト復刊にワアグナア作『ロオエングリイン トリスタンとイゾルデ』があったので、これを片手に一晩1幕ずつ3日かけて聴いた。ちなみに文庫は1953年初刷の旧かな旧漢字で、字が小さい上に印刷がかすれている。
「トリスタンとイゾルデ」の話自体は学生時代一般教養のフランス文学(単位落とした)で読んだけれど、ほとんど何も覚えていない。むしろゼラズニイの『ドリーム・マスター』の下敷きという方で覚えている。あらためて訳本でワーグナーの台本を読んでみると、誘拐同様に勝利国の王様に嫁がされる王女イゾルデが、自分の許嫁を殺した英雄トリスタンに死の薬を呑ませ自分も死のうとしたが、侍女の策略でふたりとも愛の妙薬を飲んでしまったため、悲劇の悲劇が始まるというもの。
訳者解説を読むとこのときワーグナーは故郷を追い出されて、逃亡先で妻がワーグナーマニアの夫婦(夫は40で妻は23)に引き取られ、そこの別宅に住んでいた。当然のことながらワーグナーは崇拝者の若妻と懇ろになるも夫は見て見ぬふり。しばらく夫の前で不倫を続けていたワーグナーだったが、最後には若妻の元を離れていった。その経験がそのまま楽劇に持ち込まれているという。なんともまあ、いい気なもんだが、作品自体はそんな事情に影響されることなく勝手に生き延びてきたわけだ。ちなみにワーグナーはこの若妻が作った詩に曲を付けている。
イギリスのフィルハーモニア・オーケストラを振った1952年のフルトヴェングラーの演奏は、いかにもな響きを湛えていて、狂気の台詞回しで泣き叫ぶ歌手たちの官能と嘆きを包み込む。もう一回聴きたいかというと微妙。初めて聴く全曲版がフルトヴェングラーというのは止めた方がいいかも。30年くらい前にクライバー(息子の方)やバーンスタインのが出た時は金が無くて買えなかったけれど、今はネットで安く買えそうだから、その内聴いてみよう。
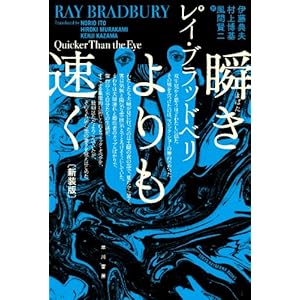 先月から翻訳成分が足りないと手を出したのが、積ん読のレイ・ブラッドベリ『瞬きよりも速く』。以前読んだ『ふたりがここにいる不思議』と同様、ブラッドベリらしい短編の味が楽しめる。個々の作品の出来はいろいろだけれど、伝記とインタビューを読んだ後だから、どれもそういう風にアイデアが生まれ言葉がわき上がってくる過程として読むことができる。ブラッドベリ自身が後書きで収録作品の多くについて解説しているけれど、読んでいて感じるのは言葉を連ねるブラッドベリ独特のパターンがあるということ。具体的にどういう風にとかまでは考えられないが、一連のサーカスものやSFらしいアイデア・ストーリーなどに使われている言葉は、ブラッドベリ自身が言うように広大な知識からではなく、何か無意識的な言葉のコレクションからの選択が働いているように見える。まあ、そのような言葉に対する感覚がなければ作家にはなれないのだろうけれど、ブラッドベリ語彙集みたいなものがあるのは確かだ。集中のベストといった作品はないけれど、冒頭の精神分析医を茶化した「Uボート・ドクター」、それに続くアイデア・ストーリー「ザハロフ/リヒタースケールV」で楽しい気分が湧いてきたらそのまま21編を最後まで愉しめる。
先月から翻訳成分が足りないと手を出したのが、積ん読のレイ・ブラッドベリ『瞬きよりも速く』。以前読んだ『ふたりがここにいる不思議』と同様、ブラッドベリらしい短編の味が楽しめる。個々の作品の出来はいろいろだけれど、伝記とインタビューを読んだ後だから、どれもそういう風にアイデアが生まれ言葉がわき上がってくる過程として読むことができる。ブラッドベリ自身が後書きで収録作品の多くについて解説しているけれど、読んでいて感じるのは言葉を連ねるブラッドベリ独特のパターンがあるということ。具体的にどういう風にとかまでは考えられないが、一連のサーカスものやSFらしいアイデア・ストーリーなどに使われている言葉は、ブラッドベリ自身が言うように広大な知識からではなく、何か無意識的な言葉のコレクションからの選択が働いているように見える。まあ、そのような言葉に対する感覚がなければ作家にはなれないのだろうけれど、ブラッドベリ語彙集みたいなものがあるのは確かだ。集中のベストといった作品はないけれど、冒頭の精神分析医を茶化した「Uボート・ドクター」、それに続くアイデア・ストーリー「ザハロフ/リヒタースケールV」で楽しい気分が湧いてきたらそのまま21編を最後まで愉しめる。
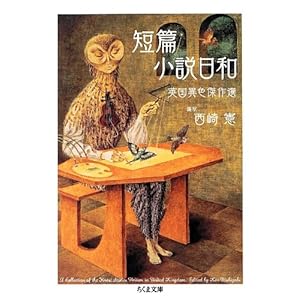 翻訳成分が足りないので読んだもう1冊が西崎憲編訳『短編小説日和 英国異色傑作選』。ディケンズを除けば、20世紀前半に書かれた作品が多く、50年代60年代の作品も収録している。作品の方向性は一見てんでんばらばらのようだけれど、ファンタジーやホラーに分類されるものも多く採られている。ディケンズからしてホラーだ。ここに収められた短編を読んでいると、ブラッドベリが書きそうなタイプのファンタジーも数編あるが、しかしブラッドベリは20世紀アメリカの作家であることがよくわかる。L・P・ハートリー「コティヨン」あたりはいかにもブラッドベリが書きそうな幽霊譚たが、感触は大分違う。集中SFファンに知られた作品はジェラルド・カーシュ「豚の島の女王」だろう。サーカスの一団にいた四肢欠損美少女とこびとコンビに気の優しい大男が無人島で暮らすこの話は初めて読んだ筈だが、もはや初めてとは思えない。
翻訳成分が足りないので読んだもう1冊が西崎憲編訳『短編小説日和 英国異色傑作選』。ディケンズを除けば、20世紀前半に書かれた作品が多く、50年代60年代の作品も収録している。作品の方向性は一見てんでんばらばらのようだけれど、ファンタジーやホラーに分類されるものも多く採られている。ディケンズからしてホラーだ。ここに収められた短編を読んでいると、ブラッドベリが書きそうなタイプのファンタジーも数編あるが、しかしブラッドベリは20世紀アメリカの作家であることがよくわかる。L・P・ハートリー「コティヨン」あたりはいかにもブラッドベリが書きそうな幽霊譚たが、感触は大分違う。集中SFファンに知られた作品はジェラルド・カーシュ「豚の島の女王」だろう。サーカスの一団にいた四肢欠損美少女とこびとコンビに気の優しい大男が無人島で暮らすこの話は初めて読んだ筈だが、もはや初めてとは思えない。
戦前の短編は、ちょっとした不可解さが持ち味のものが多いが、50年代60年代の短編となるとどれも現代的な狂気を孕んでいて、50年という時間を感じさせない。年代の如何に関わらず、個々の短編は印象的で、当然といえば当然だけれど、西崎憲自身の小説とどこか繋がっているような気がする。編訳者による「英国短編小説史」と「短編小説とは何か?」はどちらも読み応えがある。なお、この本は今年3月に出た筒井康隆の『60年代日本SFベスト集成』と同時配本の筑摩文庫。
 翻訳小説の新刊としては割と期待して読んだウラジーミル・ソローキン『親衛隊士の日』は十分期待に応える1作。250ページしかないので、『青い脂』に比べれば長中編といった分量だけれど、中身は相変わらずこってりとしている。話は、皇帝が君臨する2028年のロシア帝国で、皇帝直属親衛隊の中核を成す集団のひとりが語る親衛隊活動報告である。やることなすこと暴力の限りで、集団の団結を高める儀式がまた奇怪至極。それが一人称で語られるのだから、今の日本のエンターテインメント小説界の常識ではまず出てこない類のエグさがある。たぶんロシア以外では現れないような強靱な精神を持つ作者ならではということなのだろう。洗練と野蛮を脂で練り混ぜたような作品世界がもつ熱量は半端無い。
翻訳小説の新刊としては割と期待して読んだウラジーミル・ソローキン『親衛隊士の日』は十分期待に応える1作。250ページしかないので、『青い脂』に比べれば長中編といった分量だけれど、中身は相変わらずこってりとしている。話は、皇帝が君臨する2028年のロシア帝国で、皇帝直属親衛隊の中核を成す集団のひとりが語る親衛隊活動報告である。やることなすこと暴力の限りで、集団の団結を高める儀式がまた奇怪至極。それが一人称で語られるのだから、今の日本のエンターテインメント小説界の常識ではまず出てこない類のエグさがある。たぶんロシア以外では現れないような強靱な精神を持つ作者ならではということなのだろう。洗練と野蛮を脂で練り混ぜたような作品世界がもつ熱量は半端無い。
ところで、SF翻訳者の若手が育っていないという話はよく聞くが、この本の訳者松下隆志さんは1984年生まれでまだ20代。北大博士課程在籍のロシア文学研究者ということで、専業翻訳者じゃないけれど、うらやましいね。
 なぜ「ハローサマー、グッドバイ2」のサブタイトルがないのか、ちょっと疑問なマイクル・コーニイ『パラ−クシの記憶』は、前作のような新鮮さはない代わりによりオーソドックスなSFの形態を持った作品。主人公がかいくぐる多くの危機は、本来ならもっと厳しい苦難もしくは挫折をもたらしそうなものだけれど、そこらへんはヤングアダルト小説的なご都合主義が感じられるところ。SF的アイデアとその説明及び解決はスッキリしていて昔懐かしい感じがする。このシリーズの最大の謎の一つであった主人公たちの種族の出自が明かされ、それを乗り越えていく決意で閉じられる物語はコーニイの遺作にふさわしい。若い読者が手にとって欲しい作品だけれど、それにしてもなぜ「ハローサマー…
なぜ「ハローサマー、グッドバイ2」のサブタイトルがないのか、ちょっと疑問なマイクル・コーニイ『パラ−クシの記憶』は、前作のような新鮮さはない代わりによりオーソドックスなSFの形態を持った作品。主人公がかいくぐる多くの危機は、本来ならもっと厳しい苦難もしくは挫折をもたらしそうなものだけれど、そこらへんはヤングアダルト小説的なご都合主義が感じられるところ。SF的アイデアとその説明及び解決はスッキリしていて昔懐かしい感じがする。このシリーズの最大の謎の一つであった主人公たちの種族の出自が明かされ、それを乗り越えていく決意で閉じられる物語はコーニイの遺作にふさわしい。若い読者が手にとって欲しい作品だけれど、それにしてもなぜ「ハローサマー…
 国内に移ると、松崎有理『代書屋ミクラ』が、一部に森見登美彦を思わせるギャグを噛ませながら、東北大学をモデルにした大学町を舞台に、まったりとしたポスト学生時代のモラトリアム生活を描いている。それは『NOVA6』に掲載された連作第1作の持ち味であり、連作全体を覆う雰囲気でもある。その中で、主人公が実家に帰った時のエピソードである「ぼくのおじさん」がやや異色。話のパターンは他の収録作同様だけれど、脳内お守り「アカラ様」と主人公のルーツが語られているところがミソ。これを書いてしまうと、「モラトリアム生活の終わり」になって、繰り返される永遠の1日が終わらざるを得なくなってしまう。
国内に移ると、松崎有理『代書屋ミクラ』が、一部に森見登美彦を思わせるギャグを噛ませながら、東北大学をモデルにした大学町を舞台に、まったりとしたポスト学生時代のモラトリアム生活を描いている。それは『NOVA6』に掲載された連作第1作の持ち味であり、連作全体を覆う雰囲気でもある。その中で、主人公が実家に帰った時のエピソードである「ぼくのおじさん」がやや異色。話のパターンは他の収録作同様だけれど、脳内お守り「アカラ様」と主人公のルーツが語られているところがミソ。これを書いてしまうと、「モラトリアム生活の終わり」になって、繰り返される永遠の1日が終わらざるを得なくなってしまう。
 オリジナル・アンソロジー『NOVA』から生まれたNOVAコレクションの第1冊、東浩紀『クリュセの魚』は、各パート『NOVA』で読んでいるので、再読感が強く読書の楽しみが後退してしまった感があるのが残念。もちろん改稿部分があり、エピローグまで読めば、また別の感慨が湧くが、全体として主人公の性格付けが弱い気がする。家族や思い出、存在と意思、そして火星と地球と太陽から3万天文単位の外宇宙。これらが主人公の恋とバランスするかというと、それは難しい。こちらの感度が低いということもあるけどね。
オリジナル・アンソロジー『NOVA』から生まれたNOVAコレクションの第1冊、東浩紀『クリュセの魚』は、各パート『NOVA』で読んでいるので、再読感が強く読書の楽しみが後退してしまった感があるのが残念。もちろん改稿部分があり、エピローグまで読めば、また別の感慨が湧くが、全体として主人公の性格付けが弱い気がする。家族や思い出、存在と意思、そして火星と地球と太陽から3万天文単位の外宇宙。これらが主人公の恋とバランスするかというと、それは難しい。こちらの感度が低いということもあるけどね。
 その点、NOVAコレクションの第2冊、谷甲州『星を創る者たち』は4半世紀前の作品群と最新の書き下ろしが、記憶に新しい『NOVA』の短編を新しい枠にはめ込んだ形をつくっていて、読み応えがあった。改稿された4半世紀前の作品群は、最近書かれたものよりもはっきりとした短編の構成を明らかにしていて、読みやすいかわりに余韻が乏しい。これに対し既読の新作群は、無駄な効果を断ち切っていて鮮やか。ただしそれは余韻といえば余韻だけれど、何か取り残されるような結末でもある。それらのある意味地味なエンジニア物語群が書き下ろしの最終編で、会議室の議論から始まるというこれまた地味な謎解きがド派手なスペース・オペラとして急展開。唖然とするといえば唖然とするけれど、特攻で終わるのは個人的にはいただけない。『日本SF短編50 第3巻』の「星殺し」が結構印象深かったので、この連作でのスペース・オペラは予期はできなくとも、作者の戦争への傾斜は驚きではなかったということだろう。
その点、NOVAコレクションの第2冊、谷甲州『星を創る者たち』は4半世紀前の作品群と最新の書き下ろしが、記憶に新しい『NOVA』の短編を新しい枠にはめ込んだ形をつくっていて、読み応えがあった。改稿された4半世紀前の作品群は、最近書かれたものよりもはっきりとした短編の構成を明らかにしていて、読みやすいかわりに余韻が乏しい。これに対し既読の新作群は、無駄な効果を断ち切っていて鮮やか。ただしそれは余韻といえば余韻だけれど、何か取り残されるような結末でもある。それらのある意味地味なエンジニア物語群が書き下ろしの最終編で、会議室の議論から始まるというこれまた地味な謎解きがド派手なスペース・オペラとして急展開。唖然とするといえば唖然とするけれど、特攻で終わるのは個人的にはいただけない。『日本SF短編50 第3巻』の「星殺し」が結構印象深かったので、この連作でのスペース・オペラは予期はできなくとも、作者の戦争への傾斜は驚きではなかったということだろう。
 小説以外では、ちょっと昔に出たJ.G.バラード『J.G.バラードの千年王国ユーザーズ・ガイド』。持っているのは2009年に出たバラード追悼廉価版ソフトカヴァー。オリジナルは結構高い値段のハードカヴァーだったように記憶している。岡本俊弥さんのHPでチェックリストを参照したら2006年6月に書評があったので、出たのは5月頃かな。
小説以外では、ちょっと昔に出たJ.G.バラード『J.G.バラードの千年王国ユーザーズ・ガイド』。持っているのは2009年に出たバラード追悼廉価版ソフトカヴァー。オリジナルは結構高い値段のハードカヴァーだったように記憶している。岡本俊弥さんのHPでチェックリストを参照したら2006年6月に書評があったので、出たのは5月頃かな。
バラードの未読翻訳本が数少なくなってきたのに読んでしまったバラード唯一のエッセイ集。バラードの自己認識がSF作家なのが嬉しいし、SFに寄せる期待が(まあ市場で流行るSFは置いといて)小松左京とほとんど一緒なのも嬉しい(80年代以降はよくわからないが)。
基本は書評・映画評・美術評で対象となった作品に対するバラードの皮肉はキツいが、ユーモアがある。そして一般的な評価には全くとらわれず、ウィリアム・バロウズやサルヴァトール・ダリには熱心な賞賛の言葉を贈る。バラードは基本的に楽観的な態度で世の中を見ている。それは一般には悪いものと判断されるようなものでも、その存在が持つエネルギーがバラード視点では良いものであれば、評価するのである。その意味でバラードの大人ぶりが感じられるエッセイ集だが、戦時中の上海での子ども時代のこととなるとバラードの視線は魔法のヴェールに包まれる。
最後の自伝的エッセイに出てくる広島・長崎の原爆投下に関する言及は、日本人としては耳の痛いところ。原爆投下がなかったらより多くの犠牲者が出て、その犠牲は被爆者の世代的苦難よりも重みがあるという考えは、日本人としては受け入れがたいだろう。
 今月の積ん読本の最後は、澁澤龍彦『都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト』平成14(2002)年9月初刷の学研M文庫。親本は1990年。これは当時名古屋駅近くの三省堂で買ったもの。
今月の積ん読本の最後は、澁澤龍彦『都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト』平成14(2002)年9月初刷の学研M文庫。親本は1990年。これは当時名古屋駅近くの三省堂で買ったもの。
何で名古屋かというと、たまたま30分弱の歴史ビデオを制作することになり、NHK関連会社に注文したところ、ナレーションとBGMを入れる場所が名古屋のスタジオだったため、その立ち会いにいったのである。東京から来たナレーターは、台詞を読む前に大きくブレスを入れる。スタジオではそのブレス音を片っ端から取っていくのだ。ナレーターは気に入らないところだけを読み直して1時間あまりで仕事を終わらせた。さすがプロ。BGMの方はストックから画面に合うクラシック風インスト演奏(どこかで聴いたような音楽だけれど、一応オリジナルらしい)をはめ込んでいく。立ち会いは半日で終了。帰りに買ったのがこれ。多分帰りの新幹線で一部を読んだはずなのだが、全く記憶がない。家に帰ってそのまま書棚に放りこまれて、10年埋もれていたわけだ。
澁澤龍彦は時々読むくらいの付き合いで、あまり熱心に読んではないが、この最後の短文集を読んでいると澁澤龍彦の軽やかさが伝わってくる。澁澤龍彦の仕事自体は、情報としてこの20年でかなり消費されてしまったような気がするが、その文体は廃れることなく読める。バラードの文章を読んだ後では、このいかにも日本人らしい柔らかさが、ある意味生ぬるくまた愛おしい。
THATTA 306号へ戻る
トップページへ戻る
 歳のせいか何ということもなく気分が沈んでいる。ダウナー気分にはダウナーな曲をぶつけようと、ついにフルトヴェングラーの「トリスタンとイゾルデ」に手が伸びる。「前奏曲と愛の死」だけは生演奏でも録音でも聴いたことがあったけれど、全曲を聴いたのは初めてだ。
歳のせいか何ということもなく気分が沈んでいる。ダウナー気分にはダウナーな曲をぶつけようと、ついにフルトヴェングラーの「トリスタンとイゾルデ」に手が伸びる。「前奏曲と愛の死」だけは生演奏でも録音でも聴いたことがあったけれど、全曲を聴いたのは初めてだ。