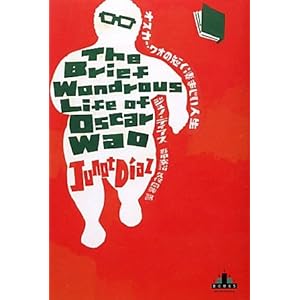震災チャリティーと銘打って沢山のCDが出ているけれど、オッと思って買ったのがマルタ・アルゲリッチがアルミンク率いる新日本フィルと演ったシューマンとショパンのピアノ協奏曲をカップリングした1枚。昨年の暮れにあった2日間にわたってのアルゲリッチ70歳の記念コンサートだったらしく当然ライブ録音。シューマンの方はピアノが独走している感じがあって、オケとの釣り合いがイマイチな感じがあるのに対し、ショパンの1番はピアノがオケをよく聴いている雰囲気が感じられて気持ちよく聴ける。アルゲリッチのピアノはフレーズどころか1小節以下の短い音のつながりの中で表情が移り変わっていく。ベートーヴェンの三重協奏曲を生で聴いたときも書いた、あのグリッサンドでの陽光を反射する滝しぶきのようなきらめきは録音では鈍くなってしまうが、それでも魅力的なことは間違いない。ちなみに当日のコンサートの感想をブログ検索してみたら、ほぼ全員が2日間の演奏会で前半に置かれたシューマンやショパンではなく、後半に奏されたラヴェルの協奏曲の演奏に対して絶賛の声を上げていた。うむむ、ちょっと残念だが、眼前で繰り広げられた圧倒的な演奏が、録音でも同様に凄く聞こえるかは別な話だろうし、アルゲリッチが選ばなかったのだからあきらめるしかないか。
 コリイ・ドクトロウ『リトル・ブラザー』は、スーパーハッカー少年の反権力ファンタジーといった趣の物語。こういう物語を読んでいると、ああ、年を取ったなあと思う。効率的に設計され、ほとんど自動的に動いてしまうアンチテロ・システムは、現実世界でこの主人公たちが経験したよりもまだ非道い扱いを受けた人々を生じさせているだろう。リベラリストの「自由であること」への信念と政府/国家の「社会(統治機構)の安全」への意志/暴力装置の発動は、常にアンバランスだ。この物語が60年代末から70年代に作られたリベラルな傾向を持ったアメリカ映画を思い起こさせるが故に、何かしら痛ましさを覚えてしまう。
コリイ・ドクトロウ『リトル・ブラザー』は、スーパーハッカー少年の反権力ファンタジーといった趣の物語。こういう物語を読んでいると、ああ、年を取ったなあと思う。効率的に設計され、ほとんど自動的に動いてしまうアンチテロ・システムは、現実世界でこの主人公たちが経験したよりもまだ非道い扱いを受けた人々を生じさせているだろう。リベラリストの「自由であること」への信念と政府/国家の「社会(統治機構)の安全」への意志/暴力装置の発動は、常にアンバランスだ。この物語が60年代末から70年代に作られたリベラルな傾向を持ったアメリカ映画を思い起こさせるが故に、何かしら痛ましさを覚えてしまう。
 多産であることが波に乗っていることを示す小川一水『青い星まで飛んでいけ』は、どちらかというと軽めの短編集。読む端から忘れてしまう人間なので、はや個々の作品がどんな話だった思い出せなくなっているのだけれど、坂村健氏の解説に話の概要が書いてあるので、それを頼りに思い出してみると、基本的には肯定的なコメディが多かったような気がする。SF的なアイデアが時事的世相的話題と絡まっている感じもある。コンスタントに人を楽しませるSFが書けるという意味で、小川一水のショウケースになっているんだね。
多産であることが波に乗っていることを示す小川一水『青い星まで飛んでいけ』は、どちらかというと軽めの短編集。読む端から忘れてしまう人間なので、はや個々の作品がどんな話だった思い出せなくなっているのだけれど、坂村健氏の解説に話の概要が書いてあるので、それを頼りに思い出してみると、基本的には肯定的なコメディが多かったような気がする。SF的なアイデアが時事的世相的話題と絡まっている感じもある。コンスタントに人を楽しませるSFが書けるという意味で、小川一水のショウケースになっているんだね。
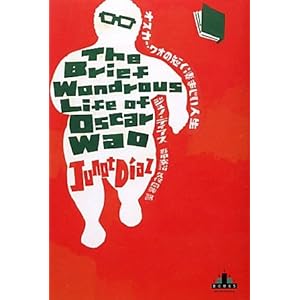 読んでる最中からこりゃまあと感心させられっぱなしで最後まで読まされたジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』。書けるんだねえ、こういう風に。トルヒーヨについて教えてもらったのははるか昔、ゴルゴ13だったけれど、これを読むまですっかり忘れていたよ。絶賛の理由はすでにあちこちで書かれまくっているので、ちょっと小ネタに引っかかったところを。「『トワイライトゾーン』の・・・例の有名な回」という本文に("It's a good life"のこと)という割注が入っているんだけれど、原作のビクスビイ「きょうも上天気」にまで言及せいとはいわないけれど、テレビ版でも映画版でも「こどもの世界」という日本語題名が有名(?)なんだからそれくらい入れときゃよかったのにと思いました。ま、この割注を読んだ読者が『トワイライト(ミステリー)ゾーン』を見て、大森望編『きょうも上天気』までたどり着く可能性は万に一つもないか。
読んでる最中からこりゃまあと感心させられっぱなしで最後まで読まされたジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』。書けるんだねえ、こういう風に。トルヒーヨについて教えてもらったのははるか昔、ゴルゴ13だったけれど、これを読むまですっかり忘れていたよ。絶賛の理由はすでにあちこちで書かれまくっているので、ちょっと小ネタに引っかかったところを。「『トワイライトゾーン』の・・・例の有名な回」という本文に("It's a good life"のこと)という割注が入っているんだけれど、原作のビクスビイ「きょうも上天気」にまで言及せいとはいわないけれど、テレビ版でも映画版でも「こどもの世界」という日本語題名が有名(?)なんだからそれくらい入れときゃよかったのにと思いました。ま、この割注を読んだ読者が『トワイライト(ミステリー)ゾーン』を見て、大森望編『きょうも上天気』までたどり着く可能性は万に一つもないか。
 久しぶりにホラーじゃない小林泰三『天獄と地国』はB級の味わいを持つ、なかなかいいじゃないかの1作。ハードな設定の中で、フォーミュラ的エンターテインメント(ある意味少年ジャンプ的)なものが展開しているけれど、小林泰三の持ち味はやはりホラー的で、ヒューマニスティックなエピソードもあっという間に血も涙もない結末になる。ホントは巨大なスケールの舞台なんだけど、柄の大きさが余り感じられない分傑作感は乏しい。でもいいよ。
久しぶりにホラーじゃない小林泰三『天獄と地国』はB級の味わいを持つ、なかなかいいじゃないかの1作。ハードな設定の中で、フォーミュラ的エンターテインメント(ある意味少年ジャンプ的)なものが展開しているけれど、小林泰三の持ち味はやはりホラー的で、ヒューマニスティックなエピソードもあっという間に血も涙もない結末になる。ホントは巨大なスケールの舞台なんだけど、柄の大きさが余り感じられない分傑作感は乏しい。でもいいよ。
 大森望編『NOVA4』は、本当に変化球だらけのオリジナル・アンソロジーになっていた。森田季節「赤い森」が一番フツーか。北野勇作「社員食堂の恐怖」も、いかにも北野勇作の書くユーモラス・ホラー話。すんなり読めたのはこの2編くらい。あとは森深紅や林讓治でさえどこかタガが外れたような違和感がある。最果タヒなんかあちらこちら読み返してみたが、表面的な物語のつながりが見えない。あらすじは判るが何が書いてあるのかわからない(何も書いてない?)。今回最大の収穫は山田正紀が試みていることがある程度分かりかけたこと。コトバとイメージとモノガタリの関係性がSFを造っている(と山田正紀は言いたいのだ、たぶん)。『神狩り2』や『イリュミナシオン 君よ、非情の河を下れ』が何故あんなにつまらなかったのか、これを読んでようやく判った。
大森望編『NOVA4』は、本当に変化球だらけのオリジナル・アンソロジーになっていた。森田季節「赤い森」が一番フツーか。北野勇作「社員食堂の恐怖」も、いかにも北野勇作の書くユーモラス・ホラー話。すんなり読めたのはこの2編くらい。あとは森深紅や林讓治でさえどこかタガが外れたような違和感がある。最果タヒなんかあちらこちら読み返してみたが、表面的な物語のつながりが見えない。あらすじは判るが何が書いてあるのかわからない(何も書いてない?)。今回最大の収穫は山田正紀が試みていることがある程度分かりかけたこと。コトバとイメージとモノガタリの関係性がSFを造っている(と山田正紀は言いたいのだ、たぶん)。『神狩り2』や『イリュミナシオン 君よ、非情の河を下れ』が何故あんなにつまらなかったのか、これを読んでようやく判った。
 積ん読をあれこれパラパラしていて、急に読む気になったのが、かんべむさし『ミラクル三年、柿八年』。長らくご無沙汰していたかんべ節だけれど、これはかんべさんが気質的には重い人であることがよく分かる一冊。ラジオ大坂の朝オビ番組のレギュラーとして三年余りの経験をかんべむさしの三人称語りで小説にしている。とはいえ、読む方は作者の一人称として読んでしまうのは当然。まあ、そこに作家かんべむさしの技法があるには違いないけれど。それはともかく週間帯番組に生で出続けて、それなりに人気を保つというのは大変なことだったろうな。番組最終回にかんべさんの娘さんたちから花束が届くエピソードがあるんだけど、ハマさんのところはウチの双子と同じ頃生まれたように記憶しているので、就職とかどうしたんだろうかと、個人的な感慨に耽ってしまった。
積ん読をあれこれパラパラしていて、急に読む気になったのが、かんべむさし『ミラクル三年、柿八年』。長らくご無沙汰していたかんべ節だけれど、これはかんべさんが気質的には重い人であることがよく分かる一冊。ラジオ大坂の朝オビ番組のレギュラーとして三年余りの経験をかんべむさしの三人称語りで小説にしている。とはいえ、読む方は作者の一人称として読んでしまうのは当然。まあ、そこに作家かんべむさしの技法があるには違いないけれど。それはともかく週間帯番組に生で出続けて、それなりに人気を保つというのは大変なことだったろうな。番組最終回にかんべさんの娘さんたちから花束が届くエピソードがあるんだけど、ハマさんのところはウチの双子と同じ頃生まれたように記憶しているので、就職とかどうしたんだろうかと、個人的な感慨に耽ってしまった。
THATTA 277号へ戻る
トップページへ戻る
 コリイ・ドクトロウ『リトル・ブラザー』は、スーパーハッカー少年の反権力ファンタジーといった趣の物語。こういう物語を読んでいると、ああ、年を取ったなあと思う。効率的に設計され、ほとんど自動的に動いてしまうアンチテロ・システムは、現実世界でこの主人公たちが経験したよりもまだ非道い扱いを受けた人々を生じさせているだろう。リベラリストの「自由であること」への信念と政府/国家の「社会(統治機構)の安全」への意志/暴力装置の発動は、常にアンバランスだ。この物語が60年代末から70年代に作られたリベラルな傾向を持ったアメリカ映画を思い起こさせるが故に、何かしら痛ましさを覚えてしまう。
コリイ・ドクトロウ『リトル・ブラザー』は、スーパーハッカー少年の反権力ファンタジーといった趣の物語。こういう物語を読んでいると、ああ、年を取ったなあと思う。効率的に設計され、ほとんど自動的に動いてしまうアンチテロ・システムは、現実世界でこの主人公たちが経験したよりもまだ非道い扱いを受けた人々を生じさせているだろう。リベラリストの「自由であること」への信念と政府/国家の「社会(統治機構)の安全」への意志/暴力装置の発動は、常にアンバランスだ。この物語が60年代末から70年代に作られたリベラルな傾向を持ったアメリカ映画を思い起こさせるが故に、何かしら痛ましさを覚えてしまう。