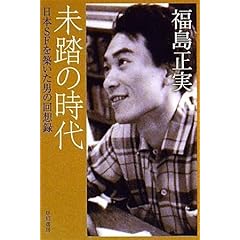今年も終わりだけれども年を食うと年越しというのもあんまり感慨がない。ま、今年は年末年始に休みが取れるのが嬉しいくらいかな。
人間ドックの帰りに久しぶりに中古CD・レコード屋を覗いたら、輸入盤でリビング・ステレオ盤のハイフェッツのヴァイオリンにライナー指揮のシカゴ交響楽団というブラームス/チャイコフスキーの協奏曲が580円だったのでついつい買ってしまった。1955年の初期ステレオ盤で昔からの超有名盤だけど、20世紀屈指のスーパー・プレイヤーのハイフェッツは敬して遠ざけていたので、ちゃんと聴くのははじめてだ。とりあえず聴いてみて定位がイマイチな録音だということとブラームスの第1楽章のカデンツァのソロが普通じゃないところがまず気になった。演奏自体は「天馬空を行く」ヴァイオリンで評判に違わずだが、自分の好きなブラームスのとはちょっと違うという感じ。ライナー/シカゴといえばバルトークの弦チェレとオケ・コンの悲劇性の高い演奏が高校生の頃から愛聴盤だけれど、ここではハイフェッツに合わせた感じがある。聴きながらちょっと早いかなと思って演奏時間を確かめてみたら、第1楽章は19分を切っている。あまりの短さにびっくりして、手元にあるケンペ/メニューイン、バーンスタイン/フランチェスカッティそれにラトル/チョン・キョンファをみると、それぞれ22分台、21分台、23分台である。ハイフェッツのあとでキョンファを聴くとさすがに遅い。キョンファの集中力がそれを要求しているんだけれど、ラトル/ウィーン・フィルの伴奏とちょっと隙間がある。ハイフェッツの速さは異常とはいえ、演奏自体に弾き急ぐ感じは全くなく、むしろ優雅に弾きこなしている印象だ。さすが天才中の天才。
しばらくyoutubeでミニスカギター/ベース娘ばかりみていたら、いい加減にしろと奥さんに怒られた。メタル姫がクリスマスにあわせてサンタ・コスで新作を発表。ちなみにメタル姫は「へたれ」というHPのブログで「オレはオトコだ」宣言をしている。ま、料理や食器やゲームの趣味から男の子的ではありますが、演奏姿に男の子っぽさはありませんね。
 むかし、大江健三郎は1作ごとに文体を造るのだといっていたが、桜庭一樹『製鉄天使』を読みながら、そんなことを考えてしまった。『赤朽葉家の伝説』からのスピンオフとして当時からウワサのあった作品は、スピードをテーマとした文体で書かれており、勢いラノベの文体がその内容と共に突っ走っていく。一度語られたエピソードがフル・ストーリーとして再現されるとき、大枠はすでに用意されているわけで、おそらく作家にとって一番大変なのは最初のインスピレーションを如何にキープするかだったと思われる。スピードがテーマならそれは時間をどう描出するかということでもある。その工夫が読みどころかな。
むかし、大江健三郎は1作ごとに文体を造るのだといっていたが、桜庭一樹『製鉄天使』を読みながら、そんなことを考えてしまった。『赤朽葉家の伝説』からのスピンオフとして当時からウワサのあった作品は、スピードをテーマとした文体で書かれており、勢いラノベの文体がその内容と共に突っ走っていく。一度語られたエピソードがフル・ストーリーとして再現されるとき、大枠はすでに用意されているわけで、おそらく作家にとって一番大変なのは最初のインスピレーションを如何にキープするかだったと思われる。スピードがテーマならそれは時間をどう描出するかということでもある。その工夫が読みどころかな。
 あまり絶賛されることのない作品ばかり選ばれてしまう日本SF新人賞の受賞作の内、今回は天野邊『プシスファイラ』を読んでみた。クジラ社会は昔からインターネット社会で、擬人化クジラたちはコミュニケーション・プロトコルによる全体意志化に向かっていく、というような話が延々と続く。しかし海水が媒体では大気中より早いとはいえ超圧縮言語でさえ高速通信は大変だろう、などという感想はこの作品の前では無意味だろうな。とにかく読んでいてまったく説得力がないかわりに何か偏執的な固定観念が強固に居座っている。それはスケール・インフレを繰り返す終章でいっそう強烈だ。読みながら思い出したのは、大昔に読んだジョージ・ゼヴロウスキーの『Macrolife』。どんな話だったかはいつもどおりもうすっかり忘れ果てているが、この話の最後の方ですべての精神存在が一つに統合されてしまった宇宙が出てくる。そうなると読者に何も説明できないので、主人公だったキャラの精神が分離されて、マクロライフから人間に理解できる範囲でこれまで起きたことの説明を受けるという、仕様もない場面が今でも印象に残っている。ゼブロウスキーはティヤール・ド・シャルダンのヌー・スフィアを作品に取り込んだというふれこみだったと思うけれど、この作品にも似たようなものを感じた。ユング派精神分析の「箱庭」みたいだというのが結論かな。
あまり絶賛されることのない作品ばかり選ばれてしまう日本SF新人賞の受賞作の内、今回は天野邊『プシスファイラ』を読んでみた。クジラ社会は昔からインターネット社会で、擬人化クジラたちはコミュニケーション・プロトコルによる全体意志化に向かっていく、というような話が延々と続く。しかし海水が媒体では大気中より早いとはいえ超圧縮言語でさえ高速通信は大変だろう、などという感想はこの作品の前では無意味だろうな。とにかく読んでいてまったく説得力がないかわりに何か偏執的な固定観念が強固に居座っている。それはスケール・インフレを繰り返す終章でいっそう強烈だ。読みながら思い出したのは、大昔に読んだジョージ・ゼヴロウスキーの『Macrolife』。どんな話だったかはいつもどおりもうすっかり忘れ果てているが、この話の最後の方ですべての精神存在が一つに統合されてしまった宇宙が出てくる。そうなると読者に何も説明できないので、主人公だったキャラの精神が分離されて、マクロライフから人間に理解できる範囲でこれまで起きたことの説明を受けるという、仕様もない場面が今でも印象に残っている。ゼブロウスキーはティヤール・ド・シャルダンのヌー・スフィアを作品に取り込んだというふれこみだったと思うけれど、この作品にも似たようなものを感じた。ユング派精神分析の「箱庭」みたいだというのが結論かな。
 そんな話の後にハヤカワSFシリーズJコレの林讓治『ファントマは哭く』を読むとホッとする。とても真っ当なスペースオペラになりつつある《AADD》シリーズ。今回はついに異星知性体ストリンガーとほぼ人間同士に近いコンタクトが(人類側からすれば)取れてしまう。知性体ならばどんな形態であろうとコミュニケーション可能とするこの楽天性は作品全体を覆っていて、それはある意味昔懐かしいアメリカSFを思わせる。ストリンガーにもお家の事情があるなんていうのは、いかにもスペースオペラらしいよ。林讓治と山本弘それに野尻抱介は意外と近いところにいるのかな。
そんな話の後にハヤカワSFシリーズJコレの林讓治『ファントマは哭く』を読むとホッとする。とても真っ当なスペースオペラになりつつある《AADD》シリーズ。今回はついに異星知性体ストリンガーとほぼ人間同士に近いコンタクトが(人類側からすれば)取れてしまう。知性体ならばどんな形態であろうとコミュニケーション可能とするこの楽天性は作品全体を覆っていて、それはある意味昔懐かしいアメリカSFを思わせる。ストリンガーにもお家の事情があるなんていうのは、いかにもスペースオペラらしいよ。林讓治と山本弘それに野尻抱介は意外と近いところにいるのかな。
 「雪風」の長編も「海賊」の短編集も息子が持って行ってしまって読めないまま、『神林長平トリビュート』を読む。テーマ・アンソロジーとして結構良い作品がそろっている。神林作品のタイトルを冠してあるだけに、一種のスピンオフ短編集みたいな趣もあるが、円城塔あたりになると原作との距離はかなり怪しそうだ。ここに集まった作家たちは短編が本歌取りであることを明らかにされていても一個の短編として成りたたせる努力を見せている。当たり前といえば当たり前のことだけれど、こんなことができるくらい日本のSF(だけじゃないか)作家層が若く厚くなっているということを見せてもらったようで、それはそれでちょっとした感慨がある。
「雪風」の長編も「海賊」の短編集も息子が持って行ってしまって読めないまま、『神林長平トリビュート』を読む。テーマ・アンソロジーとして結構良い作品がそろっている。神林作品のタイトルを冠してあるだけに、一種のスピンオフ短編集みたいな趣もあるが、円城塔あたりになると原作との距離はかなり怪しそうだ。ここに集まった作家たちは短編が本歌取りであることを明らかにされていても一個の短編として成りたたせる努力を見せている。当たり前といえば当たり前のことだけれど、こんなことができるくらい日本のSF(だけじゃないか)作家層が若く厚くなっているということを見せてもらったようで、それはそれでちょっとした感慨がある。
 いつものやつだよなと思いつつ、目を落としたらあっという間に読み終えてしまった牧野修『夢魘祓い−錆域の少女』。ホントいつものパターンなのに、読まされちゃうもんなあ。何にもないといえばなんにもないのに、このリーダビリティ。呆れるよ。
いつものやつだよなと思いつつ、目を落としたらあっという間に読み終えてしまった牧野修『夢魘祓い−錆域の少女』。ホントいつものパターンなのに、読まされちゃうもんなあ。何にもないといえばなんにもないのに、このリーダビリティ。呆れるよ。
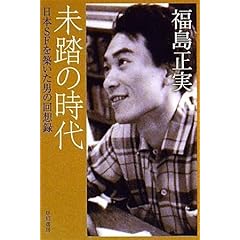 もうひとつ、あっという間に読んでしまったのが福島正実『未踏の時代』。まあこちらは30年以上前に読んでいるけれど、多分その時よりもはるかに深く心を打たれている。そりゃそうだ、もう福島正実の享年をだいぶ上回って長生きしているんだからなあ。何という想いの塊だったんだろう。SFにとっての福島正実みたいなひとたちが、あの時代にはそこここにいたのだろうと思う。戦中に育ち、戦後を生き抜こうとした精神の一つがここでも声を上げ続けている。
もうひとつ、あっという間に読んでしまったのが福島正実『未踏の時代』。まあこちらは30年以上前に読んでいるけれど、多分その時よりもはるかに深く心を打たれている。そりゃそうだ、もう福島正実の享年をだいぶ上回って長生きしているんだからなあ。何という想いの塊だったんだろう。SFにとっての福島正実みたいなひとたちが、あの時代にはそこここにいたのだろうと思う。戦中に育ち、戦後を生き抜こうとした精神の一つがここでも声を上げ続けている。
 ようやく帰ってきた神林長平『アンブロークン アロー 戦闘妖精・雪風』は、さすがご本尊、ネチこくねちこく「言葉と世界」を「言葉と心」を「言葉と言葉」をこねくり回してみせる。一緒に帰ってきた「海賊」短編集の第1作と読み比べると三つ子の魂・・・もさることながら、その言葉を如何に使うかという点でその確信の強さと練度の深さが感得される。言葉によって常に変容する作品世界の現実は、それでも混沌というよりは鏡面世界のような明晰さをイメージとして読者に提出する。そしてそのこと自体に神林長平が積み重ねてきた作品群の重みがあると思う。
ようやく帰ってきた神林長平『アンブロークン アロー 戦闘妖精・雪風』は、さすがご本尊、ネチこくねちこく「言葉と世界」を「言葉と心」を「言葉と言葉」をこねくり回してみせる。一緒に帰ってきた「海賊」短編集の第1作と読み比べると三つ子の魂・・・もさることながら、その言葉を如何に使うかという点でその確信の強さと練度の深さが感得される。言葉によって常に変容する作品世界の現実は、それでも混沌というよりは鏡面世界のような明晰さをイメージとして読者に提出する。そしてそのこと自体に神林長平が積み重ねてきた作品群の重みがあると思う。
THATTA 260号へ戻る
トップページへ戻る
 むかし、大江健三郎は1作ごとに文体を造るのだといっていたが、桜庭一樹『製鉄天使』を読みながら、そんなことを考えてしまった。『赤朽葉家の伝説』からのスピンオフとして当時からウワサのあった作品は、スピードをテーマとした文体で書かれており、勢いラノベの文体がその内容と共に突っ走っていく。一度語られたエピソードがフル・ストーリーとして再現されるとき、大枠はすでに用意されているわけで、おそらく作家にとって一番大変なのは最初のインスピレーションを如何にキープするかだったと思われる。スピードがテーマならそれは時間をどう描出するかということでもある。その工夫が読みどころかな。
むかし、大江健三郎は1作ごとに文体を造るのだといっていたが、桜庭一樹『製鉄天使』を読みながら、そんなことを考えてしまった。『赤朽葉家の伝説』からのスピンオフとして当時からウワサのあった作品は、スピードをテーマとした文体で書かれており、勢いラノベの文体がその内容と共に突っ走っていく。一度語られたエピソードがフル・ストーリーとして再現されるとき、大枠はすでに用意されているわけで、おそらく作家にとって一番大変なのは最初のインスピレーションを如何にキープするかだったと思われる。スピードがテーマならそれは時間をどう描出するかということでもある。その工夫が読みどころかな。