



地底の大魔王。うーむ、えらい直球ですな。恥ずかしがっててはこの味はだせません。本作は<新趣味>という博文館の雑誌に掲載された一品。こいつがどういう雑誌だったかイメージを得るのは、今なら光文社文庫の『「新趣味」傑作選』に付された索引を当たれば難しくないだろう。博文館の雑誌といえば大正9年創刊<新青年>がまず第一にあがってくるが(ま、普通は<太陽>あたりかもしれんが、読者として想定してるのはそーゆー人だ)、大正11年創刊<新趣味>、大正13年改題<独立>と翻訳小説を中心に据えた雑誌が併走する形で、これといった役割分担もなく(編集のセンスはともかく、少なくとも素材については今見ると違いがよくわからん)乱立しているように見えるのは謎。さすがに二つとも、長くは続かないわけですが、自分で二匹目のドジョウも用意する戦略だったのか。
 ところで、ラ・バテイユ掲載の大正11年5月号は17巻5号。って、それだとえらく続いてることに。あれれ、と驚いて調べたら、要するに<文章世界>の改題後誌の<新文学>の改題後誌で巻号を継承していたのであった。そうか<新趣味>の前身は<文章世界>やったんか、と驚くのが普通。しかし坪内祐三という人は<文章世界>の後身が<新趣味>だといって驚いているよ。ヘンな奴(←どっちも、どっちだが、想定上の読者は、ウンウンうなずいてますよ)。ちなみに<新青年>は<冒険世界>の後継誌で、<独立>は<寸鉄>の改題だ。念のため。
ところで、ラ・バテイユ掲載の大正11年5月号は17巻5号。って、それだとえらく続いてることに。あれれ、と驚いて調べたら、要するに<文章世界>の改題後誌の<新文学>の改題後誌で巻号を継承していたのであった。そうか<新趣味>の前身は<文章世界>やったんか、と驚くのが普通。しかし坪内祐三という人は<文章世界>の後身が<新趣味>だといって驚いているよ。ヘンな奴(←どっちも、どっちだが、想定上の読者は、ウンウンうなずいてますよ)。ちなみに<新青年>は<冒険世界>の後継誌で、<独立>は<寸鉄>の改題だ。念のため。
なおマイクロフィッシュ版の復刻である「精選近代文芸雑誌集」の<新趣味>の解題はというと。ええっ、<家庭雑誌>の巻号を引き継ぐとか書いてありますよ。とめなさい、とめなさい。紅野敏郎大先生ともなると偉すぎて誰も諌言でけんのか。編集者なり弟子の人は、あんまし恥ずかしいもんが世に出回らないようチェックしたれよっ。それとも逝去されるのを待って叩くつもりで、手ぐすねひいとんの? 大人ってヤだねえ。まだまだお元気で活躍されると思うぞ。
十年以上前に<新趣味>掲載作をひとわたりチェックしたおり、このベタな題の小説に遭遇。冒頭部分とリードを読んだだけだが、本当に「地底」で「大魔王」らしい。少なくともロスト・レース(失われた種族)ものであることは確かだと思われたので、SF研究者は要チェックというフラグを立てておいたところ、会津翁の年表には採用されたね。
そのまま本文を読まずにほったらかしだったのだが、ヴェルサンを眺めるとバテイユというのはPierre de La Batutで、原題は"La Jeune fille en proie au monstre"(怪物に捧げられし少女)だと見当がついた。これは<Je sais tout>というフランスの雑誌が1921年、科学的予言賞(Prix d'anticipation scientifique)と銘打ったSFコンテストを行った際の第二位に入賞した小説だという。第一位はEdmond-Edouard Bauerの"Le Neveu de Gulliver"(ガリバーの甥)という作品だったが、後世の評価だとバテイユの方が遥かに良い作品らしい。
「地底の大魔王」は1921年9月15日の189号に掲載。同作を含め、単行本が何冊かあるが、ヴェルサンには単にフランスの現代作家とのみ記されていて、経歴は良くわからない。さらに翻訳者の葛見牧夫も、さっぱりわからん。
ということで、今回は、ストーリーを紹介するだけで、とっと終われる訳なので、さっさと片付ける。
章立はこんな感じ。ほぼ原書に対応。
(葛見訳)長方形の石/謎の碑文/恋か科学か/ケルマネーの廃墟/不思議な陰影/途絶えた足跡/大地の陥落、魔国の出現/「キリュビー」王国の奇観/歌の魅惑/人面獣身の大魔王/禁制の谷と怪獣/無花果の誘惑/薔薇下の鮮血/最後の生贄
La Pierre oblongue/L'Inscription mysterieuse/Pour l'Amour ou pour la Science?/Kermaneh/La Colere du Reverend/Les Preoccupations du Maitre/La Piste interrompue/Le Minotaure/Au pays des Kirubi/Naoulfah/Le Rendez-vous/La Vallee interdite/Les Mefaits de la figue/Du Sang sous les roses/Epilogue
冒頭に付されたリード文は以下。
「小亜細亜ケルマネーの廃墟発掘中に起こつた大珍事!月明の夜、魔の歌の誘惑から、妙齢美人の失踪、不意に起つた大地の陥落、地底王国の出現、人類に対する魔族の復讐の計画!これ果して痴人の夢か?狂人の囈言か?然も科学的にして神怪、構想の奇抜と絶妙と、真に驚異に値する一大怪篇」
ここから最後までストーリーを紹介するので、現物を読むつもりでネタバレ云々を気にする人は御注意をば。
考古学者ヘンリー・カッスリーは師匠にあたる老教授ジー・イー・ステファンより不思議な史料を入手したことを告げられる。イランのケルマネー寺院の廃墟として知られる遺跡で発見された長方形の石でそこには驚異的な内容が記されているという。教授は自分の解読したそれを再確認するためにヘンリーに改めて解釈をもとめる。碑文はこのように始まっていた。「ケルマネー付近に於て「直立人種」は「キュリビー」の為に破られた……」この石は人類に先行する理性を備えた生物の手になる記録だったのである。
ヘンリーは実業家の娘ケッティー・オールドリッヂと婚約したばかりであったため、教授から求められたケルマネーへの再度の調査に参加することを躊躇する。しかし、発見の重要性と、教授の懇願に、ついに出発を決意する。そして、ケッティーは、その父親の反対を振り切って調査行に同行することになり、父親はお目付として牧師のマック・スマッツを送り込むのであった。
現地での調査によって、「キュリビー」種族の風俗の一部は明らかになってきたが、その正体の確信にまでは達することができない。発掘が続けられある日、謎の歌声が聞こえ始める。ステファンは「キュリビー」の遺跡は二万年以前のものだと推測していたが、人類と共存していた時期が数世紀あったという結論に達していた。
そして発掘現場に真新しいメッセージが記される。それはあたかもケッティーへの恋文とも解釈されるためヌサンピリという現地人の料理人の手になるものと疑われるが、さらに続いて残されたメッセージから「キュリビー」が現存していることが確信され、一行は武器を用意して待ち受ける。しかし、「キュリビー」の歌によって麻痺させられ、ケッティーは連れ去られてしまう。残された足跡を追って遺跡の中を進んで特に足跡をの集中している箇所を精査していると突然、地面が陥落する。急速度の降下が続き、一行はこれが自然現象ではなく機械的な昇降システムであることを推測する。半時間ほどして下降は停まる。そして廊下をたどると、そこには光りあふれる巨大な空間に到達する。そこには地上そのままの景色がひろがっていた。
地下世界で遭遇したのは人類であったが、これは「キュリビー」が移住した時に労働力として連れられて来た者と遺跡から紛れ込んだ者たちの子孫であり、その支配下にある者たちであった。この世界は人工的製造された滋養分を含んだ空気に満たされており、人々は空腹を知らず、食事という習慣もすたれていた。
ナウルファという案内役に連れられ一行はケッティーに再会し、この世界のあらましを教えられる。「キュリビー」は安定した世界に長く暮らしているため形而下の事象についてはほとんど無頓着となり音楽や哲学的な論争にその生を費やしているらしい。そしてその姿はアッシリアの彫刻にその形をとどめている
「翼のある人間の顔をした牡牛」である。
自生していたイチジクを見て、新しい栄養補給方法に満足できない牧師はそれに手を出す。ナウルファはそれによって食事という習慣を知り、そこから所有という概念も徐々に地底世界の人類に伝わり出す。
「キュリビー」は会見の相手としてケッティーを指定し、彼女が聞いた話は以下のようなものであった。彼らは地上に現れた最初の知的生命で長らく地球を支配していた。人類を使役することで、その文明は最高潮に達したが、人類の理智が次第に発達し、叛乱が起こり、次第に衰退した彼らは、アッシリア、バビロニア地方に追い込まれる。数世紀の闘争の後、彼らを奉じる人類と共に地下世界へ退却し、隠棲時代に至って抽象科学、形而上学、自然科学に没頭し、次第に活動力を失い、ただ音楽のみが盛んとなる。彼らに隷属する人類は平和に慣らされ、所有観念も無くし、羨望、嫉妬、憎悪も消滅し、暴力からも自由となった無政府状態の理想郷の住人となっていた。
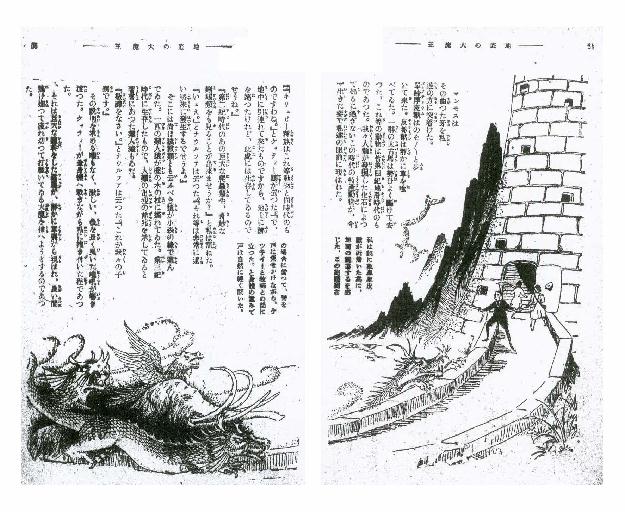 地下世界には「禁制の谷」と呼ばれる秘密の場所があった。ヘンリーとケッティーはそこに出かけ「キュリビー」が彼らを地下に追い込んだ人類に対して復讐の準備をしていることを知る。そこにはマストドンを始めとする古代の生物が飼育されており、これらが人類世界を攻撃するための手段として用意されているのであった。ここで奇妙な逆進化論説が語られ、将来的に恐竜などもその戦列に加わることが示唆される。
地下世界には「禁制の谷」と呼ばれる秘密の場所があった。ヘンリーとケッティーはそこに出かけ「キュリビー」が彼らを地下に追い込んだ人類に対して復讐の準備をしていることを知る。そこにはマストドンを始めとする古代の生物が飼育されており、これらが人類世界を攻撃するための手段として用意されているのであった。ここで奇妙な逆進化論説が語られ、将来的に恐竜などもその戦列に加わることが示唆される。
彼らの行動は制限されていたが、所有観念が次第に広がり人間社会に軋轢が生じ始め、その混乱に乗じてヘンリーと牧師は天に通じる塔から脱出を図るが、ステファン教授は「キュリビー」の催眠力のある「歌」の研究への意欲から一行とは行動を伴にしない。ケッティーに迫るナウルファをヘンリーは弓で倒すが、同時にケッティーを傷つけてしまう。
彼らを追うために「禁制の谷」の猛獣たちが放たれるが「塔」の階段が狭いことが幸いして、大型動物の群れから逃れた一行は何時間も階段を登り続ける。そして彼らは再び空腹を覚える。栄養に満たされた人工の空気の圏から離れ地上に到達したのである。彼らが目にした光景はエジプトのそれであった。そしてヘンリーは悟る。スフィンクスもまた「キュリビー」の別の種族でありエジプト文明はその簒奪物なのだと。ケッティーの傷は腫れ上がり、ついに彼女に死をもたらす。
発掘現場より逃亡した人夫たちにより、一行はケルマネー郊外で野獣に襲われて死んだと言い触らされていた。苦難の末、帰国したヘンリーは真相を語るが狂人扱いされる。牧師は通りの良い人夫たちの言葉を真実としたため、ヘンリーは一人、精神病院に幽閉されるのであった。
まあ、オリエンタリズムとか差別意識とか(アジアの古代文明は全部、アジア人じゃなくて「失われた種族」が作った)、まあ時代が時代なんで読み取ることは容易いですけど、わざわざ、ほじくりかえして糾弾することはないでしょう。
人類も衰退した終末期の地球に、滅び行く「失われた種族」のしもべである野獣が放たれ跋扈する様が幻視されるあたり、結構スケールの大きな未来史的な発想はあるようなんだが、翻訳で読むと、そこにそれほど力点はないように見えてしまうが、実際のところは、そのあたりどうなんだろうねえ。
<新趣味>(博文館)17巻5号:1922年5月1日発行。2〜69頁。伊藤孝画。