

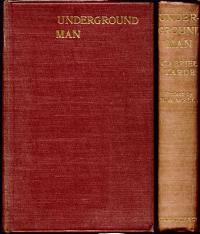
上田敏といえば山のアナタの空遠く、さいわいという名の怪物が棲んでいて暴れているのを止めに行く途中、目を刺されて帰ってくる話を書いた人というのは我々の世代では常識であるが、今の若者にも通じるのかのお(注1)。
それはさておき、訳詩集『海潮音』で知られる上田敏(1874―1916)はこれまでSFの文脈で紹介されることはなかったのではあるまいか。
SF史的に興味を惹きそうなところで、羽化仙史こと渋江保が静岡で教師をやってたときの教え子だった説、ってのはあったが、要するにそのあたりの調査が行き届いていなかったために生じた伝説で、ありったけの資料をかき集めて検証すると、微妙に年代がずれている事実が判明する(注2)。
ともかく上田敏は日本におけるフランスSF受容史において看過することのできない人物なのである。
明治39(1906)年、上田は<新小説>(春陽堂)に「穴居の民」を発表する。
「穴居の民」で、SF。それって原始人モノなのかと、ロニーとかアロークールとかロンドン(フランスゆーとろーがっ)辺りが紹介されとるのかと思ったあなたは甘い。ここで紹介されているのはガブリエル・タルドTARDE, Gabriel de(1843―1904)なのである。
 タルドといえば群衆論で有名な社会学者。ミーム理論の元祖として注目されたりもしとる大変偉い学者ということになっておるらしいが、何分不勉強なもので、なにげなく手にとった横山滋『模倣の社会学』(丸善・1991)を読んで、そーなのかと思ったぐらい。SF史だと地底SF『未来史の断片』Fragment d'histoire future(1896/単行本1904)/英訳 Underground Man(1905)/田辺寿利訳 大正14年2月11日・不及社(発売・東條書店)の人だよな。
タルドといえば群衆論で有名な社会学者。ミーム理論の元祖として注目されたりもしとる大変偉い学者ということになっておるらしいが、何分不勉強なもので、なにげなく手にとった横山滋『模倣の社会学』(丸善・1991)を読んで、そーなのかと思ったぐらい。SF史だと地底SF『未来史の断片』Fragment d'histoire future(1896/単行本1904)/英訳 Underground Man(1905)/田辺寿利訳 大正14年2月11日・不及社(発売・東條書店)の人だよな。
もっとも、同書に関してのSF方面からの紹介は意外に少なく、古いところでは、これといった文献が思い浮かばない。ただ逆に、近年になって<SFマガジン>における永瀬唯、横田順彌の両氏の連載(「デッド・フューチャーReMiX(24) 第8章
失われた終末宇宙(2)内宇宙への退却」2003年7月、及び「近代日本奇想小説史(27) 地底世界のユートピア」2004年6月)と相次いで取り上げられているので作品自体については改めて紹介するまでもないかもしれない。
問題の「穴居の民」はこのFragment d'histoire futureの粗筋を三回連載で約55枚にわたって紹介した文章である。冒頭で言及されるタルドの著作タイトルにはフランス語タイトルのルビが付されているものの、邦題を「穴居の民」としているところからみて、上田は英訳版を読んでこの文章を草したのだろうか。
永瀬氏は、進化論SFの系譜の中においてタルドを紹介しているわけだが、興味をひくのは横田氏の紹介ぶりである。意外というべきか、当然というべきか、氏の引用箇所は上田敏における紹介ポイントとかなり重なっている。
(上田敏)
「勿論百五十年間幕無しの大戦争があつた。双方各三四百万人の大軍が、幾回と無く争闘して或は武装列車を全速力で衝突させ合つたり、潜航艇の艦隊が電気の発射で、相互に爆裂し合つたり、空中戦争では、武装の風船がツキ合ひ、世界は空前絶後の大修羅場となつて」
(田辺訳)
「戦闘に参加した人員は、三百万から四百万にも上り。装甲車を連結した列車は、八方に砲火を浴びせながら全速力で馳駆し。潜航艇隊は電撃を以て相のぞみ。装甲気球隊は、銛を以て突撃し、空中雷を以て互いに破砕し、無数の落下傘を開いて突如雲際から下降し、霰弾を浴びせかける。」
なるほど、そのものずばり「ポエム君」シリーズをものした作家だけのことはある。訳詩/詩学の大家である上田敏と気脈が通じていても不思議でもなんでもないといえよう。
もっとも田辺訳でも150枚程度なので上田の文章は粗筋紹介というよりも、ほとんど抄訳といった趣があるわけで、横田氏がどこをとりあげてもぶつかって当然と見るむきもあろうが、<新小説>での連載を一見して受ける印象では、ストレスの置き方に相通じるところがあるように感じられる。
お読みになった方はおわかりだと思うが、『未来史の断片』自体も「断片」というより「粗筋」といった感のある作品で、どうも小説的な感興の薄い部分が多々ある。田辺訳でも5頁ほどで戦争を経て黄金時代が到来。
太陽の不順によって地球が寒冷化し、人類絶滅の危機が生じるのが31頁から。地下世界へ避難する模様が描かれるのが45頁から。以下、地下文明の様相が描かれていく。
ちなみに、未来ではギリシャ語が世界語として普及することによって、ギリシャの古典が全盛となり、旧来の文学作品がこっそり翻案され(エルナニヤスとかマクベテエスとかナナイスとか)るが、全然太刀打ちできない、などという小ネタが投入されてます。なぜにギリシャ語かというのは、田辺訳によれば一応、「英帝国が瓦解し、希臘―露西亜帝国が再びコンスタンチノープルを略取するに及んで、終に希臘語が世界語たるの栄冠を獲ることになつた。」と説明されているが、同様の記述がある英訳版を読んだブライラーは全然納得してません。
文学研究者として上田敏はここのところをきっちり拾いにいってます。というか、説明を加えて文学談義の部分を目茶苦茶膨らましてます。その辺の洒落っ気は邦訳版ではわかりにくくなっているせいもあってか、横田氏はスルー。
細かいストーリーについては永瀬、横田両氏の紹介に任せ、以下、脇道にそれる。
『未来史の断片』は訳した人が田辺寿利(1894―1962)という社会学の大家。どれぐらい偉いかというと、1979年から2001年にかけて、未來社から著作集が刊行されたほど。まあ全5冊に22年もかかっちゃったと見るか、22年かけても完結させようという熱意をもたれた人と見るかで評価は割れるかもしれませんが。著作集の編纂者は訳書も収録する構想で、初期のラインナップには訳書編3冊があったのだが、出版社に蹴られたらしく、かろうじて5巻に訳者序文が収められるにとどまっている。この序文に「社会学読書会」で紹介したところ翻訳を勧められたとあり、調べるとこれは大正12、3年頃のことらしい。この会の後身が「東京社会学研究会」で、その第4回例会(大正13年11月15日)で「タルドの将来社会観に就いて」という講演が行われており、それを元にした論文が『未来史の断片』に収録される予定だったが、実現されないままに終わった。果たして刊行後になんらかの形で活字化されているのかどうか気になるところである。社名が社名なんだから未來社の人には『未来史の断片』を再刊して、併せて関連資料を発掘収録していただきたいところである。
ところで英訳版の序文でウェルズは何を書いたってとこに、皆、興味があるかと思う。そのうちどっかで誰かが訳すだろうから2点だけ注目ポイントを紹介しておく。まず一つは、フランスでは洒落が通じてええのぉ。というモンティ・パイソンのお国柄とも思えぬ発言。「おめー、英米であんなもん出版したらえらいことになるぜっ、例えばハーバート・スペンサーが未来小説書いてみ、たちまち名声は地に落ちて学者生命なくして路頭に迷うね。」(大意)
まあ、スペンサーの書いているものは十分トンデモな気がするので、厭味でいってるのかも。
あと注目すべきは以下の一文。
You imagine the gentlemen in that Utopia moving gracefully ― with beautifully trimmed nails and beards ― about the most elegant and ravishing of ladies, their charm greatly enhanced by the pince-nez, that is in universal wear.
この部分の田辺訳は横田氏も引用しているし、上田敏ヴァージョンにもちゃんと出てくる。
(田辺訳)
「只残念なことには。近視眼だけは進歩を遂げた、これ、読書物の刊行が異常に普及した結果である。従って、婦人でも小児でも、鼻眼鏡をかけないものは一人もないことになつてしまつた。」
(上田敏)
「然し著者の滑稽趣味はここにも現はれて居る。というふのは近眼だけは。文明の進歩と共に、どうして無くなす訳にいかず、新聞雑誌の発達は愈々近眼を多くした。だから女子も児童も皆鼻眼鏡を掛けてゐるとは頗る可笑しい。」
タルドの場合、女子供は無知蒙昧な輩であって、文盲で眼を悪くするはずねぇ、という19世紀のジェンダー・バイアスを基盤にして、それが未来において逆転されるところにおかしさを求めるギャグとしてこの件が書かれていると推察されるのだが、ウェルズの広げ方はちょっと凝りすぎているような気がする。「charm」が「greatly enhanced」ですぜ。どうもこの記述には、未来のおねーちゃんは皆、メガネっ娘だ。バンザーイ、バンザーイ。というのが含包されている。いや、そうに違いない。そうに決めた。というのがウェルズ=メガネフェチ説。
ウェルズといえば、見かけどおりのスケベおやじですが何か、と偽悪的に女性遍歴を綴った自叙伝があって、確かH.G.Wells in loveとして公刊されとったと思うが、つきあったおねーちゃんとして名前を思い出せるのはレベッカ・ウェストぐらいだね。
そのレベッカたんは、ウェブで図像を検索した限りではメガネっ娘じゃなかったらしい。ただ確か当時、新進気鋭のジャーナリストだったはず。
ようするにウェルズの女性の好みは才気煥発の知的な娘さんだったらしく、メガネに付与された知性という記号性(メガネ=近視=読書=知性という連想)から、メガネっ娘=知的、萌えっ。ということになっていたらしい(←決め打ちすんなよっ)。
井上章一の美人論で、美人は頭が悪いとか、巨乳はアホとかいう言説が検証され歴史化されているんだと思うけれど、女性とメガネというテーマ設定はなされていないような気がする。最近のオタク・カルチャー研究に疎いだけで、既にメガネっ娘をめぐる言説とジェンダーの歴史というのは研究されとるのかのお。ま、研究するまでもなく自明だということになっとるのかもしれんが。
永瀬唯氏は『腕時計の誕生』の序章でサイボーグを補綴ではなく拡張のデバイスと定義しつつ、「つる付きの眼鏡という"道具"を措いて考えれば」と腕時計の歴史を語り出している。つまり眼鏡を補綴装置として切捨ててはいないので、サイボーグ史的な視点とメガネフェチを絡めた『眼鏡の近代』見たいな本が書かれる余地はありそうな気がするがそーゆー予定はないのか。
さて、ここいらで話を上田敏に戻して終わりにしよう。
「又他の者は勇敢にも、昇降機に乗つて死火山の噴火口にまで上ぼり行き、外界の空気に触れ瞬く間に凍死するものもある。彼等は青い空や――非常に美しいといふことであるが――今でも矢張死に瀕してゐる太陽のほの暗い色合や、又広く自然に秩序もなく散つてゐる多くの星やをよく見る暇もない中に、氷の上で二人互に固く抱き合って死んでしまふのである。彼等の愛する噴火山の頂上は、常に二つづヽ立派に保存された彼等の死骸で全く取巻かれてゐる。」(田辺訳)が上田の手にかかるとこうである。
「随て一種の心中が流行する。昔の心中は身投が多かつたが、今日のはそれと反対で、身上である。即ち死火山の坑中より外界に突出すると、忽ち凍死する仕掛なので、山上の坑口に出づれば、茫茫たる蒼空に垂死の日輪懸り、星斗爛干として、崇高極み無しといふ話であるが、もう其時は両々相抱いて氷上に倒れるのであるから、真偽のほどは保証できない。心中の流行る噴火坑口には青年男女の屍体累々として横はつてゐるさうだ」
さすが怪獣SFを書くだけあって(書いてません)、上田敏あなどりがたし(書いてないといっておろうがっ)。これなら横田順彌に対抗してもなんとかやっていけるのではないか。惜しい人をなくしたものである。
(注1)筒井康隆を読めっ。
(注2)なんでまた俺が上田敏を読み始めたかと思い返すと、教え子伝説を検証するための資料収集の一環だったのである。すっかり忘れてたよ。
  |
「穴居の民」
初出:<新小説>
第11年第5巻、明治39年5月1日、173〜176頁。
第11年第6巻、明治39年6月1日、思潮・17〜26頁。
第11年第7巻、明治39年7月1日、思潮・14〜24頁。
→単行本:『定本上田敏全集 第7巻』教育出版社、昭和55年9月10日。