まさかあるとは思っていなかった人事異動の不意打ちに調子を狂わされっぱなし。低空飛行な生活が信条だったのに上昇気流に乗れといわれてもなぁ。落ち着いて音楽も聴けやしない。眠い目をこすりながら本を読んでるとおもしろくてもいつの間にか寝てしまうよ。
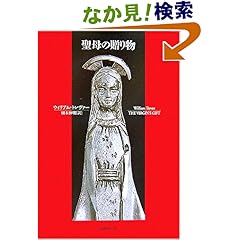 エムシュウィラーが読める叢書なら読んでおこうかと手を出したウィリアム・トレヴァー『聖母の贈り物』は全然SFじゃないけれど、面白い短編集。冒頭の「トリッジ」の意地悪さでツカミはOK。次の「こわれた家庭」はスラップスティックで書かれたタイプなら、既に似たような話があるけれど、トレヴァーは乾いた描き方なので不条理な悲惨さから笑いが出てくるわけではない。
収められた10編は「トリッジ」を別としてエンターテインメント的な物語で楽しませるようなものは少なく、物語をつむぎ出す手付きに魅力があるようだ。3部作になっている中編「マティルダのイングランド」と表題作が強く印象に残る。ところどころにシリアスな描き方をするラファティという趣がある。
エムシュウィラーが読める叢書なら読んでおこうかと手を出したウィリアム・トレヴァー『聖母の贈り物』は全然SFじゃないけれど、面白い短編集。冒頭の「トリッジ」の意地悪さでツカミはOK。次の「こわれた家庭」はスラップスティックで書かれたタイプなら、既に似たような話があるけれど、トレヴァーは乾いた描き方なので不条理な悲惨さから笑いが出てくるわけではない。
収められた10編は「トリッジ」を別としてエンターテインメント的な物語で楽しませるようなものは少なく、物語をつむぎ出す手付きに魅力があるようだ。3部作になっている中編「マティルダのイングランド」と表題作が強く印象に残る。ところどころにシリアスな描き方をするラファティという趣がある。
 筒井康隆『ヘル』が文庫になったので読んだが、特に感想はない。ここで披露されたものが様々な筒井的テクニックのうちでは、それほど効果的なものではなかったということかな。
筒井康隆『ヘル』が文庫になったので読んだが、特に感想はない。ここで披露されたものが様々な筒井的テクニックのうちでは、それほど効果的なものではなかったということかな。
 時々更新される作者のブログを読みながら待っていた清水マリコ『日曜日のアイスクリームが溶けるまで』は珍しく大人のOLが主人公なんだけれども、話が始まってすぐにノスタルジー/ファンタジイへと傾斜していく。主人公の設定が日常を強く引きずっているために、ファンタジイの方に変な錘が付いてしまっている。今回は物語のバランスが悪すぎるなぁ。残念。女性作家が競馬場を舞台にするようになったのは最近のことなのか。
時々更新される作者のブログを読みながら待っていた清水マリコ『日曜日のアイスクリームが溶けるまで』は珍しく大人のOLが主人公なんだけれども、話が始まってすぐにノスタルジー/ファンタジイへと傾斜していく。主人公の設定が日常を強く引きずっているために、ファンタジイの方に変な錘が付いてしまっている。今回は物語のバランスが悪すぎるなぁ。残念。女性作家が競馬場を舞台にするようになったのは最近のことなのか。
 東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生−動物化するポストモダン2』は前作ほどスッキリしていない感じがある。題材が前作と同傾向のもので語っているので余計そう感じるのかも。ここで取り上げられた具体的作品の内、読んだのは『All
You Need Is Kill』だけだが、この作品に関する東浩紀のぬきんでた作品という評価を割とどうでもいい感じに受け取ってしまうのは、東浩紀がこの作品を論考のための参照見本にしているからだろう。表面的にオタク作品ばかりが取り上げられているにしても、本書の提示しているものは社会学的な概念道具だったような気がする。ちなみに『SFマガジン』7月号掲載の東浩紀批判は「正しさ」を謳っていまどきめずらしい青臭さ。頼もしい。
東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生−動物化するポストモダン2』は前作ほどスッキリしていない感じがある。題材が前作と同傾向のもので語っているので余計そう感じるのかも。ここで取り上げられた具体的作品の内、読んだのは『All
You Need Is Kill』だけだが、この作品に関する東浩紀のぬきんでた作品という評価を割とどうでもいい感じに受け取ってしまうのは、東浩紀がこの作品を論考のための参照見本にしているからだろう。表面的にオタク作品ばかりが取り上げられているにしても、本書の提示しているものは社会学的な概念道具だったような気がする。ちなみに『SFマガジン』7月号掲載の東浩紀批判は「正しさ」を謳っていまどきめずらしい青臭さ。頼もしい。
 最相葉月『星新一 一〇〇一話をつくった人』はすでにその素晴らしさが言い尽くされた観があるノンフィクション。大森望がSFMで書いたことが大方のロートルSFファンの思うところだろう。50代の星新一を大長老として遇してしまったSFファンとその空気を醸成したのが小松・筒井両巨頭というのは振り返ってみれば気の毒としか言えないけれど、それを諒と出来なかった星新一も悲しい。
最相葉月『星新一 一〇〇一話をつくった人』はすでにその素晴らしさが言い尽くされた観があるノンフィクション。大森望がSFMで書いたことが大方のロートルSFファンの思うところだろう。50代の星新一を大長老として遇してしまったSFファンとその空気を醸成したのが小松・筒井両巨頭というのは振り返ってみれば気の毒としか言えないけれど、それを諒と出来なかった星新一も悲しい。
長く長くて何回も本を握ったまま落ちたダン・シモンズ『オリュンポス』。上巻は面白くてスラスラ読めたのに、下巻で神々の殺し合いが終わるあたりから10ページ読むたびにダウン。物語後半部より訳者あとがきと「註解」の方がおもしろいという始末。もともとダン・ブラウンじゃない(無意識にブラウンと打っちゃったよ)ダン・シモンズとはあまり相性がよくないので、いままででも上巻(もしくは第1部)に比べて下巻(もしくは第2部)はちょっと興味が逸れてしまうことがあったけれども、今回はひどかった。こちらの体調の所為もあるんだろうが。それにしてもこの世界における時間の一致に納得がいかないんですけど(作者も訳者もそこはQTなので許せといっている?)。
 プリーストを読んでる最中に読み飛ばしてしまった大森望・豊崎由美『文学賞メッタ斬り!2007年版 受賞作はありません編』(最近はダラダラと副題が付くものが多いなあ)。相変わらずの芸だけれど、中原昌也の作家キャラのつくり方とか芥川賞・直木賞ハズレ対談とか笑いました。それにしても取り上げられたものの中に読みたくなるような作品がほとんどないなあ。
プリーストを読んでる最中に読み飛ばしてしまった大森望・豊崎由美『文学賞メッタ斬り!2007年版 受賞作はありません編』(最近はダラダラと副題が付くものが多いなあ)。相変わらずの芸だけれど、中原昌也の作家キャラのつくり方とか芥川賞・直木賞ハズレ対談とか笑いました。それにしても取り上げられたものの中に読みたくなるような作品がほとんどないなあ。
 プラチナ・ファンタジイの謳い文句がとてもちっちゃいクリストファー・プリースト『双生児』。そこまで小さくするならもうやめればいいのに。出だしと目次からしてたくらみはほぼわかっているのにグラグラと揺らぐ世界のそのゆれ具合が気持ちいい作品。読み終えた後で大森望の解説を読み、何もそこまで蘊蓄を傾けなくてもとは思った。空ぞらしいくらいの改変歴史物なのにプリーストの叙述スタイルとテクニックの冴えがまったくそのようなことを感じさせない。ニセ・イングランド作家(そんなのがあるのかどうかは知らない)として完成されつつあるプリーストという感じ。この本物のニセモノっぽさはSF界以外のどこで評価されるのか。
プラチナ・ファンタジイの謳い文句がとてもちっちゃいクリストファー・プリースト『双生児』。そこまで小さくするならもうやめればいいのに。出だしと目次からしてたくらみはほぼわかっているのにグラグラと揺らぐ世界のそのゆれ具合が気持ちいい作品。読み終えた後で大森望の解説を読み、何もそこまで蘊蓄を傾けなくてもとは思った。空ぞらしいくらいの改変歴史物なのにプリーストの叙述スタイルとテクニックの冴えがまったくそのようなことを感じさせない。ニセ・イングランド作家(そんなのがあるのかどうかは知らない)として完成されつつあるプリーストという感じ。この本物のニセモノっぽさはSF界以外のどこで評価されるのか。
THATTA 229号へ戻る
トップページへ戻る
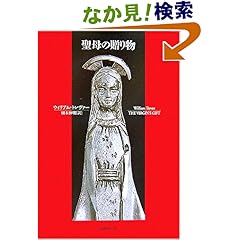 エムシュウィラーが読める叢書なら読んでおこうかと手を出したウィリアム・トレヴァー『聖母の贈り物』は全然SFじゃないけれど、面白い短編集。冒頭の「トリッジ」の意地悪さでツカミはOK。次の「こわれた家庭」はスラップスティックで書かれたタイプなら、既に似たような話があるけれど、トレヴァーは乾いた描き方なので不条理な悲惨さから笑いが出てくるわけではない。
収められた10編は「トリッジ」を別としてエンターテインメント的な物語で楽しませるようなものは少なく、物語をつむぎ出す手付きに魅力があるようだ。3部作になっている中編「マティルダのイングランド」と表題作が強く印象に残る。ところどころにシリアスな描き方をするラファティという趣がある。
エムシュウィラーが読める叢書なら読んでおこうかと手を出したウィリアム・トレヴァー『聖母の贈り物』は全然SFじゃないけれど、面白い短編集。冒頭の「トリッジ」の意地悪さでツカミはOK。次の「こわれた家庭」はスラップスティックで書かれたタイプなら、既に似たような話があるけれど、トレヴァーは乾いた描き方なので不条理な悲惨さから笑いが出てくるわけではない。
収められた10編は「トリッジ」を別としてエンターテインメント的な物語で楽しませるようなものは少なく、物語をつむぎ出す手付きに魅力があるようだ。3部作になっている中編「マティルダのイングランド」と表題作が強く印象に残る。ところどころにシリアスな描き方をするラファティという趣がある。






