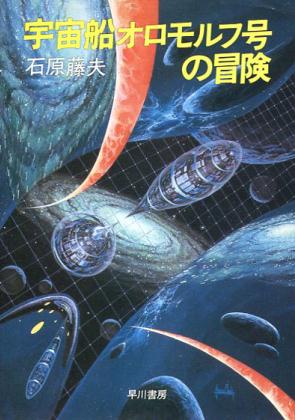
石原藤夫 『宇宙船オロモルフ号の冒険』 解説
大野万紀
ハヤカワ文庫JA
1984年8月20日発行
(株)早川書房
ISBN4-15-030191-3 C0193
ハードSFというジャンルは、非常に明確なようでいて、その実定義の難しいジャンルである。
例えば『SFエンサイクロぺディア』のピーター・ニコルズは、この用語に具体的な適用例がかなり異なる二つの用法があると述べている。その第一は「いわゆるSFの黄金時代に書かれたジャンルSFのテーマと、多くの場合そのスタイルを、反復しているような種類のSFをいう(浅倉久志訳)」。またその第二は「いわゆる〝ハード″サイエンスを扱っているSFをいう」。わが国でハードSFといえば、通常この第二の意味で使われることが多い(少なくともファンの間では)が、しかしこれはとても定義といえるものではない。
もう少し踏み込んだものとしては、本書の作者である石原藤夫さんのものがある。堀晃さんの『梅田地下オデッセイ』の解説として書かれたものだが、ぼくなりに要的すると次のようになる。
「(狭義の)ハードSFとは、〈ハードな問題意識〉〈ハードな舞台設定〉〈ハードな展開〉〈ハードな解決〉という、(広義の)ハードSFが持つべき四つの側面をすべて共有するものである」。
ここで〝ハードな″という言葉は、特に理工学的な知識に基づいた、科学的ないしは空想科学的な認識や手法を意味している。石原さんがとりわけ重視しているのは、このうちハードな展開と解決という部分だ。現代科学と人間社会の関係についての鋭い問題意識をもち、豊富な科学知識をたっぷりともったSFは、(それだけでは)良質の本格SFであっても、石原さんのいうハードSFにはならない。そのためには、さらに、ストーリーの展開と解決とが〝科学的論理または科学的手法をもつ空想科学的論理″によっていなければならないのである。
これはかなり厳しい定義である。表面だけを見て意識的にこのようなSFを書こうとすると、かえって単純なアイデア・ストーリーとなってしまう恐れがある。こういう種類のハードSFは、作者のもつ科学知識や科学的認識がいわば肉体化されていて、作品中に自然に現れるような場合でなければ実現困難だろう。もちろんこれは何らかの価値判断を含んだ定義ではないから、この定義に合わないSFがつまらないといったことではないのだが。実際、石原さんはストレートSFの領域外へも広がっている広義のハードSFというものを否定していない。石原さん自身の書かれるSFの中にも、そのようなものが多く含まれているのだ。
しかし、とはいっても、ハードSFの神髄はこの狭義の定義にあるというのが、おそらく石原さんの指摘したいところだろうと思う。石原さんはわが国で最も熱心で実践的なハードSFの研究者であり、書き手である。氏の設立された「ハードSF研究所」は、熱心なハードSFファンの同好会組織だが、幅広く有能な人材を集めており、通常のファン活動をはるかに越えた専門的な研究を行っている。優れたハードSFを書くには、(そしてその本当の醍醐味を味わうには)、科学とSFの双方を肉体化することが望ましく、そのためにはある程度の訓練が必要だということかも知れない。
さて、本書は数学的イマジネーションをSFの舞台で展開した、ハードSFの極致ともいうべき作品である。本書の成り立ちについては、石原さんのあとがきに実に明解に書かれており、ほとんど何も付け加えることはない。また本書は〈ハードな問題意識〉――「応用数学の問題をそれ自体独立した存在として描けばどうなるか」、〈ハードな舞台設定)――「現実にある巨大組織のシステム・エンジ二アリングを、巨大宇宙船としてモデル化する」、〈ハードな展開〉――「形を変えた数学的問題を、様々な解法で解こうと試みる」、〈ハードな解決〉――「数学的に正しく納得のいく方法で解が得られる」、というハードSFの四条件を全て満たしており、疑いなく狭義のハードSFの定義に合致する作品である。けれども、本書は決して純粋ハードSFの観点からのみ評価されるべきものではない。数学的幻想と組織論の面白さは、専門知識をもたない一般の読者にも、充分堪能することができるからである。
数学は本来サイエンスとは異なった領域のものである。しかし、SFでは伝統的に数学的幻想――代表的なものに四次元の世界がある――をハードSFの領域に含めて考えることが多い。だが同じハードSFといっても、そこから受ける感覚は、例えば宇宙船や未来のハードウェアを扱ったものとは大きく異なっている。未来の日常性ではなく、むしろファンタジイに近い非日常感覚に中心があるのだ。この点について『SFエンサイクロペディア』では次のように考察している。
「数学的アイデアが好奇心を刺激するのは、われわれの住む世界にそれらが通用しないという事実であり、したがって、そうしたアイデアを脚色した物語は、起こりうる事件の記録としてはまったく信頼性をもちえず、ファンタジイとして分類しなければならない。しかしながら、このタイプの物語を判定する上で、それが数学的真理に忠実かどうかということも、重要な考慮の材料になる。もし忠実ならば、その点で、その物語はファンタジイから最も遠く隔たったSFの一部、定着した科学のある一点に関わる物語から成る一部に所属するといえる(トニー・サドベリー、浅倉久志訳)」。
また、同じ著者は、いささか皮肉な口調で次のようにも述べている。
「幾何学やトポロジーからいただいた概念は、本質的に奇異で謎めいた性質を持っていて、それを直観で受け入れようとする門外漢に楽しい労苦を与えてくれる上、アカデミックな由緒正しさの御威光で、読者はその労苦を価値あるものと思いこみ、こうして驚異の感覚が倍加するのである」。
実際、ぼくの友人のあるSFファンは、全くの文科系の人間で、微分方程式という言葉に何のイメージもわかないという男だが、本書が大変おもしろかったという。理解はできないが、タンギーの絵のような抽象的なイメージが浮かぶのだそうだ。そしてそれが、単なる幻想ではなく、何か(自分には分からないが)教学的裏付けがあるらしいというところがいいのだ。実はこれこそが、この種のSFの本来の楽しみ方だといっていいだろう。
しかし、本書のユニーク性は、もう少し違ったところにある。それは本書が一般の数学SFではなく、応用数学SFという、ほとんど世界でも他に例を見ないテーマのSFだということである。本書は、世界中で毎年書かれる大変な量のSFの中で、真にユニ-クだといえる、数少ない一冊なのである。大げさなようだが、いわば日本SF史上に残るべき傑作なのだ。
これまで数多く書かれてきた数学SFは、そのほとんどが、いわゆる純粋数学の分野を題材としていた。ところが本書の数学は、もっと実用的な、基礎となる教学なのである。つまり、現実のテクノロジーを可能にするための様々な計算や、自然法則を表現するための方程式を記述するのに必要な数学なのだ。これは十九世紀までにほとんど完成していたものであり、古典的な数学といっていい。本書の中では考古数学と呼ばれている。またこれは、理工系の大学生の必須科目となっているものである。
そこで理工系の読者にとっては、本書に出てくる数学的イメージは、(好き嫌いは別として)とても具体的な、グラフィックなものとならざるをえない。文科系の読者に比べてイメージの自由度が小さいのである。そのかわり、学生時代の思い出などとも結び付いた、私的な感情がまとわりついてくる。石原さんのあとがきにある「きわめて私的な心境をつづったものとなった」という述懐も、理工系の読者には容易に納得ができるだろう。
本書がユニークなもう一つの点は、現実の巨大組織をアナロジーにより、きわめて迫真的に描き出したということである。何事も巨大な管理機構の泥沼を通さねばならず、各部の縄張り意識も強烈で、足の引っ張りあいばかり。それでいて結構うまく運営されているのだ。オロモルフ号は、SFに登場した最も生々しく現実的な管理システムの一つだといっていいだろう。
このオロモルフ号は、宇宙船ではあるが、現実のハードウェアでできたものではない。むしろ一つのシステムの象徴であり、ソフトウェアであるといった方がいいだろう。その目的は、人間の科学文明をささえる応用数学の有用性を確認し、さらにいえば、あくまでも〝微分可能性″に固執することである。科学にとっての微分の重要性は石原さんの書かれている通りである。ぼくの怪しげな思いつきのスローガンの一つに「センス・オブ・ワンダーは微分方程式だ」というのがある。逆に微分方程式を見てセンス・オブ・ワンダーを感じるというのが、神林長平さんだ。いずれにせよ、それ自体は抽象的な存在でありながら、現実のテクノロジーや自然現象と切っても切れない関係にある、生きた存在としての数学に光を当てた本書は、きわめてユニークな、〝ソフトウエア″ハードSFなのである。
初出一覧表
第一章 危機 SFマガジン49年5月号 [複素関数の特異点]
第二章 挑戦 SFマガジン50年2月号 (加筆)[四次元方程式の変数分離]
第三章 復活 SFマガジン51年11月号 [シュヴァルツシルト解のクラスカル表示]
第四章 苦闘 SFマガジン55年3月号 [漸近級数展開]
第五章 凱歌 SFマガジン55年11月号 [変分論と集合論]
1984年7月