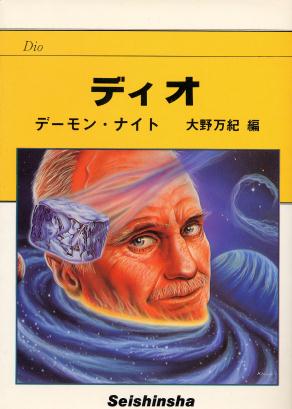
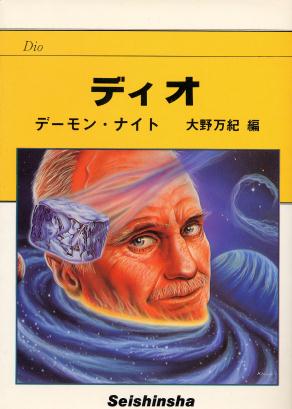
丂僨乕儌儞丒僫僀僩乛戝栰枩婭懠栿
丂亀僨傿僆亁丂夝愢
丂戝栰枩婭
丂惵怱幮SF僔儕乕僘
丂侾俋俉俀擭係寧俁侽擔敪峴
丂乮姅乯惵怱幮
Dio by Damon Knight (1957)丂擔杮僆儕僕僫儖曇廤
乗乗巚偆偵丄僨乕儌儞丒僫僀僩偼丄偙傟傑偱偵僒僀僄儞僗丒僼傿僋僔儑儞偑惗傒弌偟偰偒偨嵟傕廳梫側暥妛幰偲偄偭偰傕丄偍偐偟偔偼側偄偩傠偆丅
僶儕乕丒N丒儅儖僣僶乕僌
丂堦嬨屲乑擭堦寧丄偦偺嶰僇寧慜偵惗傑傟偨偽偐傝偺堦偮偺嶨帍偑丄帍柤傪曄偊偨丅僼傽儞僞僕僀丒傾儞僪丒僒僀僄儞僗丒僼傿僋僔儑儞乮F仌SF乯帍偱偁傞丅摨偠擭偺廫寧丄傕偆堦偮偺嶨帍偑憂姧偝傟丄僊儍儔僋僔僀帍偲柤偯偗傜傟偨丅偙偺擭丄亀壩壆擭戙婰亁偑杮偵側傝丄亀塅昪慏僺乕僌儖崋亁偑弌斉偝傟丄亀抧媴恖傛丄屘嫿偵娨傟亁傗亀柌尒傞曮愇亁偑嶨帍偵宖嵹偝傟偨丅噣SF偺恀偺墿嬥帪戙亶乮儘僶乕僩丒僗僐乕儖僘乯屲乑擭戙偑丄偙偆偟偰巒傑偭偨偺偱偁傞丅
丂屲乑擭戙SF乗乗偦傟偼屆偔偐傜偺SF偺僼傽儞偵偲偭偰丄扨側傞僲僗僞儖僕乕埲忋偺嬁偒傪傕偭偨偙偲偽偩丅傢偑崙偱偼堦嬨榋乑擭偵SF儅僈僕儞偑憂姧偝傟丄偦傟偐傜徯夘偝傟偨塸暷SF偺懡偔偑偙偺帪戙偺傕偺偩偭偨偙偲傕庤揱偄丄偝傜偵撈帺偺擬偭傐偝傪傕偭偰乮偦偟偰摉慠側偑傜丄摨偠偔傜偄偺斀敪傕堷偒婲偙偟偮偮乯岅傜傟偰偄傞丅偩偑丄屲乑擭戙偺塸暷SF偑丄懡偔偺撉幰偵丄偁偺嵟傕SF傜偟偄SF偺傕偮撈摿偺枺椡傪姶偠偝偣傞傕偺偩偲偄偆偙偲偼丄傑偢娫堘偄側偄偲偙傠偩傠偆丅
丂弴晄摨偵楍嫇偟偰傒傛偆丅亀梒擭婜偺廔傝亁丄亀廳椡偺巊柦亁丄亀壞傊偺斷亁丄亀攋夡偝傟偨抝亁丄亀屨傛両屨傛両亁丄亀恖娫埲忋亁丄亀塅拡彜恖亁丄亀壺巵巐屲堦搙亁丄亀僾儗僀儎乕丒僺傾僲亁丄亀峾揝搒巗亁丄亀奀掙杚応亁丄亀抧媴恖偺偍壸暔亁丄亀埫崟惎塤亁丄亀僞僀僞儞偺梔彈亁丄亀塅拡偺愴巑亁丄亀搒巗偲惎亁丄亀壩惎恖僑乕儂乕儉亁丄亀塅拡偺娽亁丄亀栙帵榐嶰堦幍巐擭亁丄亀埆杺偺惎亁乧乧SF慡廤偑偱偒偁偑偭偰偟傑偆丅抁曆丠丂偁側偨偺怱偵巆偭偰偄傞塸暷SF偺抁曆傪傂偲偮偁偘偰傒偰偔偩偝偄丅偦偺敿暘埲忋偼屲乑擭戙偵彂偐傟偨傕偺偱偁傞偼偢偩丅偙偺偄偄偐偘傫側儕僗僩傪尒偰傕偡偖傢偐傞傛偆偵丄屲乑擭戙SF偲偼丄SF偲偟偰摨偠暤埻婥傪傕偭偰偄傞偑丄寛偟偰儚儞丒僷僞乕儞偱傕儅儞僱儕偱傕側偐偭偨偺偩丅尰嵼偺傢傟傢傟偼丄偲傕偡傟偽偙偙廫擭偁傑傝偺SF偺乂怹摟偲奼嶶乂傪抦偭偰偄傞偩偗偵丄夁嫀偺SF偑嫹偄僎僢僩乕偵偙傝屌傑偭偨傕偺偩偲偄偆報徾傪書偒偑偪偱偁傞丅帠幚偼丄昁偢偟傕偦偆偱偼側偐偭偨偺偩丅撉幰憌偺奼戝偵偼幐攕偟偨偑乗乗偦偺偨傔僽乕儉偼曵夡偟屻偵偼幐朷姶偲僯僸儕僘儉偑巆偭偨乗乗偦偺拞偱屲乑擭戙偺SF偼偁傜備傞曽岦偵揔墳曻嶶傪偲偘偨偺偱偁傞丅
丂偦偺偙偲偼抁曆偺暘栰偱摿偵偄偊傞丅屲乑擭戙SF傪巟偊偨戝偒側拰偺堦偮偼丄埑搢揑側検偲幙偺抁曆SF偱偁傞丅
乗乗偟偐偟丄僒僀僄儞僗丒僼傿僋僔儑儞偼懠偺僇僥僑儕僀偲堎側傝丄抁曆宍幃偲偟偰傕懚懕偟偰偄傞偺偩丅抁曆偲偄偆傕偺偼丄乮嵞傃媍榑偺僞僱偵側傞偲巚偆偑乯僒僀僄儞僗丒僼傿僋僔儑儞偵嵟傕揔偟偨壽戣偱偁傞丄堦偮偺巚曎揑奣擮傪柧敹壔偟採帵偡傞偺偵棟憐揑側峔憿偲傕偄偊傞偩傠偆丅偦偟偰丄媄朄揑側抦幆偲撈憂惈偵偍偄偰丄偙偺廫擭偼抁曆SF偺儗儀儖偑懠偵椶傪尒偸偼偳崅傑偭偨帪偱傕偁傞丅嵟嬤偺廫屲擭埲撪偵敪昞偝傟偨偳傫側抁曆傕丄偙偺偙傠掕婜揑偵擭姧寙嶌慖傗嶨帍擭姧寙嶌廤偵尰傢傟偨嶌昳傎偳偵偼丄撉幰偲偦偺暘栰偵徴寕傪梌偊偰偄側偄丅
乽堦嬨屲乑擭戙SF乿僶儕乕丒儅儖僣僶乕僌丂埨揷嬒栿
丂儅儖僣僶乕僌偲偄偆恖偼丄偄偔傇傫儅僀僫乕側尰戙偺傾儊儕僇SF嶌壠偱偁傞偑丄偦偺斸昡娽偼戝偄偵擣傔傜傟偰偄傞丅斵偺榑嫆偵偼愢摼椡偑偁傝丄嫟姶偱偒傞偲偙傠偑懡偄丅偦偺斵偑丄崱傗僲僗僞儖僕乕偺懳徾偱偁偭偨傝丄妝揤揑偱扨弮慺杙側SF偺戙柤帉偲偟偰旂擏偵岅傜傟偨傝偡傞乂屲乑擭戙SF乂傪愨巀偡傞偺偼丄偦傟偑寛偟偰夰偐偟偝偩偗偱岅傜傟傞傋偒傕偺偱傕丄妝揤揑偱扨弮慺杙側偩偗偺傕偺偱傕側偐偭偨偐傜偱偁傞丅偦偆偱偼側偄偺偩丅愴慜偺僗儁乕僗丒僆儁儔偑儕僶僀僶儖偡傞偺偼傓偟傠榋乑擭戙埲崀偱偁傝丄屲乑擭戙偺SF偼傾僀僨傾偺柺偱傕媄朄偺柺偱傕丄愻楙偲懡條壔偺嬌抳偵払偟偰偄偨偺偱偁傞丅
丂偟偐偟丄崱傗丄屲乑擭戙偼乂帪偺拞偵搥傝偮偄偨帪戙乂偲側偭偰偟傑偭偨丅挿曆偼壗搙傕嵞斉偝傟偰偄傞丅亀梒擭婜偺廔傝亁偼扤偱傕抦偭偰偄傞丅偩偑丄抁曆偼丄嶨帍偵堦搙東栿偝傟偨偒傝乗乗偦傟傪撉傫偩偙偲偺偁傞崱傗擇乑戙屻敿埲忋偺撉幰偵朰傟傜傟偸報徾傪巆偟偨傑傑乗乗徚偊偰偄偭偨偺偩丅
丂偦偺屲乑擭戙偺抁曆SF偺拞偵偁偭偰丄傂偲偒傢婸偄偰偄傞偺偑丄僨乕儌儞丒僫僀僩偱偁傞丅
丂朻摢偱徯夘偟偨堷梡暥偼丄堦嬨幍榋擭偵弌斉偝傟偨僫僀僩偺寙嶌慖乗乗乂寙嶌慖乂拞偺寙嶌偲偺昡壙偑崅偄乗乗偵偮偗偨丄儅儖僣僶乕僌偺彉暥偱偁傞丅儅儖僣僶乕僌偼屲乑擭戙偺抁曆SF嶌壠偺拞偱傕丄僫僀僩傪偲傝傢偗崅偔昡壙偟偰偄傞偺偩丅偦傟偼傕偆愨巀傪捠傝墇偟偰儊儘儊儘偺堟乮丠乯偵傑偱払偟偰偄傞丅
丂僫僀僩傪昡壙偡傞偺偼壗傕儅儖僣僶乕僌偩偗偱偼側偄丅挊柤側嶌壠傗曇廤幰丄僼傽儞偑丄僫僀僩偵尵媦偡傞帪偵偼偨偄偰偄帡偨傛偆側忬懺偵側偭偰偟傑偆偺偩丅偦傟偵偼丄傕偪傠傫僫僀僩偺恖娫揑側枺椡丄偝傑偞傑側暘栰偱偺SF奅傊偺峷專偑峀偔擣傔傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲傕偁傞丅偲傝傢偗丄尰嵼偱偼丄嶌壠偲偟偰傛傝傕丄傓偟傠曇廤幰丄斸昡壠丄慻怐偯偔傝偺榬丄偲偄偭偨柺偑崅偔昡壙偝傟偰偄傞丅榋乑擭戙埲崀丄嶌昳偑悢偊傞傎偳偟偐側偐偭偨偨傔偩丅偗傟偳傕乗乗傕偆堦搙丄儅儖僣僶乕僌偵戙曎偟偰傕傜偍偆丅
乗乗僫僀僩偼丄傑偢戞堦偵丄斵偺峴側偭偨偁傜備傞妶摦偵偍偄偰戩墇偟偰偄傞乗乗曇廤丄昡榑丄挿曆丄抁曆丄偦偟偰偄偔偮偐偺偲傎偆傕側偔斱辔側媃帊偵偍偄偰偝偊傕丅傕偆傂偲偮偺帠幚偼丄斵偺斸昡壠丄曇廤幰偲偟偰偺柤惡偑丄庒偄嶌壠傗撉幰偺栚傪暍偄偑偪側偺偩偑丄堦嬨屲乑擭戙偵斵偑惗傒弌偟偨堦孮偺彫愢偼偢偽敳偗偨傕偺偩偭偨偺偱偁傞丅H丒L丒僑乕儖僪偑敪孈偟偨悢懡偄嶌壠偺拞偱傕丄僫僀僩偼丄幮夛晽巋偲斸昡偺攠懱偲偟偰偺僊儍儔僋僔僀帍偵偍偄偰丄偍偦傜偔嵟傕摿挜揑側嶌壠偱偁傝丄傎偲傫偳嵟椙偺傕偺偩偭偨偲偄偭偰偄偄丅
亀僨乕儌儞丒僫僀僩寙嶌慖亁彉暥
丂杮彂偼丄偦偺屲乑擭戙偺僫僀僩偺抁曆偺偆偪丄杮朚弶栿偺嶌昳偽偐傝傪撈帺偵廤傔偨抁曆廤偱偁傞丅幍曆拞屲曆傪僊儍儔僋僔僀帍丄擇曆傪僀儞僼傿僯僥傿帍偐傜偲偭偨丅椉帍偲傕丄僫僀僩偑偦偺嵥擻傪偍偍偄偵敪婗偟偨嶨帍偱偁傞丅
丂僊儍儔僋僔僀帍偼屼彸抦偺捠傝丄屲乑擭戙傪戙昞偡傞乮傕偪傠傫偦傟偩偗偱側偔丄偮偄嵟嬤傑偱偢偭偲寬嵼偩偭偨乯SF嶨帍偱丄堦晹偱偼F仌SF帍傛傝傕SF傜偟偝偺柺偱崅偄昡壙傪庴偗偰偄傞丅堦曽偺僀儞僼傿僯僥傿媗傕丄屲乑擭戙傪岅傞偺偵朰傟偰偼側傜側偄嶨帍偱偁傞丅僼傽儞弌恎偺儔儕乕丒僔儑僂偑曇廤偟偨SF嶨帍偱丄屲屲擭偐傜嶰擭娫偟偐懕偐側偐偭偨偑丄枅崋僄僪丒僄儉僔儏僀儔乕偺奊傪昞巻偵巊偄丄傾乕僒乕丒C丒僋儔乕僋丄傾僀僓僢僋丒傾僔儌僼丄僕僃僀儉僘丒僽儕僢僔儏丄僔儕儖丒僐乕儞僽儖乕僗丄傾儖僕僗丒僶僪儕僗丄儘僶乕僩丒僔儖償傽乕僶乕僌傜偺抁曆傪宖嵹偟偰偄偨丅憂姧崋偵嵹偭偨僋儔乕僋偺乽惎乿偼丄偦偺擭偺僸儏乕僑乕徿傪庴徿偟偰偄傞丅僫僀僩偼偙偺嶨帍偺忢楢偱傕偁傝丄傑偨彂昡棑偺扴摉傪偟偰偄偨丅偙偙偱敪昞偟偨彂昡偺懡偔偑丄屻偵亀嬃堎偺捛媮亁偵傑偲傔傜傟傞偙偲偵側傞丅僊儍儔僋僔僀傕僀儞僼傿僯僥傿傕丄屲乑擭戙偺愻楙偝傟偨暤埻婥傪嫮偔昚傢偣偰偄傞丄傂偲偙偲偱偄偊偽搒夛揑偱僗儅乕僩側嶨帍偩偭偨丅偦偟偰摉帪偺僨乕儌儞丒僫僀僩偼偦偙偵丄戝曄僗儅乕僩偱僩儕僢僉僀側嶌昳傪師乆偵敪昞偟偰偄偭偨偺偱偁傞丅
丂僨乕儌儞丒僫僀僩偼堦嬨擇擇擭丄僆儗僑儞廈儀乕僇乕偵惗傑傟偨丅彮擭帪戙傪僆儗僑儞廈僼乕僪儕僶乕偱夁偛偟丄偦偙偱SF偲偺嵟弶偺愙怗乷僼傽乕僗僩丒僐儞僞僋僩乸傪偡傞丅斵偼偨偪傑偪偦偺偲傝偙偲側傝丄摉帪弌偰偄偨嶰庬椶偺SF嶨帍偲丄挰偺彫偝側恾彂娰偱庁傝傜傟傞尷傝偺SF傪撉傒傆偗偭偨丅偩偑僼乕僪儕僶乕偼彫偝側挰偩偭偨丅僆儔僼丒僗僥乕僾儖僪儞偺杮偑撉傒偨偔偰僀僊儕僗傊庤巻傪彂偄偨傝傕偟偨偑丄僫僀僩彮擭偺搘椡偵傕偐偐傢傜偢丄斵偺杮扞傪杽傔傞傑偱偵偼偢偄傇傫帪娫偑偐偐偭偨丅
丂堦嬨巐乑擭丄斵偼廫敧嵨偵側傝丄僯儏乕儓乕僋傊弌偰棃傞丅
丂摉帪丄僯儏乕儓乕僋偵偼丄僼儏乕僠儏儕傾儞偲屇偽傟傞僌儖乕僾偑偁偭偨丅SF嶌壠偺棏丄僼傽儞丄曇廤幰側偳偺巹揑側廤傑傝偱丄偦偺悢傕擇廫恖偦偙偦偙偺彫偝側傕偺偩偭偨偑丄斵傜偙偦丄屻偺傾儊儕僇SF偵戝偒側塭嬁傪巆偡恖乆偺庒偒擔偺巔偩偭偨偺偱偁傞丅
丂斵傜偼乗乗僪僫儖僪丒僂僅儖僴僀儉丄傾僀僓僢僋丒傾僔儌僼丄僕僃僀儉僘丒僽儕僢僔儏丄僔儕儖丒僐乕儞僽儖乕僗丄僼儗僨儕僢僋丒億乕儖丄僶乕僕僯傾丒僉僢僪丄僕儏僨傿僗丒儊儕儖乧乧傒傫側庒偔丄乮廫戙偐傜擇廫戙偺弶傔乯丄昻偟偔丄SF傪垽偡傞怱偱偄偭傁偄偺儃僿儈傾儞偩偭偨丅惌帯揑偵偼儔僨傿僇儖偱丄棟憐庡媊揑丄SF偺枹棃傪怣偠丄SF僼傽儞偼枹棃偵惗偒傞幰偩偲峫偊偰偄偨丅僨乕儌儞丒僫僀僩偼斵傜偺拠娫偲側傝丄僯儏乕儓乕僋偺墭偄傾僷乕僩乗乗偦傟傪斵傜偼僼儏乕僠儏儕傾儞丒僴僂僗偲偐傾僀儃儕乕丒僞儚乕乮暻偺怓偑偦偆偩偭偨偐傜乯偲屇傫偩丂乗乗丂偱丄嫟摨惗妶傪偼偠傔偨丅斵傜偼擔忢惗妶偺柺偱傕丄妋偐偵帪戙偵愭傫偠偰偄偨丅傾僷乕僩傪嫟桳偟偰僐儈儏乕儞惗妶傪峴側偄丄忢幆揑側摴摽乷儌儔儖乸傪徫偄丄堸傫偩偔傟丄僙僢僋僗偟丄偄偭偟傚偵塖傪壧偄丄彫愢傪彂偒丄嶨帍傪弌偟丄乂奼戝壠懓乂偲偟偰偮偒偁偭偨丅斵傜偼帪戙偵愭傫偠偨價乕僩僯僋偱偁傝丄僸僢僺乕偩偭偨丅堦斣擭挿偱丄愻楙偝傟偨僯儏乕儓乕僋恆巑偱偁傝丄摨帪偵丄僼傽儞僟儉偵偍偄偰嵟傕夁寖側妶摦壠偱偁偭偨僌儖乕僾偺棟榑揑巜摫幰丄僪僫儖僪丒僂僅儖僴僀儉乗乗傏偔偼偐偮偰SFM偵楢嵹偝傟偨栰揷偝傫偺僄僢僙僀乽崱愄傆偁傫婥幙峫乿乮儌僗僐僂僀僢僣偺亀塱崊偺棐亁傪拞怱偵嶰乑擭戙偐傜巐乑擭戙偺僼傽儞僟儉偺乂峈憟乂傪徯夘偟偨傕偺丅斀僂僅儖僴僀儉攈偩偭偨儌僗僐僂傿僢僣偺僶僀傾僗偑偐偐偭偰偄傞乯傗丄僯儏乕丒僂僃乕償榑憟偑偼偠傑偭偨偙傠偺埳摗偝傫偺乽塅拡惢憿幰偨偪乿乮僂僅儖僴僀儉偺昡榑廤亀塅拡惢憿幰偨偪亁傪僯儏乕丒僂僃乕償偺棫応偐傜偙偒偍傠偟偨僄僢僙僀丅敳孮偵偍傕偟傠偄両乯傪撉傫偱丄僂僅儖僴僀儉偲偄偆偺偼摢偺屆偄寵側搝偩偲偄偆報徾傪傕偭偰偄偨丅偲偙傠偑丄僯儏乕丒僂僃乕償榑憟埲屻偺尰忬傪尒丄偄傠偄傠偲帒椏傪挷傋偰尒傞偲丄壗偺偐傫偺偲偄偭偰傕丄傗偼傝僂僅儖僴僀儉偲偄偆偺偼執戝側恖娫偩偭偨乮偄傗丄尰嵼傕傑偩偑傫偽偭偰偄傞偺偩乯偲巚偆傛偆偵側偭偨乗乗偦偟偰庒偄妶摦壠偺僕僃僀儉僘丒僽儕僢僔儏丄僼儗僨儕僢僋丒億乕儖丄僔儕儖丒僐乕儞僽儖乕僗丅斵傜偼彜嬈庡媊偵媿帹傜傟偨SF戝夛暡嵱両傪嫨傫偱戞堦夞悽奅SF戝夛偺夛応擖岥偵偡傢傝崬傫偩偲偄偆偮傢傕偺偨偪偩偭偨丅傕偆彮偟戝恖偟偄偺偼儕僠儍乕僪丒僂傿儖僗儞傗傾僀僓僢僋丒傾僔儌僼丅傾僔儌僼側偳偼丄僉儍儞儀儖偺塭嬁壓偵偁偭偰僼儏乕僠儏儕傾儞偺懡偔偲偼峫偊傪堎偵偟丄儅僓僐儞彮擭埖偄偝傟偰偄偨偑丄偗偭偙偆怓乆偲庱傪偮偭偙傫偱偄偨傛偆偩丅堦曽偡偝傑偠偄偺偼僐乕儞僽儖乕僗丅傑偁堦庬偺惈奿攋抅幰偱丄堦搙傕帟傪傒偑偐偢丄堸傫偩偔傟偰偼傾僷乕僩偺楲壓偺揹媴傪傒傫側夡偟偰偟傑偆偲偄偆偁傝偝傑偩偭偨丅傂偳偄惗妶偱偁偭偨偑丄斵傜偵偼柌偑偁偭偨丅僂僅儖僴僀儉傪偼偠傔丄壗恖偐偼嶰棳弌斉幮偺曇廤偺巇帠傪傕偭偰偄偨偺偱丄庒偄嶌壠巙朷偺儊儞僶乕偵彫愢傪彂偔応傪採嫙偟偰偔傟偨丅傕偭偲傕慡慠嬥偵偼側傜側偐偭偨偺偩偑丅僫僀僩偺張彈嶌乽抏惈乿Resilience傕丄偙偆偟偰僂僅儖僴僀儉偺曇廤偡傞僗僞乕儕儞僌SF帍巐堦擭擇寧崋偵宖嵹偝傟偨丅
丂僫僀僩偼椺偺埨傾僷乕僩乂僼儏乕僠儏儕傾儞丒僴僂僗乂偱僌儖乕僾偺拠娫偲嫟摨惗妶偟丄擭挿儊儞僶乕偺嶮愻偄傪偟偨傝丄偄偭偟傚偵僶僇憶偓傪偟偨傝偟側偑傜丄儅儞僈傗彫愢傪彂偄偰偄偨丅僼儏乕僠儏儕傾儞偺儊儞僶乕偵偼夋壠傗儅儞僈壠傕偍傝丄幚嵺斵傜偺彫愢偵偼丄僐儈僢僋揑側僔僠儏僄乕僔儑儞傪岠壥揑偵巊偭偨傕偺偑懡偄偲偄傢傟偰偄傞丅僫僀僩偑嵟弶偵攧偭偨傕偺偼丄幚偼彫愢偱偼側偔丄僐儈僢僋偺曽偩偭偨丅
丂偦傫側堦曽偱丄斵偼僼傽儞僕儞嶌傝偵傕偼偘傫偱偄偨丅巐乑擭偵憂姧偟偨乹僗僫僀僪乺傪丄斵偼傾僪儖僼丒僸僢僩儔乕偵憲傝偮偗偨丅偙傟偼婥偺偒偄偨忕択偩偲巚偭偨偺偩偭偨丅傗偑偰懢暯梞愴憟偑偼偠傑傝丄傾儊儕僇傕嶲愴偡傞偵媦傫偱丄偙傟偼忕択偱偼側偔側偭偨丅
丂僼儏乕僠儏儕傾儞偺僄僺僜乕僪傪彂偄偰偄傞偲丄偄偔傜枃悢偑偁偭偰傕懌傝側偄丅惉岟暔岅偽偐傝偱偼側偄丅偄偔偮偐偺斶寑傕偁偭偨丅斵傜偑傗偭偰偒偨傛偆側偙偲偼丄傗偑偰榋乑擭戙屻敿偵丄儘儞僪儞偱丄僒儞僼儔儞僔僗僐偱丄偦偟偰僯儏乕儓乕僋偱丄僷儕偱丄暿偺庒幰偨偪偵傛偭偰孞傝曉偝傟傞偙偲偲側傞丅SF偺乂怴偟偄攇乂偲偼堦搙偩偗偺傕偺偱偼側偐偭偨偺偩丅偦傟偼夁嫀偵傕偁傝丄偦偟偰枹棃偵傕偁傞偩傠偆丅僨乕儌儞丒僫僀僩偼巐乑擭戙偲榋乑擭戙偺擇偮偺乂怴偟偄攇乂偵丄偳偪傜偵傕怺偔娭傢偭偨恖娫偩偭偨丅擇偮傔偺攇偲偺娭傢傝偵偮偄偰偼屻偱弎傋傛偆丅偲偵偐偔丄僼儏乕僠儏儕傾儞偨偪偼丄傗偑偰屲乑擭戙SF偺拞妀偲側偭偨偺偩偭偨丅斵傜偵偼丄傎偲傫偳傾僇僨儈僢僋側攚宨偲偄偭偨傕偺偼側偐偭偨丅僌儖乕僾帺懱偑斵傜偵偲偭偰妛峑偩偭偨偺偩丅僼儏乕僠儏儕傾儞偼儚乕僋僔儑僢僾偲偟偰偺堦柺傪傕偭偰偄偨丅柧傜偐偵丄僼儏乕僠儏儕傾儞揑側憂嶌朄偲偄偆傕偺偑偁偭偨乗乗偲丄帺恎僼儏乕僠儏儕傾儞偱偁偭偨傾儖僕僗丒僶僪儕僗偑彂偄偰偄傞丅傕偪傠傫斵傜偼傗偑偰僌儖乕僾傪棧傟丄暥懱傕峫偊曽傕屄惈揑側丄惉弉偟偨嶌壠傊偲惉挿偟偰偄偭偨偺偩偑丄偙偺帪戙偵偮偪偐偭偨惛恄偲偄偭偨傕偺偑丄斵傜偲偦偺嶌昳偵崗報傪巆偟偰偄傞偺偱偁傞丅幚嵺丄僼儏乕僠儏儕傾儞弌恎偺嶌壠丄曇廤幰偨偪偼丄傒側扨偵嶌壠丄曇廤幰偱偁傞偲偄偆偩偗偱偼側偔丄偦傟埲忋偵SF偵懳偡傞幚慔揑側斸昡壠偱傕偁偭偨偺偩丅偙偺儚乕僋僔儑僢僾偲偟偰偺懁柺偼丄僨乕儌儞丒僫僀僩傗僕儏僨傿僗丒儊儕儖偵傛偭偰丄偝傜偵屻傊堷偒宲偑傟偰偄傞丅儈儖僼僅乕僪嶌壠夛媍丄僋儔儕僆儞丒儚乕僋僔儑僢僾偲偄偭偨丄怴偟偄嶌壠傪妋幚偵惗傒弌偟偰偄傞惉岟偟偨儚乕僋僔儑僢僾偼丄僼儏乕僠儏儕傾儞偨偪偑傗偭偰偒偨偙偲傪丄偄偔傇傫傾僇僨儈僢僋側宍偱嵞尰偟偨傕偺側偺偩丅
丂僼傽儞僟儉偺楌巎傪尒傞偺偼乮傏偔帺恎丄僼傽儞妶摦偵戝敿偺帪娫傪旓偟偰偒偨偩偗偵乯戝曄嫽枴怺偄丅偟偐偟丄偳偆傗傜枃悢傪偲傝偡偓偰偟傑偭偨傛偆偩丅偦傠偦傠僫僀僩杮恖偵栠傞偲偟傛偆丅
丂僯儏乕儓乕僋偱偺僫僀僩偼丄僼傽儞僕儞嶌傝丄抁曆丄僐儈僢僋側偳偺憂嶌傪偡傞堦曽丄桭恖偨偪偺偮偰偱僷儖僾嶨帍傪弌偟偰偄傞嶰棳弌斉幮偺傾僔僗僞儞僩丒僄僨傿僞乕偵側偭偨丅偦傟偐傜儕僥儔儕乕丒僄乕僕僃儞僩傪傗偭偨傝丄傑偨SF嶨帍偺傾僔僗僞儞僩丒僄僨傿僞乕傪傗偭偨傝傪孞傝曉偟偮偮丄壗曆偐偺抁曆傪嶨帍偵攧偭偨丅偟偽偟偽僕僃僀儉僘丒僽儕僢僔儏偲偺崌嶌傪帋傒偰偄傞丅偩偑丄巐嬨擭傑偱偺嶌昳偼丄偼偭偒傝偄偭偰廗嶌偺堟傪弌偢丄拲栚偡傋偒傕偺偼側偄丅
丂斵偑SF奅偺拲栚傪梺傃傞偺偼丄偦偺擭偺廐偵弌偨F仌SF帍偺搤丒弔崋乮偙傟偼摨帍偺憂姧戞2崋偵偁偨傞乯偵宖嵹偝傟偨乽抝偲彈乿Not With a Bang偵傛偭偰偱偁傞丅僫僀僩偑擇廫榋嵨偺帪偺偙偲偩偭偨丅偙偺崱偐傜尒傟偽偝偼偳徴寕揑偲傕巚傢傟側偄僔儑乕僩僔儑乕僩乗乗戝偘偝偵偄偊偽丄捠懎揑側儌儔儖偑悽奅傪柵傏偡偙偲傕偁傞偲偄偆乗乗偦偆偄偊偽僞僽乕攋夡揑側僯儏傾儞僗傕懡彮偼偁傞側偲偄偆掱搙偺榖偑丄摉帪偺SF嶨帍偵偺偒側傒宖嵹傪嫅斲偝傟丄傕偟傾儞僜僯僀丒僶僂僠儍乕偑怴嶨帍傪偮偔傜側偐偭偨側傜丄寛偟偰擔偺栚傪尒傞偙偲偼側偐偭偨偩傠偆偲偄傢傟偰偄傞丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄偙傟偼妋偐偵乂怴偟偄攇乂偺堦曆偱偁傝丄屲乑擭戙SF偺枊奐偒傪崘偘傞偵傆偝傢偟偄嶌昳偱偼偁偭偨丅埲屻丄斵偼僊儍儔僋僔僀傪拞怱偵丄乂搒夛揑偱儐乕儌儔僗乂偲昡偣傜傟傞抁曆傪師乆偵敪昞偟偰備偔丅
丂偙偺偙傠偺嶌昳偼傑偨乂僂傿僢僩偵晉傫偩僄僋僗僩儔億儗乕僔儑儞乂偲傕昡偝傟偰偄傞丅偳偪傜偵偣傛丄偦傟傑偱偺SF偲偼傂偲枴堘偆傾僀僨傾偲岅傝岥偺柇偑丄懡偔偺撉幰偵嫮偄報徾傪梌偊偨偺偱偁傞丅僫僀僩偼尵岅姶妎偵戝曄塻偄傕偺傪傕偭偰偄偨丅偦傟偑寉偄儐乕儌傾嶌昳偱偼偙偲偽梀傃傗懯偠傖傟丄愨柇側僆僠偲側偭偰尰傢傟丄傕偭偲廳偄嶌昳偱偼丄尵岅偑偮偔傝忋偘傞悽奅偦偺傕偺傊偺夰媈偲側傞丅偦偙偱偼壙抣偺揮姺偑偐側傝寑揑側宍偱偍偙傞丅偦偟偰丄屻偺幮夛傗恖娫偺栤戣傪僔儕傾僗偵埖偭偨嶌昳傊偲偮側偑偭偰備偔偺偩丅
丂彫愢偽偐傝偱側偔丄昡榑偺柺偱傕丄僫僀僩偼拲栚傪偁傃傞傛偆偵側偭偨丅偦傕偦傕偼巐屲擭偵僼傽儞僕儞偵敪昞偟偨償傽儞丒償僅僋僩偺亀旕A偺悽奅亁榑偑丄斵偺斸昡壠偲偟偰偺僗僞乕僩偱偁傞丅儔儕乕丒僔儑僂偺僼傽儞僕儞偵嵹偭偨偙偺昡榑偼丄摉帪丄偄傢偽嬼憸悞攓揑側恖婥傪傕偭偰偄偨償傽儞丒償僅僋僩傪椻惷側栚偱暘愅偟丄塻偔斸昡偟偨傕偺偱丄傾儊儕僇SF奅弶偺傑偲傕側昡榑偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅埲屻丄F仌SF帍丄僀儞僼傿僯僥傿帍丄僀僼帍側偳偺僾儘嶨帍丄偦偺懠悢懡偔偺僼傽儞僕儞偵彂昡傪宖嵹偟丄寙弌偟偨SF斸昡壠偲偟偰偺柤傪傎偟偄傑傑偵偟偨丅偙偺屲乑擭戙SF偺摨帪戙偺栚偵傛傞斸昡偼丄慜弎偺亀嬃堎偺捛媮亁偵傑偲傔傜傟丄屻偵僸儏乕僑乕徿傪庴徿偟偨乮堦嬨屲榋擭乯丅崱撉傫偱傕戝曄偍傕偟傠偔丄彮偟傕屆偝傪姶偠偝偣側偄傕偺偱偁傞丅
丂堦嬨屲乑擭搤丄僫僀僩偼怴偨偵憂姧偝傟偨儚乕儖僘丒價儓儞僪帍偺曇廤挿偲側傞丅偙偺嶨帍偼抁柦偩偭偨偑丄僂傿儕傾儉丒僥儞偺乽旕P乿傗僴儕僀丒僴儕僗儞偺張彈嶌傪宖嵹偡傞側偳曇廤偼堄梸揑偩偭偨丅屲敧擭偐傜屲嬨擭偵偐偗偰偼僀僼帍偺曇廤傕堷偒庴偗偨丅
丂榋乑擭戙偵擖偭偰偐傜偼丄僫僀僩偺憂嶌偼悢偊傞傎偳偵側傝丄傓偟傠曇廤傗偦偺懠偺妶摦偵廤拞偡傞傛偆偵側傞丅榋乑擭偵僶乕僋儗僀丒僽僢僋僗偺曇廤僐儞僒儖僞儞僩偲側傝丄埲屻榋擭娫偦偺巇帠傪偮偯偗傞丅堦曽榋擇擭偵偼丄嵟弶偺傾儞僜儘僕乕傪曇廤偟丄埲屻偙偺弌斉宍懺偑斵偺偍婥偵擖傝偲側偭偨丅乽僨乕儌儞丒僫僀僩曇乿偺暥帤傪尒偨傜攦偄偩両丂偑丄僼傽儞偺崌尵梩偩偭偨丅
丂偦偺偒傢傔偮偒偑丄僆儕僕僫儖丒傾儞僜儘僕乕偺僔儕乕僘丄乹僆乕價僢僩乺偱偁傞丅堦嬨榋榋擭偐傜偼偠傑偭偨偙偺僔儕乕僘偱丄斵偼愊嬌揑偵怴偟偄嶌壠偺怴偟偄嶌昳傪徯夘偟偰偄偭偨丅榋乑擭戙枛偐傜幍乑擭戙偵偐偗偰偺傾儊儕僇SF偵丄乹僆乕價僢僩乺偼戝偒側塭嬁傪梌偊偨偺偱偁傞丅R丒A丒儔僼傽僥傿丄僈乕僪僫乕丒僪僝傾丄働僀僩丒僂傿儖僿儖儉丄僕乕儞丒僂儖僼丄僄僪丒僽儔僀傾儞僩偲偄偭偨嶌壠偨偪偼丄傕偪傠傫懠偺嶨帍偱傕妶桇偟偨偑丄乹僆乕價僢僩乺偺忢楢偱偁傝丄乹僆乕價僢僩乺偑堢偰偨偲偄偭偰偄偄丅
丂偙偺儊儞僶乕偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄乹僆乕僺僢僩乺偼傾儊儕僇儞丒僯儏乕丒僂僃乕償偺堦曽偺嫆揰偲側偭偨偺偩偭偨丅僨乕儌儞丒僫僀僩偼丄帺恎屲乑擭戙偺乂怴偟偄乂傾儊儕僇SF偺彂偒庤偱偁偭偨偑丄崱搙偼偝傜偵怴偟偄傾儊儕僇SF偺堢偰偺恊偲側偭偨偺偱偁傞丅曐庣揑側撉幰偺掞峈偵偼偁偭偨偑丄乹僆乕價僢僩乺僔儕乕僘偼偍偍傓偹惉岟偟丄偦偺嶌昳偼傎偲傫偳枅擭偺傛偆偵僱價儏儔徿偵僲儈僱乕僩偝傟丄偝傜偵偦偺壗曆偐偼抁曆丄拞曆晹栧傪庴徿偟偨偺偩偭偨丅乹僆乕價僢僩乺偼傑偨丄摉帪偺傾儊儕僇SF偵僆儕僕僫儖丒傾儞僜儘僕乕偺堦戝僽乕儉傪傑偒婲偙偡壩偮偗栶偲傕側偭偨丅
乹僆乕價僢僩乺偵敪昞偝傟偨嶌昳偺偆偪戙昞揑側傕偺傪廤傔偨抁曆廤亀僆乕價僢僩寙嶌慖亁偺彉暥偱丄僫僀僩偼戝堄師偺傛偆側偙偲傪弎傋偰偄傞丅
乗乗偁傞斸昡壠偑乹僆乕價僢僩乺傪昡偟偰丄偙偺傾儞僜儘僕乕偺嶌昳偵偼丄SF僼傽儞傪巋寖偡傞傛偆側怴慛側傾僀僨傾偑偁傞偗傟偳傕丄乂SF乂偺傾儞僜儘僕乕偵斵偑婜懸偡傞傛偆側嫃怱抧偺椙偝傗丄恊偟傒傗偡偝偼尒偮偐傜側偄偩傠偆丄偲彂偄偰偄偨丅偙傟傪撉傫偱傢偨偟偼丄SF偵懳偟偰嫃怱抧椙偄偲偐恊偟傒傗偡偄偲偐偄偆尵梩傪偮偐偆側傫偰丄偢偄傇傫曄側榖偩偲巚偭偨丅傕偪傠傫丄SF偺嬨妱偼愭偑尒偊尒偊偱丄暯杴偱丄埨慡柍奞偩傠偆丅偱傕丄偡偖傟偨SF偲偼丄偦傫側傕偺偠傖側偄丅偦傟偼乗乗栘攏偠傖側偔偰丄僕僃僢僩僐乕僗僞乕側偺偩丅怱抧椙偝傪媮傔傞傫偩偭偨傜丄傾僗僺儕儞偱傕堸傔偽偄偄偺偩両
丂斵偼傑偨丄乽塅拡慏偑弌偰偔傞尰戙SF偼戝晹暘僋僘偩乿偲偐丄乽嶌壠偨偪偵丄斵傜偑偐偮偰撉傫偩僗儕儕儞僌丒儚儞僟乕帍乮僗儁乕僗丒僆儁儔偱桳柤乯傪朰傟偝偣傞偙偲偑偱偒偨側傜丄偡偽傜偟偄乿偲偐丄偄偐偵傕僯儏乕丒僂僃乕償攈傜偟偄敪尵傪偟偰偄傞丅偟偐偟堦曽偱偼屆揟SF偺嵞昡壙傗丄屲乑擭戙SF傪妀偲偡傞僥乕儅丒傾儞僜儘僕乕偺曇廤側偳偵傕愊嬌揑側偺偩偐傜偙傟傜偺敪尵偼塅拡慏偑弌偰偔傞傛偆側SF偺斲掕偲偄偆堄枴偱偼側偄偩傠偆丅尰戙偺嶌壠偨偪偑塅拡慏偵戙昞偝傟傞屆揟揑側SF偺僔儞儃儖傪巊偆偮傕傝側傜丄僫僀僩偨偪偑屲乑擭戙傗偦傟埲慜偵埖偭偨傛傝傕丄偝傜偵怴偟偔丄堄枴偺偁傞巊偄曽偵僠儍儗儞僕偟側偗傟偽丄僫僀僩偲偟偰偼彸暈偱偒側偄丄偲偄偭偨偲偙傠偩傠偆丅
丂僫僀僩偼丄杮幙揑偵偼SF僼傽儞側偺偩丅SF偺掕媊偵偮偄偰丄乽SF偲偼丄偒傒偑SF偺榖傪偟偰偄傞帪偵丄偨傑偨傑偦偺懳徾偲側偭偨傕偺偡傋偰偺偙偲偩乿側傫偰偄偆偺偩偐傜丅傑偨斵偼丄SF偵偍偗傞傾僀僨傾偺廳梫偝傪傛偔擣幆偟偰偄傞乮屲乑擭戙嶌壠偩偐傜摉慠偩傠偆偑乯丅傕偪傠傫丄偦傟偩偗偱偼懌傜側偄偙偲傕丅僄僪丒僽儔僀傾儞僩傊偺庤巻偺拞偱丄斵偼偙偆偄偭偰偄傞丅乽傾僀僨傾偩偗偺彫愢偼丄堦杮懌偺嶰媟偺傛偆側傕偺偱偡丅師偺偙偲偽傪巻偵彂偄偰暻偵偼偭偰偍偒側偝偄丅亀嶰媟偺懌偼嶰杮偩亁乿偲丅杮彂偵廂榐偝傟偨屲乑擭戙偺僫僀僩偺嶌昳傪撉傔偽丄偦偺偙偲偑傢偐傞偩傠偆丅杮彂偺嶌昳偵偼丄塅拡恖傕僞僀儉丒僩儔儀儖傕晄巰恖傕弌偰偔傞丅偟偐偟丄偦偺埖偄曽偼丄偳傟傂偲偮偲偟偰偁傝傆傟偨傕偺偱偼側偔丄抦揑側徴寕傪傕偨傜偡傕偺偲側偭偰偄傞偺偩丅傕偆傂偲偮偮偗壛偊傞側傜偽丄偵傕偐偐傢傜偢丄偦傟偼嫃怱抧椙偔丄恊偟傒傗偡偄傕偺側偺偱偁傞丅偦傟偙偦丄屲乑擭戙SF偺偡偽傜偟偄偲偙傠側偺偩丅
丂僫僀僩偼儈儖僼僅乕僪SF嶌壠夛媍丄傾儊儕僇SF嶌壠嫤夛丄僋儔儕僆儞SF儚乕僋僔儑僢僾側偳傪師乆偲慻怐偟偰丄僆儖僈僫僀僓乕偲偟偰傕偡偖傟偨嬈愌傪偁偘偨丅
丂僯儏乕儓乕僋傪棧傟偰偐傜丄僼儘儕僟丄儈儖僼僅乕僪偲嫃傪堏偟丄尰嵼偼僆儗僑儞廈儐乕僕乕儞偵廧傫偱偄傞丅傕偆僯儏乕儓乕僋傊婣傞偮傕傝偼側偄偲偺偙偲偩丅晇恖偼丄崱傗嶌壠偲偟偰偼僫僀僩傛傝傕桳柤偲側偭偨丄働僀僩丒僂傿儖僿儖儉偱偁傞丅側偵偟傠僂傿儖僿儖儉偺杮偼偡偱偵壗嶜傕東栿偑弌偰丄峀偔撉傑傟偰偄傞偺偵丄僫僀僩偺杮偼丄杮彂偑傢偑崙偱弶傔偰側偺偩偐傜丅
丂嵟怴偺僯儏乕僗偵傛傟偽丄僫僀僩偼怴偨側挿曆The Man in the Tree傪弌斉幮偵攧偭偨偲偄偆偙偲偩丅挿偄媥壣偺偁偲丄傑偨憂嶌堄梸偑傢偄偰偒偨偺偐傕抦傟側偄丅敧乑擭戙偺斵偺嶌昳偑偳偆偄偆傕偺偵側傞偺偐丄戝偄偵婜懸偟偨偄偲偙傠偩丅
侾俋俉俀擭係寧