内 輪 第384回
大野万紀
SFファン交流会「吉田隆一の羊のお茶会「マンガと音楽とSFと」」
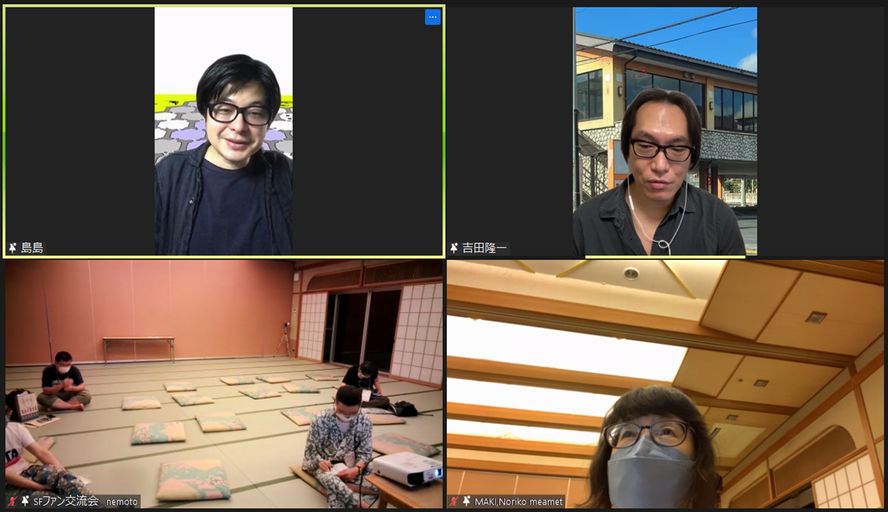 8月のSFファン交流会は8月27日(土)に、「吉田隆一の羊のお茶会「マンガと音楽とSFと」」と題して開催されました。出演は、吉田隆一さん(SF音楽家)と、西島大介さん(マンガ家)。今回は第59回日本SF大会F-CONの企画としてZoomとSF大会会場をつないで実施されました。
8月のSFファン交流会は8月27日(土)に、「吉田隆一の羊のお茶会「マンガと音楽とSFと」」と題して開催されました。出演は、吉田隆一さん(SF音楽家)と、西島大介さん(マンガ家)。今回は第59回日本SF大会F-CONの企画としてZoomとSF大会会場をつないで実施されました。
写真はzoomの画面ですが、左上から反時計回りに、西島大介さん、SF大会会場、SF大会にいるみいめさん、吉田隆一さんです。SF大会の会場の雰囲気がいいですね。
今回、開始が19時半からでしたが、ぼくは都合で参加したのが20時半すぎとなり、メモも取れていないのでちゃんとしたレポートは書けません。ぼくの聞いた主な内容は大体以下のようなものでした。
SFとの出会いについて。吉田さんは子どものころお母さんから童話といっしょにヴァン・ヴォクトを渡されたそうです。中学では神林長平と谷甲州にはまり、ハードSFだけど哲学的な内容にびっくりしたとのこと。それが後に『航空宇宙軍史完全版』の解説を書くことにつながったのでしょう。
マンガ家かSF作家になりたかったという吉田さんですが、中学の音楽の先生から吹奏楽部に入れと言われバリトンサックスをやることになり、ジャズを知って音楽の道に進むことに。西島さんとの接点は、ジョン・クリストファー『トリポッド』の西島さんの表紙を見て感激し、アルバムジャケットを依頼したことから。
西島さんと吉田さんは、いわば塩澤さん(元SFマガジン編集長)チルドレンだということ。西島さんによれば、塩澤さんはいわばフリージャズの発想で、しろうとであっても面白そうならステージにあげてしまう。吉田さんも『航空宇宙軍史完全版』の解説について、塩澤さんから今度出すので全巻解説を頼むとメールがきてびっくりしたそうです。なんで私なんですかと聞いたら、だって詳しいじゃないですかと。来た話は断らないことにしているので受けたとのことですが、バリトンサックス吹きは(「響け!ユーフォニアム」の部長もそうですが)頼まれたらイヤと言えない性分なんだそうです。
SFと音楽について。音楽もSFもどこにでもあると思う。そこにあるものを音楽と呼べば音楽になる。受け手が既定するもの、音楽という物理現象が精神に作用すること自体がSFだと思う。音楽はすべてSFだと思うと吉田さん。さらにSF作家が描く音楽について、飛浩隆さんの『零號琴』の最後の方に一カ所引っかかる文章があると言います。それは「この惑星には今後音楽が鳴り響くことはないだろう」という言葉。でも聞き手が音楽として受け取るなら風の音でも音楽だと思うので、飛さんは音楽をもっと主体が既定するものと受けとめているようだと。一方、宮内悠介さんの作品では音楽は受け手側のものとして描かれているとのことでした。
他にも色々と面白い話がありましたが、今回はこんなところで。次回のSFファン交流会は9月24日に「古書と古典SF」をテーマに開催されるそうです。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『血を分けた子ども』 オクティヴィア・E・バトラー 河出書房新社
『血を分けた子ども』 オクティヴィア・E・バトラー 河出書房新社
本書の著者オクティヴィア・E・バトラーは、1976年にデビューし、80年代後半以降、本書収録の「血を分けた子ども」や「話す音」がヒューゴー賞、ネビュラ賞を受賞して高い評価を受けたが、2006年に58歳で亡くなった。
彼女はSFジャンルでは初の黒人女性作家だった。白人男性のものと思われていた過去のSF界で、女性であるというだけでなく黒人であるという二重の差別に苦しんだ彼女の作品は、今世紀になってさらにより幅広い評価を受け、日本でも本書を始め、初期の長編『キンドレッド』の復刊など注目が高まっている。
各作品には著者の後書きがつき、最後に藤井光による訳者後書きがある。なお本書では各作品の原題が記されていなかったので、邦題の後ろに記しておく。
表題作「血を分けた子ども」"Bloodchild"(1984)は異星人トリクに支配されて保護区で暮らす人間たちを描く。ここで人間たちは異星人の卵を体内にはらむための存在となっている。だが主人公は生まれたときからトリクと一緒に暮らしており、互いに愛情を抱きあい、トリクの側も過去とは違って人間に優しく親切で、卵の出産という危険を伴う行為にも苦痛のないよう細心の注意を払っている。一種のラブストーリーでもある。あとがきで著者自身が書いているが、ぼくの感覚ではこれはまず男性妊娠小説だった。体の中に別の生き物がいて成長する。そして出産。ホストとは互いに慈しみあい、愛し合いながらもそこに大きな位相のずれが、ベースラインの不均衡が存在する。まさにジェンダー問題である。
もちろんこのSFで描かれているのはそれだけではなく、現実に存在する、悪意からではないのに一部の集団には不利益をもたらす種類のあらゆる非対称性の問題にも当てはまるものだろう。
「夕方と、朝と、夜と」"The Evening and the Morning and the Night"(1987)では遺伝的な疾患が描かれる。この病気は新薬の薬害が元で発生したが、患者の子どもにも必ず遺伝する。発症した場合、患者は自分自身を切り刻んだり、ひどい場合は他人を殺害したりする。主人公の父もこの病気にかかり、妻を殺して自分も死んだ。主人公は発症こそしていないが、周囲の偏見や発症の恐怖と戦っている。彼女には同じ病気のボーイフレンドができ、二人で彼の発病した母親が収容されている病棟を訪れる。そこは収容所のようなところではなく、患者たちは平穏な暮らしをしている。主人公はここで働くことを提案されるのだが――。
非常に深刻な遺伝病を抱えた2世の迷いと決断が描かれるが、著者は人間の行動がどこまで遺伝子に支配され、自由意志と個人の責任はどこまでの意味を持つのかという問題を追求している。これまたSF的な発想が現実に深く関わってくるタイプのSFである。
「近親者」"Near of Kin"(1979)は短い作品だが、SFではなく普通小説。一人娘を遠ざけ、別居していたシングルマザーの母が死んだ。遺品整理に来た娘。仲の良かった叔父が色々と助言し、手伝ってくれる。彼女は母があまり好きではなかったが、叔父は好きだった。そのうち明らかになってくる家族の秘密。
著者は後書きで聖書の物語に言及しているが、考えてみたらその通りだ。聖書では当たり前に描かれている聖なることが現実ではタブーであるという逆転。
「話す音」"Speech Sounds"(1983)は84年のヒューゴー賞受賞作。ここでも疫病が出てくる。世界を襲った疫病の後、人々は言語能力を失い、会話することも読み書きすることもできなくなった。大きな組織は崩壊し無政府状態の世界となっている。かつて大学教師だった主人公の女性は物々交換で乗客を乗せるバスに乗ったが、その中でトラブルが発生する。二人の男がけんかを始めたのだ。危険を感じバスから逃げ出した主人公は、警官の格好をし拳銃を持ったひげ面の男と出会う。言葉は使えず身振りでしか意思疎通できないが、彼は正義感のあるまともな男に見えた。二人は共に行動するようになり、彼女はこの男とならしばらく一緒にいてもいいと思う。だが暴漢に襲われて逃げ出した女を助けた二人に悲劇が襲いかかる。
悲痛な話だが、珍しくこの物語の結末には希望がある。
「交差点」"Crossover"(1971)もSFではなく、著者自身の過去を反映したというショートショート。工場で働き底辺の生活をしている女が、生活に疲れ薬やアルコールに溺れている。そこに3ヶ月前に刑務所に入っていた元恋人が現れる。二人は彼女のアパートに戻るが、男の口調にいらつき、元のようには戻れない。そして明らかになる真実。
これは孤独と逃避についての物語である。著者の後書きによると著者自身はこの登場人物のようにはならなかったが、実際にそうなった人々を見てきて、作品が売れるまでは自分もそうなるのではないかと怖かったと語っている。
「前向きな強迫観念」"Positive Obsession"(1989)は小説ではなく、作家になろうとする「前向きな強迫観念」を抱いた著者の半生を描くエッセイである。10歳のとき初めて一人で書店に行って「子どもも入っていいんですか」と聞くと「もちろんいいですよ」と言われた。本当は「黒人の子どもも入っていいんですか」と聞こうとしたのだ。そこで初めて馬の本や星や惑星についての本を買った。だが叔母に大きくなったら作家になりたいと言うと、叔母は趣味ならいいが黒人は作家になれないと言い放った。学校では恥ずかしがり屋で社交性のなかった彼女はノートの中に自分だけの世界を作る。魔法の馬や火星人や霊能者のいる世界。書いた物語を出版してもらおうと努力し、出版社に送っては掲載不可の通知を受け取る日々。大学では児童文学の作家である年配の女性が担当する創作の授業を受けたが、バトラーの書くSFやファンタジーを読んで「なにかまともなものは書けないの?」と言われる。大学を出て工場で働きながら売れないSFやファンタジーを書き続ける。
当時のプロのSF作家といえばほぼ全員が白人男性だった。黒人女性の自分は一体なにをしているのか。なにをしているにせよ、やめられなかった。それが「前向きな強迫観念」だ。黒人、女性、そしてSFというものに対する差別。このエッセイが書かれた当時、黒人のSF作家はサミュエル・ディレイニー、スティーヴン・バーンズ、チャールズ・サンダーズ、そしてバトラーの4人だけだった。その前はディレイニー1人だった。「黒人にとってSFにはどんな意義があるのか」という問いには、どうして自分の職業の正当性を人に証明せねばならないのかと思うが、その答えは明らかだ、とバトラーは言う。
「書くという激情」"Furor Scribendi"(1993)もエッセイ。作家志望の人たちに向けて、6つのことを指摘する短いエッセイである。読むこと、ワークショップや授業に参加すること、書くこと、書き直すこと、投稿すること、閃きや才能などは忘れ、粘ること。中でも一番大事なのは粘り強さだとバトラーは言う。
「恩赦」"Amnesty"(2003)は新しいやや長めの短編で、「血を分けた子ども」の主題が観点を変えて繰り返される。地球に集合体と呼ばれる人類とは全く異質な植物に似た異星人が現れ、砂漠地帯に植民地を作った。アメリカではモハーヴェ砂漠にドームが作られ、彼らはそこに住み着いている。初期には各国政府がそれらのドームを攻撃したが、全く歯が立たなかった。当初、集合体たちは多くの人々を拉致して研究材料とした。そこでは(人間にとって)ずいぶんひどいことが行われ、殺された人もいる。拉致された人々の間でも反目や争いがあり、暴力や強姦といった人間同士のいさかいが絶えなかった。しかしそれから何十年かがたち、集合体の人間理解も進み、ようやく曲がりなりにも共存できるような条件が整ってきた。
この作品の主人公である女性ノアは11歳のときに拉致され、彼らと意思疎通する通訳として養成された一人である。集合体との意思疎通はその中に包み込まれて全身をダンスのように動かすことで行われる。今彼女は、集合体に雇ってもらおうとやって来た6人の男女に仕事の内容を教えようとしている。だが彼らの多くは集合体に恐怖と敵意を抱いており、生活のために仕方なく異星人から仕事を得ようとしているのだ。一方集合体をまるで神のように崇拝する人もいる。
この作品は彼らとノアの会話で成り立っており、そこではノアの体験と集合体への感情、そして不可解で理解できない存在に対する人々の恐怖と怒りが、理不尽な感情が描かれる。決して多様性には解消されない断絶と、対等ではない非対称性の中での共存。殺し合うのでも言いなりになるのでもない、それぞれの独自性をもったままでの妥協と共生。通訳であるノアはそれを体現しているのである。
後書きによるとこの作品を書くきっかけとなったのは90年代に起きた李文和事件だという。何の証拠もなくスパイ容疑でいきなりロスアラモス研究所を解雇され長期拘留された事件(証拠がなかったことから後に保釈され自由の身となった)の理不尽さに衝撃を受けたのだと著者はいう。
「マーサ記」"The Book of Martha"(2003)も新しい短編。バトラー自身を思わせる女性作家のマーサが突然神(のような存在)に出会う。神は人類がより平和で持続する生き方を見つけられるように、マーサに手伝って欲しいという。神の作り出した仮想世界を二人で歩きながら、神は人類をどう変えたいのか、マーサが自由に決めてそれを口にすれば、それを実現させるという。彼女はもし間違って変なことを言ってしまえば人々が死んだり傷ついたり、取り返しのつかないことになるかも知れないと恐れ悩む。神は時間をかけてもいいからたった一つだけ、重要な変化を起こすことを考えて欲しいと言うのだ。マーサは神に色々と質問し、対話を続け、そしてついにマーサはある決断をする――。
後書きにあるようにこれはある種のユートピア物語だ。本当にそれが正解かどうかはわからない。しかしうまくいくかも知れない。何といってもそれこそがSFの、ファンタジーの本質なのだから。
 『いずれすべては海の中に』 サラ・ピンスカー 竹書房文庫
『いずれすべては海の中に』 サラ・ピンスカー 竹書房文庫
サラ・ピンスカーの2019年に出た短篇集の全訳。2013年から2017年にかけて執筆された13編の中短篇が収録されている。カチナツミさんによる日本版の表紙がとても美しい。
「一筋に伸びる二車線のハイウェイ」。事故で右腕を失った青年が、脳にチップを入れ、それでコントロールするロボットアームを装着する。彼はリハビリの後、家業である農家の仕事に戻ったのだが、なぜか行ったこともないコロラドのハイウェイのイメージが執拗に生じるようになる。それはチップの記憶なのだろうか。新しい腕は彼のいうことを聞きながらも、自分はいまだにコロラドのハイウェイにいると思っているのだろうか。
家族や友人との関係性が細やかに描かれ、道具立てはSFだが、内容的には奇想小説に近い。モノに心が宿るというのは日本人には容易に納得できることだが、そう思えば機械の運命に、どこかもの悲しい雰囲気を感じることだろう。
「そしてわれらは暗闇の中」では女性同士のカップルの一人に、夢の中でベビーが産まれる。ベビーは彼女の夢の中で成長し、また赤ん坊に戻り、またその外見にもいくつかのバリエーションがある。しかしその子は彼女にとって紛れもなく本物だ。パートナーに説明するが理解してもらえない。やがて自分だけでなく、他にも大勢の人が同じような体験をしていることを知る。あるとき夢からベビーがいなくなり、南カリフォルニアの海岸にたくさんの子どもたちが上陸する。彼女を含め、同じ体験をしていた人々はやむにやまれぬ気持ちでそこへと向かう。
この子どもたちは現実の存在だ。ある意味グロテスクだが書き方は淡々としている。パートナーはこれがカッコウの托卵のようなものではないかと訝しむが、彼女の心は変わらない。これも執着と愛する大事なものとの齟齬を描く作品であり、カルトが話題の現在、考えさせられる作品である。
「記憶が戻る日(リメンバリー・デー)」は悲惨な戦争に行った兵士の記憶に〈ベール〉を下ろし、パレードの日だけ復活させるという社会の物語。どんな戦争だったか、なぜそういうことになったかといった背景は詳しく描かれず、そういう設定の中での家族の物語が語られる。戦場に行って負傷したママと娘とお祖母ちゃん。娘の母を思う心と、その向こうにある恐ろしい戦争との対比が女の子の言葉で描かれ、短い作品ではあるが心にモヤモヤとしたものを残す。これもまた恐るべき「日常」なのである。
「いずれすべては海の中に」でも世界は破滅に向かっているようである。だがその具体的な姿はほとんど描かれない。この世界的な危機の中に、豪華客船で海に出たセレブたち。そこに同乗して演奏していたロックスターは船から逃げ出し、どこかの海岸に漂着する。彼女を助けたのはそこで漂着物を拾って生活している女性。彼女は生活力があり、現実的で容赦の無い性格だ。ふわふわとその場限りの思いつきで行動するロックスターとはあまりにも違う。二人はそれでもこの世界で生きていこうとする中で共同作業をする。そこで重要になるのが音楽だ。ボロボロのギターがそのキーとなる。
「彼女の低いハム音」も何らかの危険が家の外にある。戦争かも知れないし迫害かも知れない。短くて古いユダヤの寓話のような物語である。
おばあちゃんが死んだ後、父は粘土と金属でおばあちゃんを作ってくれた。おばあちゃんのように話し、おばあちゃんのように動くが、その中、心臓のあるはずのところには鳥かごのような空洞がある。女の子のタニアはそんな人工のおばあちゃんになじめない。しかしあるとき急に帰ってきた父が「今すぐ家を出なくちゃいけない」といい、タニアと人工のおばあちゃんを連れて家を後にする。貴重品だけおばあちゃんの鳥かごに入れて。兵士の尋問をかわし、船に乗って知らない土地へ。タニアとおばあちゃんの間にも新たな関係が生じる。
「死者との対話」は過去の殺人事件に取り憑かれた女性イライザが描かれる。語り手は彼女のカレッジのルームメイトで、ミニチュアハウスの作り手、グウェン。イライザは事件のあった家の正確な模型をグウェンに作らせ、そこにビッグデータから学習させたAIを仕込んで質問をし、死者たちに語らせる。AIの死者たちはたいていは既知の内容しか語らず、知らないことは知らないとしか言わないが、ときおり各種の情報からの創発で、未知のあり得たかも知れないことを言う。実際にそれを元に再捜査して事件が解決したこともあるのだ。イライザはこれを商売にし、グウェンは彼女に雇われて模型作りをしていたが、あるときイライザの異常さが明らかとなる――。
AIは事実を語るのではなく推理を語っているだけだが、聞く人間にとってその境目は曖昧だ。知られてはいけないことを憶測で語られる恐怖。
「時間流民のためのシュウェル・ホーム」はショートショートだが、タイトル通り、様々な時間にいる(見る?)人たちが暮らす〈ホーム〉の話だとはわかる。でもそれ以上のことはわからない。時間跳躍は厄介だとあるが、確かにそうだ。それでも語り手たちの関係性は明白で、そこには心の温まるものがある。
「深淵をあとに歓喜して」は2014年のシオドア・スタージョン記念賞受賞作品。SFというより、年老いた夫婦の強い思いを描いて心を打つ普通小説である。
建築家だった夫ジョージが脳梗塞を患って入院する。90近い妻のミリーは子どもや孫たちと彼を見舞い、半身不随で言葉も出せない彼のかろうじて動く片手が何かを描くように動くのを見る。それは建築物の設計図のようだった。ミリーは思い起こす。二人の出会いと結婚、芸術的な建築を作ろうとする彼の夢、彼の描く架空の設計図の数々、子供たちが生まれ成長し、庭に大きく見事なツリーハウスを作る彼。満ち足りた生活。だがある日、突然彼は変わってしまった。ツリーハウスの中で涙を流したジョージは、夢や情熱を捨てたごく平凡な男へと。だが今、ミリーは孫の助けを借りて60年ぶりにその謎を解こうとする。このミリーがすばらしい。また孫たちもとてもいい。辛い出来事が人生を変え、しかし心につかえていたそれをしっかり見直すのに遅すぎるということはない。楽しそうなツリーハウスも、起こったと暗示される恐ろしい出来事も、ミリーの中で一つにまとまり、彼への思いが解放されるのだ。
「孤独な船乗りはだれ一人」はセイレーンの伝説を元にしたファンタジーだが、幻想的な要素はセイレーンの存在だけだ。島の港の入り江にある岬にセイレーンが棲みつき、その歌声で港に出入りする船乗りを迷わせ海に溺れさせる。そのためこの島から誰も出入りできなくなってしまった。スマイズ船長はそれを打ち破るために、酒場で働く13歳のアレックスに声をかける。子どもにはセイレーンの歌声はきかないと言われているのだ。でも本当にそうかどうかはわからない。アレックスは死んだ父親からこの酒場に預けられ、おかみさんの下できつい下働きをしているが、元気で前向きで知恵のある子どもだ。そしてある秘密を抱えている。
ジュヴナイルの冒険小説のような読後感のある話だが、セイレーンの歌声が響く結末には世界の広がりがあり、とても美しい。歌が重要な役割を果たす作品である。
「風はさまよう」は中編で、宇宙音楽SF。そして過去の記憶と失われた歴史、文化の継承についての物語である。舞台は世代宇宙船。主人公は当初の乗員から三代目にあたる女性で、本人も実際の地球を知らないが、宇宙船生まれの子どもたちに歴史を教える教師である。また第一世代である祖母からフィドルを教わったフィドル弾きであり、古くから伝わる楽曲や歌を残すための〈オールドタイム〉という活動をしている。
この宇宙船が地球を離れて遠い星への旅を始めてすぐのころ、〈ブラックアウト〉という事件が起きた。ハッカーが放ったウィルスにより、航行や技術や生存に関する重要なものを除いて、音楽、文学、映画、ゲーム、歴史といったデータベースが破壊され、地球との通信手段も失われたのだ。そこで人々は自分たちの記憶から新たにそれらを復元し、未来へつなごうとした。それから数十年。若い世代の中にはそれに疑問を持つ者も現れる。彼女がクラスで歴史を教えていると、ある少年が二度と地球に戻ることはなく自分たちは船の中で一生を終わるのに、こんな勉強が何の役に立つのかと反抗的な態度を示す。彼女は歴史を学ぶ意義を説くが、彼は理解しようとしない。
物語は小さい日常的なエピソードをいくつも描き、「風はさまよう」という楽曲を巡るいきさつを描きつつ、文化の継承の意味を探ろうとする。これは世代宇宙船の中だけでなく、現代の宇宙船地球号の中でも切実で重要な問題である。空も風も知らない人々にとってのそれ、すでに今の社会と合わなくなった過去の文化を知ることの意味。ところで「風はさまよう」は架空の曲ということだが、ぼくには70年代に山ほど聞いたトラディッショナル・フォークの1曲として耳に響いた。
「オープン・ロードの聖母様」は2016年ネビュラ賞受賞の中編でこれも音楽SF。というか長編『新しい時代への歌』の原型となった作品である。設定は『新しい時代への歌』より後。主人公のルースは50代のおばさんパンクロッカーで、ベーシストのシルヴァ、ドラマーのジャッキーとオンボロのバンに乗って旅をしている。ステージ・ホロでの配信が主流になった今、ライブが命の彼女らは数少ないライブ巡業の場を求め、その日暮らしに近い旅暮らしをしているのだ。
衰退した世界を背景に、物語は中西部の小さな町を巡って行く彼女らの生活とそのパンクで突っ張った心情を描いていく。寝泊まりするバンの中は滅多にシャワーもできない男たちの体臭に満ち、普段はろくな食事もできない。そんな中、電気の供給も不安定なライブ会場で地元の若者たちが開いてくれたライブ演奏の描写は短いけれど圧倒的だ。今と地続きではあるが別の世界でのロックな日常生活。配信会社の人間のそれなりに理のかなった言葉に引きずられそうにもなるけど、ライブを、生身の接触を、声と汗の交感を、音楽を、まだまだ続け、そして進み続けるのだ。いやあカッコイイ。
「イッカク」もずいぶん奇妙でユーモラスなロードノベル。でも最後まで読めば何となく見えてくるものがある。とても心に残る作品だ。
主人公のリネットは若い女性で、ボルティモアに住む何でも屋。ダリアという中年の女性から、母から相続した車を交互に運転して故郷のサクラメントまで運んでいきたいという依頼を受ける。旅は8日間の長距離ドライブだ。やってきたのはクジラの形をした改造車。依頼者の女性もこの車に乗るのは初めてだという。依頼者は面白みのない頑固な女性で、道中色々と観光もして楽しみたいリネットとはそりが合わない。車のダッシュボードには謎のボタンが色々あって、ダリアは触ったらダメというが、リネットはつい押してみたくなる。その一つ花の模様のボタンを押すと車のフロントに長い角が生え、猛スピードで動き出した。ガソリンが少なくなって停まるまで操作も効かない。この車はクジラじゃなくイッカクだったのだ。
レッカー車を呼んで近くの小さな町の修理工場へ行く。この町はダリアが唯一途中で寄りたいと言っていた町だった。そこには母のゆかりの映画館があるのだという。車が直るまで一人町を散歩したリネットは、小さな博物館があるのを見つける。そこで知った恐るべき秘密とは――。初めに書いたように、謎は曖昧なまま残るが、想像することはできる。えっ、それじゃあダリアのお母さんって――。
「そして(Nマイナス1)人しかいなくなった」はタイトルからはユーモラスなSFミステリのように思えるが、読んでみると日々の選択の重みについてのシリアスな中編だった。
保険調査員をしているサラ・ピンスカーのところにコンベンションの招待状が届く。カナダ東部の孤島のホテルで開かれるそのコンベンションには、様々な並行世界から200人以上のサラ・ピンスカーが集まるのだ。ある世界で物理学者のサラが並行世界間を移動する方法を発見したらしい。「すごく変な感じ」と思ったが、サラはコンベンションに参加する。しかし嵐が来て、この島は本土から何日か孤立してしまうことになる。そんな中で一人のサラが死体となって発見される。警察が来られるようになるまで、保険調査員のサラはここにいるサラの中で最も探偵に近いという理由からその捜査を依頼されるのだ。たくさんのサラと話をし、それぞれのサラの分岐点を知ることで「もしあのときこうしていれば」とか「自分がそうだったかも知れない別の人生」についてじっくり考え、サラの住んでいるシアトルが地震で壊滅し多くの人が死んだ時間線があることも知る。そしてついに犯人を見つけるのだが――。
タイトルはアガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』をもじっているが、訳者後書きによれば And Then There Were None
の最後を(N-One)に変えたというもので、よく考えたものだと思う。誰もいなくなるのではなく、1人だけがいなくなるのだ。
 『AI法廷のハッカー弁護士』 竹田人造 早川書房
『AI法廷のハッカー弁護士』 竹田人造 早川書房
ハヤカワSFコンテスト優秀賞を受賞した『人工知能で10億ゲットする完全犯罪マニュアル』の作者による書き下ろし長編。とはいえ4編からなる連作長篇である。前作と同様、そのまま内容を表しているようなタイトルで(編集者がつけたのかも知れないが)、裁判官が人間では無くAIとなった近未来の日本を舞台に、性格に非常に問題のある個性的なやり手弁護士が、天才ハッカーのぐうたら女や物理シミュレーションを瞬時に頭の中でやれるという(まあ一種の超能力)道徳心に溢れるがどこか頼りない青年といった協力者を得て、絶対に勝てるとは思えないような裁判にあくどい手段を使っても勝ち続けるという物語である。「逆転裁判」ですね。出てくるキャラクターがみんなコミカルで名前もそれらしく、さらに決まり文句つきとエンターテイメント性は抜群だが、作者はAIの専門家であり、技術的・SF的な背景はかなりハードでよく考えられている。
Case1「魔法使いの棲む法廷」では、誰が見ても酔った友人を刺殺したとしか思えない容疑者の無罪を、裁判官がAIであることを悪用して勝ち取る。しかしその被告(彼が物理シミュレーションを瞬時にできる能力者で、裁判の後、弁護士の助手となるのだ)はその判決に納得しない。二審では犯罪現場を再現した物理シミュレーションが証拠とされるが、主人公たちはその微妙な疑惑をついて、真犯人を暴き出す。とはいえ、法廷ものの厳密なロジックによるというより、これは戯画化されたAI法廷で真犯人が自爆するみたいなものだ。それでもここで描かれるAIはシンギュラリティなどとは無縁のものであり、裁判官であるにもかかわらずバグやセキュリティホールも存在する。作者のテクニカルな知識は確かで、十分に納得のいくものとなっている。
Case2「考える足の殺人」ではそのAIが意識を持つかという問題がテーマとなっている。タイトルは「考える葦」のダジャレだろう。ここで意識をもつかどうか問われているのは義肢なのだ。今度の被告は主人公の協力者である天才ハッカー。脳波を読み取って作動する仕組みのAI義足が暴走し、被害者が線路に飛び込んで死亡したのは彼女が組み込んだ修正パッチのせいだと訴えられたのだ。ただし読者には冒頭で真犯人が誰かわかっている。それは10本もの義肢を装着し、自らポストヒューマンを名乗る被害者の上司だ。まるで千手観音みたいな彼女もぶっ飛んでいて、いかにもギャグマンガに出てきそうな人物である。これはすごい。裁判の論点は修正パッチによってAIにある種の意識(単独の意識ではなく装着者の意識とハイブリッドなもの。ここの議論も面白い)が生じ、それが暴走したということである。だが読者に冒頭で示された真相は(どうやってかわからないが)犯人が被害者の義足をハッキングして電車に飛び込ませたというものだ。その謎を解明することが勝訴につながる。結論は単純だが面白く、これまた説得力がある。よく出来たSFミステリとしてきちんと着地している。
Case3「仇討ちと見えない証人」とCase4「正義の作り方」は1つの物語である。それを言えばCase1、Case2ともつながっていて、物語全体の背後にある謎の解決編となっている。1と2が単体でも普通に楽しめる作品になっているのに対し、ここでは事件も背景も錯綜しており、テーマもずっとシリアスなものとなっている。それこそAI裁判官の存在そのものに関わる問題であり、作品の設定自体をひっくり返してしまいかねないものなのだ。ここに主人公の同級生だった辣腕検事が登場する。そしてあの天才ハッカーの姉は、昔米国で判事AIを開発したメンバーの一人であり、大学時代に彼と主人公の先生だった。今は亡きその彼女がからんだかつての事件が二人に重くのしかかっている。
Case3の事件は、かつてAI判定システムにより信用度を不正に下げられて損害を受けた企業の社長が、それを提訴したが納得のいかない理由で敗訴し、ついには精神を病んでしまったという事件について、その娘が再審請求したものである。事件そのものは主人公と協力者たちの活躍で解決するが、主人公と辣腕検事が対決するはずの裁判はおかしな形で決着を迎える。そして結末でとんでもないことが起こる。
Case4は二人の過去を巡っての最終対決だ。これまでの登場人物も総登場し、AI裁判そのものを疑う話となる。それゆえ、ここではAIそのものの内容を議論せざるを得ず、専門用語も飛び交うことになる(レイヤー・ノーマライゼーションなんて言葉が小説の中で書かれる時代になったのだなあ。いや今どきのAIを扱ったミステリでは普通なのだろうか。読んでないから知らんけど)。とはいえ、そんなに難しく考えなくてもディープラーニングでデータからパターンを学習するAIには思わぬ落とし穴があるという理解で、専門家じゃないぼくらレベルには十分だろう。となると、そもそもAI裁判官という設定に疑問がわいてくるのだが……。まあ現実の人間の裁判官でも非常識な判決は時々あるようだが。
それもこれも含めて、ちゃんと決着がつくのはすばらしい。これはぜひ続編をと思うのだが、この後の世界で主人公はこれまでと同じような活躍はできないんじゃないだろうか。それともさらにその裏をかくような「魔法」を見いだすのだろうか。
 『工作艦明石の孤独 1』 林譲治 ハヤカワ文庫JA
『工作艦明石の孤独 1』 林譲治 ハヤカワ文庫JA
新しいシリーズである。どこかで見たようなタイトルだなと思ったら、谷甲州の新・航空宇宙軍史に『工作艦間宮の戦争』というのがあったのを思いだした。
このシリーズも作者お得意の、大きな問題に直面した時の人間たちをその社会システム、政治組織、有能な現場の人間たちによる判断といった面から描くことを一つのテーマにしているように見える。
ワープ航法により人類が60ほどの星系に広がった時代。その植民星の一つセラエノ星系で突然異変が起こる。5光年ほど離れた隣のアイレム星系(ここには入植者はいない)を例外として、遠距離のワープが不能となってしまったのだ。ここ、セラエノ星系は他の人類から孤立してしまった。
この時代、人類の科学は停滞している。技術は発達したものの基礎科学への投資は少なく、ワープ航法もその基本原理は解明されていない。役に立てさえすれば原理はわからなくてもいいという思考が大勢なのだ。植民星でもその事情は変わらない。最先端技術は地球からの輸入に頼り、製造業を初めとする産業も自立しておらず、人々が生きていくためのインフラも今あるものが失われたらメンテナンス困難となる。高等教育も地球に頼っており、独自の人材確保も難しい。地球からの孤立は文明の維持にとって死活問題なのだ。
他の大規模な植民星と違い、セラエノ星系の人口は150万ほどにすぎず、民主的な体制のこじんまりとした平和な星だった。首都ラゴスが人口のほとんどを占め、アーシマ・ジャライ首相が率いる星系政府は人々の信頼を集めている。異変が起こったとき、地球から2隻のワープ船、偵察戦艦青鳳(せいほう)と輸送船津軽が訪れていた。津軽が地球へ帰還しようとして正常にワープできなくなり、セラエノ星系に所属する工作艦明石がそれに対応しようとする。明石の艦長・狼群涼狐(ろうぐんりょうこ)と妹で交錯部長の狼群妖虎、青鳳の艦長・夏クバン准将、津軽の艦長・西園寺恭介は協力してこの異変の原因が遠距離ワープ自体が不能になったことだと突きとめる。なお、西園寺以外はみんな女性である。そして作者の他の作品と同じく、その部下たちも含めて、みんな個性的でキャラが立っている。
これを知った星系政府は直ちに今後の対策と方針を検討する。この異変が長期に続くことを想定して、150万人の文明維持をどのように実現するかだ。一方で明石などのワープ船は、地球から来た青鳳や津軽も共に、星系政府と協力し、異変の解明に動き出す。どうやらかろうじてワープが可能なアイレム星系が一つの鍵を握っているようだ。
そして本書の終盤で新たな展開がある。セラエノ星系で謎の人工物が発見され、それがアイレム星系に電波を送っていることがわかる。アイレム星系に明石と青鳳がワープし、そこにある地球型惑星を調査しようとするのだが……。
いくつもの物語が並行で進み、メインとなるのは作者後書きにあるように補給を失った文明の自立と技術の維持ということにあるようだが、結末で出てくるこの新たな要素はこのシリーズが孤立した文明の存続というテーマを超えて、他のシリーズと同様、もう一つの別の視点を持ち込むものとなるように思わせる。そちらにも期待大である。
それだけではない。この巻で描かれるワープ航法の設定がとても面白いのだ。ぼくは『銀河連邦SF傑作選 不死身の戦艦』の解説で、超光速はタイムトラベルと切っても切れない関係にあり、地球とベテルギウスがスターゲートでつながったとして、ゲートの向こうは「いつ」なのか。またそこから戻ってきたとき、その地球は「いつ」なのか。二点間ならまだしも、複数の星々を結ぶとなると、もはやわけがわからない、と書いた。そしてそれを解決するには相対性理論を無視して絶対時間があるとすればいいとも。本書のワープ航法はまさにそれに対応したものなのである。
本書では地球から10光年離れた場所へワープした場合、船内時間では一瞬だが、地球時間では10年後の到着となる。ところが地球へワープで戻ると、やはり船内時間は一瞬だが、到着は地球出発時刻にワープ先での滞在時間を加えた時刻になる。乗組員が持ち込んだ地球の時計が刻む時間がそのまま有効となるのだ。ただこれでは因果律は守られるが、行きと帰りの非対称性が気になる。どうやら行きと帰りを合わせて一つの系となっているように思えるのだ(以下は作者が言っているのではなく、ぼくの勝手な解釈なので本書とは関係のない完全な蛇足です。無視していただいて結構です)。
だとすれば例えば地球からAへワープし、AからBへワープし、Bから地球へワープした場合、これが全て行きだとすればそれぞれが10光年離れていたとして地球→A→B→地球で30年かかることになる。これは超光速じゃなくなる(それともB→地球が帰りとなってタイムトラベルするのだろうか)。そこで地球→A→B→地球→B→A→地球で系が完結したとすれば出発時(+かかった時間)の地球に戻れてOKだが、これだと30年後の地球の情報を今の地球に伝えることができるので因果律が怪しくなる。本書ではワープのパラメータ設定が未知なので地球←→A、地球←→BはできるがA←→Bはできないことになっていてこれを回避している(ただ原理的に不可能だとは思えない。それに太陽系内など近距離でのワープも可能とのことだから、そういう実験も行われているのではないだろうか)。また「局所的な絶対時間」という概念も出てくる。SFだからそれで問題ないのだが、実際のところはよくわからない。まあ本書の優秀な科学者たちもワープの基本原理はわかっていないと言うのだから仕方がないだろう。それにしても(現象面はまだ不明なので置いとくとして、少なくとも運用面で)とても画期的なワープ航法である。今後さらに驚くような内容が出てくるのかも知れずワクワクする。
THATTA 412号へ戻る
トップページへ戻る
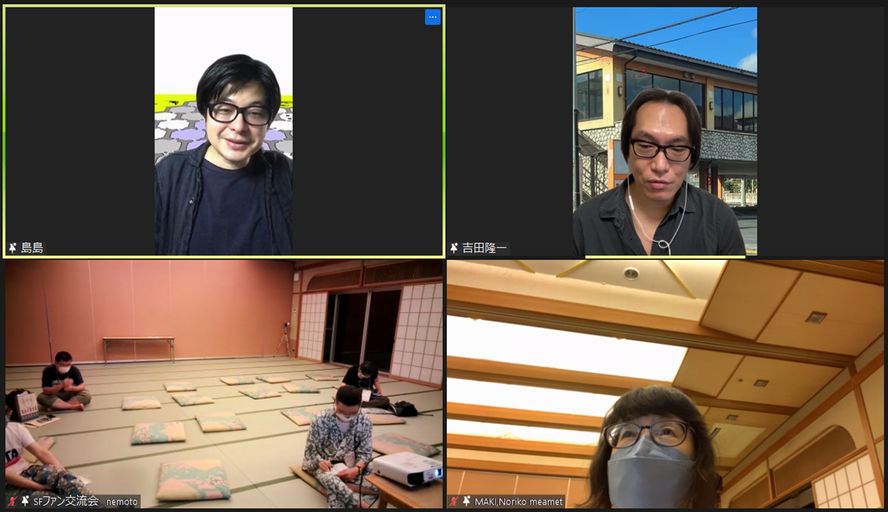 8月のSFファン交流会は8月27日(土)に、「吉田隆一の羊のお茶会「マンガと音楽とSFと」」と題して開催されました。出演は、吉田隆一さん(SF音楽家)と、西島大介さん(マンガ家)。今回は第59回日本SF大会F-CONの企画としてZoomとSF大会会場をつないで実施されました。
8月のSFファン交流会は8月27日(土)に、「吉田隆一の羊のお茶会「マンガと音楽とSFと」」と題して開催されました。出演は、吉田隆一さん(SF音楽家)と、西島大介さん(マンガ家)。今回は第59回日本SF大会F-CONの企画としてZoomとSF大会会場をつないで実施されました。 『血を分けた子ども』 オクティヴィア・E・バトラー 河出書房新社
『血を分けた子ども』 オクティヴィア・E・バトラー 河出書房新社 『いずれすべては海の中に』 サラ・ピンスカー 竹書房文庫
『いずれすべては海の中に』 サラ・ピンスカー 竹書房文庫 『AI法廷のハッカー弁護士』 竹田人造 早川書房
『AI法廷のハッカー弁護士』 竹田人造 早川書房 『工作艦明石の孤独 1』 林譲治 ハヤカワ文庫JA
『工作艦明石の孤独 1』 林譲治 ハヤカワ文庫JA