

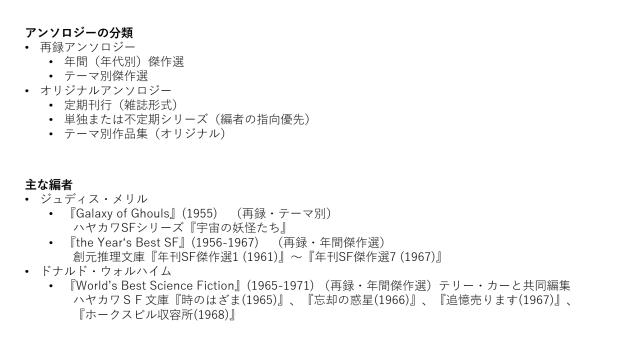
内 輪 第363回
大野万紀
 |
| 橋本さんはクリスマスペンギンです |
 |
| 冬木さん |
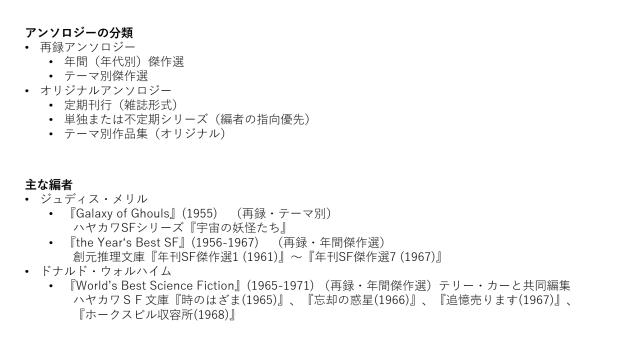 |
| 大野万紀のパワポ |
11月のSFファン交流会は、11月21日(土)の14時からオンライン(Zoom)で開かれました。テーマは「新たな時代の海外SFが読みたい!」。このたび『2000 年代海外SF傑作選』をハヤカワから出された橋本輝幸さんを中心に、レビュアーの冬木糸一さんが加わり、それにぼくがロートルの立場から昔話をするということでしたが、急遽『20世紀SF』など多数のアンソロジーを編集されている中村融さんがゲスト出演されることになって、アンソロジストの心得など、非情に深い話が聞けました。
事前の打ち合わせで、冬木さんがアンソロジーには特に興味がなく、SFファンは何でアンソロジーを作りたがるのかわからないと発言。ぼくらはアンソロジーを作る(というかその目次を考える)のが大好きで、それが当たり前だと思っていたのでびっくり。目から鱗です。橋本さんはそれについて、アンソロジストは好きなセットリストを作るDJのようなものだと説明。
中村さんはアンソロジーは選ぶのは楽しくても落とすのが大変と、実際のアンソロジー編纂の苦労を語られました。
橋本さんはネットで2000年代アンソロジーを作ることになったというとブルース・スターリングからディスられるよと言われ、その言葉をもらったから、たとえディスられても平気な気持ちになったとのこと。
ぼくは昨夜あわてて作ったパワポをZoomで共有し、アンソロジーの分類(再録アンソロジー、オリジナルアンソロジー、テーマアンソロジー等)や主な編者について、ジュディス・メリルからざっくりと話しました。ぼくもそうなのだけど、まだお若い橋本さんが初めて読んだ海外SFアンソロジーがジュディス・メリルの『年刊SF傑作選』だったと聞き、これまたびっくりです。
前半は中村さんも交えて主にアンソロジー作りのノウハウや苦労やそんな話が中心となり、後半は冬木さんと橋本さんが中心で今の最新の海外SFの話。橋本さんは中国語も読めるんですねえ。本当に貴重な人材です。
16時になったのでいったん終了し、以後二次会モードへ。
たこいきよしさんや大森望さんもここで顔出し。大森さんが入ったので、あの作品が何で入っているの?とアンソロジスト同士の闘いが始まります。いやあ面白い。そこに中村さんも参戦し、ぼくも調子にのって色々言ったと思うけれど、記憶にありません。
バベルジンの若手に期待しつつ二次会も終了しました。
おまけで、一夜漬けで作ったぼくのパワポも貼り付けておきます(リンク先はGoogle Drive)。パワポの後半はまったくの手抜きでお恥ずかしい限りです。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 『シグナル』 山田宗樹 角川書店
『シグナル』 山田宗樹 角川書店
300万光年離れたさんかく座銀河M33から知的生命のものと思われる電波信号が届く。地球外知的生命の発見だ。人類は孤独ではなかった。これは人類の新たな時代の幕開けであると、人々はこの発見に沸き立った――はずだったが、最初の熱狂が静まり、いつまでたっても信号は解読されず、宇宙人が攻めてくるといった一部のセンセーショナルな反応を除けば、人々の日常生活には何の変化もなかった。宇宙が大好きな中学二年生の芦川翔は、同級生たちがこの発見に通り一遍の興味しか持たないのが歯がゆくてならない。そこで、高等部の先輩、天文学者を母にもち、変わり者で知られている朱鷺丘昴ならこの感動を分かち合えると思う。だが彼は想像した以上に変わり者だった……。
本書の第一部はこのように始まる青春小説である。主人公の芦川は中学生ながらとても頭が良く、確かにやや中二病的ではあってもこじれてはおらず、しっかりと遠くを見る視線をもった素直な少年である。一方の朱鷺丘は天才的な高校生で、知識もあり、深く合理的な思索をするが、コミュニケーション力がゼロに近く、かなりめんどくさい人間だ。でも相手を見る目はあり、人を拒絶するだけの人間ではない。ディラックとあだ名されるこの朱鷺丘先輩のキャラクターがいい。めんどくさいけれど憎めない、それを越える魅力のある人物だ。さらに生徒会のイケメン、滝沢先輩もからんで、男の子たちばかりだけれど、300万光年という途方もない距離を介するファーストコンタクトの意味や、信号の謎について議論する、いわば至福の時間が描かれる。
そこに断片的に、本書のもう一人の主人公といえるケイこと「私」の語る断章が挟み込まれる。彼女は幼少のころから「声」を聞いていた。今度の発見で、それがM33からの声だとわかった。ネットを見て、同じように彼らからの「声」を聞いていた「受容体=レセプター」の存在を知る。選ばれた仲間の存在を。
第二部では17年の時が過ぎ、芦川は科学ジャーナリストに、朱鷺丘は科学者になっている。そしてついに朱鷺丘が信号の解読に成功する日が来た。その一方で、芦川はケイたちレセプターがある映像を幻視したということを知り、接触を試みる。レセプターたちが見たものとは……。
本書の中で『三体』への言及があるが、異星人とのコンタクトを語るときに、『三体』はすでにSFファンの閉じたコミュニティを越える(スター・ウォーズやゴジラと同様の)スタンダードとなっているのだなと思う。レセプターたちが直接M33の異星人から得た情報は、まさに『三体』とパラレルなものだったが、その後の展開は大きく異なる。
これもまたフェルミのパラドックスへの一つの回答だろう。そしてその回答は(殺伐とはしていないが)荒涼としてやはり寂しいものだ。ただM33星人についての描き方は、ぼくとしてはちょっと物足りない。何しろ300万光年を越えて情報を送ってくる相手だ。ほとんど魔法みたいなテクノロジーを持っているわけで、だからその科学技術に関する説明が少ないのは納得できる。しかしこの結論は少し情緒的に過ぎるように思える。何というかちょっとバランスが悪いのだ。レセプターたちの存在がなければこれで文句はないのだが。
とはいえ、しっかりと書かれた本格SFであり、とりわけ第一部は科学する少年たちの、瑞々しさが心に残る物語だった。
 『アメリカン・ブッダ』 柴田勝家 ハヤカワ文庫SF
『アメリカン・ブッダ』 柴田勝家 ハヤカワ文庫SF
書き下ろし1篇を含む6篇収録の短篇集。これが著者の初短篇集となる。ほとんどは既読だが、確かに民俗学・文化人類学的な観点とSF的な仮想がからみあって、独特な小説世界を作り出している。その基層にあるのはとても真面目な問題意識で、まるで民俗学の研究論文を物語しているようにすら読める。
星雲賞受賞作の「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」などはまさしくそのような作品だ。VR世界に生きることを選択したある民族についての研究報告。ネット時代にSNSの中で同一性を志向する集団が独自の文化を育てるように、それが雲南省の山岳民族というもともと独自の文化をもつ集団がテクノロジーによってそれを強化する。リアル世界との関わり方に無理があるように思え、そこに曖昧さがあるのは気になるが、発想はとても面白い。
「鏡石異譚(きょうせきいたん)」は『ILC/TOHOKU』に書かれた作品で、遠野物語と岩手に作られるリニアコライダーを掛け合わせるという離れ業。しかしILCとの関わりはあまりなく、これは未来の自分・過去の自分と出会うことのできる少女の成長物語である。ここで描かれる記憶を核とした情報のタイムトラベルは、タイム・パラドックスのような矛盾がなく、さすがにロジャー・ペンローズはもういいよとは思うが、少なくとも個人に関わるところは納得できて、面白く読めた。観光小説としての側面もあって、描かれた土地に行ってみたくなる小説である。
「邪義の壁」は初読。〈ナイトランド・クォータリー〉誌掲載のホラーである。山奥の旧家にある、ウワヌリと呼ばれる白い壁の和室。あるときその壁の一部が崩れ、中から江戸時代のものと思われる白骨死体が出てくる。そこから次第にこの家や集落の異端信仰の歴史が明らかになっていく。そこには確かに民俗学的な面白さがある。超自然的な要素は過去に封印されたものが次々と出てくるこのウワヌリくらいのものだが、主人公たちはその存在にとらわれ、徐々に狂気の世界へと入り込んでいくのだ。
「一八九七年:龍動幕の内」は長編『ヒト夜の永い夢』の前日譚。南方熊楠の英国留学中の物語で、彼がロンドンで出会った空を飛ぶ”天使”の謎を孫逸仙と共に解いていくエピソードを描く。破天荒な熊楠らしさもあって面白く、スチームパンクものとしても良く出来ている。これが『ヒト夜』のあれに繋がっていくのだろうなと思わせるが、『ヒト夜』よりずっとオーソドックスですんなりと頭に入る、読みやすい作品である。
「検疫官」は異色作。だがミームを主題とした作品として、むしろデビュー作の『ニルヤの島』に近いのではないかと思う。「物語」を疫病ととらえ、その感染を水際で防ごうとする検疫官。だが「物語」の感染を防ぐことすら「物語」となってしまう矛盾を抱えている。新型コロナと同様に、感染を防ごうと第一線で働く者が感染のリスクが高いとか、感染者への対処にワクチンのように軽い物語を使うといったアイデアは面白い。思想検閲のようなディストピアものとしても読めるが、やはり物語というミームについての物語なのである。
本書の書き下ろし「アメリカン・ブッダ」はアメリカインディアン、仏教的なミーム、仮想世界のポストヒューマン、そして社会の分断といった現代的でSF的なテーマを盛り込んだ傑作。ある大災害により、アメリカは壊滅的な被害を受け、ほとんどのアメリカ人が仮想世界に移住した未来。語り手は”Mアメリカ”と呼ばれる仮想世界の市民であり、現実世界とは違う時間の中で生きている(実世界の1秒が4時間弱に相当する)。そこへ現実のアメリカに残ったインディアンの青年から、すでにアメリカは復興しつつあり、仮想世界の人々に帰ってきて欲しいと訴えるメッセージが届く。彼は仏教を信仰し、ブッダの教えを説くのだ。ちなみに作者はネイティブアメリカンではなく、インディアンという言葉を意図的に選択している。なぜわざわざそうしているのか。ブッダの故郷であるインドを思い起こさせるためか。「良いインディアンは死んだインディアンだけだ」という言葉を使いたかったためなのか。それはともかく、このメッセージによって仮想世界は混乱し、深刻な分断が起こる。ただ、作品後半の主人公の行動と思考がぼくにはよくわからなかった。後半で出てくるシミュレーション宇宙も、科学的探求をしているのではなく、小さなパラメータを変えて再現した歴史の変化を見ようとしているだけであり、ストーリーの分岐を探っているようですごくゲーム的だ。育成ゲームで最高の彼女が現れる分岐を探るように。”推し”の地球を作ろうとするかのように(そこが作者らしいといえるところだろう)。それは『火の鳥・未来編』をやろうとしたのかも知れないが、もしかしたら結末の一言を導くためだったのかも知れない。確かにこの一言はバッチリ決まっている。ちょっとあざとい気もするが、力作であり、傑作である。
 『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』 シェルドン・テイテルバウム&エマヌエル・ロテム編 竹書房文庫
『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』 シェルドン・テイテルバウム&エマヌエル・ロテム編 竹書房文庫
とてもぶ厚い文庫で、中短篇16編と、シルヴァーバーグのまえがき、編者による「イスラエルSFの歴史について」(かなりボリュームあり)、イスラエル最初のSF雑誌編集長によるあとがきまでと、盛りだくさんな内容で現代のイスラエルSFを紹介する内容である。何しろ16編の作品のうち、知っている作者名はラヴィ・ティドハーただ一人というありさまなので、とても興味深く読んだ。
訳者代表の中村融も書いているが、本書は2018年にアメリカで英語で出版されており、ケン・リュウによる『折りたたみ北京』などの英語版中国SFアンソロジーと同様のコンセプト(英米、そして世界に向かって、この世界の片隅――中国を片隅とはいえないだろうが――にも独自のSFが発展しているんですよ!)があるように感じられる。そして(本書だけで判断してはいけないかも知れないが)中国SF以上に、その独自性が色濃く出ているように思えた。本書に見られるイスラエルSFの独自性、それはいわゆるサイエンス・フィクションであるよりも、奇想を重視した個人・家族・社会に関するスペキュレイティヴ・フィクションが中心にあるということだ。とりわけ個人よりも家族や社会の関係に重点が置かれているのは英米SFよりもアジア系に近い感触を得た。
編者による「イスラエルSFの歴史」を読むと、驚くことにイスラエルという国は「本質的にSFの国とみなしてもかまわない」にもかかわらず、そこでは奇想や空想、幻想的な文学ジャンルというものが(SFやファンタジー、ホラーも含めて)、歴史的・文化的に長い間抑圧されてきたという。英米SFでのユダヤ系作家の大活躍を思うと信じられないような状況があったということだ。ディストピア小説などを突破口にそれが崩れてきたのが70年代以降、80年代、90年代になってやっと社会的にも認められる存在になったのだという。そのあたりも中国SFとパラレルな気がする。
ただ中国SFが奇想小説も含めて「SF」への指向が強いように思えるのに対し、イスラエルSFはたとえSF用語が使われていても描かれる異様な環境に対して「なぜ」と問いかけることはほとんどなく、それを受け容れた上での人々のふるまいや感情を描くことが中心となっているように思えた。設定に凝るということもほとんどない。なので、いわゆる「SF」味は薄めで、幻想小説やホラーの味わいが強い。イスラエルといえば科学の国という印象があるのに、これはちょっと意外だった。
ラヴィ・ティドハー「オレンジ畑の香り」もそうで、宇宙時代のイスラエルを舞台にしており、仮想世界や人間と機械との一体化といったSF的な要素も多いが(そういう意味では完全に「SF」だ)、主題は何代にも渡る家族の記憶であり、土地に染みついた想いである。
ガイル・ハエヴェン「スロー族」では、人間が加速成長できるようになった時代、普通に何年もかけて育つ人々はスロー族と呼ばれて保護地区に閉じ込められている。その保護地区が閉鎖されることになって、それに抗議するスロー族の女性との話し合いがもたれるのだが、互いの認識はすれ違いのままだ。それは現代における性差別や少数者差別の非対称性とパラレルで、結末はぞっとするものだ。ここでも親子、家族の問題が別の視点から描かれている。
ケレン・ランズマン「アレキサンドリアを焼く」は中編。設定は完全にSF。エイリアンの侵略で荒廃した地球では、機械の体に人類の意識を復元したアンドロイドたちがエイリアンと果てしない戦いを続けている。そこに時間を越えて人類の叡智を保存する「アレキサンドリア図書館」が出現する。その司書とアンドロイドの会話がまるでかみ合わず面白い。しかし、最後に図書館が下す決断は、いかにもイスラエルっぽい(偏見か)マッチョなものだが、これ、女性作家の作品なのだなあ。
ガイ・ハソン「完璧な娘」では人どころか死人(死んで数日までならば)の心まで読み取れるテレパスたちの学校が描かれる。主人公の女性は死体置き場の担当となり、死んだ美女の記憶に触れ、次第に取り込まれていく。これも長めの中編で、じっくりと書き込まれた繊細な心理描写には読み応えがある。でもちょっと長すぎるかな。
ナヴァ・セメル「星々の狩人」はショートショート。大気が病み、夜空から星々が消えた日に生まれた子どもが、おじいちゃんたちと星々への憧憬を語る。ほとんどの世間の人々は夜空の星への感傷など持ち合わせておらず、それが当たり前の日常だと考えているのに。深読みすれば、かの国におけるSFファンの気持ちを代弁したものかも知れない。
ニル・ヤニヴ「信心者たち」は短めの短篇で、厳格で残酷な神が実在するようになった世界(戒律に合わない食物の組合せをカートに入れた老婆が天罰で真っ二つにされる)で、神を殺そうとする不信心者たちの物語である。テッド・チャンの『地獄とは神の不在なり」を思わすが、厳格な砂漠の宗教がより身近な国での迫真性といったものを感じる。
エヤル・テレル「可能性世界」では占い師の女性に別の可能性世界の自分について聞く作家が登場する。彼にはタイムマシンで未来へ行き、老人となった自分を殺した記憶があるのだ。作者はSFファンで、コンピュータ・サイエンスの専門家だということだが、ここには(SFファンである証拠は結末であからさまに示されているが)タイムパラドックスや並行世界についてのSF的な考察はほとんどなく、より普遍的な人生への疑問や「もし」への不安が描かれている。ぼくはチョン・ソヨンの作品を思い起こした。
ロテム・バルヒン「鏡」も可能性世界を扱っている。ここでの小道具は魔法の鏡。ヒロインはその特別な鏡を傷つけることで、もう一つの世界の自分と入れ替わることができる。向こう側の自分がより不幸になるのを見る誘惑に耐えられず、彼女は鏡を覗き続ける。だが入れ替わった自分とは誰なのだろう。
モルデハイ・サソン「シュテルン=ゲルラッハのネズミ」はまるでハードSFのようなタイトルだが(シュテルン=ゲルラッハの実験とは電子にスピンがあることを示した量子力学の有名な実験)、シュールなドタバタSFであり、知能ある巨大ネズミがエルサレムの古い通り(主人公のおばあちゃんが住む)を占拠する。主人公は〈ブリキの物乞い〉と呼ばれる絵を描いて暮らす放浪するロボット(このロボットがもの悲しくてとてもいい)と共にネズミと戦い、撃退するのだが……。ネズミは今でもそこにいるのです。
サヴィヨン・リーブレヒト「夜の似合う場所」は中編で、破滅後の世界をごく身近な狭い範囲のみで描いた読み応えのある作品だ。破滅はSF的というより黙示録的で、ほとんどの人々が死に絶え、致命的な竜巻が地を這っては生き残った人々を吸い込んでいく。列車の喫煙室にいてたまたま無事だったヒロインは、そこに居合わせた男、死んだインド人夫妻の残した赤ん坊、厭世的な老人と共にホテルに籠もり、やがて若いポーランド人や修道女がやってきて、変わり果てたこの世界で何とか生きていこうとする。サバイバルものというよりは極限状況での人間関係や心理に重点がおかれ、ホラーの雰囲気が強い。この不安な雰囲気は圧倒的であり、またヒロインの思いや行動も西欧的・個人主義的ではなく、どちらかというと東洋風で、それはこの世界においては狂気をはらんだものに見え、それが結末の残酷さにもつながっていく。ぼくは小松左京の『復活の日』を思い起こした。
エレナ・ゴメル「エルサレムの死神」は死神と結婚した女性の物語。しゃれた都会的なファンタジーであり、ゴージャスな雰囲気が楽しい。しかし何しろ相手は死神だし、ユダヤ人の歴史にからむ深い恐怖もはらんでいる。死神たちは〈疫病〉<自殺〉〈老齢〉〈戦争〉など死因によってそれぞれ存在するが、セレブなコミュニティを作り、集まってはパーティをしている。だがそこからはみ出した仲間はずれの死神もいる。死神たちの設定やヒロインとの関係が興味深く、面白かった。
ペサハ(パヴェル)・エマヌエル「白いカーテン」はロシア語で出版され英訳された作品。作者は天体物理学者で、ロシア語圏でSF作家として活躍しているとのこと。この作品も可能性世界を描いたものであるが、SF的には明確で、ハードSFなアイデアが描かれている。無数に分岐していく多元宇宙の世界線を可能性の科学的根拠に基づいて統計的に枝刈りし、さらにその枝を接ぎ木したり繋ぎ合わせたりできるというのだ。だがそんな分岐世界では起こらないはずの事象が起こった。愛する彼女が死んだのだ。分岐の数は有限であり、そのどれでも彼女は死ぬ。しかし、彼女を救うたった一つの方法があった。ストレートなアイデアストーリーではあるが、とてもよく出来ている。
ヤエル・フルマン「男の夢」では、夢を見ている間、そこに現れた相手を現実に呼び出してしまう能力をもつ男が描かれる。呼び出された相手は男が目覚めるまで、男の寝ている場所で見えない障壁に閉じ込められてしまうのだ。男が目を覚ますと、自由を取り戻し、テレポートしたみたいにその場に現れる。男が呼び出すのは彼と直接関係のない、ひと目見ただけの女性。彼女が車を運転していようと、職場でプレゼンテーションの最中だろうと、男が彼女の夢を見るとその場から男の前に全裸で呼び出されてしまう。めちゃくちゃ迷惑な話だが、男に悪気はなく、とても申し訳なく思っているのだ。誰も悪くはないのに、よかれと思ってやったことが最悪の結果を招いてしまう。これもワンアイデアの話だが、結末にはぞっとする。面白かった。
グル・ショムロン「二分早く」は3次元ジグソーパズルの話。このパズルは世界的なパズル選手権の種目となっていて、まだ10代の3兄妹がそれに挑む。だが出題されたパズルセットが兄妹の家に届いたのは規定より2分早かった。全体を管理するコンピュータや兄妹がそれぞれ頭脳を駆使してパズルを組み立てる過程が詳しく描かれていて面白い。ハッピーな結末は悪くないが、ちょっと強引な気もした。
ニタイ・ペレツ「ろくでもない秋」は中編で、モンティ・パイソン的な躁状態のスラプスティック・コメディ。こういうのもあるんだな。同棲していた恋人からの急な別れ話に動揺した主人公のハチャメチャな日々を描くのだが、ろくでもないことばかりが起こる。仕事をクビになり、UFOが着陸し、荷物を運んでいたロバが偉そうに口をきくようになり、同居している友人は新興宗教の教祖になってしまい、全てが嫌になった主人公は拳銃をもって自殺しようと海岸へ行くのだが……。しかしこの全てがまるく収まる大団円。面白かったけど、本当にそれでいいの? ロバがかわいそう。
シモン・アダフ「立ち去らなくては」はいかにもSFファンが書いたとわかるオマージュに満ちた短編。父が戦死し、母親と共におばさんの家に引っ越すことになった姉と弟。その姉の視点で描かれた作品だが、学校でいじめられている弟に、彼女はおばさんの教えてくれた、隠された部屋にあった古いSF雑誌を読ませる。弟が言うには、姉の選んだ作品じゃないとダメなのだそうだ。その作品はスタージョンの「影よ、影よ、影の国」だったり、ヘンダースンの「アララテの山」だったり、ベスターの「5,271,009(未訳)」だったりする。そしてとても不思議なことが起こる。SFやファンタジーが少年少女に現実に立ち向かう助力を与えてくれるのだ。ただし、助力だけではなく、悪夢もまた……。
しかし、この本、一冊読むと、読み終えたという満腹感が大きいなあ。読み応えたっぷりでお腹いっぱいだ。