

内 輪 第277回
大野万紀
このところ「イーガン的なSF」という評し方をしたくなる作品が多く、ついこの前もひたすらクッキーを焼くだけのゲームが壮大なSF的背景を語られるのを見ていて、色々と考えさせられました。以下は、Twitterでも呟いた内容ですが、その時思ったメモです。
「現実と区別のない仮想現実」「量子論的な、その他様々な多宇宙の原理」「人工知能と自意識の不確かさ」さらに「シンギュラリティ」や「ナノマシン」「遺伝子操作」による「なんでもありに組み替え可能な世界」。こういった概念を用いれば、どんな風変わりな物語も「現代SF」になる。
自分もよく使う「イーガン的な現代SF」というラベルというか、タグ。それらを科学的側面から追求し、単なる物語の舞台背景としてではなく、アイデアそのものを主題として徹底したのがイーガンだったといえるだろう。だから、現代の優れたSFは、多かれ少なかれ「イーガン的」と呼ばれるのだ。
その昔、フレドリック・ブラウンはミダス王の神話が宇宙人の原子変換器で説明すればSFになることを示した。そんな用語を持ち出さなくても、背景として科学的な、あるいは統一的で合理的な世界観があれば、剣と魔法の異世界ファンタジーがSFとなることは、ラリイ・ニーヴンらが示しているとおりだ。
そして今では、どんな風変わりな物語でも、SFの文脈に落とし込める武器が手に入っている。これを使えば単に「SFだ」ではなく、「現代的ハードSFだ」
となってしまうのだ。まあ、すべての物語がSFになって嬉しいのはガチなSFファンだけだから、それで誰得?ってな話なのだが。
逆にいえば、現代の世界が(もっといえば宇宙が!)、それだけ本質的にSF的なものになってしまったといえるのかも知れない。
それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。
 |
 |
『クラーケン』 チャイナ・ミエヴィル ハヤカワ文庫
NHKで深海のダイオウイカの生きた姿が撮影されて話題を呼んだが、本書は現代ロンドンの自然史博物館で、体長8メートルのダイオウイカの標本が水槽ごと消失するところから始まる。
博物館のキュレーターで、ダイオウイカを担当していたビリーは、このダイオウイカ=クラーケンを崇拝するカルト宗教の信者たちや、スコットランド・ヤードの魔術担当刑事たち、十七世紀から生き続ける不死身の殺人鬼、裏ロンドンの予言者集団、死んだはずの大魔術師――などなど、オカルトが支配するもう一つのロンドンに巣くう、ありとあらゆる秘密結社の、まるで特撮ヒーローものの中ボスや戦闘員たちみたいな連中による、世界の終わりをめぐるすさまじい闘争に、わけのわからないまま巻き込まれていく。
はじめ、不可能犯罪がらみのSFミステリかと思わせたが、すぐに本書は、不可能なことなど何もない、魔法と魔術とグロテスクな笑いがいっぱいの、やたらと錯綜したドタバタコメディだとわかる。ミエヴィルの他の作品とも通じる要素はあるが、どちらかといえばアメコミ風な、ブラックで陰惨なスラプスティック・ファンタジーである。
世界が秘密結社であふれていて、それぞれの信じる「破滅」を目指しているといったあたりは、ハードにしたラファティみたいな雰囲気もある。ところどころにはっとするほど美しいイメージや、可愛らしい描写もあって、様々なパロディやオマージュ、細かい蘊蓄も含め、作者が思いっきり楽しみながら書いているのだなと思わせる作品だ。
上巻の後半に出てくる使い魔たちのストライキがいい。使い魔のネコたちが、大英図書館の前でピケをはってぐるぐる回っているんだよ。可愛いったらありゃしない! また、魔女警官であるコリングズウッドの造形もいい。婦人警官で、魔女なのだ。
とはいえ、ストーリーは錯綜をきわめ、敵味方も最後まで判然とせず、正直いってとても読みにくかったのも事実だ。訳者が一生懸命割り注をいれてくれているが、それでも会話の半ば以上が意味不明、というか理解不能。おそらくは「バルス!」とか「じぇじぇ」とかみたいなことを言っているんだと思うんだけどね。まあ、イーガンのハードSFと同じで、飛ばし読みしても問題ないんだと思う。わかればもっと面白いんだろうけど。
しかし、せめて登場人物一覧はほしかった。所属グループ別のやつ。誰か作ってほしいな。
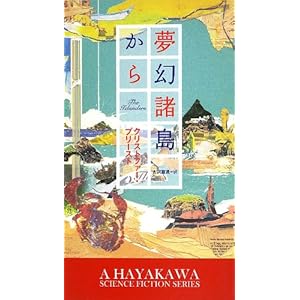 『夢幻諸島から』 クリストファー・プリースト 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
『夢幻諸島から』 クリストファー・プリースト 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
ついに出た、プリーストがずっと書き続けてきた、そしてライフワークともいえる〈ドリーム・アーキペラゴ(夢幻諸島)〉の最新巻。長いもの、短いものを含め、35編が収録された連作短篇集である。
訳者あとがきにあるように、長編として賞をとっているのだが、エピソードや登場人物に関連があり、ガイドブックとなるような体裁がとられているとはいえ、これは短篇集と見るのが普通だろう。
序文から最後まで、複雑できちんとおさまることのない、様々な関連性のネットワークがある。これはきちんとメモをとって分析しないといけないと思わせるのだが、面倒だからやっていない。でももともと、時間勾配とやらによって、ちゃんとした地図も作れない(でも船や飛行機は島々を結んでいて、インターネットのような現代的テクノロジーもある)世界なのだから、それでかまわないという気もする。
それぞれの小説自体は日常的なリアリティがあって読みやすい話なのだが(まあ何かの断片にすぎないようなものもあるが)、ついついこの世界にSF的な整合性を求めようという気になって、戸惑ってしまうことになる。でも考えちゃうんだよね。SF的などこかの植民惑星とするとつじつまが合わないので、地理的には全然違うのだが、もう一つの異世界の地球と考えることになる。いや、もう一つどころではない。時間勾配とやらによって、微妙に異なる幾千もの地球が同時に重なって並立しているというのが、SF頭には納得しやすい世界設定だろう。まあ別にそうやって納得する必要もないのだが。
必ずしも同一人物とは限らない主な登場人物がいる。作家のカムストン、画家のバーサースト、社会活動家のカウラー、パントマイム・アーティストのコミス、インスタレーション・アーティストのヨーといった名前をもつ人々だ。またコミスの殺害事件のように、何度も言及される藪の中的な事象もある。出来事も言及も微妙にずれていくので、謎はすっきりと解けることはない。
ゴランツ版のカバーには、All men are islands という言葉があって、なるほどと思う。この言葉を聞くと、ついサイモン&ガーファンクルを思い浮かべるのだけれど、彼らが孤独を歌っていたのに対し、この島々は孤立しながらつながりが、関連性がある。その関連性は実際の因果関係ではなく、この本を読む読者、並列する事象のさらに上のレベルから俯瞰する視点に、われわれの意識の中にのみ存するものだ。そして全編を覆う、重く残酷な大国間の戦争の影。
短篇として見た時、「ジェイム・オーブラック」が圧倒的だ。想像するだに恐ろしい毒虫、スライムが出てくるホラー、あるいはパニックSFとして強烈な迫力がある。スライムといってもドラクエのスライムじゃなくて、サソリっぽい節足動物なのだが、その凶悪さときたら……。
「ミークァ/トレム」は地図制作者たちの三角関係を描きながら、LEDを光らせ夜空を飛び交う謎めいた無人機の群れのイメージが恐ろしくも美しい。
そして「シーヴル 死せる塔」の、リアルな日常性と鮮烈な幻想が出会うところ。また巻末の「ヤネット」もアーティストたちの堂々たる活動がとても印象的だ。
ところでそれぞれの章の最後にある、観光ガイドっぽい通貨の記述が、何だかとても気になるのだが……。
 『日本SF短篇50 4』 日本SF作家クラブ編 ハヤカワ文庫
『日本SF短篇50 4』 日本SF作家クラブ編 ハヤカワ文庫
1993年から2002年の10編。冒頭の、大槻ケンヂ「くるぐる使い」、宮部みゆき「朽ちてゆくまで」、篠田節子「操作手」の3作は、いずれも読み応えのある中篇で、登場人物の心の動きに小説的なポイントがある。
最初の2篇はささやかな超能力が引き起こす不幸、もう1篇は介護の支援をする人間型ではないロボットの話だが、特にロボットの話はリアルでありながらSF度が高い。表題である「操作手」が誰のことかは明確だが、「共感」が人間の意識の重要な部分を成すとするなら、人工知能が本当に自意識を持つかどうかは別にして、環境からの入力によってパラメータをリアルタイムに変化させる仕組みがあれば、人間の共感がそこにフィードバックするということも十分あり得る(小説として納得できる)話だと思う。プログラムされた機械がまるで自意識をもつかのような動きをすることは、実際、わりと経験することなのだ。
藤田雅矢「計算の季節」はコンピュータの代わりに植物が計算するという話で、SF的な面白さよりも田舎の少年の夏休み小説である点に力点がある。
菅浩江「永遠の森」は『博物館惑星』の一編だが、『宇宙船ビーグル号』的な登場人物たちの個性のぶつかり合いと、謎めいた芸術品に込められた美しく切ない人の思いが心に残る。
小林泰三「海を見る人」は、奇妙な世界におけるもの悲しいボーイ・ミーツ・ガールの物語として、誰にでもアピールする実に美しい傑作。しかも、この世界のハードSF的な構築は物理学的に実にきちんと計算されたものであり、小説内ではほとんど断片的な説明しかないものの、世界の実相を見る、わくわくするような感覚がある。実はこの作品の本質はそちらにあり、少年と少女ではなく、世界そのものが主人公なのではと思える。難解な方程式を楽しめる読者は限られているだろうが、そういう読者も実際にいるのだ。
牧野修「螺旋文書」は、同性愛者のポルノ風なストーリーが突然とんがった言語SFに変わる傑作。このシリーズはぜひ単行本化してほしいなあ。
田中啓文「嘔吐した宇宙飛行士」はタイトルが警告しているので食事中に読む人はいないだろうが、食事中じゃなくてもちょー気持ち悪くなる話。でもずいぶんと壮大な話だなあ。
藤崎慎吾「星に願いを ピノキオ2076」は人間に追われる人工知能の生き残りをかけた戦いを描く。派手な戦いではなく、地味でみじめさの漂う戦いだ。
北野勇作「かめさん」は、かめシリーズ(?)の中ではちょっと異色で、量子力学や物理の言葉がわりと前面に出てくる。いつもはもう少しさりげないのだが。量子論からにじみ出してくる世界の不安定なイメージ、量子論そのものではないが、その知識からわき出してくるボケとツッコミ。そういう意味では、あんまりあからさまじゃない方が好みだな。
 『皆勤の徒』 酉島伝法 東京創元社
『皆勤の徒』 酉島伝法 東京創元社
『結晶銀河』に載って第2回創元SF短篇賞を受賞した「皆勤の徒」に始まり、『原色の想像力2』の「洞の街」、書き下ろし「泥洋の浮き城」、「ミステリーズ!」掲載の「百々似隊商」を含む連作中編4編が収録されている。
まずはとにかく奇怪に変形した日本語の用語がかもし出す異界のイメージに圧倒される。「社長」「従業者」「営業」「出社」といった身近な言葉が示す対象の、何と異形化していることか。その乖離がこの世界の絶望的な「遠さ」を感じさせる。
とはいえ、「外回り」「取締役」や「隷重類(れいちょうるい)」「兌換(だかん)」くらいまではまだいいが、「遮断胞人(しゃだんほうじん)」「冥棘(めいし)」なんてのが多用されると、むしろ言葉遊び的なものを感じてしまい、いったん遠くへ行ったものがまた帰って来て、異世界をそのまま見ているのではなく「作者」の目を通して見ている「作品」なのだと意識してしまうのは、マイナス要素でもある。変形した言葉の意味と、そのかすかに残る本来の意味との距離感に、失われた世界への絶望と切なさを味わっているのに、そこに無理やりにでもグロテスクなユーモアを混入させるのは、やっぱり関西人の性というべきか。あ、漢字のルビは漏らさずに全部打ってほしかったな。
それはともかく、本書は遙かな未来、人類が情報のみを継承して奇怪な姿へと変形した、幻想的でグロテスクな世界が舞台の本格SFであり、大森望が解説で指摘しているようにイーガン『ディアスポラ』ばりのハードSFなのである。そこらへんの読み解きは大森望の解説に詳しいので、あえて繰り返しはしないが、そこまで厳密に読まなくても、SF読みなら「だいたい合ってる」と思うだろう。
ただ、そいういうコアなSF設定を喜ぶべき小説かというと、まあ大まかにイメージできた方がわかりやすい、というところじゃないだろうか。本質的には、あらゆるものがノイズの混ざった情報に還元され、そこから再構成される時の、小さなバグや誤りが蓄積されることによる異質なものへの変化(進化ともいう)、その取り返しのつかなさ、それでも生まれてきた世界に生きていかざるを得ない、そんな生命の、有機体の、切ない営み、エデンの園を失った喪失感、そういったものが描かれているように思える。
本質的に情報でしかない存在の、それゆえにか、生々しい有機体としての触感、臭気、痛み、味、テクスチャーといったものが強調され、ぐちょぐちょどろどろと、まるで小林泰三か田中啓文かといった描写で描かれるのだが、読後感はむしろさわやかで、変化する世界への取り返しの付かないノスタルジーが残るのだ。
そういう意味では、北野勇作の『どろんころんど』や『きつねのつき』と同質のものを感じる。
 『ファンタジスタドール イヴ』 野﨑まど ハヤカワ文庫
『ファンタジスタドール イヴ』 野﨑まど ハヤカワ文庫
『know』が面白かったので読んでみたのだが(とても短いし)、アニメのノベライゼーションと聞いていたので、読み始めてびっくり。太宰治ですか。それもあからさまに『人間失格』のパロディ。
天才だが人としてどこか壊れた人間である主人公が、少年時代から大学へ進み、様々な人間関係を築いたり壊したりしながら、異常な研究へと向かうのを、私小説的なねちねちした昭和っぽい文体で追っていく。その研究というのが、まさにマッドサイエンティストらしいとんでもないもので、つまり理想の「嫁」を作るというのだ(これがアニメの前日譚というわけですね)。
大学生活あたりまでは、それなりにリアリティもあって面白く、太宰というよりは吾妻ひでおの「暗い青春の会」の面々を思い起こしたりもしていたのだが、その後の展開はちょっとぼくにはついて行けませんでした。アニメは見ていないので、そういう意味での面白さはきっとわかっていないのだけれど。
でも何でこの文体? マッドサイエンティストの内面を描こうとして採用したというのだろうか。よくわかりません。