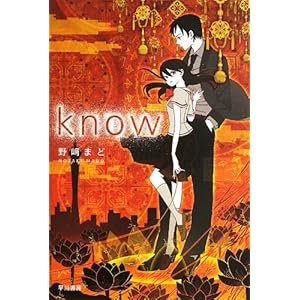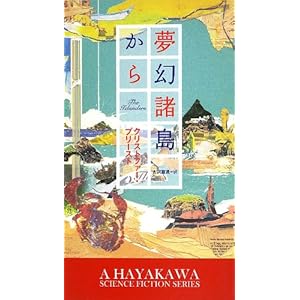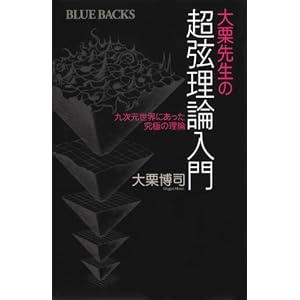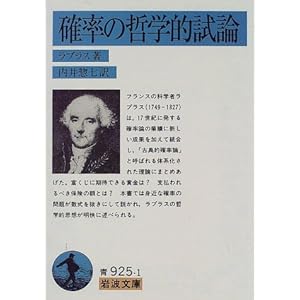たまたま日曜日が休日で雨が降っていたので、映画でも見に行こうと思い、近場では一番座り午後地のよいシートがある映画館で『風立ちぬ』やっているからということで、バスに乗って映画化まで行ったらロビーに人がわんさかいて、夕方までの席は全て売り切れだった。まあ人の考える事は皆同じ。宮崎監督の引退がニュースで話題だったしね。仕方がないので、少し離れた美術館でノグチイサムの展覧会を見て帰宅。改めて平日見に行く事に。
で、さすがに平日は半分くらいの入りで、落ち着いてみられた。ワガママだなあ、宮崎監督。というのが画面を見ながらの感想。少なくとも話で見るものを説得する気はない事がよくわかる。とりあえずこだわってきたもの/好きなものを集めてみました、そしてアニメは絵を動かす仕事だという当たり前のことをちゃんとやってみるとこういう風になるんだよということを見る者にわからせるつくりになっている。これまでの作品以上にテレビで見ても面白くない造りにしたようだ。
 ようやく涼しくなってきたので、何から聴こうかと考えたら、なぜかジョニ・ミッチェルのデビュー作から10作目まで入ったボックスセットが気になり、3000円という安さもあって、買ってみた。
ようやく涼しくなってきたので、何から聴こうかと考えたら、なぜかジョニ・ミッチェルのデビュー作から10作目まで入ったボックスセットが気になり、3000円という安さもあって、買ってみた。
68年発表のファーストは、CSN&Yのクロスビー(当時は元バーズか)がプロデュースでスティルス(当時は元バッファロースプリングフィールド?)がベースで数曲サポート。ジョニは西海岸のロック・シーンではそれなりのアイドルだったのか? しかし基本は自身のギター1本(オーヴァーダブあり)という、典型的なシンガーソングライターのスタイル。曲のクォリティは高いけど、ジョニの高音は耳に刺さるタイプなので、時折聴きづらい。セカンドも同傾向だけれど最後のトラックにはジュディ・コリンズでヒットした「青春の光と影」が入っていて、これでジョニも一躍作曲家として認められた。「チェルシー・モーニング」もタイトルのみ名高い。ジョニはギターとピアノを弾いている。サードになると初期ジョニのトレードマーク「ビッグ・イエロー・タクシー」やかの名曲「ウッドストック」に映画「いちご白書」のテーマ曲としてバフィー・セント・メリーの歌で大ヒットした「サークル・ゲーム」が入っている。これでジョニもスターの仲間入り。
そして発表したのが、ボブ・ディランがこれを聴いて「ブルーにこんがらがって」を作ったといわれる『ブルー』。記憶に残るようなシングルヒットはなかったかもしれないが、ここでのジョニはそれまでのアルバムから一段階クオリティを上げた、トータルなレベルでの充実した楽曲群を作りだしている。なによりキンキン声が影を潜め、低い地声に自信があふれ、歌う内容も数多くのライヴや大きな会場でのコンサートをこなす自分自身を表現するようになった。
『ブルー』を置きみやげにリプリーズ・レーベルからアサイラム・レーベルに移って5作目以降、ラリー・カールトンやウィントン・フェルダーそしてトム・スコットなど西海岸の腕利きのスタジオ・ミュージシャンたちが参加するようになり、歌詞もそれまでの私的な感覚からよりポップな語りへ移ってきた。ここからは70年代後半のコンテンポラリー・サウンドに乗ったジョニが聴ける。スマッシュ・ヒット「ヘルプ・ミー」もこの頃だ。いまやサウンドにどん欲となったジョニはついに、7作目『ヘジラ』でウェザー・リポートの伝説的ベーシスト、ジャコ・パストリアスを従え、自らのギターとピアノで腕こきのミュージシャンとゴージャスな演奏を繰り広げるようになった。そして10枚目。なんと死ぬ直前のチャールズ・ミンガスと意気投合したというジョニは、亡くなったばかりのミンガスを追悼するアルバム『ミンガス』を作ってしまった。バックはザヴィヌル抜きのウェザー・リポート。歌うは、ジョニからミンガスに捧げる歌、ミンガスがジョニに捧げたという曲に歌詞を付けた新作、そしてこのアルバムの2年前にジェフ・ベックがカヴァーして印象的だったミンガスの代表作のひとつ「グッバイ・ポークパイ・ハット」に歌詞を付けたもの。おまけに曲間をミンガスの喋りで繋いだという普通のポップ・スターでは考えられない前代未聞のしろもの。聴いた感じは「ジャズ・じゃない・ヴォーカル」アルバムといったところ。ウェイン・ショーターにハービー・ハンコックにジャコだから、当然バリバリのジャズ/フージョンが期待される所だけど、ジョニのギターとヴォーカルが入るとまったくジャズのノリが脱臼する。ショーターが大好きという知り合いに尋いたら、発売当時に聴いたけど全然ジャズじゃなかったのでスルーした、という返事だった。でも名盤/迷盤には違いない。偶然、「グッバイ・ポークパイ・ハット」のオリジナル演奏が入ったミンガスの「ミンガス・アー・アム」(1959年発売)が再発されたので買ってしまった。このアルバムは昔、黒人ジャズメンのプロテスト・ソング「フォーバス知事の寓話」が入っていることで有名だった。
大して思い入れもなかったのに、ジョニの68年のデビュー作から10年後の10枚目のアルバムまで聞いた感想は、オモシローというものだった。改めてデビュー・アルバムを聴くと最初の時よりも良く聴けるようになった。なお、ジャケットのイラストもジョニが描いていて、その変遷も楽しめる。『バラに捧ぐ』の見開き内写真の海辺の遠景写真に見えるフルヌードの後ろ姿はジョニ本人なんだろうか。
 とりあえず音楽話はジョニ・ミッチェルで終わろうと思っていたら、いきなりマイ・ブームが来たパク・キョンヒ(朴葵姫)。クラシックギターのファン以外には全く知名度がない若手女性ギタリスト。
とりあえず音楽話はジョニ・ミッチェルで終わろうと思っていたら、いきなりマイ・ブームが来たパク・キョンヒ(朴葵姫)。クラシックギターのファン以外には全く知名度がない若手女性ギタリスト。
ある休日、昼過ぎまで寝床でウトウトしながら、ラジオを聞き流していたら、客のいるスタジオでニュー・アルバムのプロモーションに来たらしい女性ミュージシャンになにやらインタビューしている気配。それまでに聴いていた番組の性格から、どうせ新進の女性ヴォーカルだろうと聞き流そうとしたら、なんとクラッシックギターの演奏がはじまり、曲もバリオスの「最後のトレモロ」という、たぶんそのスタジオの客も聴くのは初めてのマニアックな名曲。しかも今まで聴いた事もないような滑らかな音の流れとつややかな響き。びっくりして聴き耳を立ててしまった。目が覚めた時には、コーナーは終わっていてギタリストの名前はウル覚え。ググってみたらパク・キョンヒだった。そういえば昨年だったか「CDジャーナル」に新譜の宣伝があって、ちょっと影がありそうな表情の女性がギターを抱えているジャケットがあったなあ、と思い至る。ま、日本のトップ女性ギタリストの村治佳織(祈・病気回復)のCDさえ持ってないんだから、新進ギタリストに興味を持つわけもない。それが、ラジオから流れ出たギター演奏に一発で惹き込まれたのだから、これは10年くらい前にラジオで聴いたバンプの「天体観測」以来だ。
YouTubeで見ると、NHKが昨年放送したリサイタルの映像を中心に10数個の映像があったので片っ端から視聴。NHKのは音が小さいのでヴォリューム100パーセントで聴いた。見てびっくりしたのは、まず体が小さく手も小さい。そしてかわいい。肝心の音は、やはりとことん滑らかな響きがしている。これは聴いてみなくちゃと、CDをググると昨年のはデノン移籍のメジャー・デビュー盤で、その前にフォンテックレーベル(昔からあるけど、マイナー扱い)から2枚出していた。早速3枚を取り寄せたがフォンテック2枚のジャケットを見てびっくり。アイドル路線なジャケづくりで、本当にカワユい(きゃりーぱみゅぱみゅ系?)。選曲はギター・ファン向けで、デノンのメジャー・デビュー盤はさすがに「アルハンブラの思い出」とか「アストゥーリアス」とかギターの有名人気曲が入っているけれど、フォンテック盤は本人の得意とするものを集めた感じだ。音の方は、日本人クラシック・ギタリストの雄、福田進一がライナーに書いている通り、他のギタリストからは聴けないトレモロやタッチが聞こえる。しかし、ラジオやYouTubeで聴いた音の衝撃はスタジオ録音ではやや後退している。ま、クラシック・ギターのアルバムを聴き通すのは、福田御大のCDでさえ辛いものがあるので、仕方のないことではあるが。それでも各CDから数曲を聞き返すことができるので、クラシック・ギターのアルバムとしてはわが生涯最高のお気に入りであることは間違いない。最近発売された「最後のトレモロ」(プロモ・ビデオ)入りCDも買おう。
 『本の雑誌』の「サンリオSF文庫特集」で大森望が山野浩一にインタビューした中で、KSFAの話題がずいぶん出ていてびっくり。乗越さんの名前を覚えているとは、山野浩一恐るべし。まあ、翻訳を受けるだけ受けて、結果を出さずKSFAの評判を落とした張本人のひとりである自分にあまりツッコミは入れられない。すでに30年以上前の若気の至りとはいえ、お恥ずかしい過去ではあるなあ。
『本の雑誌』の「サンリオSF文庫特集」で大森望が山野浩一にインタビューした中で、KSFAの話題がずいぶん出ていてびっくり。乗越さんの名前を覚えているとは、山野浩一恐るべし。まあ、翻訳を受けるだけ受けて、結果を出さずKSFAの評判を落とした張本人のひとりである自分にあまりツッコミは入れられない。すでに30年以上前の若気の至りとはいえ、お恥ずかしい過去ではあるなあ。
 少し前に大森望が絶賛していた法月綸太郎『ノックス・マシン』を読んでみた。本が息子のところに送られて手元にないので、どんな話だったかうろ覚えだが、『NOVA』で読んだ表題作とその続編は、オーソドックスなSFだろう。ホームズの相方ワトソン的役割のキャラクターたちが激論を飛ばすユーモラスな「引き立て役倶楽部の陰謀」は、ほとんどの登場人物に馴染みがないので、ミステリ・ファンならニヤニヤできるんだろうなという感触だけがのこる。クリスティーの話はウィリスの大長編で読んだばかりだな。実際に読んだクリスティーは「トミーとタッペンス」シリーズの短編集だけだもんなあ。40年前だ。
少し前に大森望が絶賛していた法月綸太郎『ノックス・マシン』を読んでみた。本が息子のところに送られて手元にないので、どんな話だったかうろ覚えだが、『NOVA』で読んだ表題作とその続編は、オーソドックスなSFだろう。ホームズの相方ワトソン的役割のキャラクターたちが激論を飛ばすユーモラスな「引き立て役倶楽部の陰謀」は、ほとんどの登場人物に馴染みがないので、ミステリ・ファンならニヤニヤできるんだろうなという感触だけがのこる。クリスティーの話はウィリスの大長編で読んだばかりだな。実際に読んだクリスティーは「トミーとタッペンス」シリーズの短編集だけだもんなあ。40年前だ。
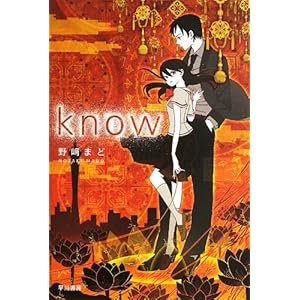 野﨑まど『KNOW』は前評判が耳に入っていたため、ちょっと期待したけれど、300ページの短編を読んだ気分で、やや肩透かし。だいたい自信満々の主人公の行きずりのセックス、それも後腐れのない素性の良い女で性欲処理、で物語を始めて、自信を打ち砕かれたあとは、聖なる14歳の美少女と情報遮断空間で清らかな愛を交わすなぞ、噴飯ものであろう(ツッコミどころが違うだろ!)。長編を読んだ気がしないというのは、こないだ読んだ藤井大洋の作品でも感じたけれど、長編を組み立てる上で多数のキャラをデクノボーにしか書けないのはどうかと思う。ま、SFの醍醐味はそんなものを吹き飛ばしてくれるのだが、エンターテインメントとしてみれば一直線は退屈だよね。
野﨑まど『KNOW』は前評判が耳に入っていたため、ちょっと期待したけれど、300ページの短編を読んだ気分で、やや肩透かし。だいたい自信満々の主人公の行きずりのセックス、それも後腐れのない素性の良い女で性欲処理、で物語を始めて、自信を打ち砕かれたあとは、聖なる14歳の美少女と情報遮断空間で清らかな愛を交わすなぞ、噴飯ものであろう(ツッコミどころが違うだろ!)。長編を読んだ気がしないというのは、こないだ読んだ藤井大洋の作品でも感じたけれど、長編を組み立てる上で多数のキャラをデクノボーにしか書けないのはどうかと思う。ま、SFの醍醐味はそんなものを吹き飛ばしてくれるのだが、エンターテインメントとしてみれば一直線は退屈だよね。
 その点、三島浩司『高天原探題』は、同じ300ページあまりを『KNOW』とは正反対といっていいくらい影の付いたキャラで埋め尽くしてみせる。こちらはこちらで過去を引き摺るキャラがワンサカいて、とても300ページで勝負するにはまとまりがつかない。話は関西地域限定の精神/異界実体化現象とそれに伴う意志不活性化というシンプルだけどなかなかのアイデア。ただしヒロインを祭り上げるカルトとかをクライマックスに持ってきて、だんだん視野狭窄になっていくのはいただけない。
その点、三島浩司『高天原探題』は、同じ300ページあまりを『KNOW』とは正反対といっていいくらい影の付いたキャラで埋め尽くしてみせる。こちらはこちらで過去を引き摺るキャラがワンサカいて、とても300ページで勝負するにはまとまりがつかない。話は関西地域限定の精神/異界実体化現象とそれに伴う意志不活性化というシンプルだけどなかなかのアイデア。ただしヒロインを祭り上げるカルトとかをクライマックスに持ってきて、だんだん視野狭窄になっていくのはいただけない。
 昔懐かしいタイトルの雑誌スタイルででた『SF宝石』は、本来ならソフトカヴァーの単行本なんだろうけど、費用対効果の一石二鳥を狙ったか。それにしても素っ気ないというか粗悪というか本としてあまりにもおもしろみのない造り。作品の方はバラエティに富んでいて悪くないけれど。読んでいて面白いのは、瀬名秀明、円城塔、上田早夕里などいわゆるジャンルの中心作家たち。しかし、昔の中間小説誌に載るタイプのものもある。小川一水なんかはその典型かな。でもプロパー系にも田中啓文みたいにストレートに凶悪なヤツもいるからなあ。ジャンル外の作家の作品も上手いけれど、SFとしては素朴なひねりが多い。
昔懐かしいタイトルの雑誌スタイルででた『SF宝石』は、本来ならソフトカヴァーの単行本なんだろうけど、費用対効果の一石二鳥を狙ったか。それにしても素っ気ないというか粗悪というか本としてあまりにもおもしろみのない造り。作品の方はバラエティに富んでいて悪くないけれど。読んでいて面白いのは、瀬名秀明、円城塔、上田早夕里などいわゆるジャンルの中心作家たち。しかし、昔の中間小説誌に載るタイプのものもある。小川一水なんかはその典型かな。でもプロパー系にも田中啓文みたいにストレートに凶悪なヤツもいるからなあ。ジャンル外の作家の作品も上手いけれど、SFとしては素朴なひねりが多い。
 今月は翻訳物をあまり読んでない。小川隆さんから訳者謹呈でいただいて(ありがとうございます)早速読んだラヴィ・ティドハー『革命の倫敦 ブックマン秘史1』は、あれよあれよという間に主人公があちこち連れ回されて、読む方も目眩がしそうな展開。現代のスチーム・パンクとしてはガジェット共々読みどころ満載で、SFの歴史に対するオマージュも良くできている。主人公の本来の目的である死んだ恋人の復活がどこかへ飛んでいきそうだ。でもシェリー・プリーストよりは安心して読めます。
今月は翻訳物をあまり読んでない。小川隆さんから訳者謹呈でいただいて(ありがとうございます)早速読んだラヴィ・ティドハー『革命の倫敦 ブックマン秘史1』は、あれよあれよという間に主人公があちこち連れ回されて、読む方も目眩がしそうな展開。現代のスチーム・パンクとしてはガジェット共々読みどころ満載で、SFの歴史に対するオマージュも良くできている。主人公の本来の目的である死んだ恋人の復活がどこかへ飛んでいきそうだ。でもシェリー・プリーストよりは安心して読めます。
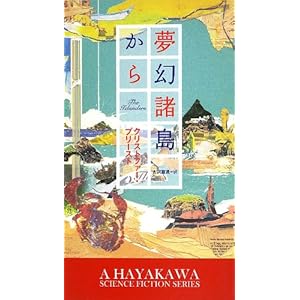 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ第1期最終配本のクリストファー・プリースト『夢幻諸島から』は掉尾を飾るにふさわしい難物。なぜこれはSFなのかという根本的なテーマから、物語を書くとは、登場人物の感情とは、目に見えるもの/見えないものを描写するとは、言葉の響きと意味とは何か、そういったことを様々に変奏して見せているのだから。
新☆ハヤカワ・SF・シリーズ第1期最終配本のクリストファー・プリースト『夢幻諸島から』は掉尾を飾るにふさわしい難物。なぜこれはSFなのかという根本的なテーマから、物語を書くとは、登場人物の感情とは、目に見えるもの/見えないものを描写するとは、言葉の響きと意味とは何か、そういったことを様々に変奏して見せているのだから。
そもそもこの世界の大作家が書いたという観光地誌の序文からして怪しい。読み進めれば、ある島でこの作家の葬式が行われているのだ。作品内目次であるアルファベット順の島名索引順に並んだ35編を読み進めていくと、ごく短い紹介だけの島から独立した短編としてドラマが展開される島までこの35編が一体どのように絡まっているのか疑いつつ読まざるを得ないようになる。見事な昆虫ホラーが展開されるオーブラック群島を含め、幾つかの短編で相互に言及される主要登場人物は島々で描かれ方がどこかずれていたりする。読者は非常に不安定な読書を余儀なくされるわけだ。しかし、小説を、物語を読むことの福音は確かにここにある。そう感じさせるだけでも、プリーストの企みは成功しているのだろう。
 一方、プリーストとは全く違う意味で難物なのが、酉島伝法『皆勤の徒』。表題作と第2作「洞の街」は再読だが、表題作は今回の方がイメージがよく掴めるようになったのに対して、2作目は集中力が途切れて前回よりもイメージが薄くなった。おかげで2作目はプロットばかりが読めて作品の印象が安っぽくなってしまった。ま、初読時のイメージは未だに残っているからいいけど。書き下ろしの「泥海の浮き城」がまた、置き換え言葉との格闘で疲れて、プロットが追えない。著者独自のイラストに助けられているのか混乱させられているのかわからない。そして最後の「百々似隊商」でようやく少し話が飲み込めるようになった。つなぎの断章を真面目に読んでなかったのが敗因だね。
一方、プリーストとは全く違う意味で難物なのが、酉島伝法『皆勤の徒』。表題作と第2作「洞の街」は再読だが、表題作は今回の方がイメージがよく掴めるようになったのに対して、2作目は集中力が途切れて前回よりもイメージが薄くなった。おかげで2作目はプロットばかりが読めて作品の印象が安っぽくなってしまった。ま、初読時のイメージは未だに残っているからいいけど。書き下ろしの「泥海の浮き城」がまた、置き換え言葉との格闘で疲れて、プロットが追えない。著者独自のイラストに助けられているのか混乱させられているのかわからない。そして最後の「百々似隊商」でようやく少し話が飲み込めるようになった。つなぎの断章を真面目に読んでなかったのが敗因だね。
大森望の解説は読み終わってから目を通したけれど、あまりにも明快な説明に納得しがたいものを感じる。別にこの置き換え言葉や宇宙SF的設定を読み解かなくてもというか、読み解かないでいた方が楽しく驚けるよねえ。デビュー作としては10年に1度の傑作!は誇大広告じゃないしね(円城塔は傑作かどうかもわからないし、伊藤計劃とはスタイルが違いすぎる)。
 限界研編『ポスト・ヒューマニティーズ 伊藤計劃以後のSF』は、帯によると「〈日本的ポストヒューマン〉を現代日本SFの特質ととらえ」た評論集。論者は若手中心。そういえば、SF大会で著者のひとりである岡和田晃さんがディーラーズ・ルームでこれを売っていたなあ。その時は買わなかったけれど。
限界研編『ポスト・ヒューマニティーズ 伊藤計劃以後のSF』は、帯によると「〈日本的ポストヒューマン〉を現代日本SFの特質ととらえ」た評論集。論者は若手中心。そういえば、SF大会で著者のひとりである岡和田晃さんがディーラーズ・ルームでこれを売っていたなあ。その時は買わなかったけれど。
各評論はわかるようでよくわからない論立てが多い。ま、こっちが歳取ったということなのだろう。第一部では藤田直哉「新世紀ゾンビ論、あるいはHalf-Life(半減期)」が参考になった。ゾンビが流行するようになって久しいけれど、個人的にはゾンビに興味がないのでみんな何を面白がっているのだろうと思っていたが、これを読んでなんとなくわかったような気がする。
第2部での評論群は、こちらが知らない世界を知らない論理であれこれ言挙げしてくれているのだが、当然ピンと来ない。基本的には思い入れの世界なのかな。飯田一史の「ネット小説論-新しいファンタジーとしての、新しいメディアとしての」は、えらく熱が入った奮闘ぶりだけれど、傍目からは空回りじゃなきゃいいけどと心配になってしまう。
そういえば大森望はこの本の応援しているみたいだけれど、それは戦略的にいいことでしょう。
 SFを離れると、まずE・S・モースとして有名なエドワード・シルヴェスター・モース『日本その日その日』。親本は昭和14(1939)年の翻訳だけれど、ほぼ普通に読める日本語。何でこんなものを読んだかというと、仕事の周辺のまた周辺本だったから。
SFを離れると、まずE・S・モースとして有名なエドワード・シルヴェスター・モース『日本その日その日』。親本は昭和14(1939)年の翻訳だけれど、ほぼ普通に読める日本語。何でこんなものを読んだかというと、仕事の周辺のまた周辺本だったから。
明治20(1887)年に、ただひとり帝国大学工科大学造兵科1期生として入学した明治元年東京生まれの有坂しょう(金へん+召)蔵(ありさかしょうぞう)というヒトがいて、その後軍艦の大砲を初めとした兵器類の技術者として大きな足跡を残したんだが、この人の伝記を読むと、有坂は、モースの弟子で後に動物学者として大成した石川千代松が義兄だったことで、子どもの時から石川の感化を受けて自然界のあれやこれやに興味を持つようになった。石川は当時ほとんど知られていなかった貝塚の発見者でもあり、有坂少年も考古学的興味を有していたのである。帝国大学教授として招聘されたモースは、初来日時すでに大森貝塚を発見していて、有坂少年はモース3度目の来日時に石川の手引きによりモースにいろいろ教えてもらっていた大学予備門時代に、これも石川の紹介で後に人類学者となる坪井正五郎や植物病理学者となる白井光太郎と知り合い、ある日向ヶ岡の貝塚調査を行った。このとき有坂が発見し、坪井に渡した土器こそ、後に弥生式土器と名付けられ、その第1発見者として有坂の名前が考古学の歴史に刻まれてる。
ということで読んだモースの日本滞在記は、聞きしにまさる日本ボメのものだった。明治時代前半期に日本に来た西洋のインテリ(男女とわず)は、江戸時代の習俗を残す日本人の生活に衝撃を受けている。江戸時だが残した社会システムは当時の日本人の行動様式を規定しており、その裏(身分社会、掟の苛烈さ)を見なければ、それはほとんど西洋社会が達成した社会システムが人間をスポイルするものだと思わされるほど「きちん」としていたのである。それにしてもモースはいい人だったんだなあ。
なおこれを訳した石川欽一は石川千代松の長男、原本からの抄訳とのこと。
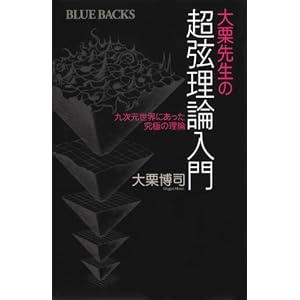 前回読んだ新書がびっくりものだった大栗博司『大栗先生の超弦理論入門』は超久しぶりのブルーバックス。中身は前回は重力が消えちゃったけど、今回は空間が消えちゃう。超弦が紐かループかという説明は、最近みたNHKの科学番組で輪ゴムを大量に集めて圧力をかけると膜(メンブレン)/シートになっちゃうというのが出てきて非常に分かりやすかった。どこかで2進法と素粒子の生成が同じものだとか出てこないかしらん。
前回読んだ新書がびっくりものだった大栗博司『大栗先生の超弦理論入門』は超久しぶりのブルーバックス。中身は前回は重力が消えちゃったけど、今回は空間が消えちゃう。超弦が紐かループかという説明は、最近みたNHKの科学番組で輪ゴムを大量に集めて圧力をかけると膜(メンブレン)/シートになっちゃうというのが出てきて非常に分かりやすかった。どこかで2進法と素粒子の生成が同じものだとか出てこないかしらん。
 仕事の周辺でもう1冊。久しぶりに丸善ジュンク堂をぶらぶらしていて見つけたのが楠見朋彦『塚本邦雄の青春』。ウェッジ文庫だけど地元の本屋ではまず見ない。2009年刊なので、完全に見逃してる。
仕事の周辺でもう1冊。久しぶりに丸善ジュンク堂をぶらぶらしていて見つけたのが楠見朋彦『塚本邦雄の青春』。ウェッジ文庫だけど地元の本屋ではまず見ない。2009年刊なので、完全に見逃してる。
塚本邦雄は滋賀県生まれの「現代短歌の極北にそびえる歌人(裏表紙)」だが、戦時中が青春時代で、徴兵検査に落ちた塚本は、徴用工員として海軍直営兵器工場である広島県呉市の広海軍工廠で4年間、敗戦まで働かされていた。兄の影響もあって少年時代に短歌を詠み始めた塚本は、呉市の短歌同人誌に出詠するようになった。それが非アララギ派の『木槿(むくげ)』である。「現代短歌の極北にそびえる」ずっと前の時代、2005年に塚本が亡くなるまでほとんど知られていなかった塚本の作歌を『木槿』から引用しつつ、若き歌人塚本の足跡を追った本。作者の興味はあくまで塚本の短歌の変遷にあるので、資料として使うには難しい本だけれど読んでおくべきものではあった。ちなみに中国歴史小説の作家塚本靑史は子息。
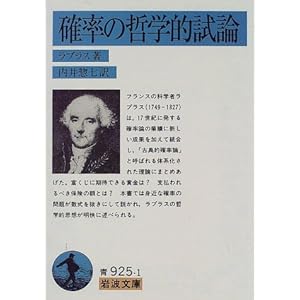 最後は積ん読の中からラプラス『確率の哲学的試論』1997年刊の岩波文庫。何でこんなものを、というところだけど、つかんじゃったので、とりあえず「読んで」みた。読めません、というのが正直なところ。
最後は積ん読の中からラプラス『確率の哲学的試論』1997年刊の岩波文庫。何でこんなものを、というところだけど、つかんじゃったので、とりあえず「読んで」みた。読めません、というのが正直なところ。
高校から浪人時代まで数学2Bを3年間もやったのに、微積どころか数列の意味さえわからない。訳者注ときたらラプラスが文章で書いたことを数式化して、「ここは数式化なしでは理解できない」からといって次々と数式をこしらえて、あまつさえ、なんでこんな前提をラプラスは置いているのか訳者にもわからない、とのたまう始末。昔ならすぐに放り投げた代物だが、歳のせいか気が長くなって最後まで目を通してしまった。まあ、コインの裏表や白黒の玉が入った壷のことを真面目に考えても前に進まないので、ラプラスのエッセイ部分だけを追った感じ。本論はたった150ページだし、訳者解説も一応面白い。
初めの方に、有史以来5000年毎日昇った太陽は明日も昇るか、という確率が出てくるのだけれど、5000年は182万6000日あまりなので、これを使って確率計算すると明日太陽が昇ることは、ほぼ間違いない確率がでる。しかし訳者解説で、これが200万日先でも太陽が昇る確率となると0.5を切ってしまうという。こういうのは文化系人間が困ってしまう説明だ。ここで問題になるのは確率に使うデータ計算の性質であって、太陽が200万日後にも昇ぼるかどうかという話は、文化系人間にすれば式のデータ計算の性質とは別の話なのだ。地球の成り立ちを38億年前にすれば、ラプラスの式による明日太陽が昇る確率は限りなく1に近付くだろうし、40億年後に昇る確率はやはり0.5以下だろうが、いまの天文学の常識では、どちらも数式のデータ的な正確さが無意味なものになっている。38億年前の地球はいまの自転速度や公転周期だったのか、40億年後に地球は存在するか、とかそういう知識が確率論のお勉強を邪魔するのである。
しかし、確率論で太陽系の成り立ちまで解いてしまうのは凄いよね。ラプラス偉い。
THATTA 305号へ戻る
トップページへ戻る
 ようやく涼しくなってきたので、何から聴こうかと考えたら、なぜかジョニ・ミッチェルのデビュー作から10作目まで入ったボックスセットが気になり、3000円という安さもあって、買ってみた。
ようやく涼しくなってきたので、何から聴こうかと考えたら、なぜかジョニ・ミッチェルのデビュー作から10作目まで入ったボックスセットが気になり、3000円という安さもあって、買ってみた。