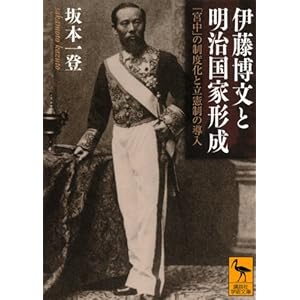地元の島をロケハンしたというアニメを見にシネコンなるものにはじめて行った。映画は昔ながらのもぎりのオジさんオバさんにいる2D専門の映画館しか行ったことがなかったので、余りの商売気に目が回った。こんなサービスに1800円払って高い飲み物や食い物を買わされてみんなよく我慢していられるねえ。設備自体は文句ないけれどね。という話を若い人にしたら、今映画を見る人はそんなこと考えませんよといわれた。
ようやく聴き終わったケンペの「マイスタジンガー」はやはり素晴らしい出来で、1950年代後半のケンペがHMVにグイド・カンテルリと一緒に有望株として買われていて、ベルリン・フィルやウィーン・フィルを振って何枚もレコードを作らせて貰ったのがよく分かる好調ぶり。病弱と素朴な気風(田舎者気質?)が災いしたか、その後はあまり重用されなかったけれど。まあ、どちらにしてもカラヤンみたいなハードワークは無理だったろうな。
 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ3冊目、イアン・マクドナルド『サイバラバード・デイズ』は、本当に久しぶりのマクドナルド。全体的な印象は、大枠は割とオーソドックスなプロットなのに、膨大なエキゾティック趣味で読者の目をくらませる類に見える作品集といったところ。『火星夜想曲』の頃のナイーブさは後退し、テクニカルな操作が前面に出ている。バチガルピほどストーリーとエキゾティシズムがしっくりいっていないように感じられるのが難かな。作者が新大陸を発見したらしい興奮は伝わってくるので、それは嬉しいんだけれど、危なっかしさもかなりのものだ。集中ではエキゾティズムが当たり前の日常に戻ってくる「小さき女神」や「ジンの花嫁」あたりが読みやすい。書き下ろしの「ヴィシュヌと猫のサーカス」は書き方の所為か散漫な印象。
新☆ハヤカワ・SF・シリーズ3冊目、イアン・マクドナルド『サイバラバード・デイズ』は、本当に久しぶりのマクドナルド。全体的な印象は、大枠は割とオーソドックスなプロットなのに、膨大なエキゾティック趣味で読者の目をくらませる類に見える作品集といったところ。『火星夜想曲』の頃のナイーブさは後退し、テクニカルな操作が前面に出ている。バチガルピほどストーリーとエキゾティシズムがしっくりいっていないように感じられるのが難かな。作者が新大陸を発見したらしい興奮は伝わってくるので、それは嬉しいんだけれど、危なっかしさもかなりのものだ。集中ではエキゾティズムが当たり前の日常に戻ってくる「小さき女神」や「ジンの花嫁」あたりが読みやすい。書き下ろしの「ヴィシュヌと猫のサーカス」は書き方の所為か散漫な印象。
 小川一水『天冥の標Ⅵ 宿怨PART1』は、ホントに話半分で終わっているため何とも言えないけれど、作者が読者に見えるようにしてきたスケールと実際に読ませて貰っている話の間にはちょっとギャップが生じているような気がする。まあ、そうはいっても今は話半分なのでこの違和感が続くかどうかは話の続きを読んでからにしよう。
小川一水『天冥の標Ⅵ 宿怨PART1』は、ホントに話半分で終わっているため何とも言えないけれど、作者が読者に見えるようにしてきたスケールと実際に読ませて貰っている話の間にはちょっとギャップが生じているような気がする。まあ、そうはいっても今は話半分なのでこの違和感が続くかどうかは話の続きを読んでからにしよう。
 山形浩生訳のケインズ『雇用、利子、お金の一般理論』をダラダラと読み続けてようやく終わった。大学では一応経済学部にいたんだけれど、何にも覚えていない。ゼミのテキストはレーニン『帝国主義論』で、英書講読はポール・スウィージーというケインズとはまったく縁のないマルクス主義世界だった。でも、ケインズの先生だったマーシャルの『経済学原理』全4巻は古本屋で買って本棚に飾っていた。1ページも読まなかったけれども。
山形浩生訳のケインズ『雇用、利子、お金の一般理論』をダラダラと読み続けてようやく終わった。大学では一応経済学部にいたんだけれど、何にも覚えていない。ゼミのテキストはレーニン『帝国主義論』で、英書講読はポール・スウィージーというケインズとはまったく縁のないマルクス主義世界だった。でも、ケインズの先生だったマーシャルの『経済学原理』全4巻は古本屋で買って本棚に飾っていた。1ページも読まなかったけれども。
ケインズに限らず古典的経済理論の著作は大抵辛気くさい。特に数学に似た論理操作が施されている処なんかは、もう勝手にして頂戴というくらい面倒くさいだけで何にも面白くない。それでもこの本には読んでいて面白いところがいくつかある。訳者解説にもあるように、投資専門家の判断とはクイズ百人に聴きましたタイプの美人投票の当選者を当てることだとする第14章や金持ちがピラミッドを建てたり、貯金をはたいて「地面に穴を掘れば」雇用も国民への実物配当も向上するというようなエキセントリックな例えが出てくる16章などもそうだけれども、巻末のおまけ第23章「重商主義、高利貸し法、印紙式のお金、消費不足の理論についてのメモ」がまた面白い。特にケインズによるマンデヴィル『蜂の寓話』解説は抱腹絶倒で、最後まで読んだ読者へのご褒美になっている。
山形浩生の訳でなければ多分一生読まなかっただろうケインズの主著。お礼を言うべきかな。そういえばこの間の朝日新聞でもポール・クルーグマンはケインズを持ち出していたね。
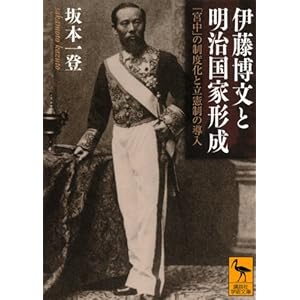 ケインズと同じ月に出た講談社学術文庫で、阪本一登『伊藤博文と明治国家の形成 「宮中」の制度化と立憲制の導入』が目に付いたので、そういや明治10年代の伊藤博文の動きも知っとかないとなあと思い、読んでみた。著者30代半ばの博士論文に手を入れたという作品で、出版翌年にサントリー学芸賞受賞という1991年の親本からの文庫化。ものすごく単純化すれば伊藤博文/オールマイティ・ヒーロー論なのだけれど、ま、それだからエンターテインメントとして読めるわけでもある。ここ20年余りの間に、歴史資料の読み込みとして国会図書館憲政資料室にあるような歴史的人物の書簡類や日記類を多読し、政治的重要人物たちの人間関係からその時代を活写しようというスタイルがはやってきたように感じるけれど、どうやらこの本がその手の傾向の初期作らしい。この本を読んでいると伊藤博文の精神形成に興味が湧くが、いまから吉田松陰というのもねえ。
ケインズと同じ月に出た講談社学術文庫で、阪本一登『伊藤博文と明治国家の形成 「宮中」の制度化と立憲制の導入』が目に付いたので、そういや明治10年代の伊藤博文の動きも知っとかないとなあと思い、読んでみた。著者30代半ばの博士論文に手を入れたという作品で、出版翌年にサントリー学芸賞受賞という1991年の親本からの文庫化。ものすごく単純化すれば伊藤博文/オールマイティ・ヒーロー論なのだけれど、ま、それだからエンターテインメントとして読めるわけでもある。ここ20年余りの間に、歴史資料の読み込みとして国会図書館憲政資料室にあるような歴史的人物の書簡類や日記類を多読し、政治的重要人物たちの人間関係からその時代を活写しようというスタイルがはやってきたように感じるけれど、どうやらこの本がその手の傾向の初期作らしい。この本を読んでいると伊藤博文の精神形成に興味が湧くが、いまから吉田松陰というのもねえ。
 何故か息子がくれたブノワ・ペータース/フランソワ・スクイテン『闇の国々』は、とても寝転がって読めるような重さではないので、もっぱらトイレで読んでいた。収録された『狂騒のユルビカンド』『塔』『傾いた少女』の3作はどれもイマジネーションの生々しさを感じさせて圧倒的である。手のひらの乗る大きさの棒で組まれた立方体が増殖して巨大化して果ては都市を呑み込み、そして消える巻頭作。うち捨てられた巨大な塔の塔守が地上に降りて再び塔頂を目指し、頂上に何もないのを悟って、塔を下りると別世界に出てきてしまう2作目。傾いた少女の突飛な遍歴と異常な惑星の存在を発見した天文学者と訳も分からず廃屋に壁画を描き続ける画家の話が、傾いた少女を接点に結びつく3作目。これぞ想像力という力業。好き嫌いをいう前にノックアウトされてしまったよ。
何故か息子がくれたブノワ・ペータース/フランソワ・スクイテン『闇の国々』は、とても寝転がって読めるような重さではないので、もっぱらトイレで読んでいた。収録された『狂騒のユルビカンド』『塔』『傾いた少女』の3作はどれもイマジネーションの生々しさを感じさせて圧倒的である。手のひらの乗る大きさの棒で組まれた立方体が増殖して巨大化して果ては都市を呑み込み、そして消える巻頭作。うち捨てられた巨大な塔の塔守が地上に降りて再び塔頂を目指し、頂上に何もないのを悟って、塔を下りると別世界に出てきてしまう2作目。傾いた少女の突飛な遍歴と異常な惑星の存在を発見した天文学者と訳も分からず廃屋に壁画を描き続ける画家の話が、傾いた少女を接点に結びつく3作目。これぞ想像力という力業。好き嫌いをいう前にノックアウトされてしまったよ。
 ハヤカワSFシリーズJコレクションは、新人作家に書かせる方針が固まったようで、なにより。とはいえ創刊10周年記念作品の冠にはやや弱いかなあ、という感じの2作だった。
ハヤカワSFシリーズJコレクションは、新人作家に書かせる方針が固まったようで、なにより。とはいえ創刊10周年記念作品の冠にはやや弱いかなあ、という感じの2作だった。
法条遙『リライト』は、タイトル通りのストレートな時間旅行トリックで、ラベンダーの香りが何回もしてやや鼻がバカになる。おおざっぱな印象は『時をかける少女』を「チューリップ・チューリップ」で割ったような感じ。ただしスラップスティックじゃなくてホラー系。現地時間2週間の間に2年間も同じループを回り続けるタイムリーパーってやっぱりスラップスティックだよなあと思ってしまうのは、タイムマシンや時間跳躍者が機能した途端に「時は分かれて果てしもなく」が可能性から現実になると思っているせいだろうな。時空間は壊れるより分裂する方がなんとなくしっくりくるもの。しかし、思いついたアイデアをとことん追い詰めた作者の力ワザは認める。
 倉数茂『始まりの母の国』は『リライト』とは随分感触の違った真面目な異世界ファンタジイで、「女の国もの」とでも呼べそうな一連の作品が思い浮かぶオーソドックスな作風。作品内のテンポは非常にゆっくりしており、わずか260ページ足らずで終わるとは思えない重厚さで、物語をどう終わらせるのかが気になる作品だった。しかし、その期待は後半のテンポの乱れにより萎んでいく。せめて倍半分長く書けていれば、前半のディテールが生きただろうにと思われて残念だ。編集側ももうすこし熟成させた方がよいと判断しなかったのだろうか。まあ、数をこなしていく内にマスターピースが書けるのかもしれない。『リライト』が徳間の新人賞タイプとするなら、こちらはファンタジー大賞長編賞タイプか。
倉数茂『始まりの母の国』は『リライト』とは随分感触の違った真面目な異世界ファンタジイで、「女の国もの」とでも呼べそうな一連の作品が思い浮かぶオーソドックスな作風。作品内のテンポは非常にゆっくりしており、わずか260ページ足らずで終わるとは思えない重厚さで、物語をどう終わらせるのかが気になる作品だった。しかし、その期待は後半のテンポの乱れにより萎んでいく。せめて倍半分長く書けていれば、前半のディテールが生きただろうにと思われて残念だ。編集側ももうすこし熟成させた方がよいと判断しなかったのだろうか。まあ、数をこなしていく内にマスターピースが書けるのかもしれない。『リライト』が徳間の新人賞タイプとするなら、こちらはファンタジー大賞長編賞タイプか。
 世に流行るゾンビものに手を出す気にはなれないのだけれど、新世代スチームパンクということで読んでみたシェリー・プリースト『ボーンシェイカー ぜんまい仕掛けの都市』は、危険地帯に潜り込んだ息子の救出に向かうのがタフなオヤジならぬ子離れできないオフクロというまさに現代的な一作。翻訳の上手さも手伝ってとにかく読みやすい。そこら中を掘りまくったというボーンシェイカーは最初にちょこっと動き回って、最後にまた止まったままの姿でちょこっと出てくるだけ。作者はボーンシェイカーという言葉の響きは気に入っているが、その機械の魅力を語る気はないようだ。だけれど、男の子にはその機械が魅力なのだ。基本的にはヤングアダルト向けの物語だし、ワンダーはあってもセンス・オブ・ワンダーはない世界。背景世界はかなり面白そうなのに、ここではまだ遠い谺だし。などと文句ばかり並べているが、愉しく読ませてもらったことは間違いないし、それになんといっても表紙の文字デザインが素晴らしい。でも元少年にとってオフクロは鬱陶しいよ、やっぱり。
世に流行るゾンビものに手を出す気にはなれないのだけれど、新世代スチームパンクということで読んでみたシェリー・プリースト『ボーンシェイカー ぜんまい仕掛けの都市』は、危険地帯に潜り込んだ息子の救出に向かうのがタフなオヤジならぬ子離れできないオフクロというまさに現代的な一作。翻訳の上手さも手伝ってとにかく読みやすい。そこら中を掘りまくったというボーンシェイカーは最初にちょこっと動き回って、最後にまた止まったままの姿でちょこっと出てくるだけ。作者はボーンシェイカーという言葉の響きは気に入っているが、その機械の魅力を語る気はないようだ。だけれど、男の子にはその機械が魅力なのだ。基本的にはヤングアダルト向けの物語だし、ワンダーはあってもセンス・オブ・ワンダーはない世界。背景世界はかなり面白そうなのに、ここではまだ遠い谺だし。などと文句ばかり並べているが、愉しく読ませてもらったことは間違いないし、それになんといっても表紙の文字デザインが素晴らしい。でも元少年にとってオフクロは鬱陶しいよ、やっぱり。
そういえば今月のSFマガジンのブックレビューで〈はるこん〉の翻訳SFシリーズ3冊目がアレステア・レナルズ『武道館にて』と知ってビックリ。たまたま去年のハートウェルのSFベスト・アンソロジーで読んだのがこの表題短編だった。ロボットのメタリカとかティラノザウルスのロック・スター(T・レックス)だとかが出てくるかなりズッコけた話で、登場人物が金儲けのアイデアにおぼれて自業自得な結末を迎えたように記憶している。本当に面白いのかコレ。
THATTA 289号へ戻る
トップページへ戻る
 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ3冊目、イアン・マクドナルド『サイバラバード・デイズ』は、本当に久しぶりのマクドナルド。全体的な印象は、大枠は割とオーソドックスなプロットなのに、膨大なエキゾティック趣味で読者の目をくらませる類に見える作品集といったところ。『火星夜想曲』の頃のナイーブさは後退し、テクニカルな操作が前面に出ている。バチガルピほどストーリーとエキゾティシズムがしっくりいっていないように感じられるのが難かな。作者が新大陸を発見したらしい興奮は伝わってくるので、それは嬉しいんだけれど、危なっかしさもかなりのものだ。集中ではエキゾティズムが当たり前の日常に戻ってくる「小さき女神」や「ジンの花嫁」あたりが読みやすい。書き下ろしの「ヴィシュヌと猫のサーカス」は書き方の所為か散漫な印象。
新☆ハヤカワ・SF・シリーズ3冊目、イアン・マクドナルド『サイバラバード・デイズ』は、本当に久しぶりのマクドナルド。全体的な印象は、大枠は割とオーソドックスなプロットなのに、膨大なエキゾティック趣味で読者の目をくらませる類に見える作品集といったところ。『火星夜想曲』の頃のナイーブさは後退し、テクニカルな操作が前面に出ている。バチガルピほどストーリーとエキゾティシズムがしっくりいっていないように感じられるのが難かな。作者が新大陸を発見したらしい興奮は伝わってくるので、それは嬉しいんだけれど、危なっかしさもかなりのものだ。集中ではエキゾティズムが当たり前の日常に戻ってくる「小さき女神」や「ジンの花嫁」あたりが読みやすい。書き下ろしの「ヴィシュヌと猫のサーカス」は書き方の所為か散漫な印象。