

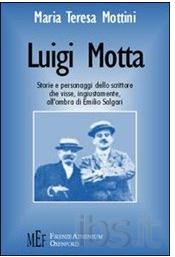
小松先生も逝かれてしまいましたか。うーん。まあ、我が身のポンコツ化ぶりを思えば、いかに偉い人だろうと、大先輩がいつまでもお元気で御活躍、なんて訳にはいかないことは頭ではわかってはおるとはいえ…涙。ゴー・トゥ・ザ・シー・ヒポポタマ〜ス。
ということで小松左京追悼を口実に無理やりなイタリア編である。「作者を探す」ってとこでピランデルロもSFっぽい気はするけど違うよねえ。ダンテとなるとさらに離れる気が。とはいうもののカンパネラでもないか。ということで、御登場いただくのはルイギ[ルイジ]・モツタ Luigi Motta(1881〜1955)である。って誰だよ。しかも翻訳されているわけでもないがな、という非難には耳を塞ぎつつ先に進みたい。
ルイギ・モツタ『薔薇の里の姫君』ってのは、こんな話。
「欧洲と亜細亜の両大同盟国が、大戦争をおつ始めた悲劇を描いたものである。云はば前独帝の夢想した黄禍が、白禍へ向つて攻寄せるわけで、其亜細亜軍の指揮者たり、又た先鋒たるものが、誰あらう日本国であるなどは振つて居るではありませんか。亜細亜側には土耳其も属して居る。戦争の起りは伊太利から土耳其に来て国王の娘の聟になつた一使臣が、素的な驚くべき飛行機を発明した。その図案を狙つて奪ひ取らうとする一人の土耳古人がある、それさへ奪へれば、亜細亜軍は蜂起して直ぐ欧州に攻寄せる事が出来るのである。其土耳古人は恐ろしい詭計に富んだ男で、馬鹿と見せて其付馬に油断させ、とうとう元の使臣であつた国王を殺して了つた。結局飛行機の半分の機械は手に入れたが、未だ半分は何処ヘ隠したものか見付からない。
薔薇の里の姫君と云ふのは、この国王の娘ウエルシダ姫である。彼女は忠実な老臣の助けで命は助かつたが、例の土耳古人で今は亜細亜側同盟の午耳を執つて居る、奸雄ライムが、何時自分を捉まへに来るか分らない、しかし彼女は伊太利人の父の血を受けた頗る勇悍な美人である。何とかしてライムを屠つて此国を元の運命に還さうとする。一方奸雄ライムはウエルシダの父から奪つた飛行機の図案によつて、飛行界に未だ見た事もない、驚ろくべく精巧な大飛行機ジヤダルカンド号を拵らへ上げた。彼は数十人の兵士とそれに搭乗して、瞬く間に欧州へ飛んで来る、星なき闇の巴里の空、伯林の空を輝かして刹那に消えて行く怪火の為に、夜毎おひやかされる欧州国民は、素よりそんな恐ろしく迅速な飛行機があらうとは知る訳もない、之が天が示す全欧州の滅びの火であると云ふので日となく夜となく恐怖におののいて居る。そこへ疫病が流行り出した、それここぞと待構へた亜細亜国民は、無数の飛行機に飛乗つて、欧州へ攻め寄せた。
(中略)
「亜細亜飛行隊は、直ぐと欧州同盟軍の機械力の、著るしく劣つて居る事がはつきりとわかつた、中にも勇敢を以て鳴る日本の飛行艦隊は、仏蘭西軍のかためた戦線の真只中へ割つて入り苦もなく滅茶々々に潰散して更に陣上に舞上り、蟻のやうに密集した仏軍飛行機の気嚢の上から、爆烈弾榴散弾を雨霰とそそぎ掛けた。つけて加へて怪速力を持つた無数の空中水雷が、目にも留らず駆廻つては、彼等の不敵大胆と勇気に任して、四方八面に致命的な発射をするのだから溜つたわけのものぢやない」
こんな次第で日本軍の勇敢が、盛んに濫発されて居る、とどのつまり欧州は第二の匈奴のうき目に遭はうとする、処がライムの弟にロバアトと云ふ勇気なる青年がある、ライムとは腹違ひの弟で、母系の仏蘭西の血を承けただけ、東洋よりも欧州に同情を寄せて居る之れが薔薇の里の姫君と恋に落ちて、協力した末に、彼の父が隠して置いた、新飛行機の図案を発見する、それによつて有力な飛行機を拵らへ、どうにか東洋の襲撃を撃退する。其時は北米合衆国までが戦争に参加する。ライムは飛行機が落ちて惨死し、ここで全く戦雲が収まつた、二人は目出度く結婚して国王となるのがおしまひである。」
この後の戦後の描写もふるっているらしいが、長くなったので略。La Principessa delle rose(1911)が原作で、仏語訳La Princesse des rosesは1914年、英語訳が出たのは第一次大戦の1919年になってからのようだが、飛行機を活躍させたりロシア革命を予見してた、ってとこが評価されて訳されたものか。
英訳版を読んで、この紹介記事を1920年11月の<東方時論>に発表しているのは千葉亀雄(1878〜1935)である。千葉亀雄といえば、まったくなんでも読んでいるエイリアンとして有名だった人。
日米関係が緊張してるんで、なんか未来戦ものでも紹介してという原稿依頼だったのではないかと思われるんだが、米国物は新聞事業関連の文献以外はあんまし読んでないんで、といってイタリア製未来戦小説を紹介してくるのが凄いね。
ゆまに書房から『千葉亀雄著作集』という全5巻の選集が出ていて、編纂には古書収集の世界で、神様クラスと目されていた福田久賀男氏が関わっているので、それを見れば大体のことはわかるかと思いきや、その書誌から落ちている文献も結構あって、本人がきっちり記録を採って置くキャラではない健筆の人を追っかけるのは至難の技だということが良くわかる。
千葉の翻訳書として、1930年にラツコ『戦の人々』平凡社(世界プロレタリア傑作選集)、1931年にコレリ『ヴエンデツタ』改造社(世界大衆文学全集)があるが、本人曰く、「私の名で出てるのは、私のやつたものではなく、大抵私の子供などのやつたもの」だとか。読むのに忙しくて訳している暇はないっ。と、良い本だと思っても他人に仕事を回していたらしい。
それじゃあ<大日>に「嵐の瞽使者」の題で連載していたヴェルヌのミハイル・ストロゴフも別人の訳なのかねえ?
恐らく北原尚彦氏が指摘するまで誰も気がついていなかったと思われるフィッツ=ジェイムズ・オブライエンの翻訳、「不思議な話」<日本及日本人>1920年1月1日ぐらいは本人の訳っぽい気がするけどねえ。
ちなみにペルッツのことをえらく気にかけていたようで、1930年8月5日発行の<新青年>夏期増刊で「包み紙が無くなつたので、国籍が一寸見当がつきませんが、Leo Perutzといふ作家の"From Nine to Nine"といふ、怪奇極まる作物のやうなものが好きです。一寸どんな作物といつて一口に云へぬほど、陰惨で気味の悪いものですが。」と書いていて、翌年3月1日発行の<作品>という雑誌では「脱稿したものにはペルツの「九時から九時まで」」と訳了した(もちろん他人に訳させたらしい)ことが記されている。って、出版されてないよねえ。「陰惨で気味の悪い」と言って出版社が蹴ったの?
「「九時から九時まで」の作家も、同国[墺太利]ですが、ドイツ作家に属してゐるやうです。どの位ゐの地位に居るかわかりませんが、普及版の二三の叢書にも彼の著作が在りますから、相応に評判な作家でせう。「九時から九時まで」は、文字通り、或る男の九時から九時までの行動を取材したもので、探偵小説と怪奇小説の合の子のやうな、そして、エロとグロ趣味がわういつして居て、それで、芸術的価値はちつとも傷はれない、奇怪な作物です。」ですって。