 世間はお休みな年末年始にかけて読んでいたのが、ジョー・ヒル『20世紀の幽霊たち』で、世評どおりの素晴らしい短編集だった。つくりはホラーなのに叙述のタッチがメインストリーム小説的で、しかも文体とテーマの乖離がないうえにメインストリーム小説的な後味を残すという相当な代物。「蝗の歌をきくがよい」でさえ、マシスンあたりが書いてもよさそうなモンスター小説なのに、カフカには向かわない文学系のタッチが感じられる。「文学的」才能は父親よりも上なんだろうな。
世間はお休みな年末年始にかけて読んでいたのが、ジョー・ヒル『20世紀の幽霊たち』で、世評どおりの素晴らしい短編集だった。つくりはホラーなのに叙述のタッチがメインストリーム小説的で、しかも文体とテーマの乖離がないうえにメインストリーム小説的な後味を残すという相当な代物。「蝗の歌をきくがよい」でさえ、マシスンあたりが書いてもよさそうなモンスター小説なのに、カフカには向かわない文学系のタッチが感じられる。「文学的」才能は父親よりも上なんだろうな。|
続・サンタロガ・バリア (第82回) |
平成21年でも2009年でもあまり実感がない生活をしながら、それでもわが息子より若い23才という英語の先生に「あなたの人生を変えた重大な出来事は何ですか」と訊かれて、「13歳の時に『2001年宇宙の旅』を見たことかなあ」などと答えていると、突然40年もの歳月が実感されて思わず英語をしゃべるのを忘れてしまったのは、たまたま居合わせた目の前の女子高生の何の屈託も感慨もない目つきのせいではないだろう。
先月聴いたドゥダメルとユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラの「マランボ」をCDで聴いてみようと『FESTA』というタイトルの南米出身作曲家たちの曲のアンソロジーみたいな1枚を買った。ライヴ録音という割にはヒナステラのバレエ組曲『エスタンシア』は整然とした演奏でスタジオ録音的な感じであった。ついでに買ったカラヤン最晩年のベルリン・フィルとのロンドン・ライヴは、いかにもライヴ的な音の悪さも手伝って、異様な感じのする演奏だった。シェーンベルクの「浄夜」は、クールそのものな70年代初期のスタジオ盤とは大違いで、熱気溢れるというかオン・マイクなオケの響きが悲劇的な様相を見せている。宇野功芳が褒めちぎったというブラームスの1番はシェーンベルクとは違ってちょっと乱れた感じがする(音はベルリン・フィルだけど)演奏で、何回も聴きたいとは思わないが、結構衝撃的ではある。そういえば前号でフヂモトさんがヒンデミット作曲のフィッツ=ジェイムズ・オブライエンの作品があるって書いておられたけど、ヒンデミットは有名曲しか聴いたことがありません。マイナー系(って、ヒンデミットは十分メジャーですが)作曲家の作品を聴くのはELPとかカーブド・エアとかで引っかかるレベルです。
 世間はお休みな年末年始にかけて読んでいたのが、ジョー・ヒル『20世紀の幽霊たち』で、世評どおりの素晴らしい短編集だった。つくりはホラーなのに叙述のタッチがメインストリーム小説的で、しかも文体とテーマの乖離がないうえにメインストリーム小説的な後味を残すという相当な代物。「蝗の歌をきくがよい」でさえ、マシスンあたりが書いてもよさそうなモンスター小説なのに、カフカには向かわない文学系のタッチが感じられる。「文学的」才能は父親よりも上なんだろうな。
世間はお休みな年末年始にかけて読んでいたのが、ジョー・ヒル『20世紀の幽霊たち』で、世評どおりの素晴らしい短編集だった。つくりはホラーなのに叙述のタッチがメインストリーム小説的で、しかも文体とテーマの乖離がないうえにメインストリーム小説的な後味を残すという相当な代物。「蝗の歌をきくがよい」でさえ、マシスンあたりが書いてもよさそうなモンスター小説なのに、カフカには向かわない文学系のタッチが感じられる。「文学的」才能は父親よりも上なんだろうな。
 河出の奇想コレクションに収められたグレッグ・イーガン『TAP』は、いわばB面集といった面持ちがある短編集。ここには昔風の「短編小説の書き方」的小説作法によって書かれたと思われるものばかりが集められている。強面イーガンもちょっと冗長な感じのするアイデア・ストーリーをいっぱい書いていたんだなあ、と思わせるのが編者の狙いだったのかと。しかしながら、アイデアから引き出される論理とテーマは昔のSFには見られなかったものだろう。「森の奥」なんてほとんど20世紀半ば以降の何時誰が書いていてもそれほど不思議はないオチ小説として読むことが可能だし、そういう外見のハナシだけれど、イーガンの手になるものだからやはり認識論とかのややこしいテーマを扱っているということになる。表題作はハナシの運びがいかにも推理ものなのに、結末はそちらではなくストレートなイーガンのテーマの提示で終わっているのが、ストーリーテリング以上にいいたいことのあるイーガンらしい。
河出の奇想コレクションに収められたグレッグ・イーガン『TAP』は、いわばB面集といった面持ちがある短編集。ここには昔風の「短編小説の書き方」的小説作法によって書かれたと思われるものばかりが集められている。強面イーガンもちょっと冗長な感じのするアイデア・ストーリーをいっぱい書いていたんだなあ、と思わせるのが編者の狙いだったのかと。しかしながら、アイデアから引き出される論理とテーマは昔のSFには見られなかったものだろう。「森の奥」なんてほとんど20世紀半ば以降の何時誰が書いていてもそれほど不思議はないオチ小説として読むことが可能だし、そういう外見のハナシだけれど、イーガンの手になるものだからやはり認識論とかのややこしいテーマを扱っているということになる。表題作はハナシの運びがいかにも推理ものなのに、結末はそちらではなくストレートなイーガンのテーマの提示で終わっているのが、ストーリーテリング以上にいいたいことのあるイーガンらしい。
 伊藤計劃『ハーモニー』は前作で抱かせた期待に十分応える仕上がりの一作。とはいえ全体的な印象はライトノベルな面もないではない。メインアイデアそのものは見事なセンス・オブ・ワンダーを持っているし、それをワンダーと感じさせるだけの物語の積み重ねがおこなわれてもいる。それでもライトノベル的に読めてしまうのは、ひとつに少女3人の物語が前面に出てきていること、またヒロインがあまりにもエンターテインメントのキャラ的な強さを発揮してしまうからだろう。これらは作品世界を狭く見せているように感じられる。サハラもバクダッドも舞台として機能しているにもかかわらず、作中でその距離が実感できないこととも関係があるのかも。
伊藤計劃『ハーモニー』は前作で抱かせた期待に十分応える仕上がりの一作。とはいえ全体的な印象はライトノベルな面もないではない。メインアイデアそのものは見事なセンス・オブ・ワンダーを持っているし、それをワンダーと感じさせるだけの物語の積み重ねがおこなわれてもいる。それでもライトノベル的に読めてしまうのは、ひとつに少女3人の物語が前面に出てきていること、またヒロインがあまりにもエンターテインメントのキャラ的な強さを発揮してしまうからだろう。これらは作品世界を狭く見せているように感じられる。サハラもバクダッドも舞台として機能しているにもかかわらず、作中でその距離が実感できないこととも関係があるのかも。
 キャンベル賞受賞が何を評価してのものなのかよくわからないナンシー・クレス『プロバビリティ・スペース』は、3部作の最終巻としてまったく期待はずれのものだった。この作者の長編を構成する力のなさが露呈した代物で、「世界」も「最終破壊兵器」も敵宇宙人「フォーラー」もみんな腰砕けになってしまった。その大きな原因が、天才数学者の娘の逃避行に物語の半分を費やしたことにある。この娘をはじめとしてこれまでそれなりに良くできていた主要キャラがどいつもこいつもデクノボウと化してしまい、肝心のハードSF的宇宙戦争の行方は火星/地球のドメスティックな話題に蹴散らされてしまっている。いまごろ『SFマガジン』のグラビアでデカデカと扱われても・・・。
キャンベル賞受賞が何を評価してのものなのかよくわからないナンシー・クレス『プロバビリティ・スペース』は、3部作の最終巻としてまったく期待はずれのものだった。この作者の長編を構成する力のなさが露呈した代物で、「世界」も「最終破壊兵器」も敵宇宙人「フォーラー」もみんな腰砕けになってしまった。その大きな原因が、天才数学者の娘の逃避行に物語の半分を費やしたことにある。この娘をはじめとしてこれまでそれなりに良くできていた主要キャラがどいつもこいつもデクノボウと化してしまい、肝心のハードSF的宇宙戦争の行方は火星/地球のドメスティックな話題に蹴散らされてしまっている。いまごろ『SFマガジン』のグラビアでデカデカと扱われても・・・。
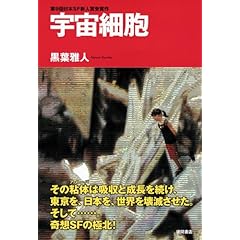 今月最後に読んだのは第9回日本SF新人賞受賞作、黒葉雅人『宇宙細胞』。これまたこの新人賞から出てくる作品は完成度の低いものが多いという先入観を強化する一作。ただし、破天荒という意味では評価していいかもしれない。それにしても説得力に欠ける描き方のハナシだなあ。B級SFホラー映画(もしくはXファイル)を下敷きにしたような出だしからスケール感のないパニック映画に移行、主要キャラに魅力はほとんど無くそれがB級感をさらに印象づける。ところが人間キャラがいなくなって最終章にはいると『ブラッド・ミュージック』やステープルドンもかくやというスケール・インフレを起こす。なんじゃい、こりゃ。現代日本のレイ・カミングスというのが妥当なところが。
今月最後に読んだのは第9回日本SF新人賞受賞作、黒葉雅人『宇宙細胞』。これまたこの新人賞から出てくる作品は完成度の低いものが多いという先入観を強化する一作。ただし、破天荒という意味では評価していいかもしれない。それにしても説得力に欠ける描き方のハナシだなあ。B級SFホラー映画(もしくはXファイル)を下敷きにしたような出だしからスケール感のないパニック映画に移行、主要キャラに魅力はほとんど無くそれがB級感をさらに印象づける。ところが人間キャラがいなくなって最終章にはいると『ブラッド・ミュージック』やステープルドンもかくやというスケール・インフレを起こす。なんじゃい、こりゃ。現代日本のレイ・カミングスというのが妥当なところが。