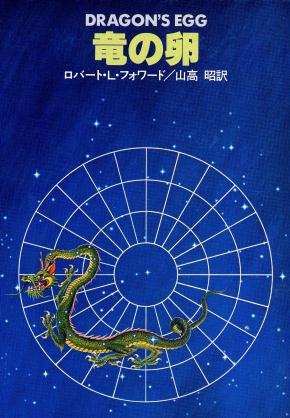
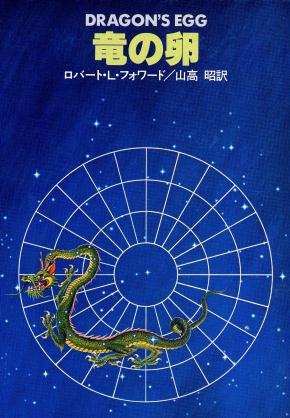
ロバート・L・フォワード/山高昭訳
『竜の卵』 解説
大野万紀
ハヤカワ文庫SF
昭和57年6月30日発行
(株)早川書房
Dragon's Egg by Robert L. Forward (1980)
ハードSFの世界に一人の超新星{スーパー・ノヴァ}が現われた。その名はロバート・フォワード。本書『竜の卵』は一九八〇年に発表された彼の処女長篇であり、中性子星上の知的生命という魅力的な仮説を、科学的かつイマジネーション豊かに展開した傑作SFである。
*
今から三十年ほど前、ハル・クレメントは『重力の使命』で、地球の三倍から七百倍という大重力をもつ惑星メスクリンを舞台に、その自然条件に適応した非人間型知的生物の活躍を描いて、多くの読者に感銘を与えた。
クレメントが書いたのは、徹底的に異星人の立場から見た異星の環境だった。もちろん本当の異星人が人間と同じような思考をするはずがないという考え方からすれば、異星人の立場に立って見るなどということは不可能であるし、矛盾していることになる。実際、より正確にいえば、クレメントが書いたのは、もし人が異星人であったなら、どう考え、どう行動するかという、一連のスペキュレーションであった。ウサギが人間のことばを話せたら、いったい何を語るだろうかというのと同様、これはおとぎ話に近いものなのである。愛すべきメスクリン人たちのファンタスティックな冒険を、われわれ地球人が感情移入して楽しむことができたのも、そのためなのだ。
これは有効な手法である。SFの、知的ゲーム的な側面を最大限に生かしつつ、ガチガチのハードSFファンだけでなく、もっと幅広い読者層にもアピールし、受け入れられるための――。クレメントはそれに成功したのだった。そして『重力の使命』は、ずばぬけた傑作とはいわれぬものの、SFファンの心にいつまでも残る古典的な地位を獲得したのである。
それから三十年近くが過ぎた今、ここにまたひとつのメスクリンが生まれた。
本書『竜の卵』を読まれた方ならもうおわかりだろう。本書はこの三十年間の科学の成果をふまえて書かれたもうひとつの『重力の使命』である。メスクリン人と同様、チーラたちも、かつてSFの生み出した最も魅力的な異星人の殿堂に入る資格は充分である。
中性子星に住む知的生物! クレメントがニュートン力学と有機化学の知識を駆使して描いたのは、木星の十六倍の質量、赤道部分で八万キロメートルの直径、十七分四十五秒で一回転し、極での重力が六百七十G、水素の大気とメタンの海をもつマイナス百七十度の惑星だった。そこに住むメスクリン人は体長四十五センチのムカデのような知的生物である。一方フォワードが量子力学と重力を伴う相対性理論を駆使して描いたのは、クレメントに合わせていうなら、木星の五百倍以上の質量、二十キロメートルの直径、〇・二秒で一回転し、重力六百七十億G、鉄の原子核の大気をもつ地表温度八千度の回転する中性子星(パルサー)である。そこに住むのは体長三ミリの殻のないアワビのような知的生物――チーラなのだ。
このように数字を並べると、何だ数値を極端にしただけではないかと思われる人がいるかもしれないが、重力が一億倍違う世界を科学的に考証しようとすると、とてもそれだけですむものではない。正確な科学知識が要求されるのはもちろんだが、それ以上に一貫した豊かな想像力が必要である。
本職が科学者で、重力理論の専門家であるフォワード博士には、当然それを書けるだけの科学知識がある。さらに、本書によって、博士には魅力的なストーリイを語るSF作家の才能と、首尾一貫した論理的な想像力、そのうえ、最後まで本書を読まれた方なら同意してもらえるだろうが、過去の多くの傑作SFにも通じる、あの何ともいえないSF特有の高揚した気分を味わせてくれるだけの、SF的センスさえもっていることが証明された。
かつてのフレッド・ホイルと同様、単なる科学者の余技ではない、本格的なSF作家の誕生といっていいだろう。
本文の中では細かな科学的背景説明は必要最少限のものをのぞいて省かれている。本書の中心テーマとなっているのは、一つの種族が原始時代を脱し、文明を開花させ、宗教を改革し、科学をうち立てるまでの全歴史だ。チーラの時間感覚がわれわれの百万倍であるため、これは地球からの探査船が中性子星へ接近したわずか一ヵ月あまりのできごととして描かれている。先に述べた高揚感は、われわれが個人ではなく、一つの種に感情移入することから生じるものだ。
より詳細な科学的ディテールは、『重力の使命』と同じく、付録にまとめられている。『重力の使命』の「メスクリン創世記」が一九五三年六月号のアスタウンディング誌に科学記事として掲載されたのと同様、本書の付録「専門的補遺」も「竜の卵の味」と題して一部抜粋の上アナログ誌一九八〇年四月号に科学記事の形で掲載された(アスタウンディング誌はアナログ誌の前身なのである)。
恒星に住む生物という発想はSFの世界では決して珍しいものではない。クラークの『二〇〇一年宇宙の旅』では海と陸と空気と宇宙の他に、火の領域に生きる生命がいることが示唆されている。ソ連の作家が書いた「竜座の暗黒星」は、偶然にも本書と同じく竜座の方向にあり、太陽系のごく近くにありながら暗くて発見されなかった黒色倭星上の生命を描いている。もちろんこれらの他にも同様の作品がたくさんあることだろう。
だが中性子星上の生物となると、話題が新しいだけに数少ない。本書をのぞけば、ポール・アンダースンの『アーヴァタール』にちょっと顔を出している程度だ。おそらくプロのSF作家にとっては、今さら中性子星上の生物というアイデアだけで何が書けるのかという気持ちがあったに違いない。フォワードの成功は、妙にひねった処理をせず、ごくストレートにアイデアを表現したところにあると思う。作家としての資質があったのはもちろんだが、もう一つは、やはりアイデアの勝利である。科学的に扱われた中性子星上の生物というアイデアは、それだけで長篇を充分にささえるだけの奥ゆきをもったものだったのである。
この仮説は、今から十年ほど前、七〇年代のはじめに、先端的な科学者の間で論じられていたものだった。フリーマン・ダイソンは中性子星の外層にある種の疑似化学反応が存在すると述べた。G・コッコーニは素粒子のレベルで生命の素材となる物質が作られ得ると示唆した。こういった議論の上に立って、コーネル大学のフランク・ドレイクやT・ゴールドが、中性子星上に存在し、化学反応のかわりに核反応を利用して生きる生命体という仮説を提出したのだった(このあたりの経緯は、一九七一年に開かれたソ連邦ビュラカンでの地球外知的生物との交信に関する第一回米ソ会議の記録『異星人との知的交信』でも述べられている)。フランク・ドレイクは七三年十二月号のアストロノミー誌でこのアイデアを一般向けに述べ、多くのSF作家たちの注目を引いた。それが作品に結びつかなかったのは、先にあげた理由の他に、当時の英米SF界でハードSFが低調だったこともあげられるだろう。ベトナム戦争や公害の影が、アポロ以後の世界に悪夢としてのしかかっていたのだ。西側の国々で科学が復権するには、さらに数年かかったのである。
*
ロバート・L・フォワードはヒューズ研究所の科学者。重力理論を専門とし、天文学や恒星間飛行に関する一般向けの解説をいろいろな雑誌に発表している。その中にはギャラクシイ、アナログ、オムニといったSF誌も含まれている。博士はその昔メリーランド大学のウェーバー教授がおこなった重力波検出実験で、検出器の作成に協力した。ヒューズ研究所には博士の手によるレーザーを応用した最新式の重力波アンテナがある。このアンテナはすでにいくつかの信号を捉えている。今のところ、それらはすべて単なるノイズにすぎないが、もしかしたら〈竜の卵〉からのものが混っているのかも知れない。実際、現代の天文学によると、今から十万年ほど前に、太陽系からおよそ三百光年離れたところ――〈竜の卵〉の五十光年には及ばないが、かなりの近距離で、超新星の爆発があった形跡がある。その時生じたパルサーが、すぐそばまで来ているかもしれないのだ(マサチューセッツ大学のE・ハリスソによれば、太陽からわずか千天文単位のところに未知の中性子星が存在している可能性があるという)。
フォワード博士は、自分でSFをよく書くようになる以前からSF界に大きな貢献をしている。もともとSFが好きだった――彼とSFのなれそめは、高校時代、後にポール・アンダースン夫人となるカレン・アンダースンに昼食をおごったことだそうだ――が、初めてSF雑誌に執筆したのは六二年のギャラクシイ誌である。それは回転する超高密度物質の周囲に発生する重力場を扱った科学解説だった。当時はまだSFに対する評価が低く、SF雑誌に関係しているなどと知れると、科学者としてはうさんくさい目で見られるような風潮があった(今でも皆無とはいえまい)。しかしフォワードは徐々にSF界との接触を深め、雑誌に寄稿したり、SF作家たちの集まりで講演したりもするようになる。SF作家の方で最もこの恩恵に浴したのはジェリー・パーネルとラリイ・ニーヴンである。ニーヴンの『時間外世界』の解説ですでに紹介したエピソードだが、彼のブラックホールを扱ったヒューゴー賞受賞作「ホールマン」は、実はフォワード博士の示唆の下に書かれたものだったのである。
それだけではない。SFマガジン八〇年十二月号によると、わが石原藤夫氏の初期の傑作「空洞惑星」にも、フォワード博士の名が言及されている。石原氏はかつてフォワード博士のいくつかの論文に強い感銘を受けたのだそうだ。偶然だとしても、大変に面白いエピソードである。
まだある。アーサー・C・クラークだ。『地球帝国』の著者あとがきによると、彼にミニ・ブラックホールのアイデアを教え、宇宙船の推進方式をアドバイスしたのがフォワード博士なのだ。
このように今まで舞台裏にいてSF界にアイデアを提供してきた彼が、とうとう表舞台に登場したのだ。これからのハードSFはますます面白くなることが期待できよう。
博士はロサンジェルス近郊オックスナードに、妻と末娘といっしょに住んでいる。上の三人の子供たちは学生で、たまにしか帰って釆ない。もう一人の家族といっていいコンピュータ・ターミナルは、いつも故障寸前まで過熱気味であるという。
1982年6月